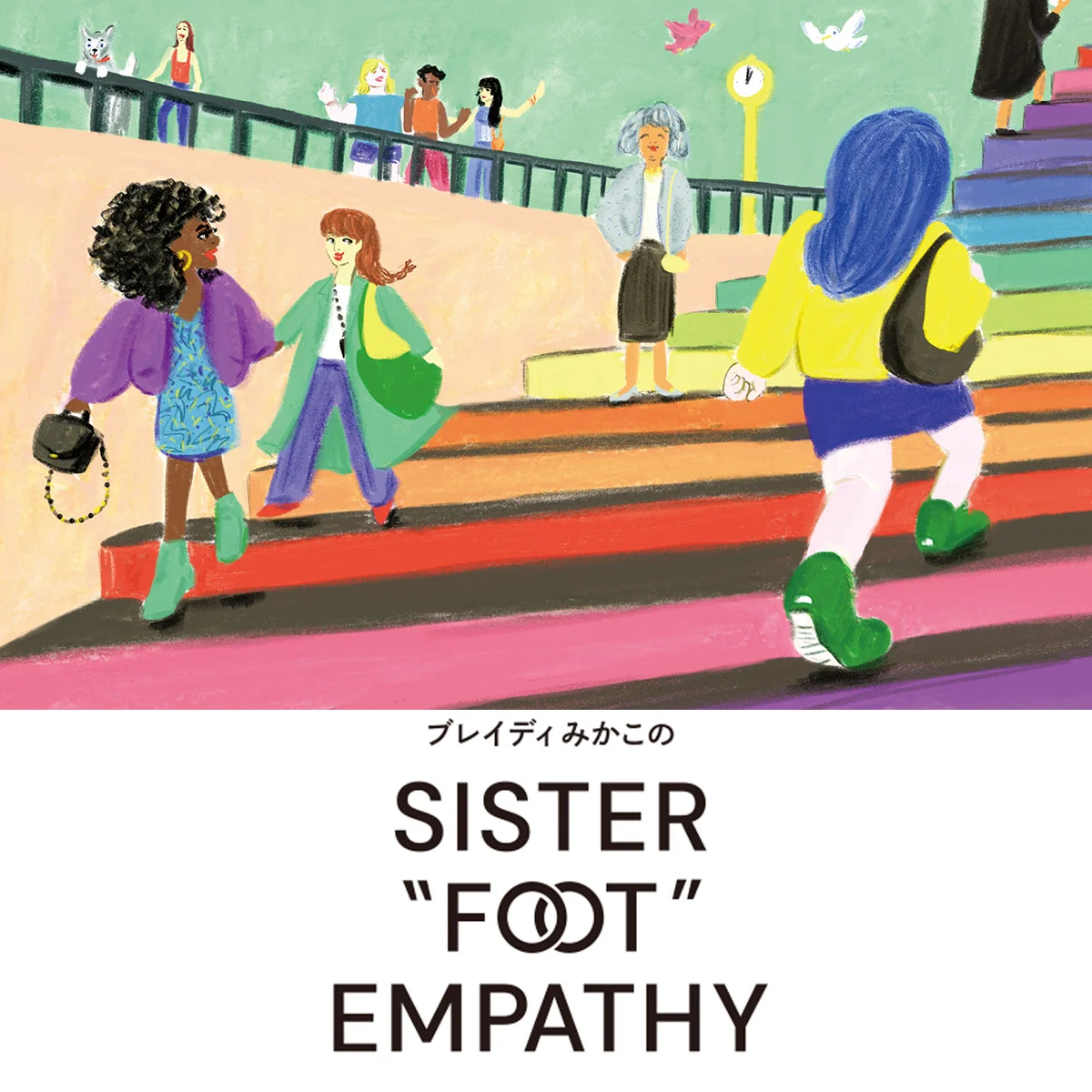"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。

ブレイディみかこライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国ブライトン在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)、『女たちのテロル』(岩波書店)など、多数著書あり。
新連載
女たちのストライキ— 共謀するシスターフッド —
最近、インタビューで女性の問題について発言を求められるたび、同じことを尋ねられる。
「日本は世界ジェンダーギャップ指数ランキングで120位です。毎年、先進国ではダントツで最下位なんですけど、どうしたらこの状況を変えられるでしょうか」
四半世紀を英国で暮らしてきたわたしには、正直、日本のいまの状況はわからない。だから、おいそれと答えられる質問ではないが、日本の順位がそんなに低いなら、上位の国は何をしてきたか探ってみるのも参考になるだろう。
というわけで、アイスランドである。12年連続で世界ジェンダーギャップ指数ランキング1位。もはや独走状態と言っていい。日本の順位がふるわない理由は、「政治への参画」と「経済活動への参加と機会」の分野での順位が特に低いからだ(2021年の結果を見ても、前者が147位、後者が117位)。が、正反対に、アイスランドはこの2分野が強いので総合1位をキープし続けている(前述と同年の結果で前者が1位、後者が4位)。
両国の差は何なのか? 日本はおっさんが幅を利かせている社会だからとか、いまだ家父長制文化が根強いからとか言うこともできる。だが、わたしは、アイスランドの足もとから始まるシスターフッド、すなわち、「女たちのストライキ」の伝統に注目したい。
たとえば、アイスランドでは2018年に世界で初めて男女の賃金格差を違法とする法律ができた。この法律制定の原動力となったのも、2016年10月24日に行われたストライキだといわれる。この日、アイスランドの女性たちの多くが午後2時38分に仕事を終わらせ(男性と同じ賃金をもらっていれば女性たちはこの時間に業務を終了できる計算になる)、抗議活動を行なったのだった。
彼女たちが10月24日を選んだのは、それが伝説のアイスランドの「女たちのストライキ」が行われた日だったからだ。1975年のこの日、アイスランドの女性たちは勤労、家事、子どもの世話を行うことを放棄してストライキを決行した。なんと全国の女性の90%がストに参加したという。
わたしが執筆作業を行うためによく利用する小さな北欧風カフェがあり、そこの店長がアイスランド出身だ。彼女はこのときのことをよく覚えているそうで、「あの日、アイスランドの少女たちはみんなフェミニストになった」と言う。当時12歳だった彼女は、母親や叔母や祖母、近所の女性たちが一丸となって闘う姿を見てワクワクするような興奮を覚えたという。
それは当日だけの話ではなかった。ストが近づくにつれ、ストリートのさまざまな場所に女性たちが集まって話し合っている姿を目にするようになったそうだ。店長の家族の中でも議論は行われていた。彼女の祖母は工場で働いていて、ストに参加するつもりはないと頑固に言い張った。それでも、工場で自分とまったく同じ作業をしている若い男性たちの賃金が自分よりも高いことには不満を持っていた。
「何かしないと何も変わらない。あなたの孫の世代になっても、ひ孫の世代になってもこのままだったとして、それでいいと思う?」
自宅のキッチンで、母親がそう言って熱心に祖母を説得しているのを聞いたそうだ。スト当日、祖母は工場に行かず、自分の娘たちと一緒にデモに参加した。
店長の母親は当時30代で、ベーカリーで働いていた。上司の女性は50代だったが、「ストなんかしたら、社長やお客さんに申し訳ない」と当日も働くと言って聞かない。母親は仕事帰りに上司の自宅を訪ね、「働かない日の分を、最高においしいパンを開発することで取り返しましょう」と説得したそうだ。また、20代だった叔母は、スト当日、学生時代に大嫌いだった保守的な女性教師がデモに参加している姿を見て衝撃を受けていたらしい。「あの人まで参加していたのだから、とんでもないことが起きた日だった」と後々まで語っていたという。
こうして女性たちが盛り上がる一方で、男性たちは途方に暮れた。その日、会社や工場や商店は、子どもたちであふれ返ったそうだ。その多くが女性である教員たちや保育士たちがストを行なったため、学校や保育園は閉鎖され、家庭の女性たちも家事を放棄して外出したため、男性たちは職場に子どもを連れて行くしかなかった。仕事の途中でお菓子を買いに走る者、鉛筆と紙をかき集めて子どもにお絵描きをさせようとする者、幼児の世話をさせようと年長の子どもたちを買収する者などで職場は混乱した。この日、アイスランド全土のスーパーでソーセージが売り切れたという(焼くだけでいい食べ物で、子どもたちの人気も高いからだ)。
女性社員が消えた新聞社から翌朝発行された新聞はいつもの半分の薄さだったそうだ。銀行の窓口業務を行なっていた女性たちは、上司の男性が窓口に座っているのを見て、わざと客として銀行に行ったりした。アイスランドの男性たちが、この日を「長かった金曜日」と呼んだのも無理はない。女性たちはいつだって「長い毎日」を過ごしていたことを思い知らされたのである。
この話を聞いて驚くのは、世代、経済的階層、学歴、未婚・既婚、趣味、思想・信条などさまざまな軸で分かれてクラスター化しがちな女性たちが、一つの目的のもとにつながって一緒に闘ったという事実である。女性の9割が結託したというのだから半端ない。どうしてそんなことが可能だったのだろう。
それは、カフェの店長の母親がしていたような地べたでの説得活動が全国津々浦々で行われていたからと考えるのが自然だろう。少女時代の店長が目撃したという、ストリートのさまざまな場所で行われていた女性たちの話し合い。店長の母親が世代や立場が違う女性の心情を考えながら言葉を選んで説得したように、そこにはエンパシー(他者の靴を履いてみること)の介在があったのは間違いない。
この1975年のストから5年後、アイスランドでは世界で初めて民主的に選出された女性の大統領が誕生している。
まさに、千里の道も地べたから。シスターフッドとは共謀することだ。互いに他者の靴を履きながら、足もとからつながって一緒に企む。「女たちのストライキ」前夜にアイスランドの少女たちが感じた興奮は、その共謀のワクワク感だったに違いない。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。
SOURCE:SPUR 2022年4月号「ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY」
illustration: Yuko Saeki