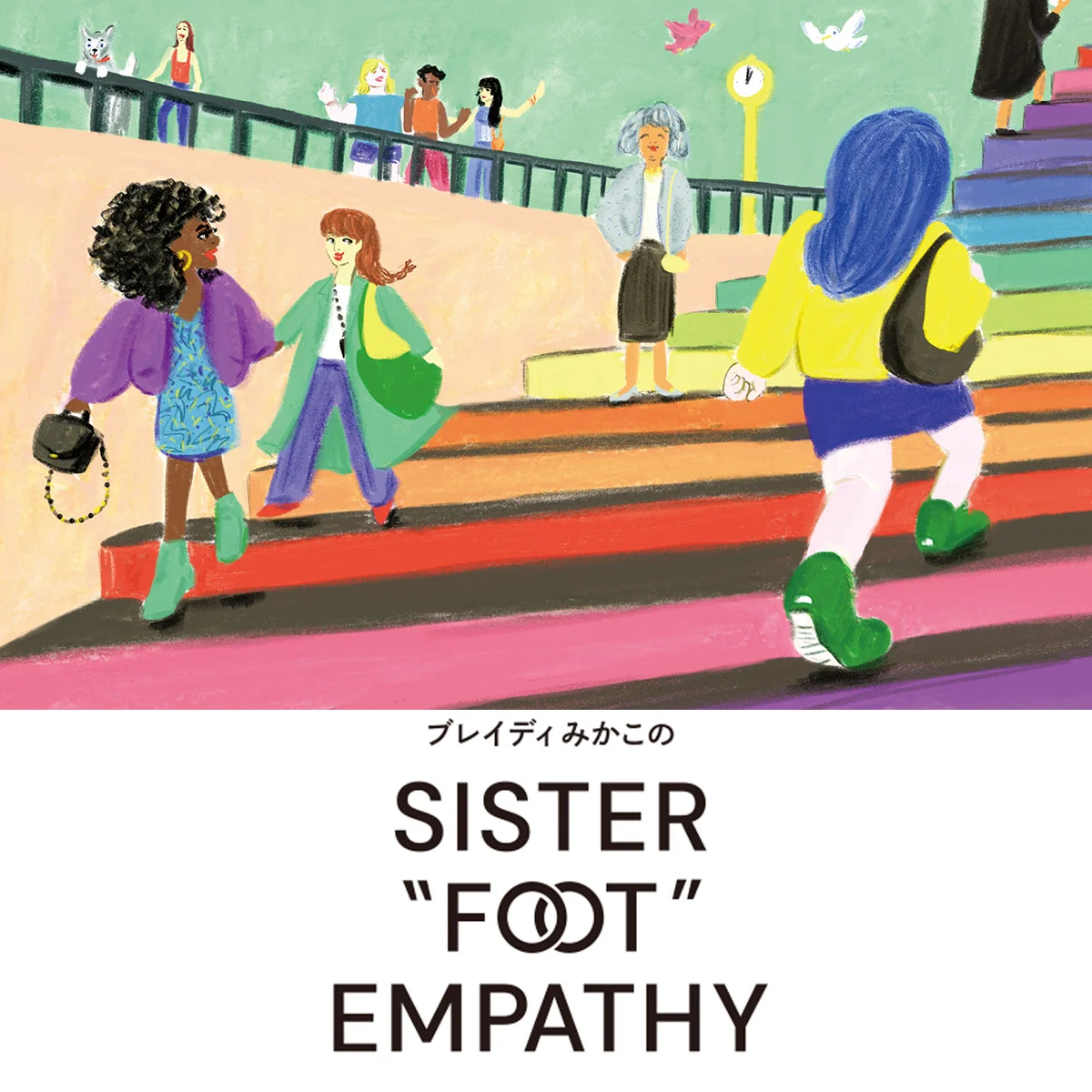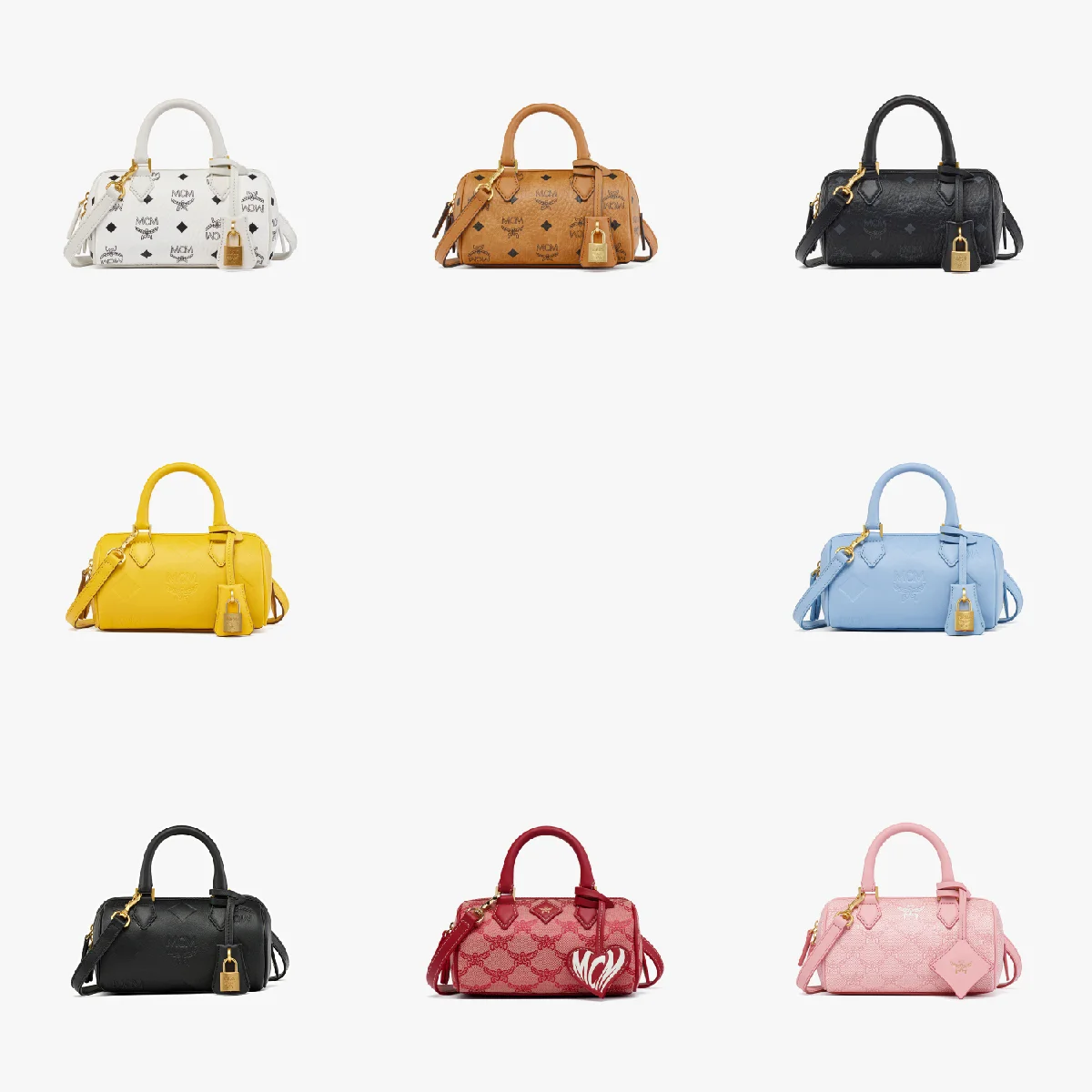"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。

ブレイディみかこライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。
ポリティカル・コレクトネスに反する言葉には、ぐるっと一周回って使ってもOKになるものがある。たとえば、その代表的なものが「クィア(queer)」だ。言葉そのものの本来の意味は「奇妙な」「不思議な」であったが、やがてそれが同性愛者への侮蔑語として使われるようになってしまった。しかし、1990年代に入ると、セクシュアル・マイノリティの一部の人々が「queer」という言葉を自分たちの手に奪還し、自己肯定的に進んで使ってやろうというラディカルな運動を精力的に展開するようになる。そのおかげで言葉のイメージが徐々に変化し、現代では「クィア映画祭」「クィア・スタディーズ」というように、公に使っても問題視されない言葉になっている。
そして現在、こうした言葉の一つになるのかとメディアを騒がせているのが「bimbo」だ。TikTokで展開されている「bimbo」復権運動が話題になっているのである。もともとは「外見はいいが知性のない女性」とか「浅はかで浮気な女性」とかいう意味で使われてきた言葉で、「blond bimbo」のようなステレオタイプ化された表現が多く、女性蔑視的とされてきた。ところが21世紀の今、「bimboという言葉をミソジニスト的文脈から取り返そう」と訴えるムーブメントが登場し、Z世代の注目を集めている。
リーダー的存在であるクリッシー・チュラペッカは、新しい「bimbo」の定義を「胸を出すのが好きな左派」とユーモアたっぷりに語っている。胸の谷間を強調する服を着て、金髪の長い髪をポニーテールにして目尻を跳ね上げたアイメイクを施し、絵に描いたような「blond bimbo」を演じながら、彼女たちは動画で独自のbimbo哲学を語る。新たなbimboたちはLGBTQやブラック・ライヴズ・マターとも親和性が高く、すべてのジェンダー、すべての人種の「超フェミニンなもの」を愛する人々を迎え入れるという。だが、一見すると非常に男性好みの格好をしているため、動画で彼女たちが政治的主張を始めると混乱してしまうのか、ストレートの男性から意地の悪いコメントが寄せられることが多いらしい。
「~はこういう服装をしているはず」という固定観念は、ドレスコードに似ている。医師はこういう服装をしているはず、政治家はこういう服装をしているはず、ラッパーはこういう服装をしているはず。わたしたちの頭の中にはいつしかそういうドレスコードができ上がっていて、その枠からはずれる人が現れると混乱し、自分の中の秩序が乱されてしまう気になる。だから、「自分の理解の範疇を超えないでくれないか」という気分になり、新たなbimboたちを叩く男性たちが出てくるのだろう。
彼女たちが挑戦しているもう一つのドレスコードは、「フェミニストはこういう服装をしているはず」という概念だそうだ。ピンク色のガーリーな格好をしたり、体の線の出る超セクシーなミニドレスを着たりしてもフェミニストでいられるというのが新たなbimboたちの主張だ。知的に見える服装をして女性であることを強調しない古いタイプのフェミニストのドレスコードにあらがう理由は、「フェミニズムに誰でもアクセスできるようにするため」だという。マリリン・モンローやバービー人形も参加できるフェミニズム。そしてセックス・ワーカーや、整形手術を受けたり、ダイエットしたりする人もアクセスできるフェミニズム。そんなイメージだろう。
フェミニストのドレスコードは存在しないということを、よりラディカルな形で表現しているZ世代のbimboたちの動画を見ていると、思い出すのは90年代に一世を風靡した英国のガールズ・グループ、スパイス・ガールズだ。いまや「ヴィクトリア・ベッカムが在籍したグループ」としてしか知らない人々も多いが、全盛期の彼女たちは英国では単なるアイドルを超えた存在だった。実際、いま英国で活躍している30代の女性のライターたちには「スパイス・ガールズでフェミニズムに目覚めた」と公言する人が何人もいる。
スパイス・ガールズの5人組は、当時、英国中の小学生の女子たちを熱狂させた。ファンキー・ヤンキー系のスケアリー・スパイスにガーリーでブロンドのベイビー・スパイス、上から目線のモード系ポッシュ・スパイスに体育会系のスポーティ・スパイス、そしておきゃんなストリート・ガールのジンジャー・スパイス。5人のスパイスたちは、それぞれまったく違うクラスターを代表する女の子たちだった。あの頃、スパイス・ガールズの人形を手にし、スパイス・ガールズのイラストがついたバッグを手にストリートを行き来する子どもたちを見ていてわたしが気づいたのは、あの子たちは、それぞれのお気に入りのスパイスだけでなく、5人のスパイスたちの友情を崇拝していたということだった。ふつうだったら友達になりそうもないし、出会うことすらなさそうな、ファッションも趣味趣向もバラバラに見えるスパイスたちが、なぜか仲よさそうに肩を抱き合い、一緒に歌い踊っている姿は少女たちに勇気と希望を与えたのだ。
しかも、彼女たちがスローガンとして使った言葉は「ガール・パワー」。スパイス・ガールズのファンの小学生たちは、女子が連帯して何かをすることを「ガール・パワー」と呼ぶのだと思っていた。だからこそスパイス・ガールズの解散が発表されたとき、幼いファンたちは泣き叫んで悲しんだ。ソロになったスパイスなんてどうでもよかった。少女たちは5人が一緒にいる姿を見たかったのである。
スパイス・ガールズは、これからの女性の連帯は「こういう人はフェミっぽくない」とか「あの人はダサい」とかいう条件つきのものであってはいけないという、難しい言葉で言えばフェミニズムの包摂性の概念を小学生の少女たちの心に焼きつけたのかもしれなかった。
「所詮は大人たちによってつくられたグループ」と当時はいわれたスパイス・ガールズだが、差異を持つ女性たちのエンパシーによる連帯のイメージを子どもたちに広げた功績は大きかったと思う。フェミニズムのドレスコードが存在しないように、シスターフッドのドレスコードは、むしろ「差異万歳!」なのだから。
SOURCE:SPUR 2022年8月号「ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY」
illustration: Yuko Saeki