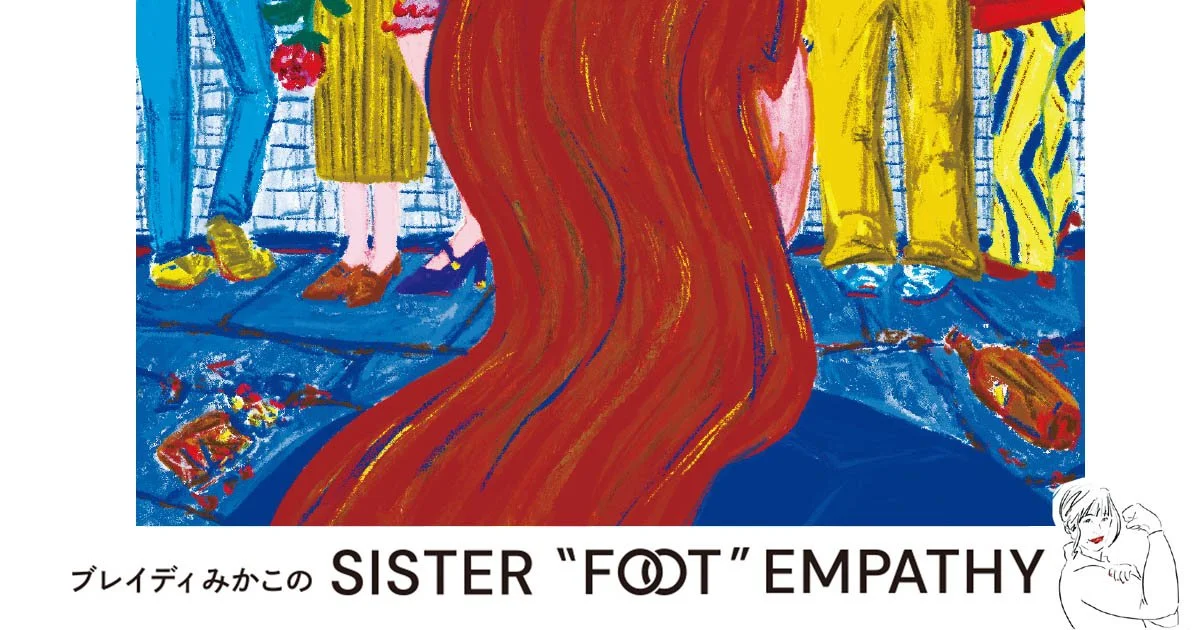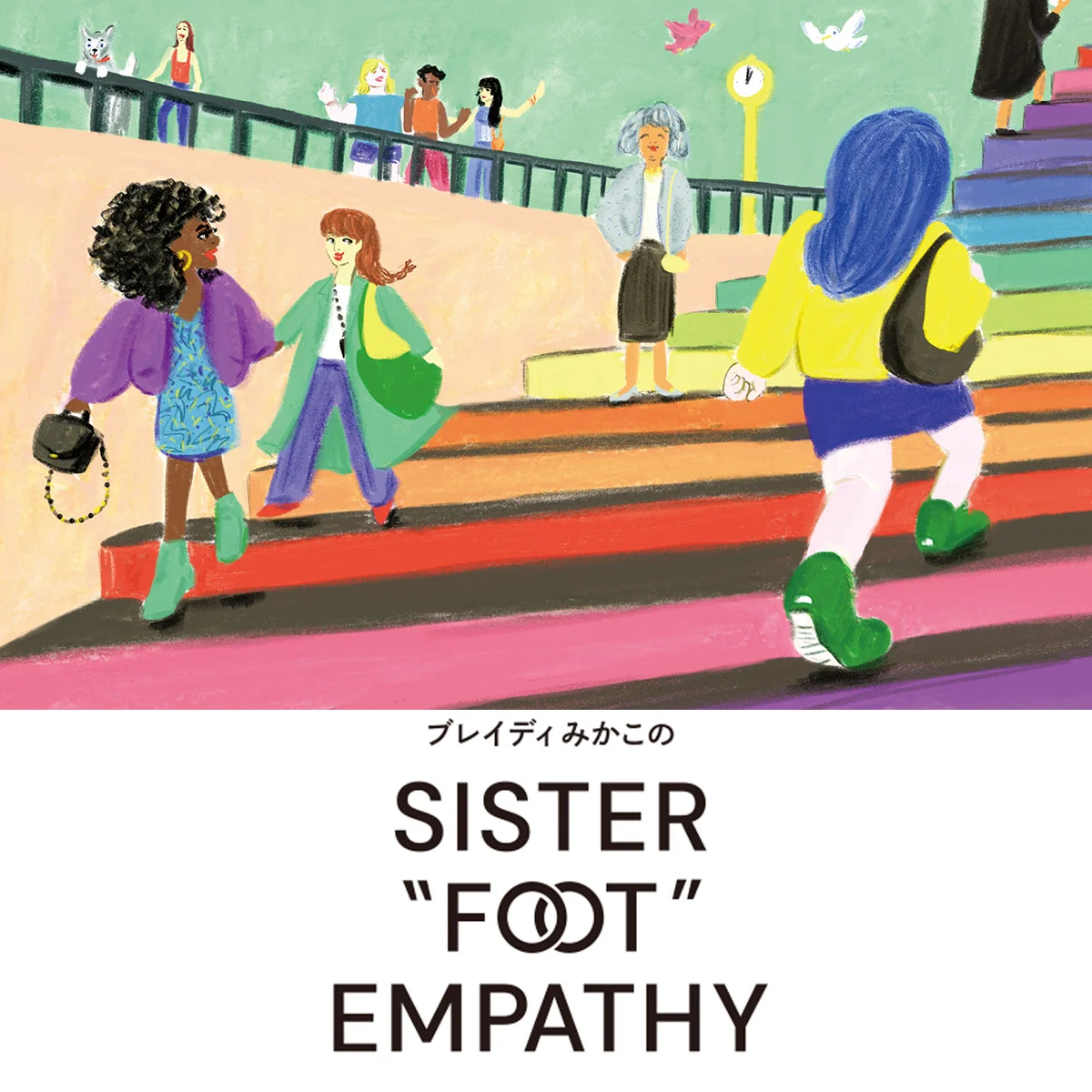"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
ブレイディみかこ
ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。
数年前に歯の治療をしていた頃、歯科医院の待合室でよく顔を合わせた日本人のおばあさまがいた。60代ぐらいにしか見えなかったが、一度だけ戦時中の経験を話されたことがあったので、もしかして80代?とも思った。いかにも英国の上品な老婦人というようなファッションに身を包んだ彼女は、日本語を忘れているらしく、「ごめんなさい、ここからは英語でしゃべらせて」と言って、ぶわーっと英語でしゃべり始めることが多かった。でも、ぽつり、ぽつり、と日本語の表現が断片的に交じるときがあり、自分でもまだ日本語を覚えていることに驚き、そのたびにうれしそうにほほえんでいらっしゃった。
で、このおばあさまから聞いた身の上話が、すべて本当だとしたら、波乱万丈すぎるのだった。話されたことを全部覚えているわけではないが、確か、10代の終わりの頃に留学か何かで英国に来て、英国人の青年と恋に落ちた。でも、やがて彼女が日本に帰る日がやってきた。いよいよ涙の別れを告げるとき、小高い丘の公園の木の下で、恋人たちはこう約束したのだった。3年後の同じ日に、この場所で必ず会おうと。
なんで3年後だったのかは覚えていない。何かの事情があったんだろう。離れ離れになった二人は文通を続けた。いまのようにメールやSNSですぐに返事が送り合えるわけではない。当時は英国から郵送した手紙が1週間で日本に届く時代でもなく、海を渡る途上で紛失されることも少なくなかった。だが、それだけにドラマティックで熱い文通が続き、おばあさまの恋心は燃え盛ったらしい。
3年後、彼女は家族の反対を押し切り、なけなしのお金をはたいて船に乗り英国に向かった。日本を出る前に届いた彼からの手紙には「必ず君を迎えに行く」と記されていたそうだ。
が、約束の場所に彼は現れなかった。何時間待っても、大粒の雨が降り始めても、恋人は来なかったのである。
まあ、よくある話だ。
と思いきや、おばあさまの人生はそこからが「よくある話」ではなかった。彼が迎えに来ることを疑わず、文無しで渡英していたので、日本に帰ろうにも船賃もない。そこで最初に目についたパブに飛び込み、「働かせてください」といきなりランドレイディ(おかみ)に頼んだ。ずぶぬれで旅行鞄を提げて入ってきて、片言の英語でそんなことを言う日本人の女の子におかみも驚いたろうが、一生懸命に英語で事情を話すと、「男なんて信じるからよ」とおかみは首を振り、とにかく今夜は2階に寝なさいと言ってくれた(むかしの英国のパブはだいたい2階が旅宿になっていた)。宿賃はいらないから、全室のシーツを替えて掃除をしてくれないかと言われたらしい。
これがきっかけで、おばあさまは結局、パブの2階の旅宿でメイドとして働きながら船賃を貯めることになった。だが、日本で習った生け花の腕を活かしてパブの店内に花を飾ったらそれが近所のホテルの支配人の目に留まってスカウトされ、今度はそのホテルで働いていたときに地域の事業家に見初められて結婚し……、と、まるでわらしべ長者のような経緯で英国に住み着いた人なのだった。
こういうのを運というんだろうな、と思っていつも話を聞いていた(またこれが、会うたびに同じ話をされるのだった)が、「ラッキーでしたね」と言うと、彼女はきりっとした顔つきでこう言ったことがあった。
「運だけじゃない。自分をオープンにしてたからです。すると未来のほうからこっちにやってくる。若くてどん底にいたときは、生き延びるために自分を開くしかなかったから最強だった」
もし彼女が80代だったとしたら、このわらしべ長者ストーリーは1950年代後半から60年代ぐらいの話だ。わたしが若い頃、日本でバイトを掛け持ちしてお金を貯めては渡英してしばらく住み、また帰って働いては渡英するという暮らしをしていたのは80年代だったけど、はっきり言って、あの頃だって単身で英国に来ていた若い日本人女性には猛者が多かった。
「英国に憧れていたけど、いざ住んでみると年中暗くて嫌になった」と言って英国を去り、イタリアのトマト農家で働いているというポストカードが届いたかと思ったら、今度はスペインでワインを造っているという手紙が来た女の子もいた。ビザが切れても滞在していたのが当局にバレて強制送還されたはずだったのが、なぜかまたリバプール港から再入国を果たしてロックバンドでドラムをたたいていた女の子もいた。
わたしが貧乏だったから、知り合う子たちもお金のない女子ばかりだったが、なんかみんなたくましかったというか、しぶとかった。でも一見するとそんなにゴリゴリに押しが強そうなタイプではなくて、歯科医院で会ったおばあさまが言っていたように「自分をオープンにして」流れに任せて生きている感じのキャラだった。
おばあさまが若かった時代にせよ、80年代の猛者たちの時代にせよ、いまのようにネットで前もって英国の情報が手に入る時代ではなかった。どこに行けば住居や仕事が見つかるとか、どこに行けば安い食事にありつけるとか、そういうことを検索して下調べすることが不可能だったから、ほとんどのことは出たとこ勝負で、毎日がイチかバチかのギャンブルだった。
最近、日本の若い女性から「不安でたまらない」という悩みを聞かされることがある。これだけ便利になったのに、出たとこ勝負の時代のほうがシスターたちは楽天的だったような気がする。たぶんそれは、ギャンブルに失敗はつきものだと知っていたからじゃないだろうか。逆に、失敗しないように検索を重ねて情報を最適化し、たった一つの正しい答えを見つける作業は、自分の身に起こることの可能性を狭めていくことでもある。「自分を開けば未来のほうからやってくる」というくだんのおばあさまのモットーとは逆行している。
「不安です」と日本の若い女性に言われるたびに、たくましい足で国境を越えたシスターたちの話をしたくなる。ウザいかもしれないし、時代が違うと思われるかもしれない。だけどシスターフッドは世代をつなぐ縦の友情でもある。現在の常識という固定観念を壊す手伝いをしてくれるのは、時に昔の人の話だったりするのだ。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。