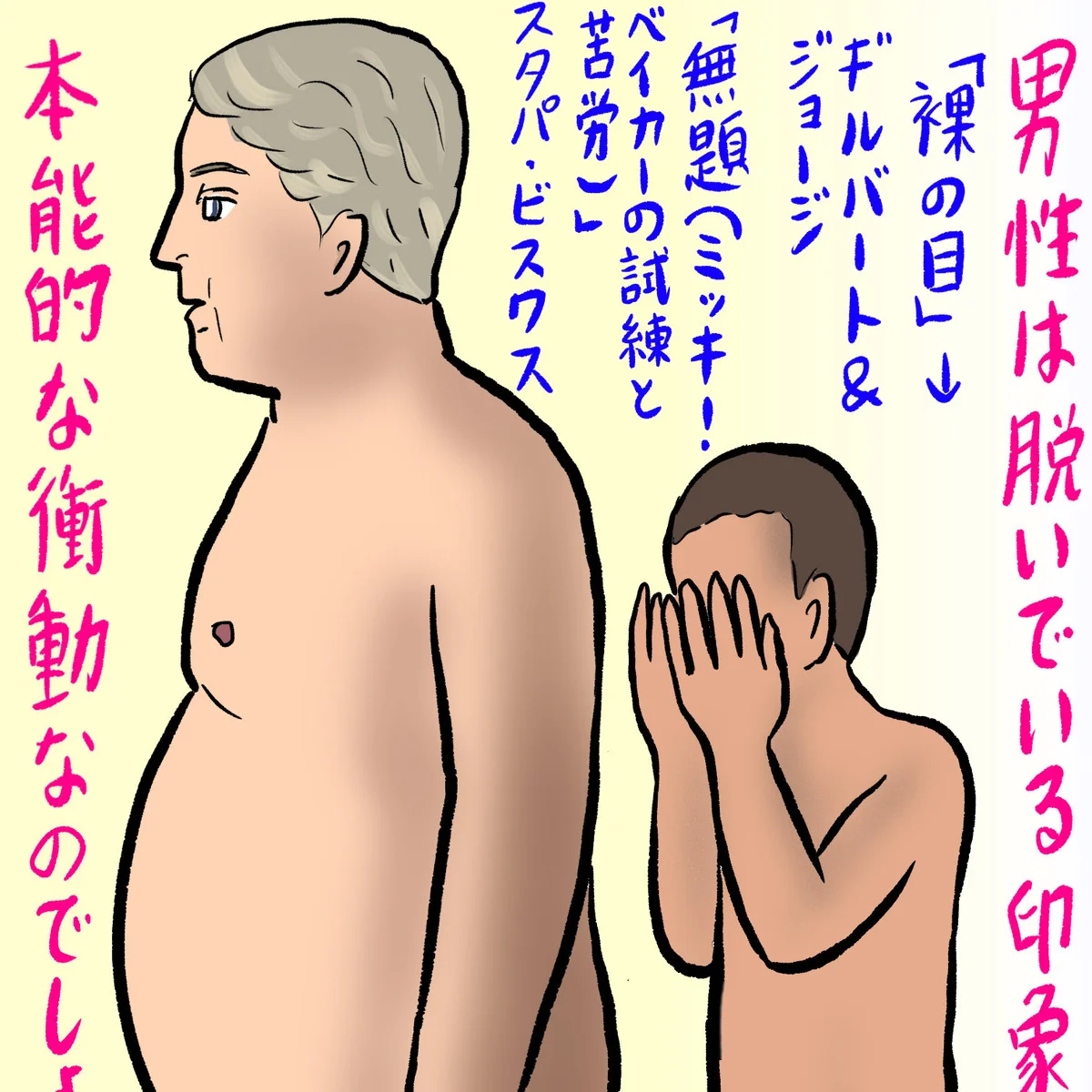恋に、性に、生きることすべてにわがままでいるってどういうことなの?
でも、野枝にそんな発想はありはしない。かの女は、素で約束そのものを破棄しようとしていた。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないというきまりごとなんて存在しない。それはどんなに良心的にかわされたものであったとしても、ひとの生き方を固定化し、生きづらさを増すことにしかならないからだ。平等になって男のような女になることも、女らしい女になることも、めんどうくさい。けっきょく、よりよい社会なんてないのである。約束を交わして生きるということは、なにかのために生かされているのとおなじことだ。やりたいことだけやって生きていきたい。ただ本がよみたい、ただ文章がかきたい、ただ恋がしたい、ただセックスがしたい。もっとたのしく、もっとわがままに、ぜんぶひっくるめて、もっともっとそうさせてくれる男がいるならば、うばって抱いていっしょに生きる。不倫上等、淫乱よし。それが人間らしくないといわれるならば、妖怪にでもなんにんでもなってやる。欲望全開だ。
大変な本が出てしまった。栗原さん、文章うますぎでしょう。アジテーションがむちゃくちゃうまい。しびれる。アナキストを名乗り、はたらかないでたらふく食べる生き方を提唱している栗原さんと、お金と買い物が大好きな私ではまったく方向性が違うはずなのに、読んでいるともう、すっかりその気になってしまう。なにもかもかなぐり捨てて自由に生きたいと思ってしまう。
その栗原さんの文章で描かれるのが、伊藤野枝だ。これはやばい。やばい。やばい。三回書くけどやばすぎる。面白すぎて死にそうだ。野枝そのものが面白すぎるしすごすぎるのに、それを栗原さんが書くんだからもう5倍増しぐらいのインパクトになっている。書店で見かけたら周りの本を全部なぎ倒したくなる。「今読むべき本はこれだけでいい!」と叫びたくなる。それぐらい、むちゃくちゃに面白い。伊藤野枝とか思想とか政治とかなんも知らなくていい。知らなくてもむちゃくちゃに面白く読める。保証する。
本書は伊藤野枝の生涯と思想を辿るものだが、伊藤野枝の思想は、フェミニズムとは違う。とにかく、ことごとく「約束事」や「取り決め」を徹底的に嫌い、はねのけた人生だ。大杉栄と恋に落ちて自由恋愛(大杉には複数の女性がいた)とかやっているが、大杉が自由恋愛の条件とか言い出してルールを提示すると、もうダメだ。結婚制度を否定して自由恋愛だとか言っても、またルールかよ、と。ルールというのは、結局、常識とか道徳とか、法律とかと同じじゃねえか、自由とか言っといて縛るのかよと、そういうことだ。私を縛るものは、何人たりとも許さない、みたいな人生である。
実は私はこの本を読むのが怖かった。だって、約束がないと怖い。なにかが奪われそうで怖い。失いそうで怖いから約束が欲しい。そういう自分の弱いところを徹底的にぶっ叩かれそうで、本当に怖かった。でも、そうじゃなかった。真にひとを力づけるもの、勇気づけるものとは、そういうもんじゃないんである。真にひとを力づけるものは、こっちを叩きのめしてなんかこない。好きなように生きたいだけでなにが悪いんだ、と思う伊藤野枝は、ひとのわがままにも肯定的だ。どう生きてもいい、ただ、私に何かを押し付けるなと思っていただけのことだ。それだけのことで、伊藤野枝は政府に殺されている。こっちのほうがよっぽどむちゃくちゃだけど、そう言えるほど今が自由で豊かですばらしいかと訊かれると、なんだか全然、そうは言えない。秩序だらけの現代にドロップキックしたあとに一斗缶で頭をガーン! と殴りつけるような、最高の本だ。こんなに面白くていいんだろうか。面白すぎるせいでだまされちゃってるんじゃないか、私は。それくらい魅力のある、おそろしい本でもある。
 「村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝」(栗原康/岩波書店)
「村に火をつけ、白痴になれ 伊藤野枝伝」(栗原康/岩波書店)

ライター。『女子をこじらせて』(ポット出版)で書籍デビュー。以後、エッセ イを中心にカルチャー系の分野でも執筆。近著に『東京を生きる』(大和書 房)、『自信のない部屋へようこそ』(ワニブックス)がある。