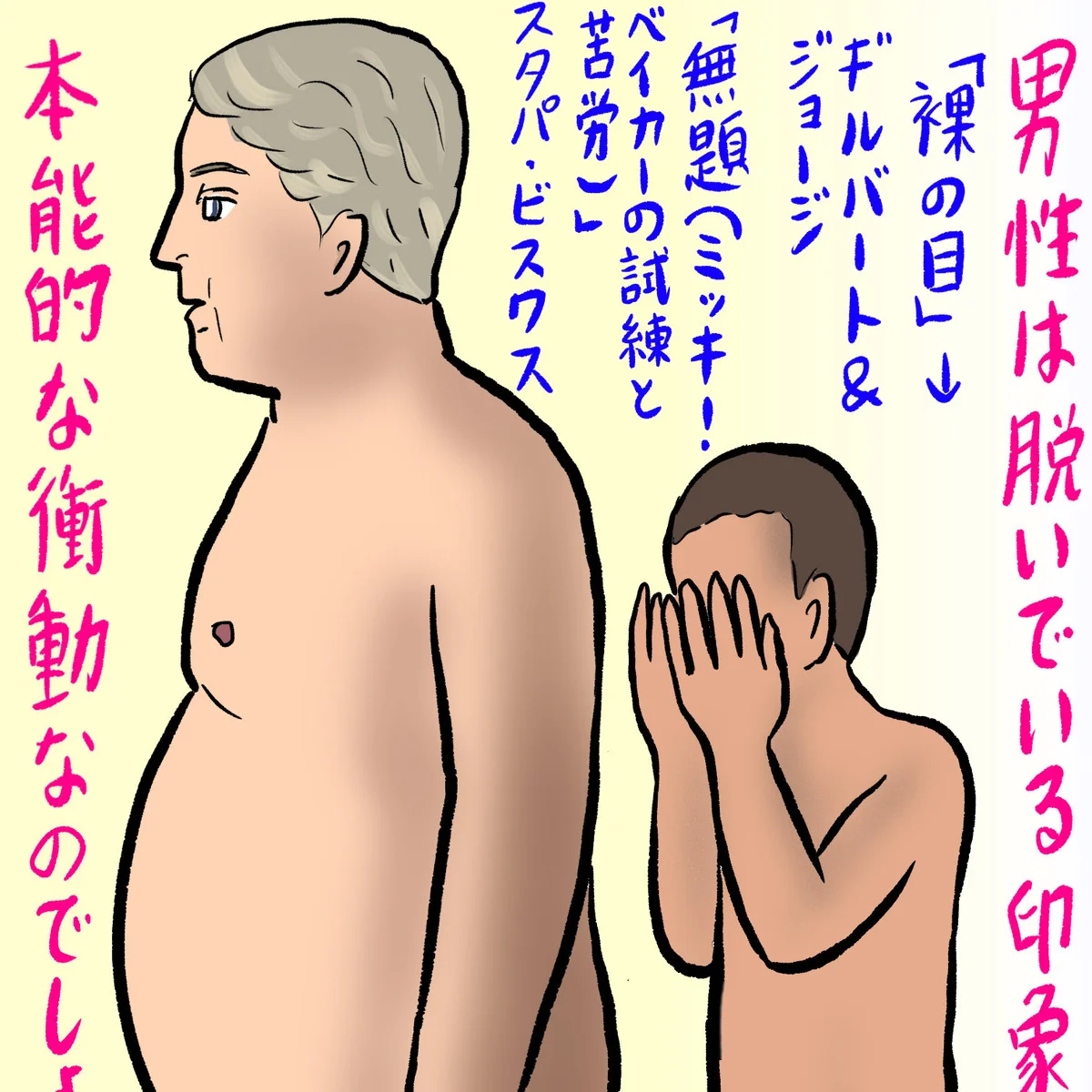人口の半分が女性なのに、女性であることが特殊になってしまう不思議
 左から、蜷川実花さん、寺島しのぶさん、スプツニ子!さん
左から、蜷川実花さん、寺島しのぶさん、スプツニ子!さん
2017年に巻き起こった「#MeToo運動」をきっかけに、映画界では性別に囚われない人材活用の重要性がますます叫ばれている。たとえば2018年にフランス国立映画センターに登録された映画のうち女性監督の割合は23.3%、そして同年封切りの日本映画における女性監督の割合は7.01%にとどまる。
映画界をとりまく現状について、蜷川さんはこのように語った。「私が初めて映画を撮ったのは、2007年に公開された『さくらん』でした。当時は、どのインタビューでも常に“女流”という言葉がついてまわっていたのを覚えています。ですが、今年『Diner ダイナー』と『人間失格 太宰治と3人の女たち』の2本の映画を公開しましたが、“女性”という切り口で取材されたことはありませんでした。少しずつ変化している実感はあります」。
1992年に文学座に入団以来、俳優を続けている寺島さんは、「20代の“かわいい文化”が日本にはあり、大人の女性の話が映画として成立しづらくなっているのを感じます。私自身、ある時から圧倒的に母親役が増えました」という。また、映画界では圧倒的に男性のスタッフが多いことについては、「女の子らしい女性や男っぽい女性がいるように、男性にもいろんなタイプの男性がいます。性別で判断をするのではなく、いろんな人のパワーを結集して作品を作るというのが理想ですよね」と語る。

今年、カンヌ国際映画祭でも「ウーマン・イン・モーション」のイベントに参加したスプツニ子!さん。「#MeToo運動の影響もあって、映画界に限らずさまざまな場面で女性が声を上げられる雰囲気ができてきました。ソーシャルメディアが一般化し、誰でも発言できる状況が生まれたことはすごく良いことだと思います。今までは表に出てこなかった複雑な女性像を目にする機会が増えることにつながるからです。人口の半分が女性にもかかわらず、映画の担い手に男性が多いというのは、女性の気持ちをストーリー化できてこなかったということ。そうなると必然的に女性が主役の作品が少なくなりますよね。女性であるだけで“ニッチ”になるというのは、本来おかしなことなんです」。
バリバリ働きたい時期と子どもを産む時期が重なる悲劇を解決するには?

映画界で働く女性が少ない理由のひとつに、映画技師として独り立ちするタイミングと妊娠・出産の適齢期とが一致してしまうことがある、と蜷川さん。「現状では“稼いで雇う”という解決策が最も現実的。私は出産の3日前まで撮影をし、産後1か月から現場に戻りましたが、家事や育児の代行を頼むことで仕事と子育てを両立してきました。あとは、どんな男性と結婚するかでしょうか。一緒に働くスタッフには、女性が働いて男性が育児をしている家庭も多いんです」。
寺島さんは「現在7歳になる息子がいますが、とにかくいろいろなものに追われています。もっと仕事に時間を費やしたい思いもありますが、今は限られた中でやるしかない」という。蜷川さんも「何かが降りてくる瞬間を待っているゆとりはないんですよね。生活をすべて捨てて、クリエイションをしている人とどう闘えばいいのか、と思うことはあります。ですが、自分は限られたなかでクリエイションをしているのだというストレスを糧にして、高く飛べるように頑張るしかありません」とその覚悟を語った。
一方、スプツニ子!さんは「私は今34歳で、仕事大好き、クリエイション大好き、やりたいことがいっぱいある。そのため、なかなか子どもを産むという選択に踏み切ることができません」と率直な思いを話した。「人類はさまざまな課題をテクノロジーやサイエンスで解決してきましたが、今まで妊娠・出産の分野は手つかずでした。たとえば、私は今年卵子を26個凍結したのですが、このような卵子凍結のことももっと早く語られるべきことだったと思います。妊娠・出産の概念やタイムリミットがあることへの解決策を、作品で表現することも含めて探っていきたいですね」。
ジェンダーレスな視点を持てたのは、育った環境のおかげ

話題は、自分自身のキャリアの追求から、子どもをとりまく環境へと及んでいく。
「子どもにとって環境がすべてだと思います。少なくとも私はそうでした」と寺島さん。「歌舞伎界という特殊な環境ということもありますが、5歳の時に弟が生まれ、一斉に家族の目が弟に向かいました。男子が求められていたんだということを目の当たりにして、そのことに対してずっとコンプレックスも感じていました。ですが、19歳で蜷川幸雄さんの舞台『血の婚礼』(1993年)に出演した時に、蜷川さんから『そのコンプレックスはいいものになるから、捨てずに技術を磨いていけ』と言われたんです。この言葉にとても助けられたので、本当に感謝しています」。
そんな蜷川幸雄さんを父に持つ蜷川実花さん。「我が家は、母が女優で父よりも稼いでいたので、0歳から5歳まで父に育てられました。常に父から『男を通じてしか社会と繋がれない女になるな』と言われ、経済的にも精神的にも自立した女性になれ、と刷り込まれていたように思います」。
スプツニ子!さんも、共働きの家庭に育った。「中学は日本の学校に通っていましたが、お弁当はいつもリンゴやピーナツバターサンド。イギリス人の母からは『みんなのお母さんは豪華なお弁当を作っているけど、私は大学でバリバリ教えている超カッコイイお母さんなの。大学教授の女性なんていないんだから。カッコイイ母に育てられてあなたはラッキーなのよ』と毎日言われていたので、友人のお弁当を見てもなんとも思わずに育つことができました。自信たっぷりに母が言っていたので、信じられたんだと思います」と子ども時代の思い出を語った。
これからの社会に向けて

例えば学校や会社の中で、あるいはTVのコマーシャルを観て。ジェンダーギャップを感じずに育った女性はいない。おそらく、男性も。さまざまな先人たちの闘いの積み重ねと、#MeToo運動をはじめソーシャルメディアの発達によって個人が自分の言葉で自由に発言できるようになったことで、今ようやくその問題の本質が可視化されつつある。「ウーマン・イン・モーション」のイベントでは、寺島さん、蜷川さん、スプツニ子!さんが、現状やこれからの社会に向けて一歩踏み出すヒントを語ってくれた。誰にとっても理想と思える社会が一日でも早く実現するよう、3名の言葉を一人一人が行動を起こすためのエネルギーにしていきたい。私たちはまだ、ジェンダーギャップのない社会へと舵を切ったばかりなのだから。