ロサンゼルスでの大規模な回顧展が予定されている日本人アーティスト、奈良美智。自身が音楽から得たものについて話してくれた
日本最大の島、本州の最北地で育った奈良美智は、その耳を通して、外にはもっと広い世界があることを知った。それは80年代後半、彼が著名な美術大学「デュッセルドルフ美術アカデミー」で絵画を学ぶために渡独した何年も前であり、また2019年、サザビースで彼の絵画作品《Knife Behind Back》(2000年)が約2,500万ドルで落札される何十年も前のことだ。

奈良美智と、“大きな頭の女の子”を描いた彼の作品《Miss Moonlight》(2020年)。栃木県にある彼の自宅スタジオにて撮影
60年代から70年代、当時、彼はいわゆる“カギっ子”で、午後になると旧日本帝国陸軍基地の敷地に放置された弾薬庫でのんびり遊んで過ごすような子どもだった。夜は、家にあったラジオや8歳の時に自分で作ったもので、米軍が駐屯する地域に音楽やニュースを配信するアメリカのラジオ放送「FEN(米軍極東放送網、現在はAFNに名称改変)」を聴くことに熱中した。その放送を通じて出会ったのが西洋の音楽だった。フォーク、そしてロック。英語という奇妙な外国語によるその歌声は、歌詞が理解できなかったため、彼にとってギターと一緒に発せられるもう一つの音に過ぎなかったという。そうして、信じられないことに、奈良は60年代半ばのフラワーチルドレンたちの平和を求める音楽から、70年代後半の恍惚と激しく打ち鳴らすパンクロックまで、西洋のポップミュージックの進化を貪欲なまでに目の当たりにしていったのであった。
レコードを集めていた当時(最初に買った洋楽シングルは、1967年にリリースされたビージーズの『マサチューセッツ』)、「素晴らしい芸術作品」と思ったアルバムジャケットを彼は細部まで食い入るように観察した。特に気に入っていたジャケットは、ジョニ・ミッチェル自身が描いたと知って感動したという『かもめの歌』(1968年)と、野の花を刺繍したようなルーク・ギブソンの『アナザー・パーフェクト・デイ』(1971年)。こういった音とビジュアルが組み合わさったクリエーションは、奈良の想像力を鍛え上げ、のちに大人になり、奈良自身が文化的アイコンになったのち、少年ナイフやR.E.M、ブラッドサースティ・ブッチャーズといったバンドにジャケットのアートワークを提供していくことに繋がっていく。

奈良の制作スペース。左にあるのは彼の作品《Thinking at the Table》(2020年)
美大生だった90年代、奈良は自身のシグネチャーとなる作風を生み出した。このとき描き始めたのが、先日、ファイドン社から出版された本で“大きな頭の女の子”と紹介されている絵画である。そのアクリル絵の具で描かれたアニメ風のプロポーションの無邪気な人物は、一見、アメリカ的な“Twee(風変わりで魅力的)”と日本的な“kawaii(かわいい)”の両方の感覚に紐づいたもののように思えるが、それほど単純ではない。細長い切れ目状の口とティーカップの受け皿のような目。その顔は、相反する感情の交錯を強烈に放つ。日本の戦後美術の研究者である吉竹美香は「よく少女や子どもの肖像画だと言われますが、それらの作品は、実は(奈良の)自画像なのではないか、と私は思います」と言う。

奈良が描くキャラクターの多くは、花や楽器、さらに恐ろしいものなど、小道具を持っている

奈良はドローイングや彫刻も制作。彼の最も有名な作品シリーズは主にアクリル絵の具で描いている
奈良は、1995年、東京のスカイザバスハウスで開かれた個展『深い深い水たまり』で一躍注目を集めるが、その時までに、これらの架空のキャラクターはミューズとして奈良作品に欠かせないものになっていた。その後20年にわたって、彼は何度もそのキャラクターを描いてきた。たいていは、1.5メートルを超えるキャンバスに、濃い乳白色を背景にして。ある作品では、自身のデニムの上に鉛筆で、それらを10代の若者のように熱狂するジョーイやディー・ディー・ラモーンに変身させて描いている。奈良のいたずらっ子たちも豊かな音楽とともに生きてきたのである。ドラムを叩いたり、マイクスタンドをにぎったり。文字通りのパンクスではなかったとしても(しかし、彼らはしばしばそうであったが)、パンクロック的なアティチュードを示してきた。内巻きのカールヘアや赤ちゃん人形のドレスを着用しながらも、しばしば火のついていないマッチやピストル、のこぎりといった、不穏なシンボルを振り回し、彼らは“グレムリン・キューピー”になった。(続きを読む)
SOURCE:「Yoshitomo Nara Paints What He Hears」By T JAPAN New York Times Style Magazine:JAPAN BY NICK MARINO, PHOTOGRAPHS BY TETSUYA MIURA, TRANSLATED BY MASANOBU MATSUMOTO AUGUST 06, 2020
その他の記事もチェック
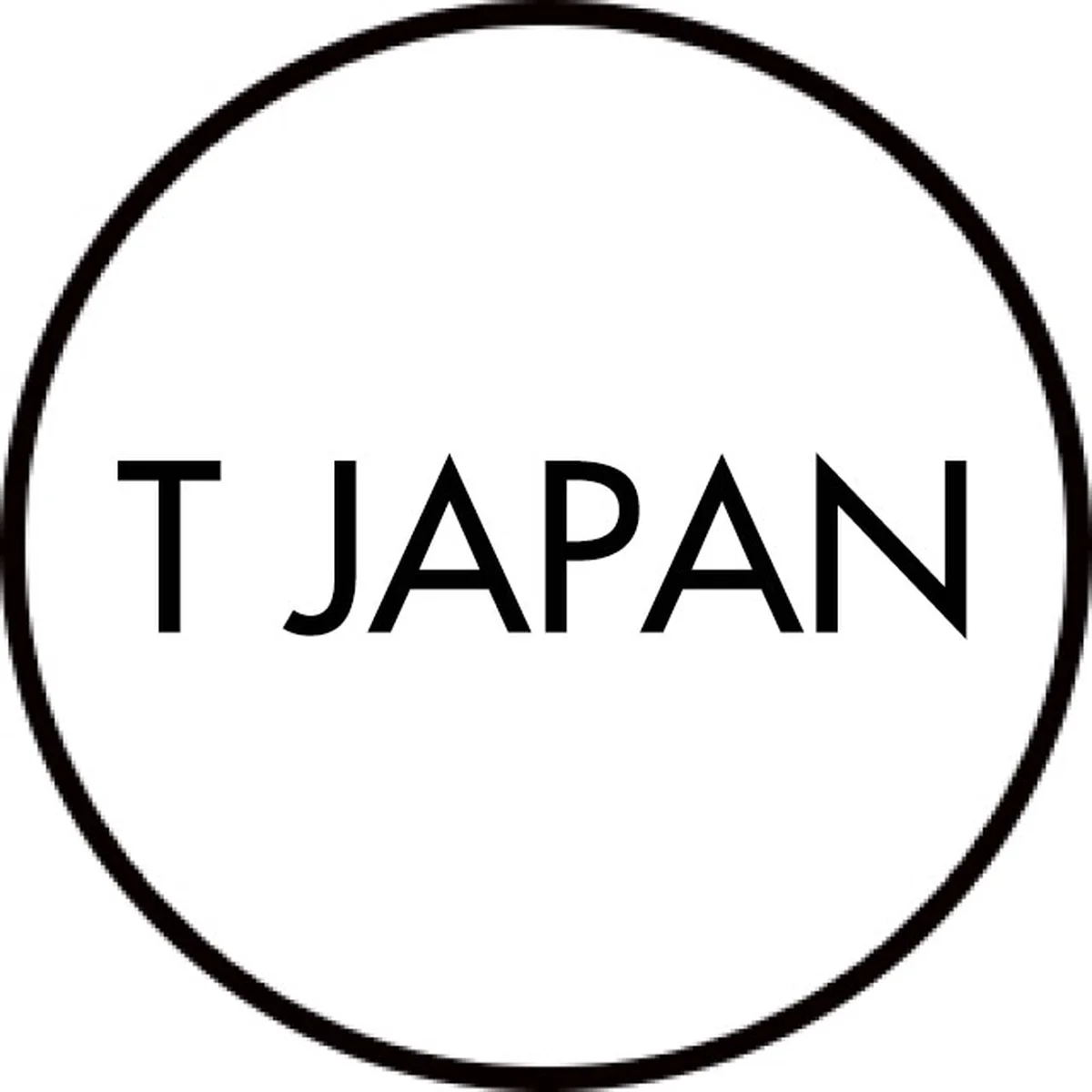
T JAPANはファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。
































