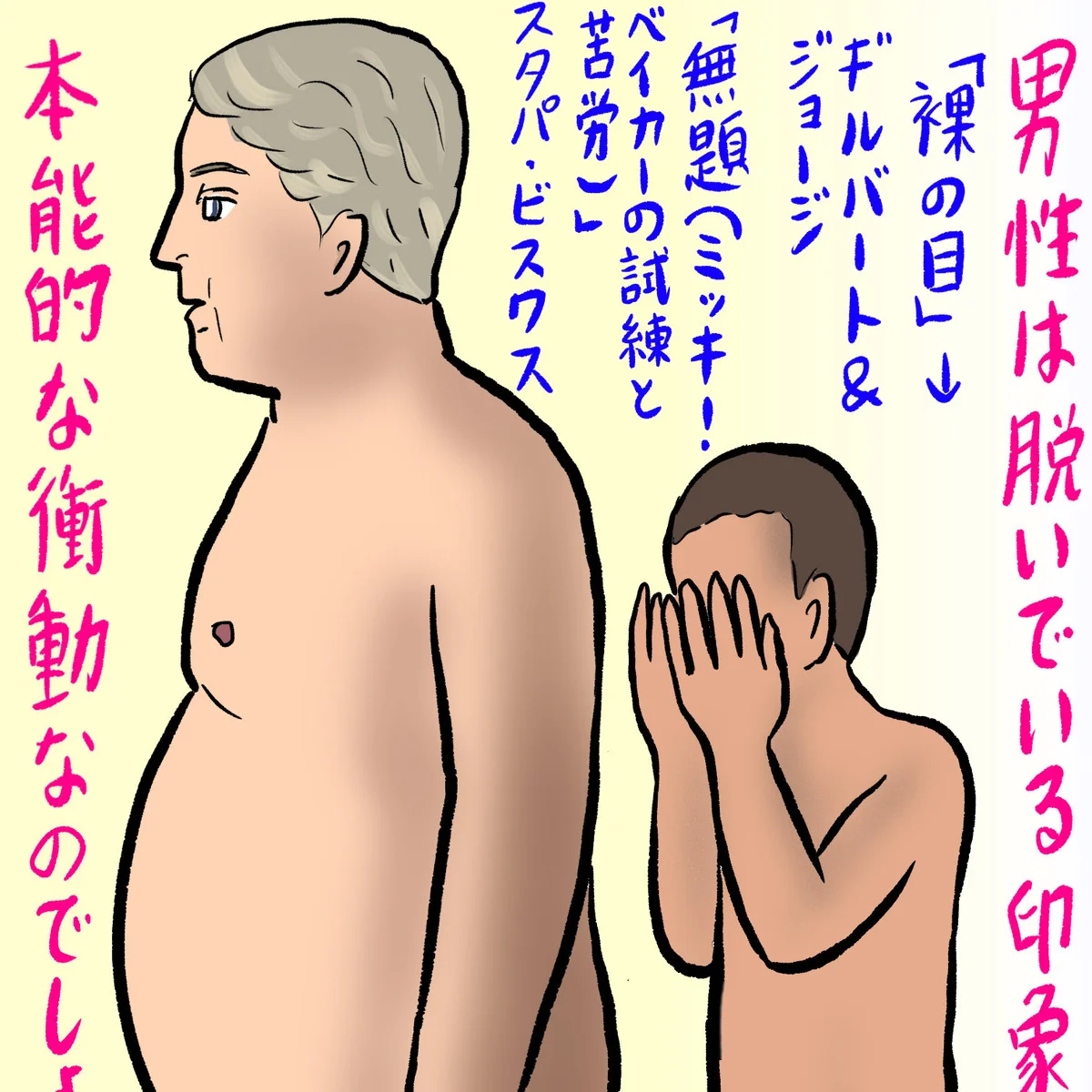多彩なジャンルで才能を発揮した、セルジュ・ゲンズブール。音楽と映画、スタイルについて、3人の識者の視点を通して理解したい
MUSIC: "雑食主義"な音楽性 Interview with立川直樹(プロデューサー)

プロデューサー、ディレクター、ライター。音楽から映画、美術、舞台まで活動は広範囲。1998年、1時間に及ぶコンピレーションアルバム『Une heure avec Serge Gainsbourg』(右・マーキュリー)を監修・編集。著作に『セルジュ・ゲンズブールとの一週間』(左・リトルモア刊)がある。
MOVIE: マルチな才能で音楽、俳優、監督まで By乗松美奈子(ジャーナリスト)
「"ゲンズブール&バーキン"の世界にどっぷりと浸かったのは、10代の終わり。昼間は大学に行きつつ、夜間に通っていたアートスクールでのフレンチ・カルチャー好きの友人と、夜な夜なホームシネマをしていました」。
こう語る乗松さんは、仕事でゲンズブール作品に触れる機会も多い。たまたまバレンタイン用商品の資料翻訳をした際に知ったのが、『スローガン』(’69)秘話。ブリジットに振られて不機嫌な彼は最初ジェーンをひどく嫌ったが、監督が企てた二人きりのディナーをきっかけに接近して恋に落ちた、という逸話だ。また同時に、見逃していた『Jane B. par Agnès V.』(’88)もチェック。アニエス・ヴァルダがジェーンに密着した、虚実が交錯するシュールな映画では、1987年2月にパリ・バタクランで開かれたジェーンの初めてのソロ・コンサートの前夜を収録。
「セルジュが『私とわたし(Le moi et le je)』を練習するジェーンについて指導するシーンが観られて、感動」

本誌でもおなじみ、上智大学卒業後、渡仏してパリ在住30年近くになるフリーのファッションジャーナリスト。ライフスタイルやアート、特にサブカルチャーにも詳しく、本テーマの取材と執筆を担当した。
FASHION: パリシックの基礎となるメンズアイコン By清水奈緒美(スタイリスト)

スタイリスト。ファッション誌の編集者を経て、2010年よりスタイリストとして独立。学生時代からフレンチ・カルチャーにも精通。ハイジュエリーやスカーフなど上質なもの選びの審美眼にも定評がある。