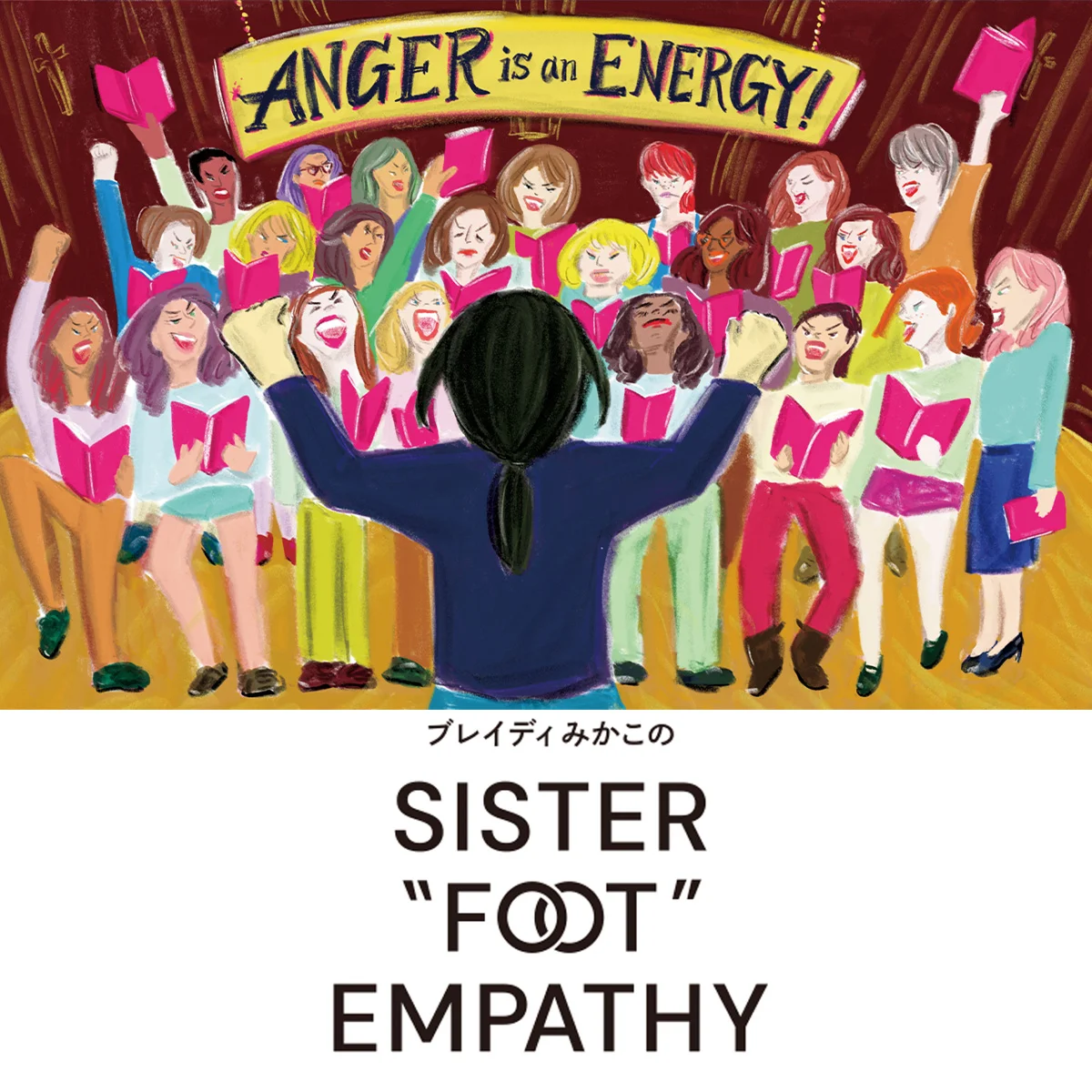海外の観客は、映画と一緒に呼吸していた

――映画祭は昨年の第69回ロンドン映画祭、第38回東京国際映画祭と回られましたが、海外の映画祭での印象はいかがでしたか?
「僕が最初に行ったのはロンドンの映画祭ですね。2,500人くらいかな、観客がいて。とにかくね、受けるんですよ。ものすごく。観客が映画の中に参加していく、という感じがあって、静かに観る、という感じじゃなかったです」
――どのシーンで反応が大きかったですか?
「どのシーン、というより、全体的に映画を楽しんでいる、という感じですね。ちょっとした仕草のシーンで笑いが起きたりして、『バーッ』と劇場内がわくところもある。静まり返って観る、というより、一緒に映画を体験している感じがありました。緊迫のシーンでも笑いが起きたりとか。あちらのお客さんは、本当に映画と一緒に呼吸しているんですよね」
英語のセリフも日本語のセリフも、本質は同じ

――英語のセリフのお芝居が、とても自然に聞こえました。準備はされたんですか?
「もちろん、英語のお芝居についてはコーチについていただきました。ポロポロと、いろいろ教えてもらって」
――どのくらいの期間準備されたんですか?
「どのくらい、と言われると、それなり、ですけどね。どれくらいやれば十分か、正直よく分からない」
――英語のセリフで苦労されたことはありますか?
「それは、もちろんありますよ。英語だけに限らず、日本語でも、いつも苦労しています」
――日本語と英語で、芝居の感覚は違いますか?
「発音とか、テクニカルなことは別にして、基本は同じです。人間の気持ちを表す仕事ですから。そこは、言語が変わっても変わらないと思っています」
「言えない」という地点から、芝居は始まる

――英語でも日本語でもお芝居は難しいとのことですが、往年の名優・喜久雄という役を演じてみて、気づいたことはありますか?
「いや、基本はいつもと一緒です。書いてあることを言う、それだけ。でもね、“書いてあることを言う”って、実はすごく難しい」
――難しい、というのは?
「人の書いたセリフを、そのまま言えばいいわけじゃない。セリフは、台本に書いてある時点では、まだ誰のものでもない。それを、自分の体を通して、相手に届く言葉にしなきゃいけない。だから、セリフをもらうと、そのセリフを探す旅に出る、という感覚になります。今喋っている言葉とは違うんですよ。こうやって会話している言葉じゃないから。台本に書かれたセリフですから、それは『言えない』のが当たり前なんです」
――「言えない」のが当たり前。
「そう。書いてあることを、『言えない』という地点まで行かないと、本当は始まらないんです。最近はね、若い人に、このことをちゃんと教えてくれる人が少ないんじゃないかな、とも思う。それがやっぱり日本と海外の違いでもある気がしますね。どんな仕事でもそうだけど、できると思ってやったらできない。そのできない、なんでできないのかを考えることから何かが始まるわけじゃないですか」
一つを選ぶということは、無限を捨てること
――キャリアを重ねても、答えは見つからないですか?
「答えはないですよ。やっているのは、無限にある中の一つを選んでいるだけ。一つを選んだ瞬間に、他の可能性は全部捨てている。それを分かった上で選べるといいんじゃないかな、と思います。人間は安心したいから、一つにしがみつくけれど、どれを選んでも、本当は同じなんです。だけど、おそらく一つを選んだってことに安心しちゃうと、自慢たらしいものになっちゃったりなんかするのかな」
ブレンダン・フレイザーとの、言葉を超えた交流

――ほとんどのシーンで一緒だったブレンダンさんとの撮影の思い出を聞かせてください
「ブレンダンはね、とても素敵な人なんですよ。普段の人間が素敵。芝居も柔らかくて、いい。無理しないで、そのままフィリップになる。そこがね、とても素敵だなと思いました。一緒にやらせてもらって、本当に勉強になったし、受け止めてもらえる感じがあった。とてもいい相手に恵まれたなって。ブレンダンとできて、HIKARI監督に感謝ですね」
――オフの時間はどんな会話をしていましたか?
「喋れないですよ(笑)。通訳を介しているから。べちゃくちゃ話したわけじゃない。でも、お互い芝居をやっている人間だから、通じるものはあった。監督の指示で、その場所に行って、目を合わせる。それだけで、通じるものがありました。ロンドンに行ってもね、お互い探すんですよ。会場で、目で探して。『あ、いた』って。で、近づいていって、ハグする。喋れないけど、それでいい」
――言葉を超えた繋がりですね
「ブレンダンはスーッと入ってくる。芝居に無理がないんです。ブレンダンから、スーッとやってきて、スーッとゆっくり、無理なく行く。僕も舞台をやってきましたから。ブレンダンも舞台をやってる。そこら辺は何かこう、言葉がなくても通じ合えるものがありました」
HIKARI監督の現場、東京の映像の印象
――HIKARI監督の現場で印象に残っていることは?
「英語が飛び交っている現場でした。人も多いし、スケールの大きさは感じましたね。でも、やることは一緒です。結局、それに尽きます」
――東京の景色や作品全体の映像についてはいかがでしたか?
「撮影監督の石坂(拓郎)さんがもっぱら向こうで活躍されている方だから、やっぱり絵の撮り方が、いわゆる日本で活躍しているカメラの方とは違いますよね。東京の景色になんとなくファンタジーを感じて、すごくいいなと思いました」
孤独を商売にするということ

――報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣するレンタル・ファミリーを題材にしていますが、このテーマについてはどう感じましたか?
「最初は、そんな職業があること自体知らなかったので驚きました。孤独を商売にする、ということへの違和感もありましたね。そういうものを商売にしちゃうんだっていう。人間の、どちらかというと良くない意味での、経済に対する欲望の強さみたいなものを感じました。それに目をつけたのは、とても面白い発想だと思いますが。でも、孤独ってそんなにいけないことなのか、とも思いますね。だって、人間はみんな孤独なんだから(笑)。でも、そういうものを追い求めるのが人間だと思う。人は孤独を求めるし、同時に、繋がりも探す。それも人間なんだと思います」
海外の評価、そして「様になっている」ということ

――完成作を観て印象に残ったシーンはどこですか?
「(フィリップと交流する美亜役の)シャノン(ゴーマン シャノン 眞陽)が可愛らしかったですね。それと、やっぱりブレンダンがすごくよかった。さっきも言ったけど、どのシーンでも無理なく、スーッと入ってくる。フィリップとして芝居に無理がないんです」
――ご自身のシーンを観るのはいかがですか?
「自分のシーンは、正直、どうなんでしょうね。自分もやっているわけだから、客観的にどう、というのはあまり分からない(笑)。ただ、僕は好きなシーンばかりでした」
――海外の観客からは柄本さんのお芝居を多くの方が絶賛していますが、その評価を聞いて、どう感じますか?
「それはありがたいですね。自分ではよくわからないけど、褒めてもらえるのは嬉しいです(笑)。この映画で海外の映画祭に行って改めて思うのは、やっぱり様になっていてさすがだなって改めて実感しました」
柄本明
えもと・あきら 1948年11月3日生まれ、東京都出身。自由劇場を経て、1976年に劇団東京乾電池を旗揚げし、演出としても参加。舞台のほか、ドラマや映画にも数多く出演。、『悪人』(10)で第34回日本アカデミー賞助演男優賞を受賞するほか、様々な賞を受賞。近作に『盤上の向日葵』、『栄光のバックホーム』(ともに25)、『架空の犬と嘘をつく猫』(26)がある。『幕末ヒポクラテス』が初夏公開予定。
『レンタル・ファミリー』
『ザ・ホエール』で第95回アカデミー賞主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーが主演を務め、全編日本で撮影を敢行したヒューマンドラマ。長編デビュー作『37セカンズ』やドラマ『BEEF ビーフ』などで注目された日本人監督・HIKARIがメガホンをとり、東京で暮らす落ちぶれた俳優が、レンタル・ファミリーの仕事を通して自分自身を見つめ直していく姿を描く。レンタル・ファミリー会社を営む多田役で平岳大、レンタルファミリー社の俳優として働く愛子役で山本真理、そして同じく俳優として働くフィリップ役のブレンダン・フレイザーと出会う老優・喜久雄役で柄本明が共演。
2025年製作/110分/G/アメリカ
配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン
劇場公開日:2月27日
https://www.searchlightpictures.jp/movies/rentalfamily