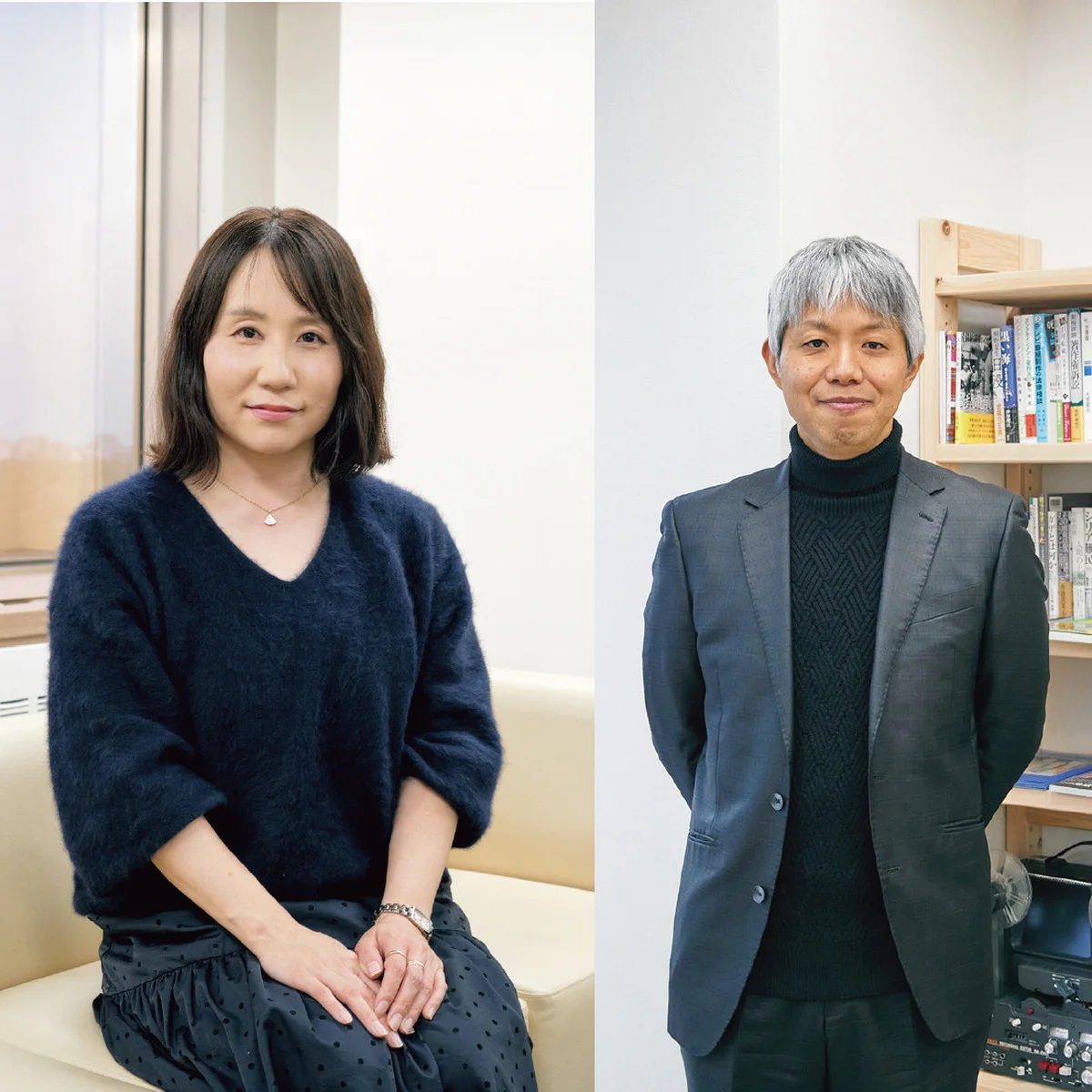29歳、女性、独身、地方出身、非正規雇用労働者。生活のために選んだ「代理母」という選択肢は、自ら望んだ道なのか、それとも社会にしいられたのか。新刊『燕は戻ってこない』で現代女性の困窮と生殖医療ビジネスを描いた桐野夏生さんが説く、「自己責任じゃない」私たちの体と性、生殖に関する権利の話。

Profile
桐野夏生さん1951年、石川県生まれ。’93年『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。"平凡な主婦"とされる女たちの犯罪を描いた『OUT』をはじめ、女性を取り巻く不条理と抵抗を描いてきた。3月4日に刊行された最新作『燕は戻ってこない』では困窮する非正規雇用労働者の女性のリアルと代理母ビジネスを取り上げ、話題になっている。
「あなたに責任はないよ、と言ってあげたい」
昨年の5月に女性として初の日本ペンクラブ会長に就任した、小説家の桐野夏生さん。会見では「ジェンダーが欠かせない視点であるという認識は広がっており、楽観的に思ってはいるが、それでも必ず反動や差別はあると思うので、それとは闘っていきたい」とスピーチした。「この70年で日本の女性も変わりました。特に、2017年の#MeTooのムーブメントの影響は大きかったと思います。日本ペンクラブでも、性差別を女性問題として扱わず、男性も率先してジェンダー問題に取り組もうという声も上がっています。文学界全体を見渡しても、女性の読者が増えていることを追い風に、文学賞の選考委員や受賞作の作家に女性の比率が増えました。少しずつではあるけれど、確実に変わってきています」
社会の中で記号化されがちな女性たちに目を向ける
作品を通して、女性の直面する不条理と足掻きに、スポットライトを当て続けてきた桐野さん。日常生活でも「集団として塊や記号としか見られず、一人ひとりの顔が見えない状況の女性たち」に目が留まるという。
「『OUT』を書いたとき、若い男性編集者が『パートのおばさんにもいろいろな人生があるんだな』とポロッとこぼしたんです。これまで彼にとって『パートのおばさん』は、記号でしかなかった。これが一般的な見方なのか、(女性の人生は)見えないものだな」と振り返る。
「数年前に、出版業界の方とカラオケに行ったとき、別のテーブルに歌わない4、5人のグループがいたんです。気になって聞いてみたら、『あの人たちは派遣さんだから歌わないんです』と。正社員同士でマイクを回し合って、彼女たちは黙って聞き手に徹している。その場にいた人にとっては当たり前でも、そういう光景を目にすると引っかかります」
3月4日に発売された新刊『燕は戻ってこない』の主人公リキは、地方出身の29歳の独身女性。彼女もまた、社会の中で記号化されやすい非正規雇用労働者だ。
「日本では女性の約6割が非正規雇用労働者。コロナ禍で多くの人が職を失ったことからもわかるように、景気が悪くなれば雇用を切られる立場の弱い存在です。今や年収200万円以下の割合が若い女性の約3人に1人。こんな先進国はないし、生死に関わる問題になっています。
リキは、北海道のちっちゃな町の出身。地方出身の女性が地元で職を探すと、「介護ならあるよ」などと言われ、ケア労働しか選択肢がないことが多い。じゃあ地元を出て、東京に出たらどうなのかというと、そこでも非正規雇用の求人しかない。しかも、頼れる人間関係、学歴、コネ、居場所などのインフラがなく、結局は貧困に追い込まれてしまいます。今、こういう人はたくさんいるんじゃないでしょうか。リキが29歳なのは、卵子提供の年齢制限が多くは30歳までと知り、ギリギリの年齢に設定したから。もし、リキが24歳だったら、もう少し未来を信じられたかもしれませんね」
ニュースなどで報道される「若い女性が貧困に追い込まれている」という情報だけでは伝わらない、リアルな苦境の手ざわりを、小説を通して届けることにこだわりがある。
「たとえば、100円ほどのコンビニのコーヒーすら買えないというシーン。多くの人が無造作にしている出費すらままならない場面を描くことで、お金がないというのはどういうことかを実感してほしい。表現する上で、こういう些細なディテールを書くことには特に一生懸命になります」
困窮する女性が「代理母」を持ちかけられたら?
『燕は戻ってこない』では、貧困に直面した主人公に「いい副収入になる」と、代理母出産の話が持ちかけられる。本作のテーマとして、生殖医療を取り上げた理由は?
「生殖医療が発達していることは耳にしていました。女性の側の心理や法律と乖離したところで医療だけが進んでいる現状に危機感と疑問があって。今日本では若い女性の貧困が深刻化している。彼女たちが苦しんでいる渦中に、ふっと代理母出産を引き受けることになったら、どんな物語になるだろうというのがスタートでした」
日本では代理母出産は認められていないが、世界を見渡せばすでに行われている現実がある。
「アメリカでは、セレブリティが出産で体の線が崩れるのを避けるために、代理母出産を選んだと語り、話題になりました。お金さえ出せば、スタイルを保つためという理由で、他人の体を借りて出産できるなんて、すごくグロテスクな話。言葉を選ばずにいえば、代理母ビジネスには、妊娠出産する体を“ただの産む機械”とみなす側面があるように感じます。女性の体をお金に換算するビジネスは、女性の自己決定だけの話に矮小化できない、社会が向き合うべき問題なのではないでしょうか」
また、本作の執筆過程では、生殖医療にまつわる用語や基準、テクノロジーが次々とアップデートされるのを目のあたりに。生殖医療業界の盛り上がりを感じたという。
「やはりそれだけニーズが高く、ビジネスチャンスがあるということでしょうね。すごく勢いがある巨大なビジネスなのに、制度も当事者の気持ちもついていってないのが問題です」
物語の中で、「代理母のリキはお金がないから、売るものがないから、自身の卵子と子宮を売った。あなたのやっていることは搾取だ」という一文がある。これは、他者に対して性的欲求や恋愛感情を抱かない(または抱きにくい)、アセクシュアルの登場人物りりこの口から語られる台詞だ。
「実は、アセクシュアルという言葉は、りりこを書いた後で知ったんです。生殖医療のまっただ中にいるリキや悠子とは、関係ないところにいる対照的なキャラクターを描きたくて作った、小説的な人物です。生殖やセックスにとらわれないりりこは、書いていて自由な感じがして楽しかったですね」
リミットを提示され、結婚・出産に追い立てられる
本作では、不育症と卵子の老化の診断を受け、主人公に代理母を依頼した夫婦の妻である悠子の苦しみも描かれる。
「最近は少子化も相まって、子どもを産むことを選ぶ人が人生の勝者であるかのように語られがちですよね。
ネットニュースでも、出産することで、人として一人前になったかのような論調の記事が多く、メディアによる誘導や刷り込みを感じます。そういった中で、卵子の老化とか出産年齢とかリミットを提示されて、追い立てられるのはつらいはず。これは、いわゆる出産適齢期といわれる層だけでなく、若い女性に対しても当てはまる話です。低賃金で使われて、出世できなかったり非正規雇用で不安定だったりする中で、それだったら結婚したら?と。まるで、結婚して子どもを産めば楽になるように勘違いさせられる。そういう論法に、騙されてはいけません」
多様化する家族像に社会全体で目を向ける
「最近、少子化対策として、人工授精に補助金が出るようになりました。これは、妊娠に困難を抱える方々にとってはとてもありがたい制度です。でも、子どもを持つという選択肢が、夫婦の実子でなければという枠の中で語られすぎている気がします。
父親が働いて、妻は家事をするかパートで家計を支えて、子どもをできるだけ多く産んで家で育てる。今の社会が想定している伝統的な家族像って、せいぜい昭和止まりのモデルで、今となってはとっくに崩れてきている。現実には、子どもを持たない夫婦やひとり親家庭、同性同士だったりと、いろんな家族の形がすでにある。それを無視して、昔の家族像や家父長制に固執すると制度や法律からこぼれ落ちてしまう人が出てきます。本当はもっと多様な家族の形を想定して、里親制度とか戸籍制度まで含めて見直す必要がある。自分の子どもじゃなくても育てようとか、シングルでも子どもが持ちやすいようにとか、そういう方向に社会全体で動かなければ、と思います」
さらに、桐野さんのまなざしは、女性の性と体を取り巻く問題全般にわたる。
「日本では、世界で当たり前の安全な中絶方法が普及しておらず、人工中絶薬へのアクセスも難しい。きちんとした避妊の知識が教えられず、避妊手段も限られています。そういう状況が許されてきた背景には、どこかで女の選択肢を狭めて、制度からはずれる女を罰したいという心理や文化があるのではないでしょうか。本来は、人権そのもののテーマなのに、そういう視点が巧妙に隠されている気がします」
自己責任の呪縛を解いて自由に生きてほしい
「現代社会では、女性の選択肢が増えたぶんだけ複雑になり、さまざまな苦しみや葛藤も生まれています。そこしか道がないからと選んだ選択肢について、『自分で選んだのだから自己責任だ』と決めつけないでほしい。本当は、閉ざしている側の社会に問題があるのだと、気づく視点を持ってほしいですね。
もちろん、人間関係とか些細なことなら、自己責任もあるかもしれません。でも、女性として生まれたというだけで、入試で合格点に差をつけられたり就職先が見つかりづらかったり。そんなの自己責任なわけがない。性差別であり、社会問題です」
『燕は戻ってこない』を通して、みんなに「あなたがその選択肢を選ばざるをえなかったのは自分の責任ではないよ、と伝えたい」という桐野さん。
「自己責任論が出てきてから、底辺にいる人の苦しみが理解されづらくなりました。私は、物語の中で今困っている人、苦しんでいる人を描くことで可視化したい。具体的なディテールを与えてその人の心理や状況を描き出すことで、わからしめる。問題の本質をあぶり出すことで、あなたのせいではなく、構造やシステムの問題が大きいんだよと客観視することを助けたい。小説にはそういう役割もあると思うんです。自己責任だからと自分を責めるほうに向かっていた思いがあるとしたら、それを世の中を変えるパワーに転換してほしい。自己責任の呪いが解けたら、多くの女性がもっと自由に生きたいと願い、行動するようになるはずです」
『燕は戻ってこない』(集英社/2,090円)
北海道の小さな町で育った29歳の女性リキ。地元での介護職を辞めて上京したものの、不安定な非正規雇用から抜け出せず生活は困窮していく。そんなとき「いい副収入になるよ」と生殖医療ビジネスを紹介され、裕福な夫婦の代理母を依頼される。生活のために、子宮と自由と尊厳を他人に貸す近未来のディストピアを描いた一冊。

読者の質問に率直に回答!
教えて、桐野先生
女性が直面するリアルを描き続けてきた桐野さんに、ぶつけてみたい疑問を大募集。日々のモヤモヤや将来への不安、プライベートに迫る問いにまでズバッと答えてもらう。

- Q.今後ますます、女性が結婚、出産を選ばず、ひとりで生きていく社会になるような気がします。私自身も自分の子どもが大きくなったらそういう選択をすると思います。不安と心配でいっぱいなのですが、気持ち、心の構え方などをお伺いしたいです。(きょうこさん 28歳)
- A.少子化も非婚化も進んで、単身者が多い世界になりつつある。そうなると、ますます単身者同士が助け合って生きていくことが大切になってきます。「産めよ殖やせよ」は国力の問題で個人の問題ではない。子どもが減ると国が困るから焦っているのが現状ですが、そういう大きな力に左右されず、自分にとっての幸せを優先してほしい。
- Q.桐野夏生先生がデビューされた頃から、新刊が出るたびに拝読しております。飽くことなく「女」であることを軸におきながらの小説を綴り続ける中で、正直「脱力感」や「無力感」を抱くことはなかったですか?(白猫さん 48歳)
- A.小説を書くことには、全裸で荒野に立つような怖さがあります。ライターズハイみたいな瞬間もあれば、はっと恐ろしくなる瞬間も。なんとか乗り越えては、やっぱりこれしかないなと思い直すことの繰り返しです。
- Q.最近の生活スタイルを教えてください。(KK 37歳)
- A.朝6時に起きて、1時間はベッドの中でネットやSNSを見ています。午前中はバレエや犬の散歩以外は、執筆しています。夕方の18時には、ごはんを作ります。ご飯を炊いて、お味噌汁とおかずを作ってと、人に言えるほどではない素朴な献立(笑)。20時から22時までは机の前に戻って執筆です。お風呂に入り、その後ベッドで、タブレットで配信の韓流ドラマを視聴。コロナ禍になる前はまったく見なかったのですが、「愛の不時着」をきっかけに、配信されているものはだいたい見ました。お気に入りはゾンビものと世子(セジャ)もの。いちばんよく見たのは「トキメキ ☆成均館スキャンダル」です。コロナが収まったらファンミにも行ってみたい。
- Q.何にインスピレーションを得ているのか知りたいです。(たみさん 39歳)
- A.なんだろう。日々のどうってことない暮らしですね。60代70代の同級生や友人たちとのよもやま話から、ああ、みんなこういうこと考えて生きているんだとヒントをたくさんもらっています。
- Q.きれいの秘訣はなんですか?(えりさん 26歳)
- A.撮影があるときは、1週間前からお酒を抜きます(笑)。執筆する間に、おせんべいやクッキー、りんごなどをつい食べすぎてしまうので、日常的に体を動かす習慣が欠かせません。犬の散歩を毎日、30年続けているバレエは週3、4回。ゴルフは週1のペースで通っています。バレエは合間のおしゃべりも楽しい。
- Q.子育てをする女性の仕事のフォローが、絶賛婚活中の女性に回るのが当たり前になっていることに理不尽を感じます。既婚女性が「独身女性が既婚男性を誘惑している」と下衆の勘繰りをすることも。そんな暇はない! 女の敵は女ですか?(ネロリさん)
- A.女の敵は女、私は思ったことがないですね。ただ、既婚と未婚の分断は昔からありましたよね。古くは「アグネス論争」というものがあったんだけど、若い人は知らないかな(笑)。割りを食ってると感じる未婚の人と、見下されているような気持ちになる既婚の人と……。既婚女性VS未婚女性の構図になってしまうのは、女性同士に落ち度があるのではなく、職場環境の問題や男性が仕組んだ罠では? あとは、誘惑される男が悪い!
SOURCE:SPUR 2022年6月号「その生きづらさや苦しみを可視化する 桐野夏生が寄り添う女たち」
interview & text: Anna Osada photography: Mai Kise hair & make-up: Takae Kamikawa 〈mod’s hair〉