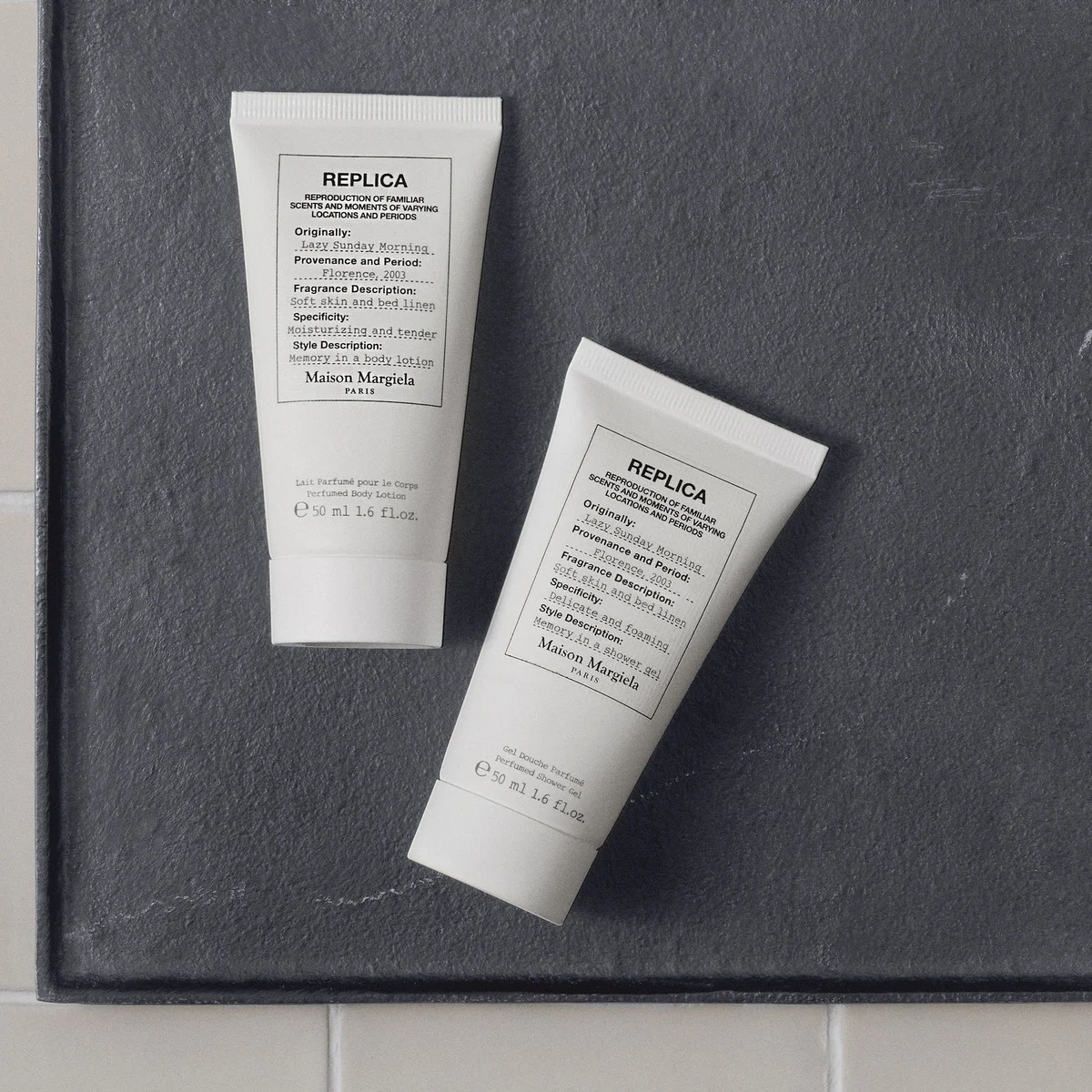悩みやストレスの原因、対処法などについて読者623名に聞いた「メンタルヘルス」にまつわるアンケート。その結果、「仕事」や「職場の人間関係」につらさを感じる人が圧倒的に多いという現状が見えてきた。
仕事や職場でのストレス軽減に向けたアクションのヒントを紹介した前編に続く今回のテーマは、「聞き手の心得」。
つらさを打ち明けてくれたとき、本人からは言わないけれどつらいだろうと感じるとき。聞き手としてコミュニケーションを取る際に、意識しておきたいことを精神科医の星野 概念さんに伺った。
悩みやストレスの原因、対処法などについて読者623名に聞いた「メンタルヘルス」にまつわるアンケート。その結果、「仕事」や「職場の人間関係」につらさを感じる人が圧倒的に多いという現状が見えてきた。
仕事や職場でのストレス軽減に向けたアクションのヒントを紹介した前編に続く今回のテーマは、「聞き手の心得」。
つらさを打ち明けてくれたとき、本人からは言わないけれどつらいだろうと感じるとき。聞き手としてコミュニケーションを取る際に、意識しておきたいことを精神科医の星野 概念さんに伺った。
まずは「どうしたらいいんだろうね」と悩みに寄り添い続ける
──同僚や部下から悩みを打ち明けられたとき、どう“聞く”のがいいでしょうか?
困っている人に対してできることって思いのほか少ない。なので、できることに徹する、つまり話を聞くのは大事だと思います。
アドバイスしたくなるかもしれませんが、それよりも「その人がどうしたいのか」を常に想像しながら「どうしたらいいんだろうね」と悩みに寄り添い続ける。するとはっきりしない感じになりますが、それでOK。はっきり物を言うと、相手に立ち入りすぎて致命傷になることもあるので、それが安全な聞き方なのかなと思います。
「本人がどうしたいのか」を軸に話を進めていくことがとても大事
──星野さんは「本人の意志を無視して、無理やり休職させない」というスタンスですよね。その意図を教えてください。
あくまでも僕個人のスタンスですが、一方的に医師側が決めるのはいいことばかりではないと思っています。相手の悩みについて「どうしようか」と言いながら、話に付き合い続ける。「休む」を決断するにいたるまでも、周りからどう見られるか、お金のこと、戻れなくなる心配……など抱えている不安を一つずつ聞きます。
もちろん客観的に見てまずい状況の場合は、「僕から見るとかなり限界だと思うので、休むのもひとつの選択肢だと思います」と正直に伝えます。そのうえで、相手に選択をゆだねるというか「その人がどうしたいか」ご自身も決断に参加してもらう。主語を自分にして決めていくことが、とても大事だと思います。
──日本では自分で決めずに「医師の診断結果に従う」ケースが多い気がします。時間がかかっても、決断に自分が参加するのは大事だと思いました。
ただ、人によってはバシバシ決めてもらいたかったり、診断書が早く欲しかったりする場合もあるので、一概にどんな診察が適切かは言えないですね。やり取りをしているなかで本人が「もう決められない」となったら、僕から「じゃあ、この局面はリードしてもいいですか」と事前に伝えて、やり方を変えていく場合もあります。
意見を伝えるときは、 “I(アイ)メッセージ”で言葉を交わす
──安全な“聞き方”の距離感として、自分の意見を言うときは星野さんのように「私はこう思う」と自分を主語にして話すことが大事なんでしょうか?
“I(アイ)メッセージ”と言われるものですが、主語を持って意見を伝えることはとても大事だと思います。心配な人が周りにいたときに、心配だと思っている自分をスルーしてほしくない。「個人的に心配になっちゃったから声かけたんだけど、違ってたらごめん」みたいに、Iメッセージで声をかけた理由を伝えると、受け取り方が和らぐかなと思います。
あとは「いつもと違う感じがしたんだけど、どうですか」と様子を聞いてみたり、「今日なんか気にしいなのかも」と自分の感覚起点であることを伝えるのも一案です。そこから「大丈夫」と言われたらそれ以上介入せず、また心配になったら話しかけてもいいと思います。相手のタイプや空気感に合わせたIメッセージを意識してみてほしいです。
自分の価値観ではなく、相手への想像力を働かせて言葉をつむぐ
──「元気を出してほしい」という気持ちから、エンパワメントするような声がけや、気を遣いたくなったりもします。これも気をつけた方がいいですか?
弱っている状態で、元気で健康な人たちの価値観ベースでコミュニケーションを取られると、傷つく可能性があります。具体的には、「浮かない顔してどうしたの?」「なんで1人でご飯食べてるの?」「元気だしなよ」「あの人は結構繊細だからさ」などです。今の自分の状態はよくないんだと、周囲に気を遣わせてしまっていると自責の念を感じてしまうかもしれません。
大切なのは、相手の気持ちを想像し続けること。「こうしてみなよ、こうした方がいい」という前提があるコミュニケーションでは、相手に立ち入りすぎてしまう可能性があります。「こうするのがいいのかな、と私は思ったけど」と、押し付けることなく、間合いを見ながらコミュニケーションを取ることを意識してみてください。

精神科医として働くかたわら、執筆や音楽活動も行う。いくつかの場所での連載や寄稿のほか、『こころをそのまま感じられたら』(講談社/2023)などの著作もあり。音楽活動はさまざま。対話や養生、人がのびのびとできることについて考えている。
兎にも角にも、コミュニケーションに大切なのは「想像力」。それがあるかないかで、同じメッセージでも受け取られ方が大きく変わってくる。話を聞くときも、何かを伝えるときも、「相手はどう感じるだろうか」「私はこう思うけれど」という押し付けのないスタンスでいることで、微力ながらもつらさを感じる人の力になれるかもしれない。