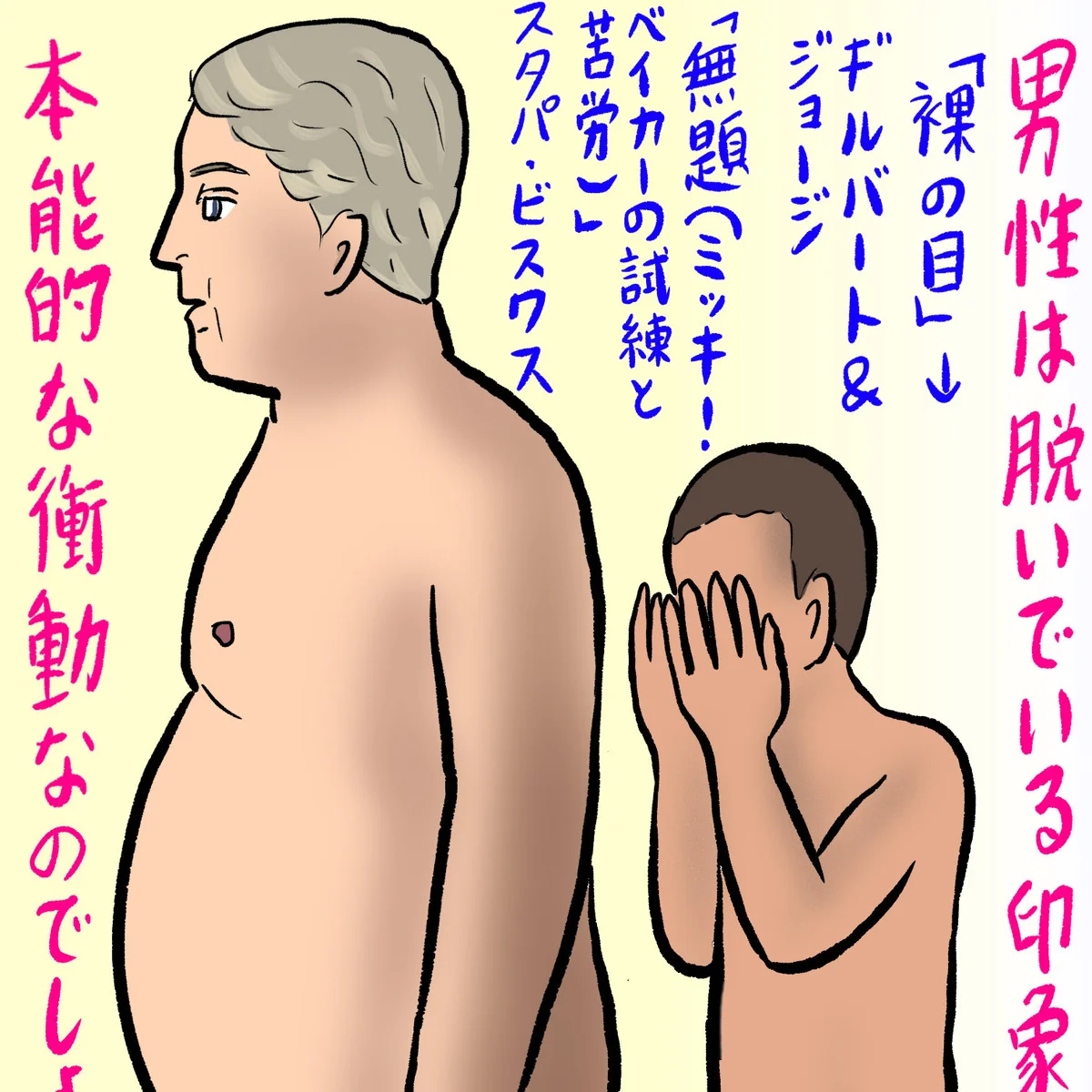「繭子ひとり」のNYロケでのスナップ写真。パーマヘアと眼鏡は役作りのためのもの
「繭子ひとり」のNYロケでのスナップ写真。パーマヘアと眼鏡は役作りのためのもの
昭和51年に始まり、同一司会者による最多放送番組としてギネス世界記録に認定されている「徹子の部屋」。番組開始にあたり、黒柳さんが「政治の話はしない」と決めたというのは有名だ。さまざまな分野のゲストは、その立場や考え方もいろいろ。先入観なしでニュートラルに受け入れることは、番組ホストとして必要不可欠と言えるだろう。
もっとも、葬儀における黒柳さんの感動的な弔辞が話題となった永六輔さん、そして小沢昭一さんなど、より強い絆があった人はみな、生涯を通して戦争に反対してきた。
「先の天皇陛下(現在の上皇)がご退位なさるのにあたって、『平成は戦争のない時代でした』と声を詰まらせながらおっしゃったのには胸を打たれました。そこまでちゃんと言及なさったんだ、と。私も戦争は本当にイヤです。戦場で人の命が奪われたりするだけでなく、親と子がバラバラになったり、朝、学校に出かけていっても、帰ったら家が爆撃で焼かれていたり、家族が亡くなっていたりということが実際に私の周りでもあった。つまり、家族はみんな無事だろうか、と心配しながら通学するわけです。もちろん食べ物がなくなって、ひもじい思いもしました。あるとき、母が15粒の炒った大豆を封筒に入れて、私にくれ、『はい、これがあなたの今日の食糧よ。5粒ずつ朝昼晩と食べてもいいし、一回で全部食べてしまってもかまわない。その代わり、家に帰ってきてもお夕飯は何もありませんからね』と言うので、子ども心に悩むわけです。どういうふうにこの15粒を分配しようか、と。でも、いろいろ考えるうちに、お昼に5粒食べて、空襲になって防空壕に入り込んで3粒食べて、『もっと食べたいけど、家に帰って、何もないと困る。でも、空襲で死んじゃうんなら、今のうちに全部食べちゃおうかな』と悩みました」
青森の三戸のりんご農園の小屋に疎開してからも、「それはイヤなことはいろいろありましたよ」と言う。「ただ、母が壁に花を飾ったり、東京の家から風呂敷として物を包んで持ってきたゴブラン織の布でカーテンを掛けたり、その小屋を精いっぱい、心地いい空間にしてくれました」
ゴブラン織の布とは珍しい。
「私も不思議で聞いたんです。『これ、どうしたの?』と。すると『家にあったソファの布よ』とけろっとした顔で言うの(笑)」
『風と共に去りぬ』(’39 )のスカーレット・オハラも『サウンド・オブ・ミュージック』(’65 )のマリアも、カーテン地でドレスを作っていたけど、「うちの母は、ソファから風呂敷、そしてカーテンですから(笑)。でも、東京ではN響のコンサートマスターをしていた父を支える、いわば音楽家の妻として家を守っていた母が、私たち子どもを守るために、いろんな知恵を働かせていた。そのひとつが、野菜を手に入れ、それらを背負って八戸の港に行き、スルメを買って、それを煮てお弁当にし、野菜市場で売ることでした。三戸の隣の“諏訪ノ平”という小さな駅でも人は行き交っていて、結構売れたらしい。『あんなにお金を儲けたことは、私、なかったわ』と言っていましたから(笑)。実は私、栄養失調で体中にオデキができていたんですね。でも、母が魚をもらってきて、煮たものを食べさせてくれた。私はそれまで煮魚は苦手だったんですけれど、それを食べたら一回で治りましたから。タンパク質、恐るべし!ですよ。ですから、今もユニセフの仕事でアフリカや紛争地域の難民キャンプなんかで、栄養失調でやせこけた子どもを見ると、『とにかくタンパク質を! タンパク質の豊富な食べ物をあげてください』とみなさんにお願いするの。それは、戦争中の私自身の体験から出ているもの。そう考えると、日本は確かに戦争がない年月が70年以上続いているけれど、世界規模では戦争はまだ続いているんだと暗澹たる思いにとらわれてしまいます」。
ちなみに、自身の栄養失調体験が、難民や災害を受けた地域の子どもたちとの接し方のヒントになっているのと同じように、三戸での疎開体験も、後に女優・黒柳徹子を意外な形で飛躍させることになる。
「昭和46年かな。NHKの朝の連続テレビ小説で、山口果林さんがヒロインを演じた『繭子ひとり』という作品に、青森出身の家政婦さんの役で出演しました。一番手のかからないチリチリにかけたパーマの短い毛に、メガネ、体も綿を入れて太らせて、衣装も自分なりに考えて」
なんと言っても素晴らしかったのは、ネイティブに近い(?)青森弁! それまでの黒柳さんは「若い季節」など、都会的な女性を演じる作品が多かったから、「NHKには投書が殺到したそうですよ。『黒柳徹子が出るって書いてあるのに、出演していないじゃないか!』って(笑)。そういう意味でも、人生って無駄になることはないな、と感じました」。