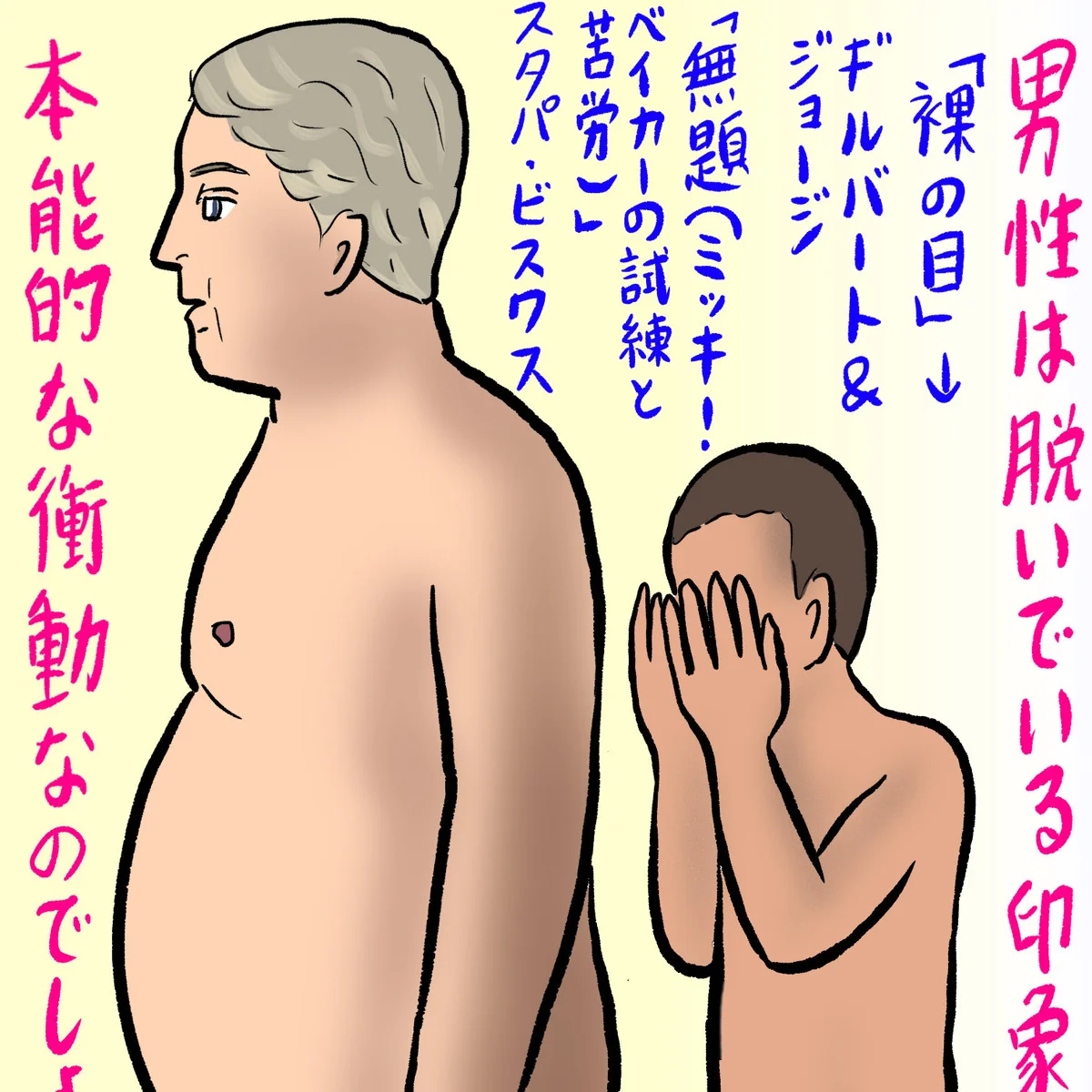今年5月にレバノンを訪問。パレスチナ、シリア、レバノンの子どもたちと交流する黒柳さん(写真:田沼武能)
今年5月にレバノンを訪問。パレスチナ、シリア、レバノンの子どもたちと交流する黒柳さん(写真:田沼武能)
どのような形であれ戦争を体験した人間は、その経験を積極的に人々に伝えようとする人と、口をつぐんでしまう人に分かれるようだ。父・守綱さんは、あまり中国、ソ連での日々を語らなかったという。
「江戸っ子というのもあったのかな、ほとんど戦争のことは話しませんでした。一回、『ソ連は寒かった。移動のトラックは零下20度くらいだった』と言っていました。でもそういう体験者が口をつぐむということと、だったらあの時代のことを忘れていい、勝手にいいように解釈していいというのとは絶対に違います。放っておくと、令和の時代は“戦争のない時代”をキープできなくなるかもしれない。それが私は恐ろしいです」
今にして思うと、1984年に黒柳さんをユニセフ親善大使としてアジアから初選出した当時のユニセフ事務局長ジェームス・P・グラント氏は、先見の明があった。選出理由として挙げた「子どもへの愛と、障がいのある人々や環境への広範囲な活動実績」は、ある日突然黒柳さんが覚醒、行動し始めたものではなく、先述した「自分の、戦争中の栄養失調からくるオデキ体験」のように、時代も世界規模での地域差もポーンと越えて、ひとつの大きな流れ、うねりのようにつながっているのだ。
もっと言えば、「徹子の部屋」で、ゲストの話を真剣に聞く、という姿勢の原点は、最初の小学校を退学になり、次に行ったトモエ学園で、黒柳さんの話を一生懸命に聞いてくれた校長先生にある。
「子どもって正直だから、自分が話しているときに、相手の大人が時計を見たり、他のものにちょっとでも気を取られるそぶりを見せると、たちまち集中力が途切れてしまう。あのとき、トモエ学園の校長先生は、『それで? どうした?』と私に話すことを促し、気づけば延々4時間しゃべっていた(笑)」
障がいのある方々へのサポートも積極的だ。
「私はろうあの方々の劇団をオーガナイズしています。38歳でアメリカ・NYに行っていろんな舞台を観たりしているときに、デフ・シアターという、ろうあの方々の劇団があって、これが素晴らしかった。そこで、『窓ぎわのトットちゃん』の印税をもとにトット基金というのを作って、劇団を立ち上げました。私もろうあの方々と一緒に手話で出演することも。耳の聞こえない方の拍手って素敵なんですよ。手話でアイ・ラブ・ユーの形を作って両手でひらひらさせるの(笑)」
こうした支援は、かつて森繁久彌さんなどが中心に行なっていた“あゆみの箱”というチャリティ運動がきっかけ。
「私ももちろん賛同して、お金を集めるだけでなく、実際に養護施設などに行って清掃とかいろいろお手伝いをしていたんだけど、けっこう疲れ果てて、本業の俳優業に支障をきたす心配も出てしまった。これじゃ本末転倒だな、と思って、自分の名前を使ってできること、基本的にはいろんな意味で不幸な子どもたちを一人でも救いたい、という活動に集中させてもらうことにしました」
ユニセフで各地を飛び回る黒柳さんには、当初「(貧困にあえぐ地域に出かけるのに)あんなにきれいな格好をして行って。ジーンズで行くべきだ」などと“街の評論家”のような人たちから批判も寄せられたという。でも、そんな黒柳さんに抱き締められた子どもたちが、「白い木綿の服の、すごくいい匂いのする女の人がとてもやさしくしてくれた」と喜んでいる姿を見ると、実際に行動する人間のほうが圧倒的に説得力があることがわかる。
「戦後すぐかな。アメリカの女性がギンガムチェックのブラウスやワンピースを着て颯爽としている姿を見て、素敵だな、大人になったら私も着よう、と私自身憧れたように、子どもたちが見るだけでうれしくなる格好で接したい、と。それも現地で少しずつ体得した思いです。ある日、タンザニアで現地の人が『◯△×$トット!』と言うので、びっくりして『今のトットって、どういう意味?』と聞いたら、『スワヒリ語で、子どもという意味だよ』って(笑)。トットである私が、あの子どもたち、世界の子どもたちのために働くのは、生まれたときから必然のようなものだったのでしょう」
こうしたトットイズムが浸透すれば、“令和の平和”もより堅固なものになっていくはずだ。