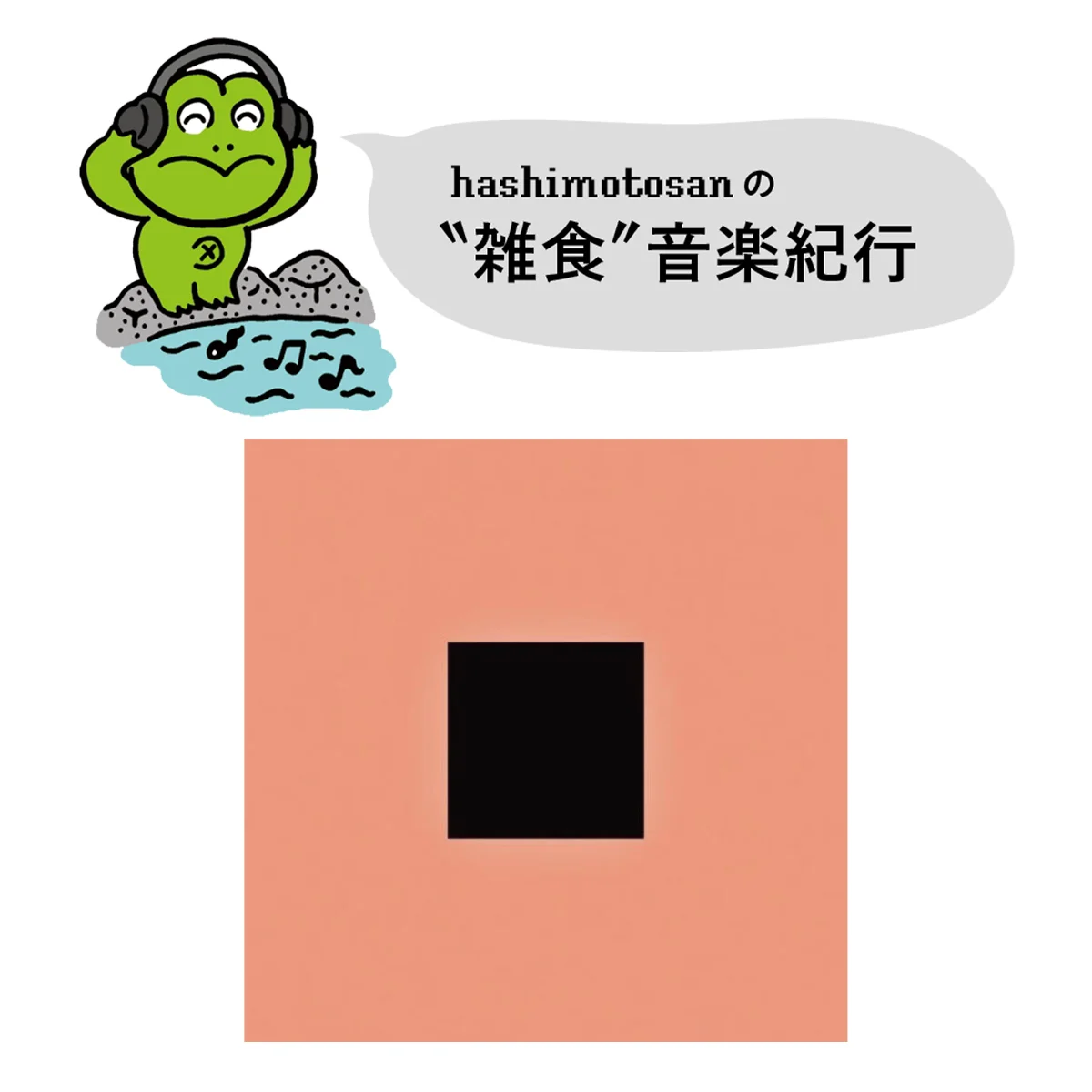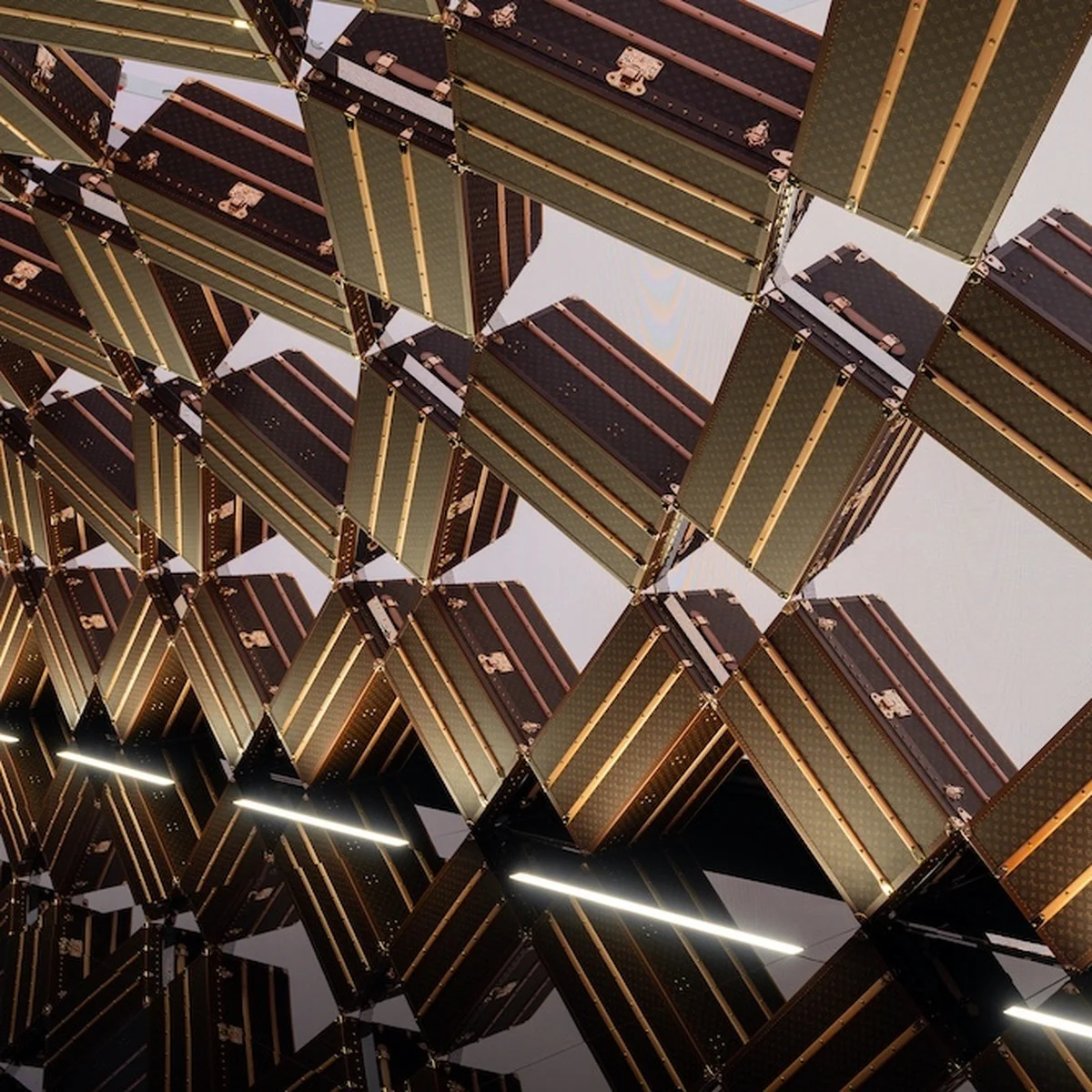「ラッパー間抜け話」の先にある叙情と激情
「音楽は勝ち負けじゃないですよ」
とその日共演した人に言われた。
俺は、
「色んな考え方があって良いと思います」
とだけ伝え、その場を離れた。
彼はまだ何か言いたげにこっちを見ていたが、俺は早々と会場を後にした。
「勝ち負けじゃないと思える所まで俺は勝ちにこだわるよ」という曲をつくり、演奏するようになってから、その手の議論をふっかけられることが多々あった。

この本の面白さを、SPURのウェブサイトをご覧の、おそらくおしゃれで素敵な女性たちにどう説明したらいいのだろうか……。まず、滝原勇斗さんというのは、MOROHAというアコースティックギターとラップの二人組のバンドで、アフロという名義でラップをしているラッパーである。当然、リリックも彼が書いている。というわけで、文章を書ける素地は十分にあったのだろう。でも、その文章がすごかったのだ。
ラッパーといった言葉から連想されるカッコ良さや気取りとはまったく無縁の、田舎の少年がラッパーに憧れてことごとく失敗しまくる情けない話。タンクトップを一枚で着るのに憧れてたのに、お母さんがYシャツの下に着るアンダーシャツを買ってきてしまい、ゴツいネックレスの代わりに自転車の鍵用の太いチェーンを首に巻いてみたら、あだ名が「ドMの変態社長」になってしまった、とか、もう……ヒップホップにこんなにピュアに憧れてる青年がこんな目に遭ってきたのかと思うと、涙と笑いが交互に押し寄せてくる。
でも、この本はそんな「ヒップホップ間抜け話」だけでは全然終わっていない。もし、ただそれだけの本だったら、よくある「ギャップで笑える話」だし、面白くてもわざわざ紹介するほどのことではなかったかもしれない。
この本には、笑いの中に詩情がある。詩情だけで書かれているパートもある。私が特に好きなのは「あれもこれも歌えない」という文章だ。「彼女は声が素敵な人だった」から始まるこの話は、二年間の遠距離恋愛でたくさん電話で話して、でも、別れることになる。別れた後、一度だけ電話で彼女と話す機会があって、声を聞いたら、声が昔とは全然違っていた、というところで終わる。あんなに素敵だった声がもう濡れてなくて、気持ちが変わるとここまで変わるんだ、ということと同時に、あのとき自分がどんなに愛されていたのかを実感する、という話だ。
正直で恥ずかしい話の告白の間に挟み込まれる、切れ味の良いセンチメンタリズム、抑えきれないんじゃなくて、抑える気なんかない熱気が気持ちの良い本で、読んでいる最中もさまざまな思いが胸の中に生まれて、ごちゃ混ぜになってうねっていくような感覚に襲われる。音楽を作る人の言葉だからなのだろうか。
「俺のがヤバイ」(滝原勇斗/飛鳥新社)

ライター。『女子をこじらせて』(ポット出版)で書籍デビュー。以後、エッセ イを中心にカルチャー系の分野でも執筆。近著に『東京を生きる』(大和書 房)、『自信のない部屋へようこそ』(ワニブックス)がある。