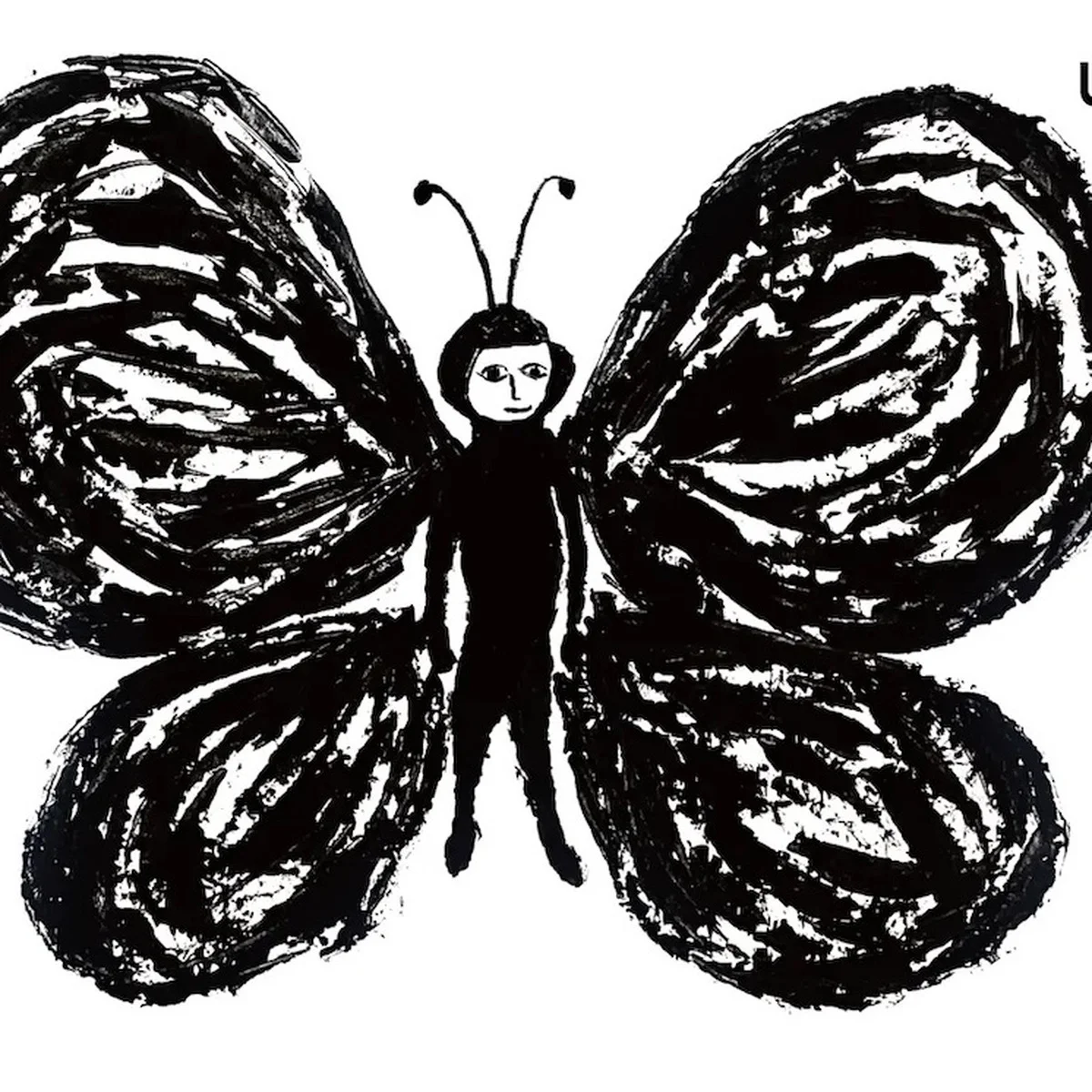"他者の靴を履く足"※1を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。

ブレイディみかこライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国ブライトン在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)、『女たちのテロル』(岩波書店)など、多数著書あり。
いまの時代精神を体現する色はグリーンなのだそうだ。理由は深く考えてみなくてもわかるだろう。人類はついに環境問題を重要視するステージにたどり着いたのである。グリーンは正義だ。グリーンは新世代の色。そんなわけで街を歩いてもグリーンの服やバッグがやたらと目につく。
しかし、このグリーンはやけにストレートだ。あるカラーがファッションとして流行するとき、普通はもっとひねりというか、「色のあわい」があるものだろう。が、昨今のストリートで見るグリーンは、オリーブ色でもなければ、モスグリーンでもない。基本の8色だけが入ったクレヨン・セットのグリーンのような、単純でわかりやすい色なのである。
この色は「ボッテガ・グリーン」とか「ズーマー(Zoomer※2)・グリーン」とか呼ばれている。英国では、イタリアのメゾン、ボッテガ・ヴェネタのクリエイティブ・ディレクターのフルネームを知っている人より、「ボッテガ・グリーン」という言葉を知っている人のほうがはるかに多いだろう。英国でも大流行している抹茶ラテのような、雨上がりの公園の芝生のような目にも鮮やかな色。
いや、これはクロマキー合成のグリーン・バックの色なのかもしれない。デジタル・テクノロジーを使いこなす世代の色にふさわしい。いや、でも待てよ。「主人公はわたし、背景なんて勝手に作り替える」という傲慢さは、「これからは人間が主人公ではなく、われわれの環境を大切にしなければ」というグリーンな思想とは矛盾してやいないだろうか?
いずれにせよ、数年前までヒップとされたミレニアル・ピンクを、グリーンは完全に塗り替えた。ピンクはトランプ前大統領に代表されたマチズモに対抗するための色であり、ジェンダーの自由を象徴し、既成概念から解放されるための色と言われた。ミレニアル世代のピンクも、Z世代のグリーンも、わかりやすいほど政治的なのである。
そうなってくると、わたしたちの世代の色は何だったのだろうと考えてしまう。ピンクにしてもグリーンにしても、”Pink is the new black””Green is the new black”と言われて何かと新しいブラックにされがちなのだが、ではブラックはいったいいつからいつまでの世代の色だったのだ?
パンク世代の人間としては、ブラックと言われて思い出すのは、70年代後半から80年代にかけて登場したUKの女性パンクロッカーたちの革ジャケットやわざと破いた網タイツやスリムジーンズの黒である。セックス・ピストルズの元親衛隊で、自分もバンドをつくって歌い出したスージー・スーなんかはとりわけかっこよかった。当時の彼女のファッションは後のゴスに引き継がれている。わたしも彼女に憧れて髪を逆立て、黒い犬の首輪を自分の首につけて歩いていた。シド・ヴィシャスの南京錠ネックレスだって、ステンレスのチェーンを通して再現し、安全ピンなんて大ぶりのものを何箱も買いあさった。パンク・ショップでそれらしいアクセサリーなんか売ってなかった時代である。ペットショップから金物屋まで、「あんた、そんなん何に使うの」と店主のおっちゃんに訝しがられながら素材を集め、DIYするしかなかった。
80年代になるとカラス族なるクラスターも出現する。こちらはパンクのDIYとは違い、デザイナー主導の黒ずくめのファッションで身を固めた若者たちだ。ひと目見れば「ギャルソンの」「ワイズの」とわかる高額な服を着たいかにも都会っぽい子たちも、家の近くでは「今日はどこで葬式があるんね」と近所の人に聞かれてしまうとこぼしていた。パンクもカラスも地域社会では「変な黒い服を着た子たち」という点で同じだったのである。
DIYパンク組と、デザイナー派カラス組のあいだに階級闘争は勃発しなかったし、いま思えば不思議なほど曖昧に交ざっていた。実際、クラブやライブハウスに集まった「変な黒い服を着た集団」は、服の色が画一的なわりには多様性に満ちていた。経済階層、性的指向、学歴、職業などはそれぞれ違っても、そこにSNSの時代のようなシャープな断絶や分裂はなかった。フィジカルに顔を合わせる場があれば、エンパシーなどという概念を知らなくても、なんとなく互いの環境や言葉の出どころを想像し合いながらつき合うことは可能だった。何よりもわれわれは、「可愛がられ、支配されるための女性のファッション」に対抗する黒い服の集団として、細かい違いで決裂せずに緩くつながっていた。
ところで、パンクやカラスには大先輩がいる。そもそも20世紀に黒い色をモードの世界に進出させたのはガブリエル シャネルだった。彼女が黒を打ち出したのも、派手な色彩のドレスを着ている当時の女性たちを見て、彼女たちに黒を着せてみたいと思ったからだと言われている。20世紀の初めまで、黒は喪服であり、メイドや店員の制服の色と考えられていた。が、シャネルはそうした既成概念を覆し、「リトル・ブラック・ドレス」を大流行させる。
さらに黒の歴史をさかのぼれば、19世紀のフランスのアナキスト、ルイーズ・ミシェルがいた。社会主義的共和主義運動の闘士としてパリ・コミューンで戦った彼女は、フランス本土を追放された後に帰国したとき、「もはや赤旗は要らない。これからはどん底の色、黒旗を掲げよう」と宣言し、ばーんと黒旗を掲げてみせた。以降、社会主義・共産主義の赤に対し、アナキズムの色は黒になったのだが、言い出しっぺが女性であったというのは特筆に値する。
翻って2022年。パンデミックの時代の色はグリーンだ。これは人々が希望を欲していることの表れかもしれない。鮮やかなグリーンは、信号の緑も連想させるからだ。そろそろ前進、というオプティミズムが求められている時期なのだ。
しかし同時に、パンデミックによる経済の落ち込みで打撃を受けたのは世界的に男性よりも女性だったという調査結果がある。そう考えると、グリーンはニュー・ブラックなのかもしれないが、黒をまったくの「オールド」にするのは時期尚早ではないか。どん底の旗を掲げて既成概念に抗う。そのスピリットはむしろこの時代にこそ、小さな違いを乗り越えたシスターフッドを立ち上げるかもしれないからだ。
※1 ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。
※2 Z世代のこと。1990年代半ば以降に生まれデジタルネイティブとも言われる。
SOURCE:SPUR 2022年5月号「ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY」
illustration: Yuko Saeki