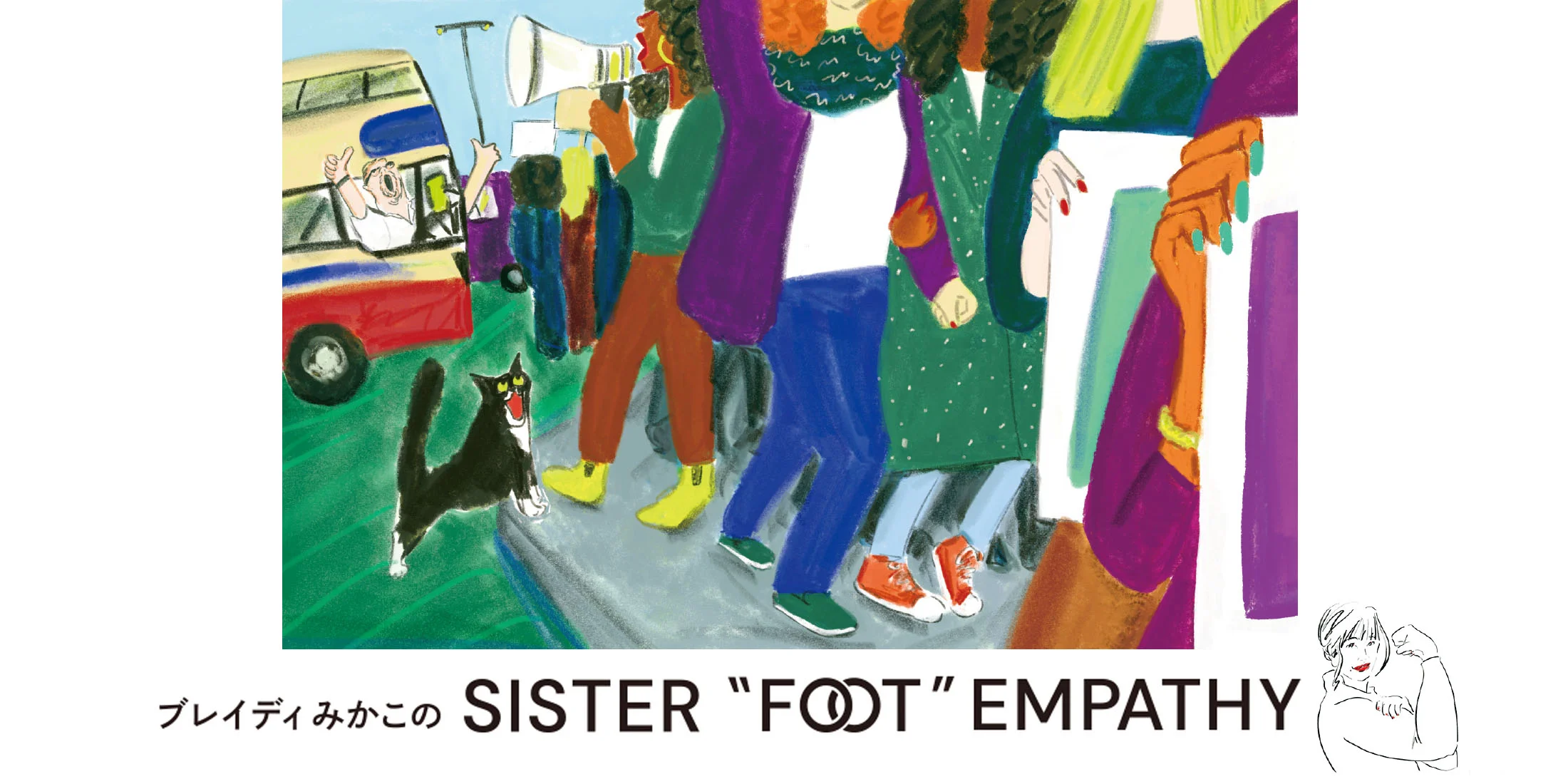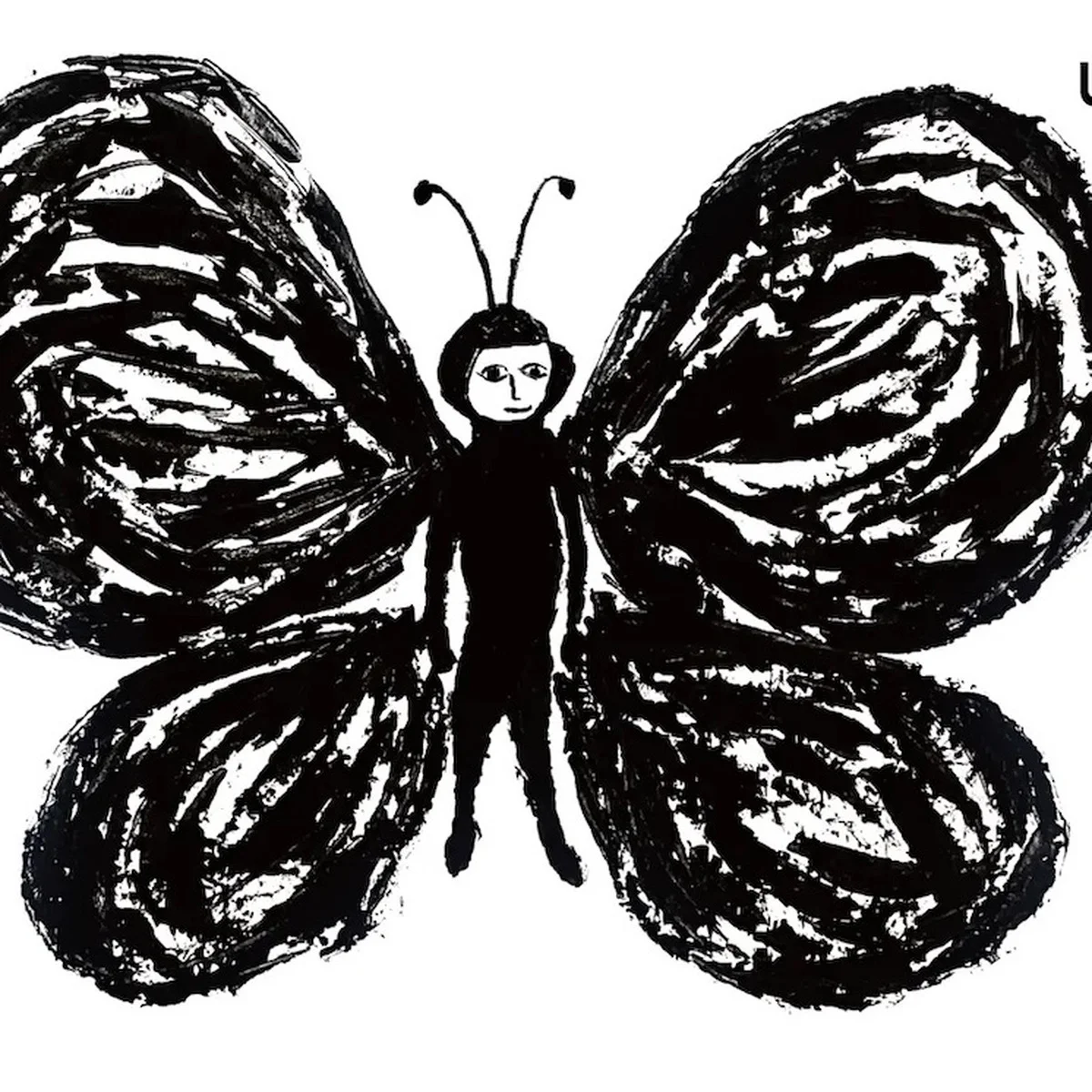"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

今季の英国の冬は「ストライキの冬」と呼ばれた。過去30年間で最大規模といわれる鉄道のストライキが初夏から断続的に続いているのに加え、看護師、救急隊員、郵便局職員、教員など、コロナ禍中に「エッセンシャル(必要不可欠)」な仕事をしている人々と呼ばれ、称賛された労働者たちが、まるで波状攻撃のようにストを打ち続けている。
わが町、ブライトンにもロイヤル・サセックス・カウンティ・ホスピタルという大きな病院があり、スト中の看護師たちが病院の前に大勢集まってデモを行なっている姿を見た。狭い片側一車線の道路の真ん中まではみ出してプラカード片手に叫んでいる看護師たちの集団に、車がクラクションをさかんに鳴らしている。邪魔になるから道路にはみ出るなと言っているのかなと思いきや、そうではなかった。バスやタクシーやトラックの運転手たちが、窓を開けて片手を出し、親指を突き上げながら「頑張れよ」と声をかけているのだ。「労働者の連帯」という、いまや遠い昔の、80年代を舞台にした映画(『パレードへようこそ』『リトル・ダンサー』など)でしか見られないと思っていた光景が、2023年に目の前で展開されていた。
デモに参加している看護師たちの大半は若い女性たちだったが、NHS(国民保健サービス)の看護師は移民が多いので、非常に多国籍な集団で、一見するとどこの国のデモだかわからない。しかも、ブライトンは英国のゲイ・キャピタルと呼ばれてきた街であり、医療従事者にもLGBTQ+の人々が少なくない。
つまり、ブライトンの病院の前に集まっていた看護師たちは国籍もジェンダーもセクシュアリティも多様性に満ちた集団だったのだが、近年は「多様性の敵」扱いされていた労働者のおっさんたちが路上に立つ看護師たちを応援していた。その姿は、分断の時代と呼ばれるいまだからこそ妙に感動的だった。
物価高と光熱費の高騰で、末端の労働者たちの生活が一様に苦しくなっているいま、垣根を越えて連帯し、必要なものを勝ち取っていこうという機運が高まっているように思う。労働運動が盛り上がっているというと、じゃあジェンダーや差別の問題はどうなるのかという人たちもいて、不毛な陣取り合戦が始まるのが過去の悪習だったが、昨今のフェミニズムは労働運動と結びついている。というか、女性たちの運動は最初からそうだった。
たとえば、名探偵シャーロック・ホームズの妹が活躍するNetflixの「エノーラ・ホームズの事件簿2」には、1888年に英国で実際に起きたマッチ工場の女性工員たちのストライキが出てくる。ロンドン東部のマッチ工場で現実にあったこのストライキには約1400人の若い女性や少女たちが参加したといわれており、彼女たちは14時間労働をしてもわずかな賃金しかもらえず、遅刻したりトイレに行ったりすると罰金さえ取られていたそうで、工具も自分で買わされていた。劣悪で不衛生な労働環境のためリン性壊死にかかる工員が続出し、雇用主であるブライアント&メイ社はこの事実を隠蔽しようとしていた。これに怒って立ち上がった女性たちのストライキは、英国全土に非熟練労働者の労働運動が広がるきっかけになったといわれている。
そもそも、「どうしてこんなに労働をしているのに賃金が安いの?」とか、「これだけ家事労働しているのに無収入なのはなぜ?」とかいうような「搾取されている」感覚が女性たちの原初の不平等への目覚めだったのは間違いない。搾取という言葉がいかめしすぎるなら、「ぼったくられ」感でもいい。人は誰しも、ぼったくられるのは嫌だし、腹が立つものなのである。
それなのに、あまりにも長い間、「ぼったくるな」と闘う運動がアンファッショナブルになり、ともすれば恥ずかしいことのように見なされてきた。差別や多様性の問題で立ち上がるのはクールでも、賃上げを求めて労働争議とかやっちゃうのはダサい、みたいな固定観念が出来上がってしまったのだ。
だが、「エノーラ・ホームズの事件簿2」のような人気ドラマが賃金や労働待遇の改善を求めて闘う女性たちを取り上げるようになったのは、潮目の変化を表しているだろう。英国では明らかに変化が起きているからだ。おっさん臭いイメージだった労働組合の指導者も、ここ数年で続々と女性に代替わりした。英国最大の労働組合ユニゾン初の女性事務総長クリスティーナ・マカネアをはじめ、英国第2の組合員数を持つユナイトの初女性書記長シャロン・グレアム、大学およびカレッジ組合UCUのジョー・グレイディ書記長など、いま英国で起きている大規模ストライキを引っ張っている組合のトップは、実は女性たちなのである。
これは新しい動きのように見えて、実はフェミニズムの先祖返りでもある。いまからおよそ100年前に女性参政権を求めて闘った英国のサフラジェットたちには、労働者階級の女性たちも多くいたことが知られており、彼女たちもまた、参政権を持つことで自分の生活を少しでも楽にするために闘っていたからだ。サフラジェットといえば、その核となる団体WSPU(Women’s Social and Political Union)の指導者エメリン・パンクハーストとその娘のクリスタベルが有名だが、パンクハースト家にはこの二人から破門されたシルビアという娘もいた。彼女は、参政権を持っていなかったのは女性だけでなく、一定の資産と財力を持たない男性たちも同様だったことに重要性を感じていた。だから、参政権のない労働者階級の貧しい人々に目を向け、労働組合や男性たちとも共闘した(そしてそのためにWSPUから追放されてしまった)。シルビアにとっては、女性に参政権がないのは「女性差別」だが、資産のない男性に参政権がないのは「経済的差別」だった。そして差別はともに撤廃すべきものだったのである。この視野の広さは、明らかに彼女のエンパシー(他者の靴を履く姿勢)がもたらしたものだ。
こうしたシルビアの考え方は、ストライキが復権している2023年にこそ見直されるべきものだろう。シスターフッドは女性の連帯だが、シスター〝フット〟(女性たちの足もと)には泥臭い労働と経済の問題が転がっている。再び足もとに戻る時代が来たのだ。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。