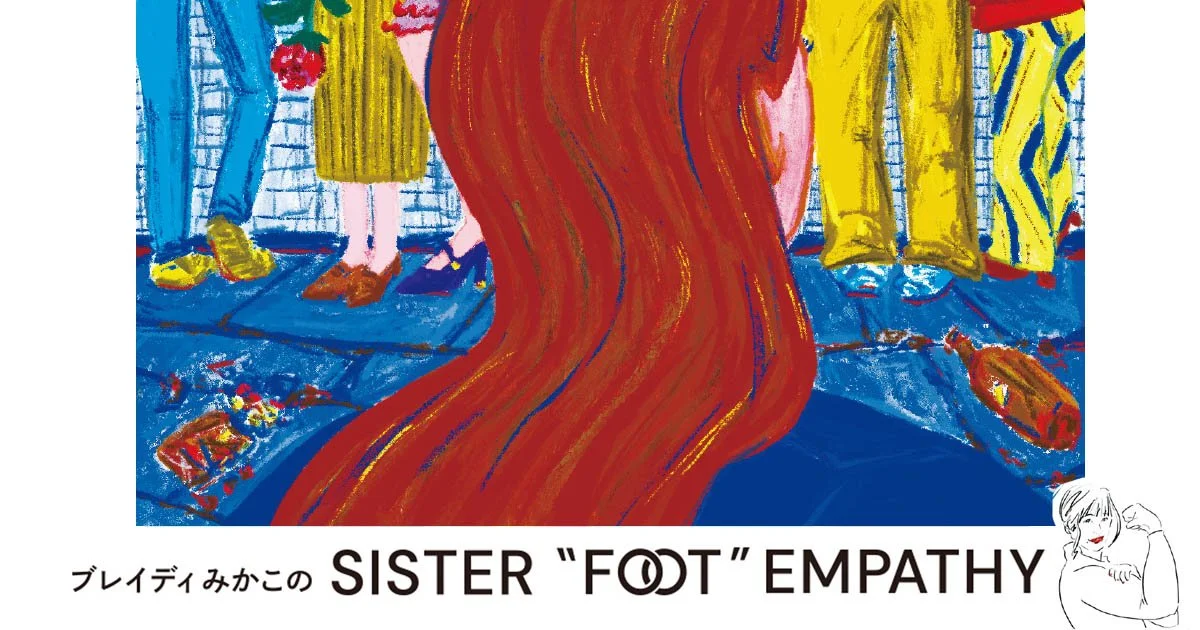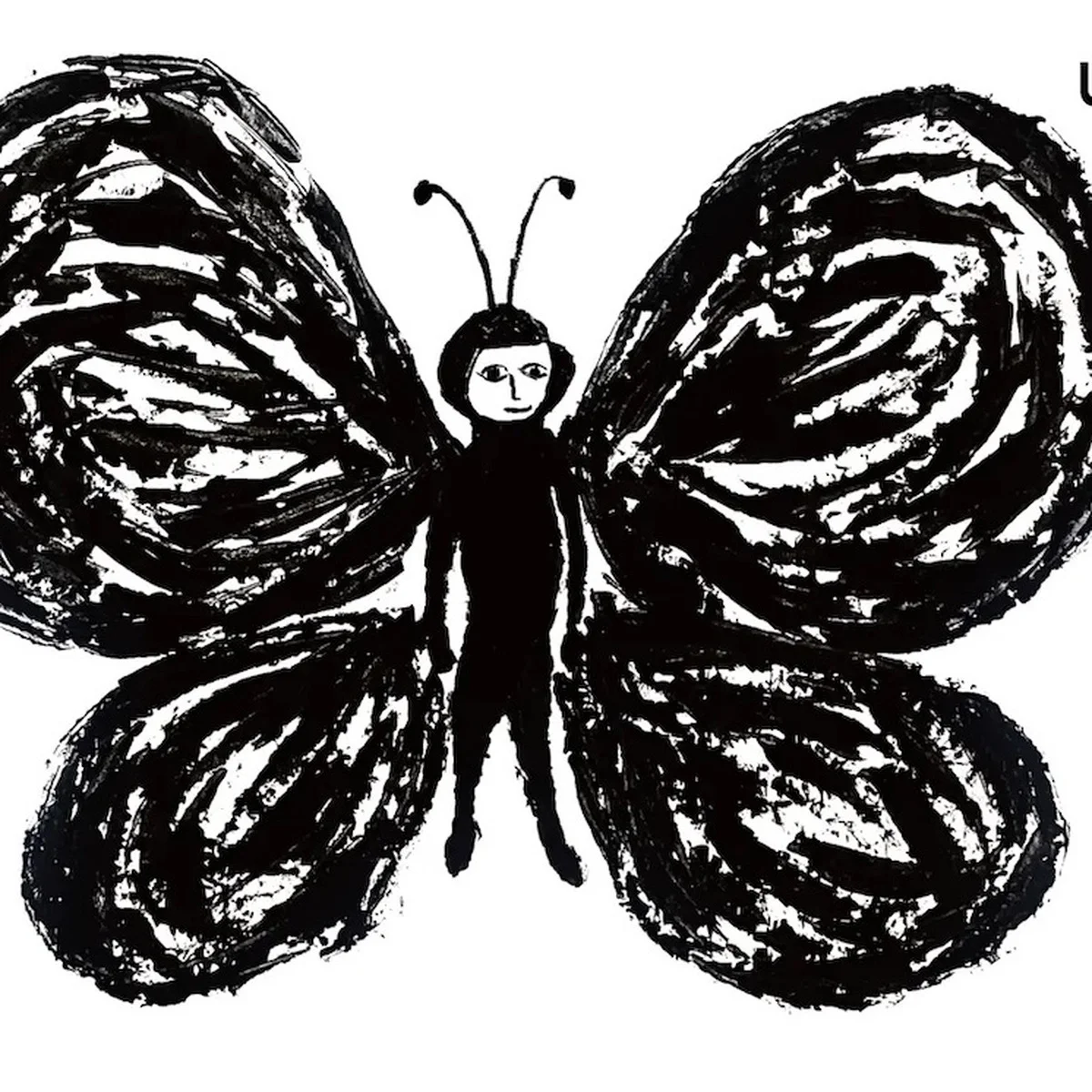"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
帰省中に女性向けメディアの取材をいくつか受けたが、必ずと言っていいほど聞かれた質問がある。
「日本の女性たちは自分をポジティヴにとらえられない人が多い。どうすればもっと自分に自信がもてるようになるのでしょうか」
おお。日本でもそういうことが言われるようになってきたか、と思った。「もっと自信をもって」「ラヴ・ユアセルフ」「自分を認めてあげよう」みたいな言葉は、過去10年ばかり、英国では女性向けメディアのスローガンであり続けたからだ
他方では、こうした風潮を「自信カルト」と呼んで批判してきた人々もいる。このような人々の主張はこうだ。まず、女性の生きづらさの原因を、本人たちの自己肯定感の低さにしてしまうと、それは女性側が何とかしなければならない問題になる。さらに、自信のなさを個人の欠陥と定義してしまえば、それは矯正しなければならない資質ということになる。実際、企業の女性リーダーや女性政治家などは、女性の成功の秘訣に「自信をもつこと」や「ポジティヴな考え方」を必ずと言っていいほど挙げる。が、こういうことばかり言っていると、女性指導者が少ない国は自信のない女性が多いからだ、ということになってしまう。なぜ女性が自信をもてないのかという構造的、環境的な問題がカムフラージュされ、すべては個人の内面的資質の問題(ポジティヴになれない、自分を愛せない)に還元されてしまうのだ。「自信」「自分を愛する」というと、いかにもポジティヴでいい感じの言葉だが、女性の不安や自信のなさを「それは個人の内面的な問題」で片づけてしまうのは、きわめて自己責任論的とも言える。
近年、特に「自信」と関連づけて語られてきたのがボディ・イメージの問題だ。どんな体も美しいというキャンペーンが展開されてきた一方で、摂食障害の問題を抱える人々の数は減っていない(どころか、英国などはコロナ禍中に増加している)。「みんな違ってみんないい」と考えられるようになりましょう、そう考えられないのはその人の問題です、というやり方では解決できない何かがあるのは明らかだ。
そういえば、8年ほど前、あるパーソナル・ケア製品のブランドのキャンペーンが話題になったことがあった。これは、自分に自信がもてない数名の女性たちに、おおよそ2週間のあいだ「ビューティ・パッチ」というパッチを貼って過ごしてもらうという実験だった。このパッチには、だんだん自分は美しいと感じられるようになる効果があるのだと女性たちは医療専門家に説明される。そして実際に、パッチを貼って日常生活を送った女性たちは、徐々に自信がもてるようになったと語り、体を露出する服が着られるようになったという人さえいた。が、実のところ、このパッチは偽薬であり、何の医療効果もないということが最後に明かされる。つまり、この実験を行なった企業が言いたかったのは、こういうことだろう。
――女性の自信は「気のもちよう」であり、ポジティヴ・シンキングで自信のなさは克服できる。
だが、自信というものはそれほど主観に基づいているのだろうか。たとえば、特定の服を着たり、特定の化粧品をつけると自信が湧くという人の話をよく聞くが、それにしたって、その服を着たり、化粧品をつけたりしていると誰かに褒められたことがあるからだろう。褒めてくれる人がいるという環境や、褒められたことがあるという経験は、「気のもちよう」とは違い、他者を必要とする。
さらに、自信を与えてくれる環境や経験は必ずしもポジティヴではない。死ぬほどつらい失恋の体験を乗り越えたという経験や、逆境を生き抜いたというサバイバル経験が自信に結びついていることもある。「あたし、追い込まれたらけっこうやれる」というやつである。いぶし銀のような揺らがぬ自信を感じさせる女性たちは、だいたいこのタイプだ。
自信が単なる「気のもちよう」であるならば、自己啓発本を読んだり、セミナーに通ったりすれば得られるだろう。が、本物の自信というものは環境と経験によってどっしりと培われるものなのである。であれば、日本の取材で冒頭のような質問を何度も聞かれるということは、女性たちを取り巻く環境的、経験的問題があるのではないかと考えるのが妥当だろう。つまり、女性が自信をもてなくなるような環境や経験がふんだんにあるのではないだろうか。
保育士時代にわたしの師匠だった英国人女性は、貧困地域に無料託児所を立ち上げた人だった。その託児所では多くの女性たちが働いていた。保育士資格取得のため実習しているシングルマザーや移民の女性たち、福祉や児童心理学を学びながら託児所でボランティアをしている人、依存症や精神の病から回復中の人など、さまざまな女性たちを受け入れていた師匠は、こんなことをよく言っていた。
「女性の自信を育てるのに最も必要なものは、コミュニティです」
師匠はまた、女性どうしが競い合い、足を引っ張り合わなければならない環境があるとすれば、それは男性中心の社会の中で「女性の椅子の数は限られている」という固定観念が存在するからだと言っていた。女性の自信と家父長制は強く結びついていると師匠は信じていた。そうだとすれば、それは個人が自分の内面と向き合って克服できる問題ではない。だから師匠はコミュニティの重要性を語っていたのだろう。
そもそも、自信を身につけるプロセスはそんなにキラキラしていない。必ずしもポジティヴではない経験や失敗、傷つくこと、そしてそこから立ち直ることもこのプロセスには含まれている。だからこそ、わたしたちは一人でそれを成し遂げることはできないのだ。話を聞いてくれる人、支えてくれる人、ただそばにいてくれる人の存在が要る。まさに女性たちのコミュニティ(=シスターフッド)の出番なのだ。
パンデミックや経済不安で先が見えない時代に、女性たちの足もとを照らすスローガンはきっと以前とは違うはずだ。いま必要な言葉は、「もっと自分に自信をもって」ではなく、「わたしたちは互いを必要としている」ではないだろうか。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。