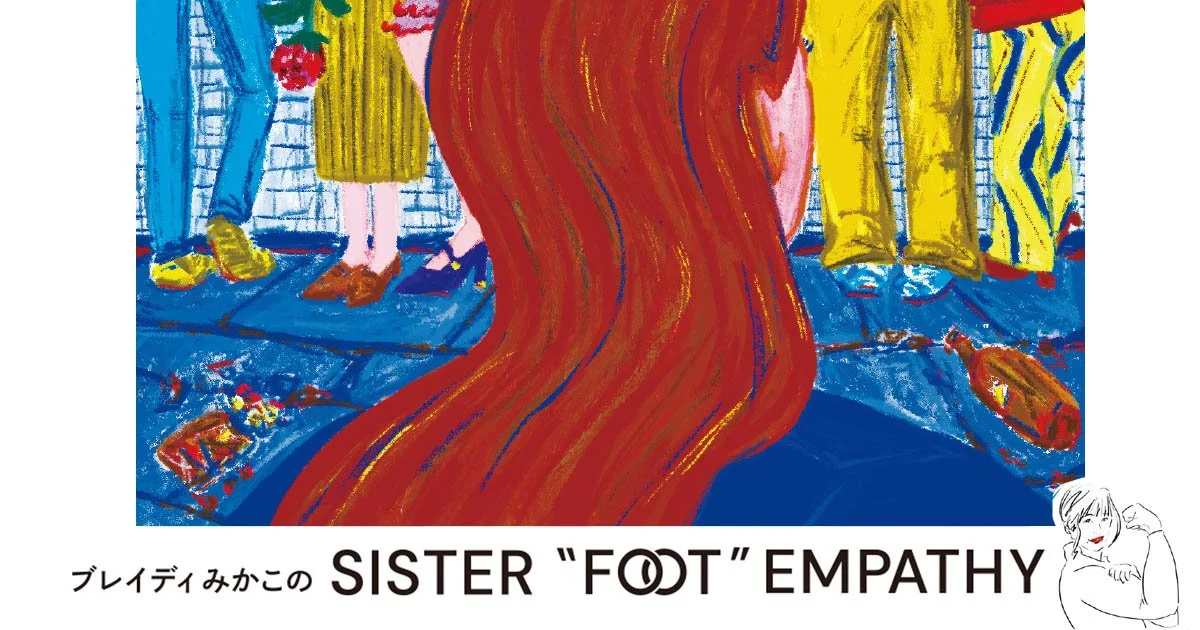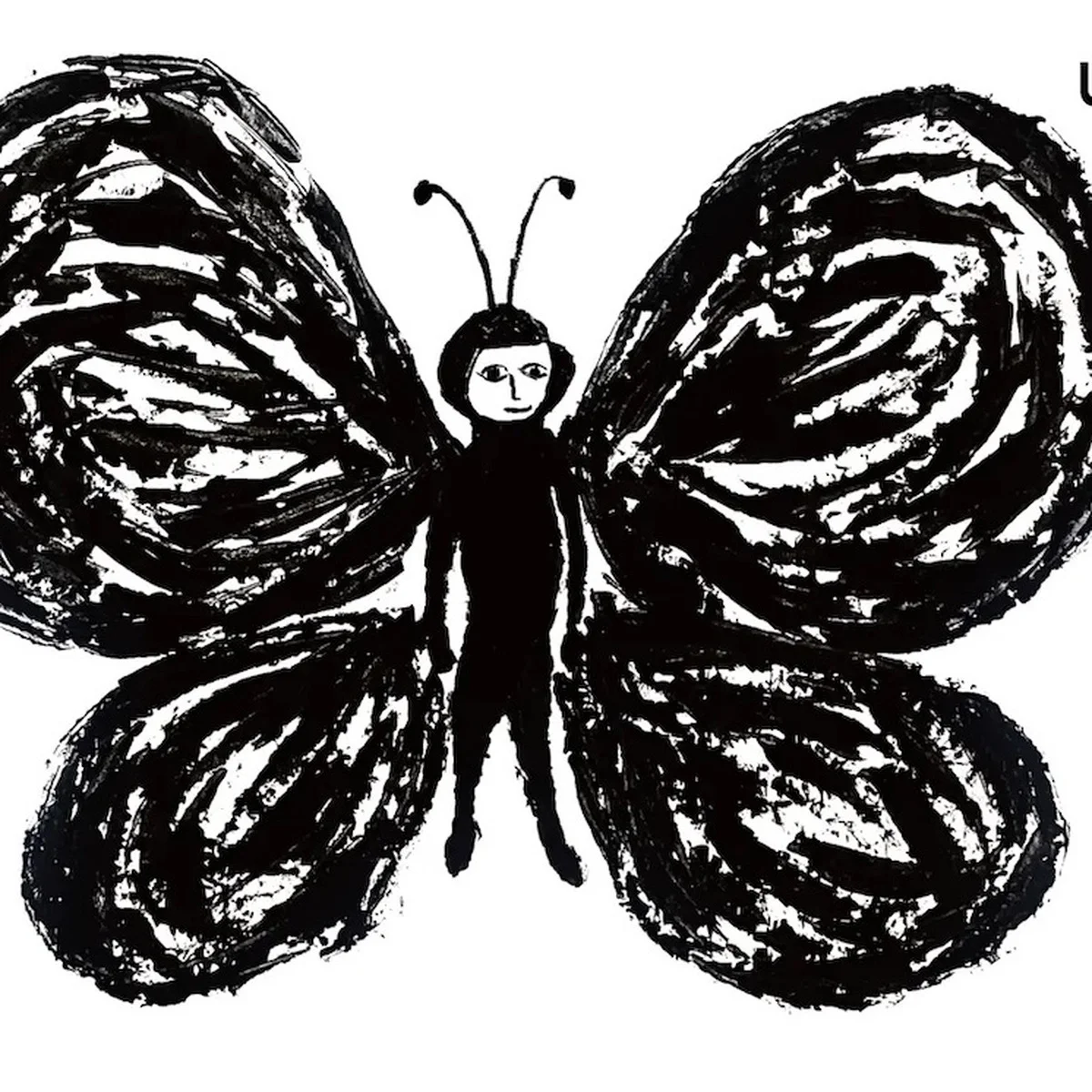"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。

今年の夏は3年ぶりに日本に帰省したのだが、おかげで目撃し損ねてしまったのが、サッカーの女子イングランド代表チームのEURO初優勝に対する現地の反応だ。「サッカーの母国」イングランドでは、ワールドカップとUEFA欧州選手権(EUROと呼ばれる)は常に二大イベントとして受け取られ、イングランド代表の試合の時間帯にはストリートに人がいなくなるぐらいの大騒ぎだ。
しかし、強豪のイメージがあるわりには、1966年にワールドカップで優勝して以来、両大会を制したことがない。が、2021年に(コロナのために一年遅れで開催された)EURO2020年大会で決勝に進出、(結局はイタリアに敗れたのだが)英国は盛り上がりに盛り上がった。そのときに国中で交わされた言葉が「イッツ・カミング・ホーム」だ。これは「スリー・ライオンズ」というイングランド代表チームの応援歌の歌詞の一部。この歌詞を延々と繰り返すこの応援歌は、代表チームの試合中も歌われるが、負けたときにも歌われる。「我々は信じている。それは母国に戻ってくる。サッカーは母国に戻ってくる」と英国の人々は涙ながらに歌い、イングランド代表が再び優勝する日を半世紀以上も待ちわびていた。
ところが、今夏、女子代表チームがつるっとそれを成し遂げた。
優勝後の記者会見の席に入ってきたときの女子代表チームのメンバーたちは、ぴょんぴょん飛び跳ねながら「イッツ・カミング・ホーム、イッツ・カミング・ホーム……」と大声で合唱していた。「勝てないイングランド」の惜敗と悲願を象徴する、はっきり言って暗い呪いの歌だった「スリー・ライオンズ」を、彼女たちは陽気でからっとした歌に変えたのである。「あたしらがやってやったぜ」と言わんばかりのその光景はあまりに痛快だったが、あの頃、英国の巷はとんでもないことになっていたらしい。
不在中のニュース番組のビデオをチェックしていたら、この夏の女性たちの熱狂ぶりが伝わってくる。ふだんはおもに男性たちが着ているイングランド代表チームのレプリカシャツを着て大勢の女性たちが集い、ビールを片手に、野外に設置された巨大スクリーンの前で叫んでいるのだ。フェイスペインティングをした娘を肩車して観戦している若いお母さん。イングランドの旗を体に巻いて大声で歌っている小学生の少女たち。
サッカーが火をつけたシスターフッドの大爆発。なんかそんな感じだ。
しかし、歴史を振り返ればそれも無理はない。彼女たちの歓喜の裏側には、あまりにも長かったイングランド女子サッカーの不遇の時代があるからだ。とは言っても、いまから100年以上前には、イングランドには女子サッカーの黄金期があった。1890年代にはすでに複数の女子サッカークラブが存在し、ロンドン北部のクラブの試合などは1万人以上の観衆を集めていたというし、第一次世界大戦が始まると、軍需工場で働いていた女性たちが昼休みなどを利用して練習を行い、女子サッカークラブが次々と結成されていく。男性たちは戦地へ赴き、FA(イングランド・サッカー協会)が男子サッカークラブのリーグ戦を中断したため、代わりに女子サッカークラブが人気を集め、観戦客もどんどん増えていった。ランカシャー州の軍需工場で働く女性たちで結成されたディック・カー・レディースFCなどは特に人気で、1920年12月にリバプールで行われた試合には5万3000人の観衆が集まり、入場できなくて帰された観客が1万人以上いたという説もある。この女子サッカーの動員記録は、2012年のロンドン五輪で女子イングランド代表チームの試合が7万人を超す観客を集めるまで破られることはなかった。この日の試合の収益は、戦争で障がいを負ったり、失業したりした元兵士たちを助けるために使われたそうだ。集まったチケット代は、当時のイングランドにおけるチャリティ試合の収益としても新記録だったと新聞が伝えている。
このような人気の高まりの中で、FAは1921年に女子チームへのグラウンドの貸し出しを禁止し、事実上の女子サッカー禁止令を出す。その理由は、サッカーは女性には向かないスポーツだというものだった。
実際に、女性がサッカーをすることを快く思わない人々もいた。しかし、それよりも、FAは女子サッカーの成功に危険を感じたのだろう。女性たちのサッカーが大金を集めるようになり、労働者階級の人々を支援するような政治目的のためにそれを使い始めたからだ。FAのおじさまたちは、女性たちが勝手に物事を動かし始め、自分たちのコントロールが及ばなくなることを恐れたのだ。第一次世界大戦が終わって男子サッカーのリーグ戦が再開しても、女子サッカーの人気が衰えないことへの危惧もあったろう。
この禁止令は1971年まで解除されることはなく、半世紀近くも続くことになる。
もちろん、FAに認められることはなくても、諦めずに女子サッカーの灯を燃やし続けた女性たちはいた。だが、彼女たちの練習や試合の場は近所の公園やラグビー場などの限定的な場所に追いやられ、ひっそり活動することを余儀なくされた。まるで女子サッカーいじめのようなこの仕打ちは、イングランドの黒歴史の一つである。
だからこそ、今年の女子代表チームの優勝に泣いた人は多かったのだ。そして、代表チームのメンバーたちは、優勝したときに行われていた保守党の党首選の二人の候補者たちに手紙を送った。そこには、どちらが首相になろうとも、イングランドのすべての少女たちが学校の体育の授業でサッカーができるようにしてほしいと書かれていた。「現在、体育の授業でサッカーができる少女たちはほんの63%です。私たちが少女たちを発奮させても、彼女たちの多くは学校に行ってもサッカーができないのです」と記された手紙に、両候補はポジティブな答えを返した。
男子サッカーのように巨大な資本が動くビジネスにならなかった女子サッカーの歴史は、禁止され、締め付けられてもそのたくましい足でボールを蹴り続け、次の世代にボールを渡したシスターたちの歴史だ。今夏のイングランド女子サッカー代表の快進撃は、まさにシスター「フット」の勝利だったのである。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。