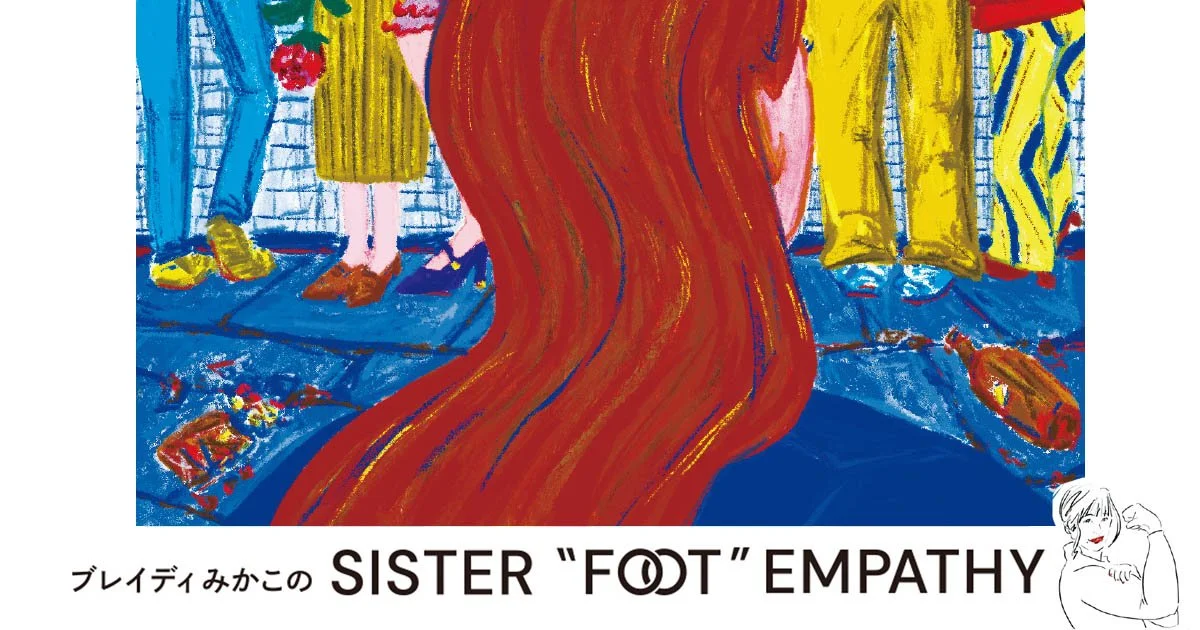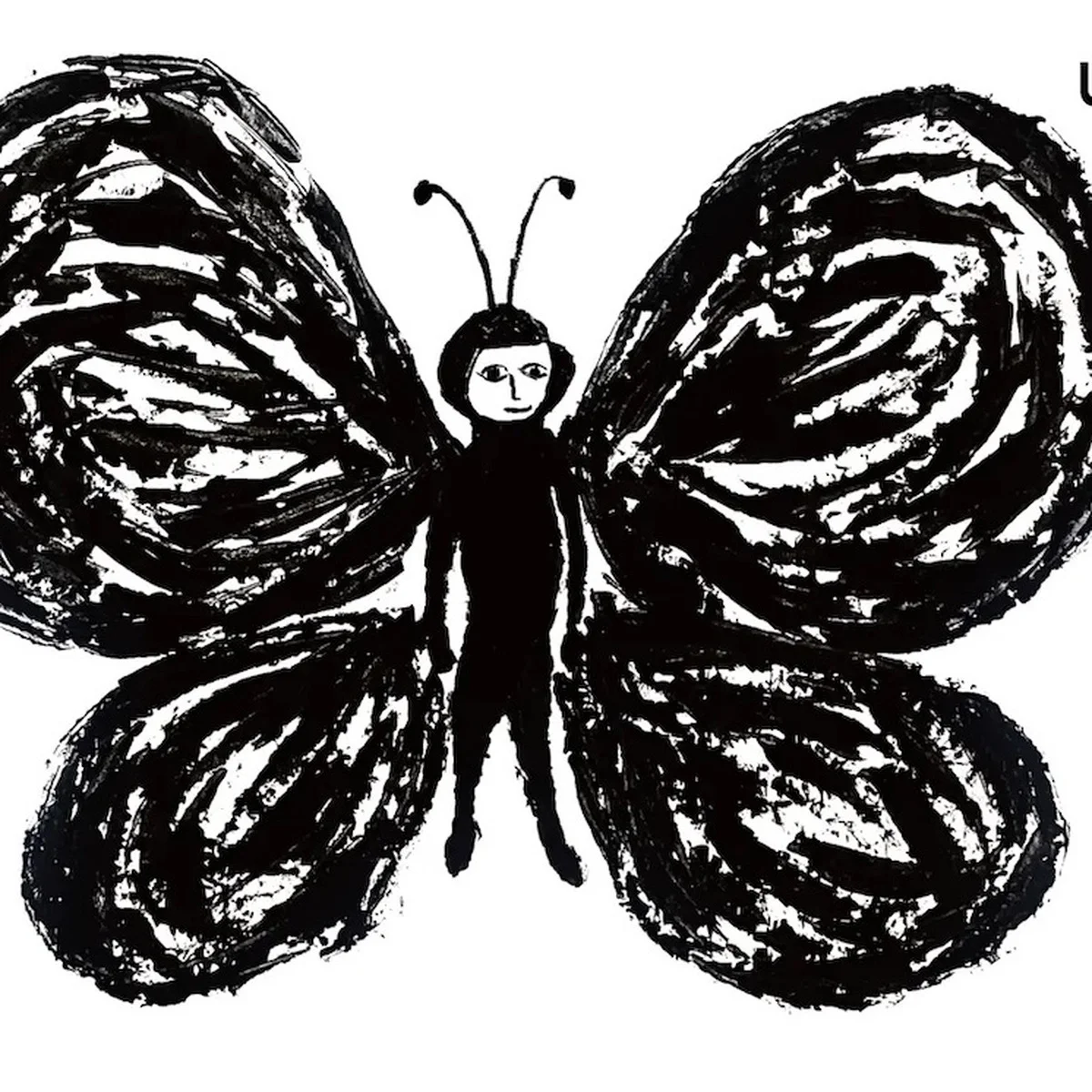"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
英国では10月最後の週末に夏時間が終わり、時計の針が1時間遅らされる。だから11月に入るといきなり日が暮れる時間が早くなる。昨日まで18時ぐらいまで明るかったのに、今日から17時になると日が暮れる、という唐突な変化が起きるのだ。
この変化に合わせて、生活スタイルを変える女性たちがいる。仕事を終えてからジョギングやランニングをしていた女性たちが、ジムで室内ランニングマシーンの上を走るようになる。
なぜだろう。
暗い公園や道端を走っていると、身の危険があるからだ。わたしの住むブライトンは海辺の町だが、少し内陸に入れば丘もあり、羊たちが戯れる田園地帯もある。この辺りの美しい光景を楽しみながら一人で走っている女性のランナーは、夏の間は多い。わたしの友人・知人にもそういう人たちがいる。一日中デスクに座って仕事をした後は、鮮やかな緑色に輝く丘陵やみずみずしい樹木の香りを嗅ぎながらストレスと疲れを癒やすという。わたしは走るより泳ぐタイプなのでよくわからないが、彼女たちにとって自然の中を走る時間がメンタルヘルスにもよい影響を与えているらしかった。
ところが、そうした女性たちは11月になるとその習慣を諦める。ひと昔前なら、あなたは女性に生まれたのだからしょうがない、自分で自分の身を守るしかないと言われただろう。だが、コロナ禍を経て英国の女性たちは変わった。
2021年3月、ロンドンの公園を歩いていた30代の女性が殺害される事件が起きた。この時期はコロナ禍中でみんなテレビやネットでニュースを見ていたこともあり、また、容疑者の男性が警察官だったこともあって、女性たちの間で大きな反応を巻き起こした。
外出は禁止されていたにもかかわらず、亡くなった女性の追悼集会や、女性たちによるデモが発生し、警官が過剰に反応した映像がテレビやネットで流れたせいもあって各地に抗議運動が飛び火した。何を隠そう、うちの息子が当時通っていた公立中学校でも、一部の女子生徒たちがデモを計画し、前もって決めた時間帯にいっせいに教室から飛び出し、プラカードを持って校庭をデモ行進した。そのときの動画を息子にスマホで見せてもらったが、「女の子たちはいつもロックダウンされている」と書かれたバナーが印象的だった。
女性たちは以前から、暗くなるとロックダウンされていたも同然だった。あの頃、抗議運動に参加していた女性たちがニュース番組でそう言っていたのを何度も聞いた。どうして女性だけが特定の時間に外出すると危険な状況にさらされるのか、そして、危険な目に遭ったとしても、「そりゃ夜道を歩いていたほうが悪い」と批判されるのか。なんか、おかしくない?という根源的な問いが女性たちの中に湧き上がったのである。ロックダウンで「移動の自由」という人権問題がさかんに議論されていたからこそ、わたしたちはコロナ禍じゃなくても移動を制限されているではないかと気づいたのだ。
そう考えれば、好きな時間にジョギングやランニングする権利も移動の自由と結びついている。だからこそ、「なんで女性だけが日没時間が早くなる時期になると戸外を走れなくなるのか」と感じる人が増えた。それが当たり前というこれまでの常識を疑うようになったのだ。
英紙『ガーディアン』には、男性の立場からこの問題について書いた記事が掲載されていた。元自転車競技選手でオリンピックの金メダリストでもあるクリス・ボードマンが、配偶者が冬は近所へジョギングに行かなくなることについてコラムに書いた。アスリートだった彼は、薄暗い季節ほどエクササイズをすることが、体のためにも、メンタルヘルスにもよいという信条を持っていた。だから、配偶者が外に出て行かなくなる季節になると、彼女にその持論を聞かせていたという。
しかし、ある秋の夕暮れ、配偶者と一緒に散歩していたとき、彼女が冬になると外に出て行ってエクササイズしない理由が彼にもわかった。彼女は、暗くなった戸外を歩きながら、そこを走っていると女性としてどんな怖い状況に出くわすかを一つずつ彼に話して聞かせたのだった。
英国の『Women’s Running』誌のサイトによれば、2022年の全国調査で、47%の女性たちがランニング中に叫ばれたり、ぶしつけな言葉を投げられたりした経験があると答えている。また、ほぼ11%の女性たちが、ランニング中に後ろからつけられたり、怖がらせられる経験をしている。
これらは女性ならみんな知っていることだ。
だが、クリス・ボードマンの記事を読んで気づくのは、女性なら当然わかることを男性は全然わかっていない場合があるということだ。冬の夕方に配偶者の女性が外を走らなくなる理由なんて一つしかないだろうに、体とメンタルにいいから冬こそ走るべきなんて説教していたのかと思うと、なんとも言えない気分になる。しかし、ボードマンは配偶者の言葉で開眼し、『ガーディアン』紙上で男性たちに呼びかけている。女性たちが戸外でエクササイズしているときには「距離を保て」「たとえ誉め言葉でもコメントしない」「友人や家族でも女性に失礼なコメントをする者がいたら、異議を唱え、なぜそれがよくないのか説明する」など、男性側ができることをコラムの中に書いている。
これは、女性どうしの「わかる、わかる」「わたしにもその経験がある」というシンパシー(共感)とは違う、男性側からのエンパシー(他者への想像力)だ。「シスターフッド大事」と言うと、よく男性から「ブラザーフッドはどうなるんだ?」と言われるが、男性と女性は、どっちが大事か合戦を繰り広げているわけではない。男性たちは、シスターたちのブラザーでもあるのだ。そして、ブラザーたちは自分の経験の外にあることはよくわからないということを想像せず、「言わなくてもわかってるはず」と憤るのは、シスター側からのエンパシーの欠如かもしれない。わたしたちの靴を履いてもらおう。他者の靴を履く人は、他者にも自分の靴を履かせる人でなくてはならないからだ。そうやってわれわれは、自分の足でいつだって自由に走り、移動することのできる社会に一歩ずつ近づいていくのである。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。