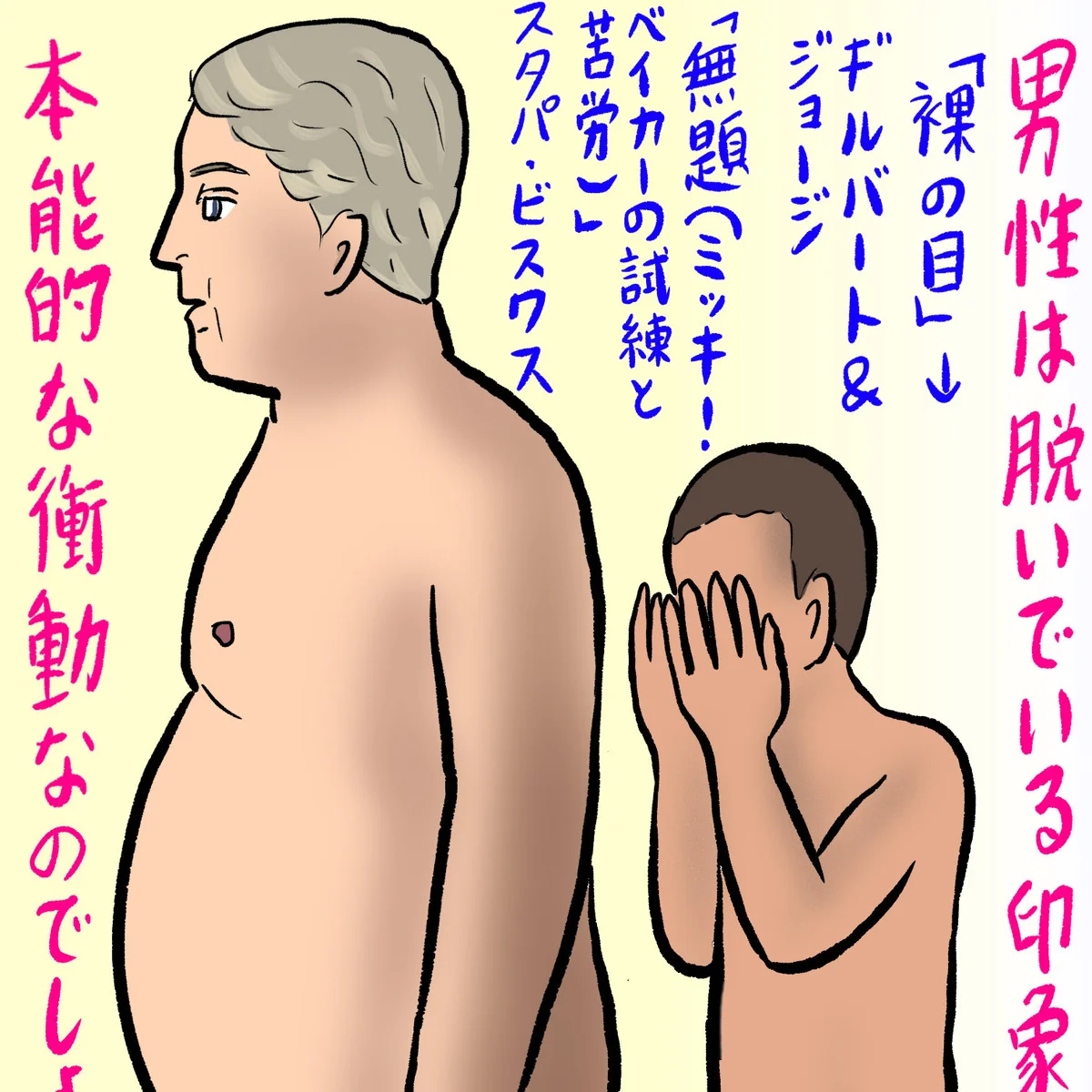アメリカ現代アート界の重鎮、クリス・オルデンバーグ。日用品をモチーフにした巨大なパブリックアートや柔らかい素材を使った“ソフトスカルプチャー”など前衛的な作品を生み出し、ジェフ・クーンズやレイチェル・ハリソンなどにも大きな影響を与えた人物だ。一匹狼で個人主義的。強烈すぎる変わり者ゆえ、美術史的にもさまざまな解釈をされてきた彼の、作家人生を回顧するインタビュー後編。
ポップアートの“挑発者”彫刻家、クレス・オルデンバーグ<前編>
彼と同時代の、すでに研究され尽くされた芸術家たちの何人かとは違い、オルデンバーグはインタビュー好きで、これまでに同じようなインタビューを何十回もこなしてきた。だが今日は、過去の作品をじっくり振り返りたい気分のようだった。彼が最初にフォルダから取り出したのは、シカゴで過ごした中学高校時代に描いた作品だった。スウェーデンの外交官だった彼の父のゴスタは、領事として米国に赴任するにあたり、家族を連れて1936年にオスロからシカゴに移ったのだった。
彼の娘はプラスチックのシート内に保管されている大量のスケッチを見てこう言った。「私、ここにあるものは全部見たといつも思っていたけど、これは今まで見たことがなかったわ」
戦時中のシカゴで育った経験を通し、ヨーロッパからやってきた本好きの子どもだったオルデンバーグには、アメリカの厚かましいまでの自信過剰さが強く印象に残った。それは無神経さと残酷さと、切っても切り離せないものだった。そのときの経験が、彼の初期の作品の混沌として不安に満ちた感覚につながる。これらの作品は、年を経てますます、この国の政治状況との関連性を強く物語るようになってきた。
彼の子ども時代のスケッチは、戦闘機を描いたものや、漫画の絵コンテ、同級生たちを誇張した似顔絵などで、特別なものではない。だが、そこには3つの点がはっきりと見て取れる。幼い頃から構図力がずば抜けていたこと。常に遊び心を忘れずユーモアに満ちていたこと。そして、建築物に対しては、エンジニアがもつのと同じレベルの情熱をもっていたことだ。彼の最も素晴らしいドローイングの多くが、驚くほど精密に書かれた設計図や建築デザインであったことは偶然ではない。もし、後期モダニズムにおける象徴的なアーティストを集めたクラブというものがあるとしたら、彼はそのオリジナルメンバーのひとりだといえる。同じグループのほかのメンバーには、ブルース・ナウマン、リー・ロザーノ、クリス・バーデンなどが含まれるだろう。

オルデンバーグは成人するまで芸術の道に進もうとは思っていなかった。「シカゴ美術館は子ども時代の私には、なんだかよくわからない場所だった」と彼は言った。「自分が行くなら断然、フィールド自然史博物館で、美術品を見るよりも物体を見ていたかった。ほかの何よりも、いつも物体にいちばん興味があったんだ」
1946年にイェール大学に入ると、文学に興味をもち、「新批評主義」を提唱した批評家クレアンス・ブルックスのもとで学んだ。だが、彼は普通の学生の枠に収まらなかった。「卒業する前に一度学校を去ったんだ」と彼は言った。「ある日、ふらりと列車に乗りニューヨークにやってきた。そして市役所の前の公園のベンチに座って『白鯨』を読んだんだ」。
20代前半はあちこちを転々として過ごし、ジャック・ケルアック(ビートニクの作家)信者のような生活をしていた。シカゴでは駆け出しの新聞記者として働き、川に浮かぶ死体を探すよう命じられた。広告代理店での仕事は、殺虫剤メーカーのために虫の絵を描くことだった。オークランドでは皿洗いをし、家賃を現金のかわりに絵画で払った。サンフランシスコでは詩人のローレンス・ファーリンゲティと出会い、ロサンゼルスでは命の危険に脅えた。「夕食の席でふたりの男の隣に座ったら、彼らは殺人計画を話し合っていた。神に誓って本当の話だよ。最初の頃、LAは自分にとってはすごく恐ろしい場所だった」(その他の作品もチェックする)
SOURCE:「Claes Oldenburg」By T JAPAN New York Times Style Magazine
T JAPANはファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。