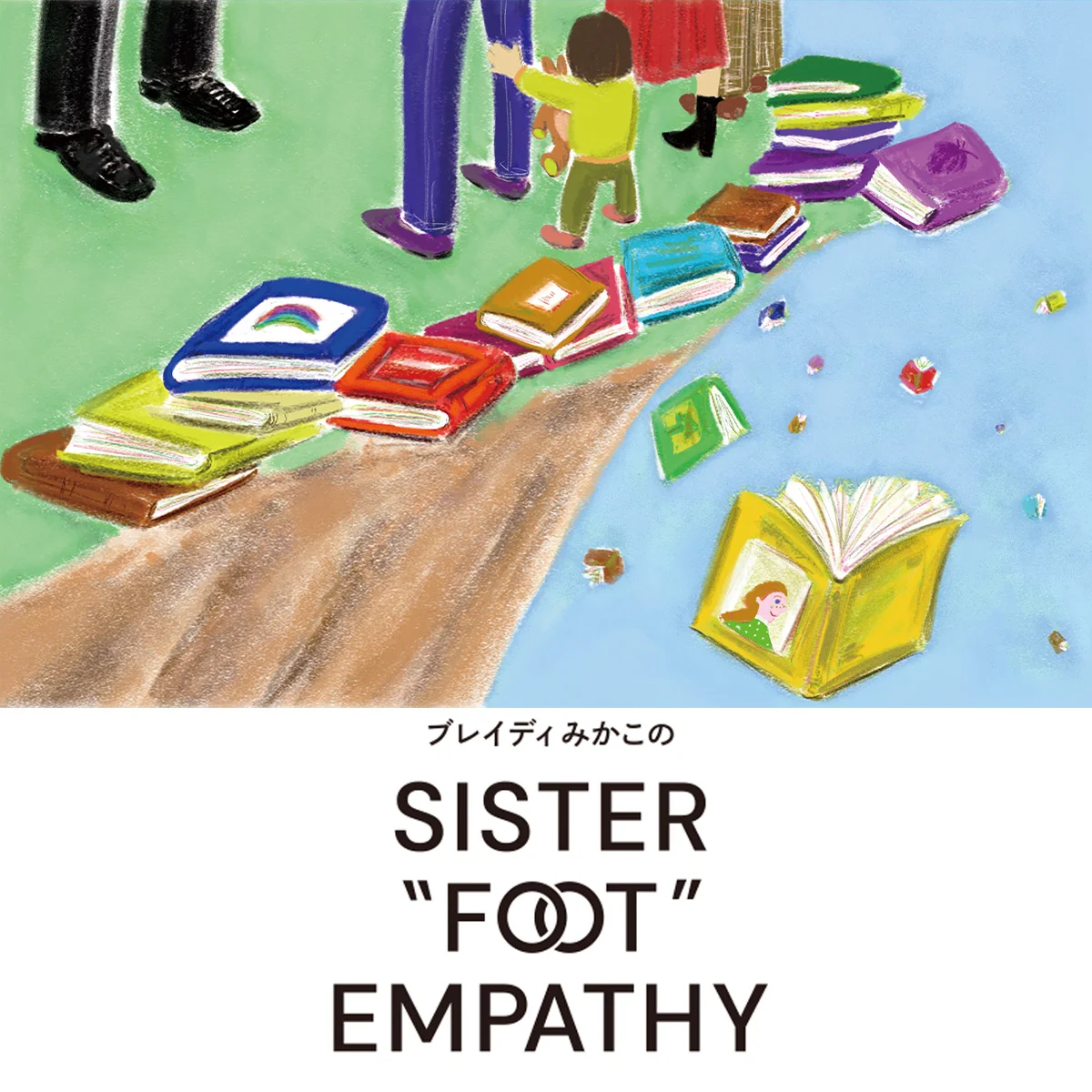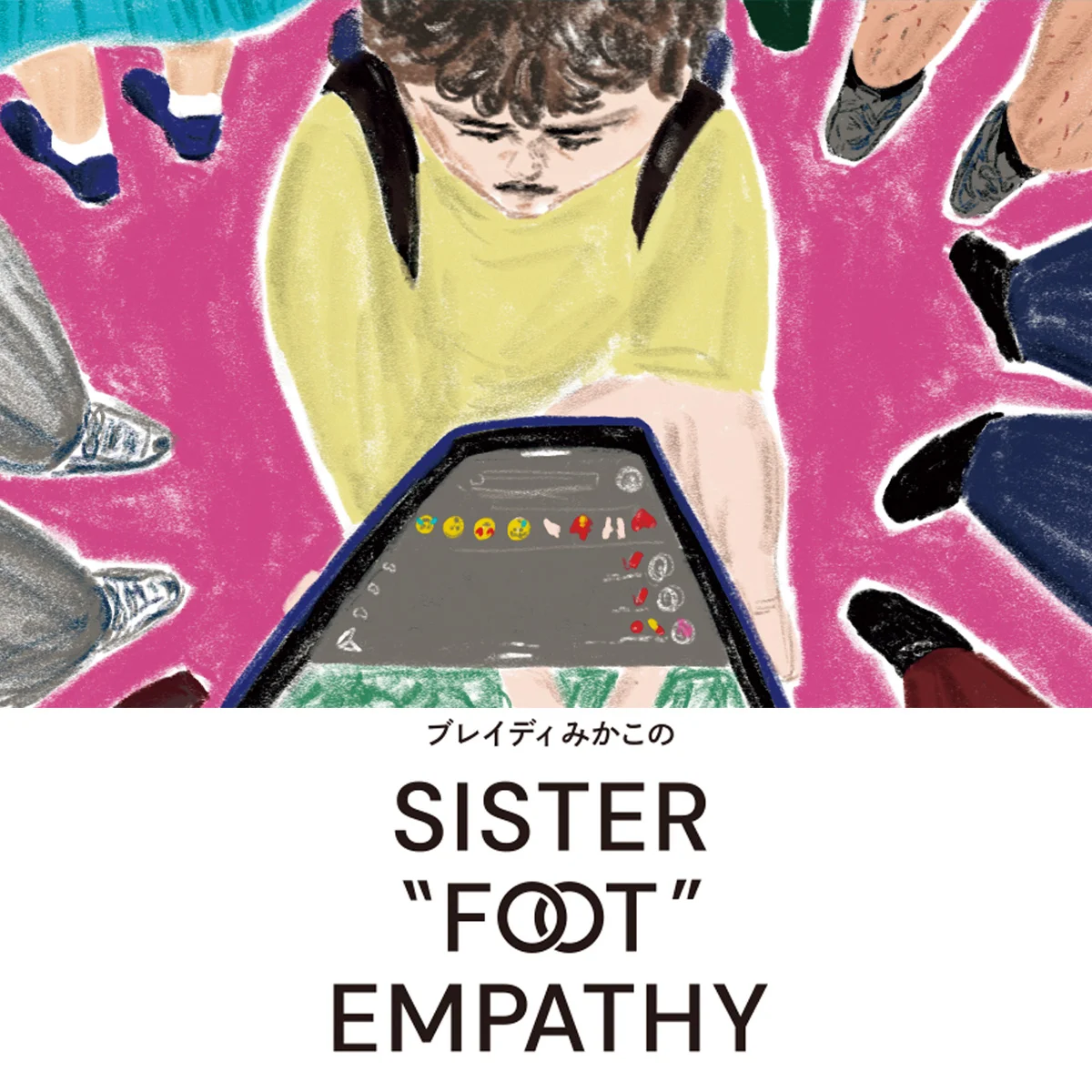ニューヨーク市内のレストランや家庭のキッチン、そして街の露店がグローバルな食材をまず最初に受け入れた。そしてそこから新しい食が広がっていった
そもそもの始まりはキウイだった。中国南部原産で、現地では「ミホウタオ」または「猿の桃」という名で知られる。フサフサの毛に覆われて葉緑素がたっぷり詰まった、内側が翡翠色のあの果物だ。ニュージーランドから米国に、まとまった量のキウイが初めて輸入され始めたのは1950年代のことだ。当時は「中国産グースベリー」と呼ばれていた。同じように毛がフサフサ生えているキーウィ鳥にちなんだ新しい名がつけられるまで、このフルーツは米国でほとんど普及しなかった。もしかしたら、共産国である中国に対する冷戦時代の恐怖心が原因かもしれない。

80年代初頭のニューヨークで市場を拡大した、かつてエキゾチックだった食材。(左上から時計回りに)コリアンダー、山羊のチーズ、ホワイトチョコレート、食用花のナスタチウム、天日干しのドライトマト、キウイフルーツとピンクペッパー 19TH-CENTURY MEISSEN PORCELAIN BUST OF GIRL, ALEXANDER’S ANTIQUES.
だが80年代初頭になると、マンハッタンじゅうのレストランを席巻するような勢いでキウイが普及し始めた。パイやペストリーはもちろん、フルーツサラダやコンポート、塩味のきいたデザートにまでキウイが使われた。白いバターソースにもキウイの緑色の風味が加えられた。1983年には、キウイはあらゆるスーパーの棚に陳列され、ケーキミックスの箱の裏側にキウイを使ったレシピが載るようになっていた。ニューヨーク・タイムズ紙は、キウイの流行はピークをすぎたと宣言した。
ともあれ、キウイはその使命を果たしたのだ。これまで親しまれてきたリンゴやオレンジやバナナ以外の、さまざまな色や形や食感をもつフルーツに人々の目と味覚を開かせたという意味で。ニューヨーカーたちは、表面に小さな斑点がたくさんついたアジアの梨や、湿った黒い種がぎっしり入ったパパイアを喜んで受け入れた。硬い皮をむくとなめらかで柔らかな白い実が出てくるライチ、ドアの取っ手のような形で中の果実はカスタードのような味わいのチェリモヤ、鋭くとがった星形で、プラスチックのような光沢のあるスターフルーツも歓迎された。はるか彼方からやってきた、見慣れない奇妙な皮や形でその実を包んだこれらの果物は、食料品店やスーパーの棚に根づいていった。確かに、キウイはまたたく間に誰もが話題にする存在になったし、ほかのどんな果物もキウイほどの圧倒的な人気は得られないだろう(ニューヨーク・タイムズ紙のレストラン批評家ミミ・シェラトンは、1982年にキウイを“フルーツ界の皇帝の新しい衣服”と呼んだ)。だが、キウイやその他の果物はいずれも、一見ありふれたように見えながら、じつは革新的な役割を果たしていた。すなわち、昔からずっとそこにあったように都会の風景の一部になるという偉業をなしとげたのだ。まるでニューヨークが─そしてのちにはアメリカ全体が、これらの果物なしでは存在しえなかったかのように。
しかしこうした恩恵には闇の部分もある。新しく入荷された生鮮食品は、決して安価ではなかったのだ。たとえば、しゃれたディナーパーティの席でデコレーションの氷柱に代わって主役となった、ある種のレタス。街に新しく開店したグリーンマーケットなどで買えるこのレタスは、ヨーロッパから輸入された高級なエキストラ・バージンオイルとバルサミコ酢で味つけされた。専門店ではこうしたさまざまな食品が手に入るようになった。天日干しのドライトマトや、円形をしたフランス産の山羊チーズ、シラントロとも呼ばれる新鮮なコリアンダー、食用花のナスタチウムにピンクペッパーといった品々だ。米国食品医薬品局(FDA)は1982年、毒性の疑いがあるという理由でピンクペッパーの米国への輸入を一時禁止した。だが、ソーホーの地元店としてアーティストたちを中心に支持されていた食品専門店の「ディーン&デルーカ」がピンクペッパーを回収すると発表すると、客たちの一部は花のように香ばしいその実を手放したがらず、こっそり隠し持つようになった。結果、市場に出回らなくなったピンクペッパーに、より高値がついただけだった。
60年代から70年代、自分の身体に何を取り入れるかという関心は、おもにカウンターカルチャーの思想からきていた。人工的なものより自然なもの、大量生産されたものより手製のものをよしとする価値観だ。アリス・ウォータースのような西海岸の活動家兼シェフたちが愛用してきた伝統的な手法で生産された食材が、当時のニューヨーカーにも歓迎されるようになった。その頃ニューヨーカーたちは、20年間にわたる社会的動乱と、70年代に起きた財政危機で疲弊していた。市の公共サービスを中心とするセーフティネットが壊滅状態にあっただけでなく、そのインフラを支えてきたリベラル思想そのものが意気消沈していた。そんな時代には思考が内向きになり、人々は公に背を向け、私事に目を向けるようになる。ロナルド・レーガン大統領時代の経済的好況もその一因だ。おかげで人々はついに、イタリアから空輸されたチコリやフランス産のクレームフレーシュ(サワークリームの一種)に散財できるだけのゆとりをもつようになった。政治的な選択だったはずの「食」が、個人的な贅沢の対象になった。革命はついに起こったのだ。サラダという形で。(グローバルな食事が広まる傍ら、廃れていったデザートは?)
SOURCE:「How It Changed ―― FOOD」By T JAPAN New York Times Style Magazine BY LIGAYA MISHAN,PHOTOGRAPHS BY PATRICIA HEAL, STYLED BY LINDA HEISS, FOOD STYLED BY REBECCAJURKEVICH, TRANSLATED BY MIHO NAGANO AUGUST 16, 2018
その他の記事もチェック
T JAPANはファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。