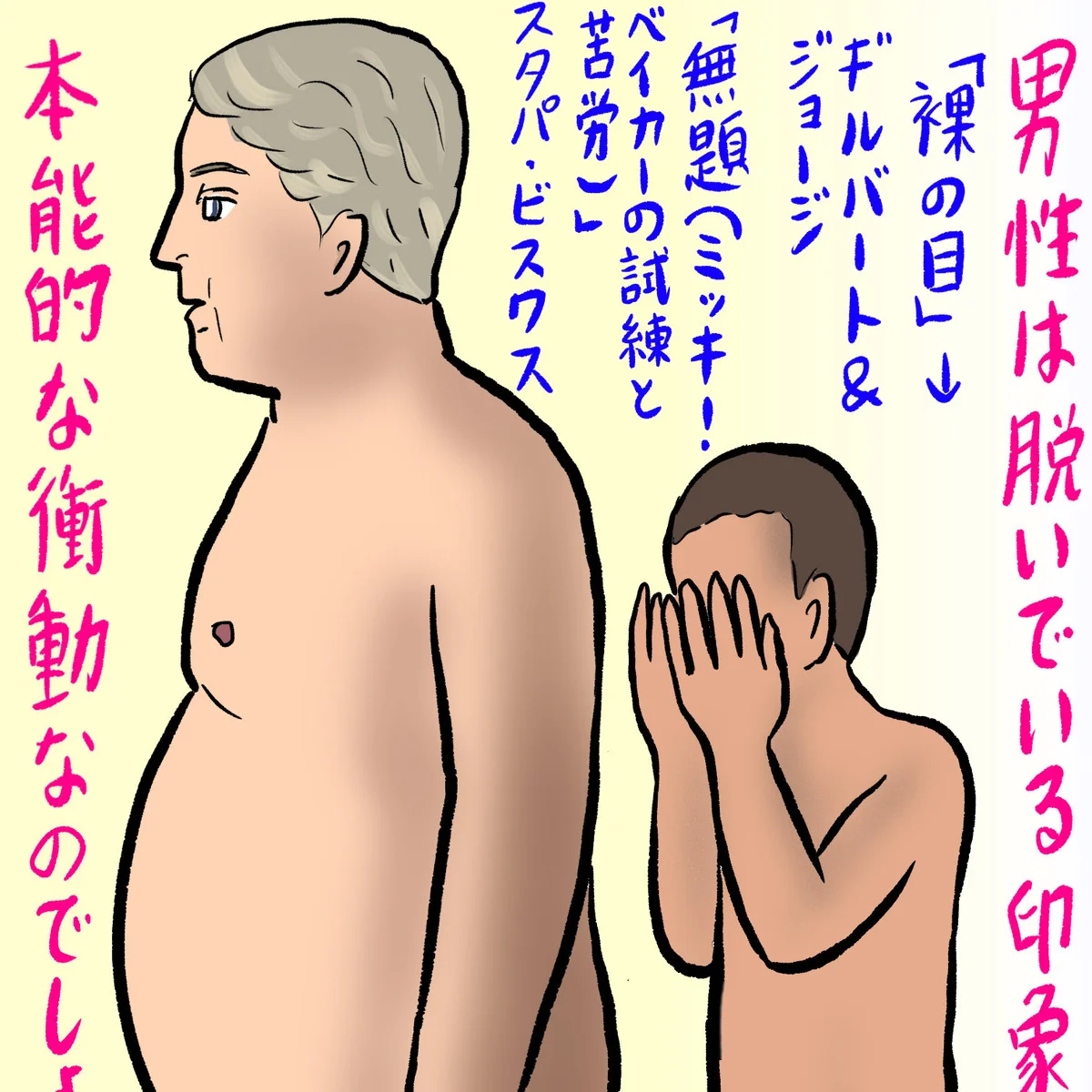東京・成城に、老若男女に愛される甘味処がある。つやつやの小豆は絶品、地野菜たっぷりの定食も評判だ。繰り返し食べたくなるやさしい味の作り手を訪ねた
つやつや、ふっくら。その小豆はぴかぴか輝いて、「食べて! おいしいよ!」と私に語りかけていた。口に含めば、上品な甘みとともに、やさしい滋味が広がる。今まで食べた煮小豆のなかで、もっとも好ましく、小豆らしい味わいだ。

煮小豆のおいしさをストレートに味わえる「白玉金時」¥995
作り立ての白玉はもっちり歯ごたえがあり、ふんわり柔らか。温かいバージョンもある
東京・成城にある甘味処「櫻子(さくらこ)」は1979年創業、40年の歴史がある。店内は広々していて、ビルの3階ながら自然光がたっぷり入る、気持ちのよい空間だ。店主の森田享子さんが穏やかな笑顔で迎えてくれた。「うちは9割が常連さんなんです。ご家族で通ってくださるところが多く、お子さんが大人になって来てくださることも。うれしいですね。お客さまの最高齢は102歳。昔ながらのお客さまと、私はともに歳を重ねてきています」
メニューは大人気の白玉やみつ豆、おしるこなどに加えて、まぜ御飯や蒸し寿し、お弁当類など約50種類。すべてのメニューを森田さんが作っている。どれもしみじみおいしい、手作りの味だ。森田さんは1941年生まれ。陸軍将校の娘として生まれ、母に大変厳しくしつけられたという。「母が45歳のときの子でしたから、自分が死んだときに一人前になっていなければならないからと。料理はもちろん、生きていく術を習いました」

厨房で料理をする店主の森田享子さん。「母に『大根1本買って10種類のおかずを作れるようになったら楽に暮らせる』とよく言われました。今の方たちにもそういうことを伝えたいですね」

「氷宇治金時(抹茶アイス付き)」¥920に、白玉5個をトッピング(+¥200)。丁寧に煮上げた小豆。注文を受けてからしっかりこねて湯に放つ白玉。ふわりとした口あたりのかき氷。 仕上げの抹茶はその都度、茶筅で点てる
生家には全国から来客があり、森田さんは7、8歳の頃からお手伝いさんとともに台所を手伝った。まず教えられたのは、お客さまの出身地に合わせて料理の味や素材を変えること。関西の方には豚肉より牛肉、玉子焼きはだし巻きに、関東の方なら玉子焼きは甘めになど、小学生には難度の高い注文だ。「母は戦前、都内を訪問される皇族の方々へも昼食をお出ししたこともあると言っていました」。明治生まれのかくしゃくとした母と、森田さんの姿が重なって見える。
縁あって、森田さんが甘味処を開いたとき、料理には覚えがあったものの、甘味はほぼ初挑戦だったそうだ。「義理の姉の実家が和菓子屋で、小学生のとき、そこで小豆のゆで方をじっと見ていたんです。何十年もたって、あのときの経験が役立つとは。覚えたものは荷物にならない、と言っていた母の口癖を思い出します」。今もそのときのレシピで作っている。
森田さんに煮小豆の作り方を教わった。そのとおりに作ったら、今まででいちばんの出来だった。それから私は森田さんのことを、ひそかに「小豆の師匠」と呼んでいる。彼女の作り方は一般的なレシピとは異なり、常識破りなのだ。
本来、小豆は水に浸つけず、すぐにゆでるのだが、森田さんは小豆をひと晩水に浸ける。「水に浸ければ、ほら、こんなにふっくら膨らんでくるでしょう?」。なるほど、ふくふくに仕上げるコツは、ここに始まるのだ。次に、「しぶ抜き」という作業に入る。一般的には、小豆をゆでて、アク(=しぶ)が出たら煮汁をすぐに捨てるのだが、森田さんは、鍋を火にかけ続け、アクをどんどん出していく。全体にメレンゲのような泡(アク)がわいてきたら、上から水を注ぎ、小豆を決して空気に触れさせないようにしながら、アクを流す。「小豆が風にあたると皮が弾けてしまうから」。柔らかく煮上げた小豆には砂糖を直接加えず、糖蜜を作って小豆を浸け、さらに5時間火にかけて味を含ませる。

煮上げた小豆を糖蜜と合わせて、強火にかけ、沸いたら弱火にして5時間ほど煮る。水は足さない。塩も加えない。「あっさりとして、後口がよいので」と森田さん。ひと晩おくと、さらにおいしい
「5時間も、と言われますが、火にかけておくだけです。時間短縮もできますが、そのぶん、おいしく仕上げるテクニックが必要になります。時間はかかりますが、豆にご機嫌麗しくしていただくだけで、おいしくなります。そのほうが簡単なんです」
森田さんは五感を総動員し、小豆と対話しながらこまやかに仕上げていく。「難しいことはひとつもありませんが、工程ひとつひとつを丁寧に。だから、お客さまの多い土曜日は小豆を煮ないのよ」。蜜を含んだ小豆はつやつや。このまま食べてもいいし、水分をきって練れば、あんこになる。(続きを読む)
SOURCE:「Today, as Ever」By T JAPAN New York Times Style Magazine:JAPAN BY MIKA KITAMURA, PHOTOGRAPHS BY MASANORI AKAO MAY 27, 2020
その他の記事もチェック
T JAPANはファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。