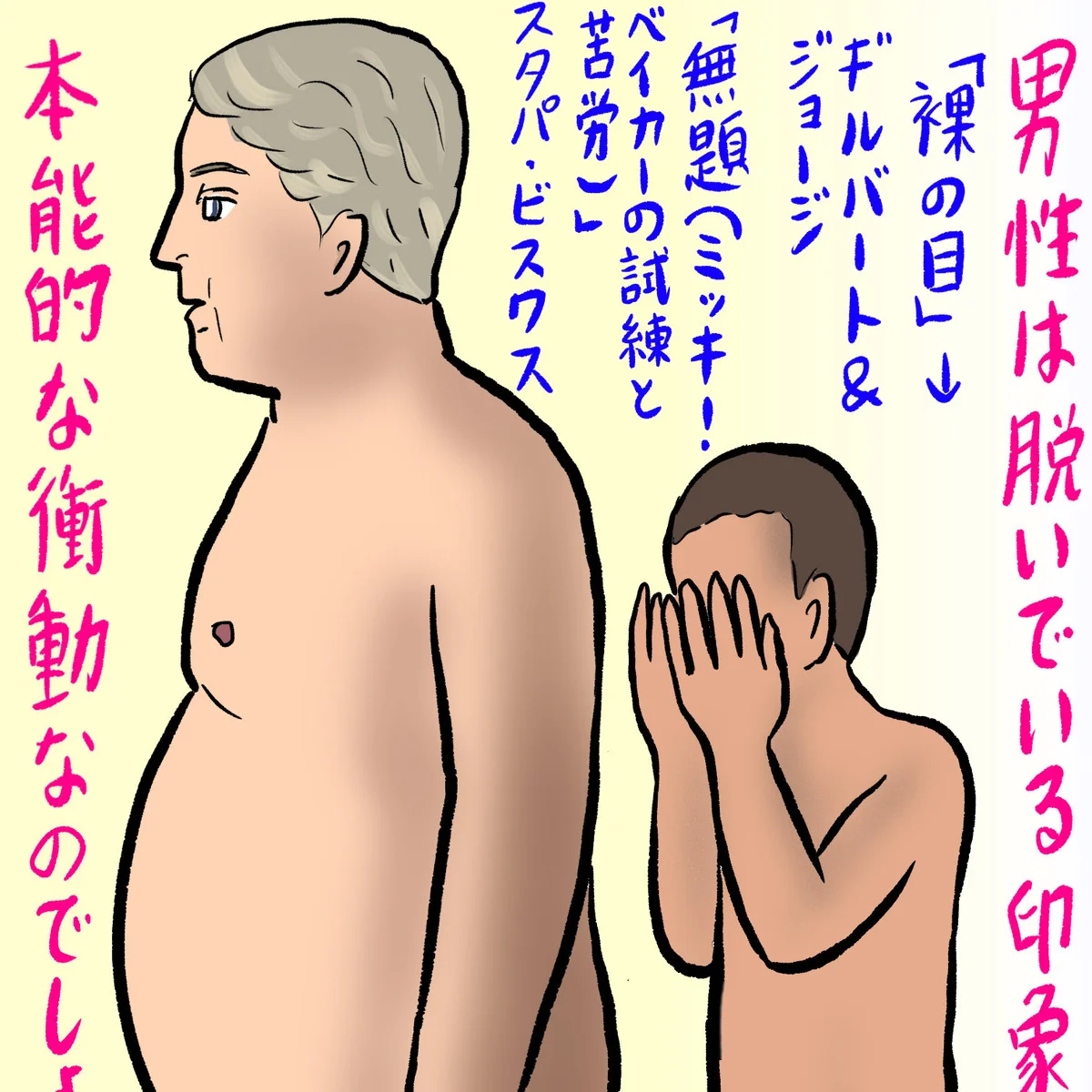すべての原点である、本との出会い
 Courtesy Film at Lincoln Center /Mettie Ostrowski
Courtesy Film at Lincoln Center /Mettie Ostrowski
——この映画を作りたいと思ったきっかけは何だったのですか?
「私は10代の頃、シチリアのパレルモで、変わった、孤独な少年でした。今思えば、この映画に登場する空やパームツリーのようなイメージの原点は、あの場所や時間にある気がします。
よく本屋に通っていました。お金がなかったので立ち読みばかりしていましたが。ある日、ウィリアム・バロウズという名前に出会いました。真っ白な背景に奇妙なグラフィック『Diverso』(『クィア』のイタリア版タイトル)というタイトル。“多様な”“異なる”という意味のその言葉に強く引き寄せられました。まるで鏡のように、自分自身を映していると感じたんです。私はずっと“Diverso”なんだと思って生きてきました。その時ばかりは思い切ってその本を買い、読み始めてすぐ、これまで知らなかった美しい言葉と、圧倒されるような作家の声に出会いました。
私が常に感じてきた“願望”と“つながり”に触れるものでした。たしか1988年頃だったと思います。それ以来、ずっとこの作品を映画にしたいと思い続けてきました。実は20歳の時に、ひどい脚本も書いたんです(笑)」
“ラブストーリー”である確信
 ©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
——原作のままにしたかった部分と、変えようと思った部分はありますか?
「この小説は1951年頃に書かれましたが、バロウズは1985年まで発表せずに封印していました。あまりにも私的で、彼自身にとって“近すぎる”内容だったのだと思います。彼はあえて未完のままにしておくことを選びました。だからこそ、私とジャスティン(・クリツケス/脚本家)にとっての自由は、この物語を“完成させる”ことでした。アヤワスカ(アマゾン北西部で伝統的に用いられている幻覚剤)を見つけたらどうなるのか、を描こうとしたんです」
——鍵となるテーマはどう作られていったのですか?
「本の中で、重要な手がかりを見つけました。ひとつは、バロウズらしいトーン。彼の持つ独特のユーモア、そしてピカレスク的な形式――。つまりアウトサイダーたちが繰り広げる風刺的で放浪的な物語のかたちを捉えることです。同時に、私は最初から確信していました。これはラブストーリーなんだ、と。本当に、本当に深く根ざした愛の物語です。しかし、そこでは、2人の関係は常に“同期している”わけではなく、むしろ“ずれている”ことのほうが多いんです。
でもこれは、“片想い”の物語ではありません。『彼にも自分を愛してほしい』と誰かが懇願するような話ではないんです。『彼も愛してくれるはずだ』という願いを描いたものでもない。
愛されることや愛することが不可能であるという状況の前に、人間という存在そのものが崩れていくような感覚。そして同時に、私たちがこの原作を映画として翻訳していく過程では、その“不可能性”が、果たして乗り越えられるものなのかどうか——その可能性を探りたいという思いがあったんです。
このテーマは、これまで私が何度も自身の作品の中で探ってきたものです。でも、今回のように本当の意味で深くそのテーマと向き合うことができたのは初めてかもしれません」
 ©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
——思いの深いシーンはありますか?
「特に印象的だったのは、原作の中で未完のまま残されていたある場面です。リーが禁断症状に苦しんでいる最中、エクアドルでうなされながら眠っているとき、アラートンが夢の中で彼の足の上に自分の足をそっとのせる――その描写です。
その場面を読んだとき、「ああ、これだ」と思いました。
自分自身さえコントロールできないときに、彼らがどうやって愛を表現しようとしていたのか。他者に自分を捧げるという“可能性”を抑圧しているものが、一時的に外れたとき、そこにこそ愛が姿を現すのだと。これは、彼らが“何を望んでいるのか”、そして“アヤワスカなしでは決して手に入れられないもの”についての物語です。彼らは“ひとつになりたい”と心から願っていた——2人で、完全に溶け合うように。その願いが、あの“混乱”の瞬間へと導いた。よくあるような思考や感情では説明できない、もっと深いところでの“錯綜”。私はそれが、とてもロマンティックだと思いました」
クレイグとスターキー、奇跡のような起用
 Courtesy Film at Lincoln Center /Sean DiSerio
Courtesy Film at Lincoln Center /Sean DiSerio
——ジェームズ・ボンドのイメージを一掃するダニエル・クレイグの熱演が印象的でした。彼の起用はいつ決まったのですか?
「話し合いの中で決まりましたが、正直……絶対に断られると思っていました」
——(笑)なぜですか?
「現実的に考えなきゃいけないでしょう?(笑)この脚本を渡して、“この役をやってください”なんて……普通は“イエス”って言ってもらえない。でも、なぜか“彼ならきっとやってくれる”と信じて突き進みました(笑)。しかも、“完璧なパートナーになるし、現場もやりやすくて、全てうまくいく”と思っていた。そして実際にその通りになったんです。まさに“人生の奇跡”でした」
——新星ドリュー・スターキーの演技も素晴らしかったですね。
「彼のオーディションテープを見た瞬間、引き込まれました。“なんて印象的な顔!”と心をつかまれ、すぐに会わなきゃと思いました。ロサンゼルスで会って何度かミーティングを重ね、ジョナサン(・アンダーソン)が“相談役”として撮ってくれたテープも素晴らしくて、その時点で“彼がアラートンだ”と感じていました。そして、彼が“スターである”ことは最初から伝わってきました。彼は1950年代の男性像を見事に体現してくれて、もう“クレイジーなくらいにハマっていた”と思います」
ジョナサン・アンダーソンと再びのコラボ
 ©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
——演出の細部も見事でした。映画『赤い靴』(1948年)に影響を受けたそうですが?
「映画に取り組むとき、私はよく“あの人ならどうするか?”と考えます。今回はマイケル・パウエル&エメリック・プレスバーガー監督のことを考えていました。彼らは“失われたイギリス”の価値観を描きながら、夢と現実のあいだにある世界を創り出してきました。『天国への階段』(1946年)、『赤い靴』『黒水仙(1947年)などがそうです。
原作の舞台は、歴史的現実というより、バロウズの精神世界の投影。ならば、“パウエルだったらどう描くか?”と想像することが、映画づくりの出発点になりました」
 ©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
——ジョナサン・アンダーソンの衣装も美しかったです。
「私は、いつも、衣装を作る以前に“その人物を深く理解してくれる人”と仕事がしたいと思っていて。だから、伝統的な“衣装デザイナー”という枠組みの外で考えることが多いんです。今回ジョナサンにお願いするのは、正直簡単な決断ではありませんでした。彼は衣装デザイナーではないし、普段はファッションブランドのクリエイティブ・ディレクターとして活躍していて、何十億ドル規模の企業を回しているような人です。『チャレンジャーズ』(2024年)で衣装を手がけてくれたとはいえ……。でも頼んだら、裾上げの針仕事まで自分でやってくれたんです(笑)。信じられないほど献身的で、美しくて、謙虚で、そしてもちろん才能にあふれています。
ジョナサンは自身のキャリアを通して、“クィアの身体”という概念を深く掘り下げてきた人で、それが何を意味するのかについての洞察や、衣装の歴史についての知識が本当に深いんです。そして、あの彼がブランドではあれほど前衛的で、思い切った表現をする彼が、映画の衣装においては、常に“キャラクター”と“物語”のために仕える姿勢を貫いてくれていた。そこがまた感動的でした」
——裾上げまで、ジョナサンが!
「彼のアプローチは本当に綿密で、この登場人物たちはどんな服を着るべきか、そしてその服が“どう着られるか”まで、徹底的に考えてくれた。私たちは一緒に深く掘り下げて、バロウズ本人が当時本当に着ていたんじゃないかと思えるような服を探し出してくれたんです。本当に素晴らしい仕事でした」
5月9日(金) 新宿ピカデリー 他 全国ロードショー
監督:ルカ・グァダニーノ(『君の名前で僕を呼んで』、『チャレンジャーズ』)
出演:ダニエル・クレイグ、ドリュー・スターキー 他
配給:ギャガ
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l.
『クィア/QUEER』公式サイト>
衣装担当ジョナサン・アンダーソンからのコメント
 ©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
©2024 The Apartment S.r.l., FremantleMedia North America, Inc., Frenesy Film Company S.r.l. © Yannis Drakoulidis
「このプロジェクトは、まずブルックリンでダニエル(・クレイグ)と会ったところから始まったんだ。すごく緊張して、どうすればいいかわからなかった(笑)。でも、結果はうまくいった。
彼に伝えたのは、スーツケースに入る分しか作らない、ということ。衣装はすべて一点もの。予備は作らない。すべてオリジナルで、何度も洗ったものもあれば、まったく洗っていないものもある。下着もすべて当時のヴィンテージ。ルカがその姿勢を理解し、信じてくれたからこそ、全力を尽くそうと思えたんだ。
今回、衣装で考えていたのは、「どんな物語を語るか?」ということだった。映画の冒頭で彼が着ている真っ白なシャツは、僕の中では“コカイン”の象徴。そして物語の終盤には、彼はヘロインに手を出しているから、衣装の色もどんどん濃くなっていく。白から闇へ。その色の変化を通して、彼の変化を表現したかった。
そういうことができたのも、ルカという監督の存在があったからこそ。『イマジネーションを思いきり使っていいんだ』、って思わせてくれた。たぶん、それはチーム全体がそうだったと思う。ローマの“家族”の中で過ごした、素晴らしい時間だった」