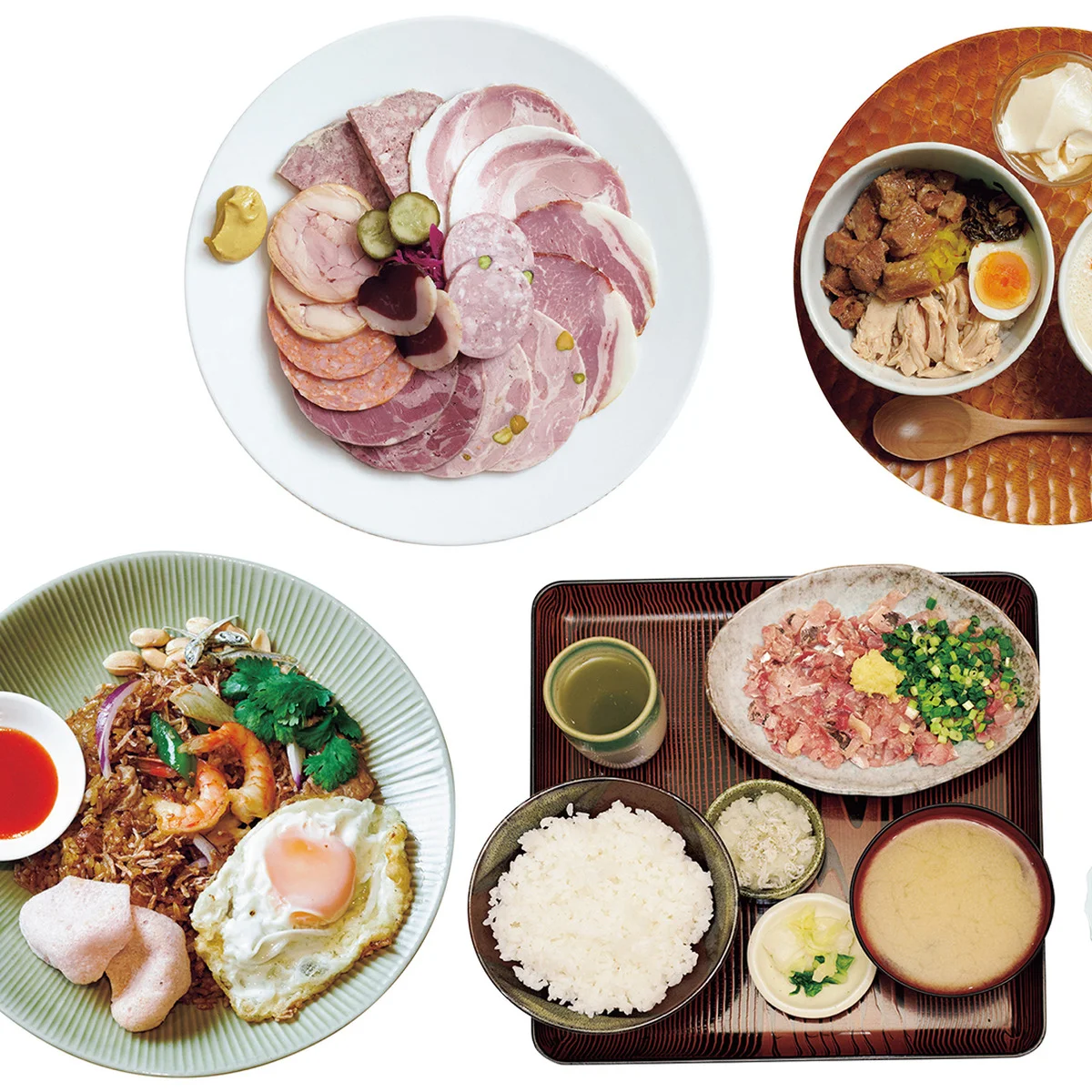理想の私 背筋

東京国立近代美術館でアートを堪能、靖国神社に参拝、皇居の周りをお散歩——。
九段下、オフィス街のど真ん中で涼子はスマホを見つめていた。
東京に出張なんてそうそうあるものじゃない。しかも取引先との打ち合わせは予定よりもかなり早く終わった。予約した新幹線の乗車時間をわざわざ早めることもないだろう。せっかくの機会だ。少しでも東京観光をして帰りたい。
そんな思いで今、現在地に近い観光スポットを探している。
どうせだったら浅草まで行ってみようか。だが、平日とはいえ東京だ。観光客で混雑しているのだろう。スクロールを続けつつそんなことを考えていたとき、それが目に留まった。
『神保町で古書店&カフェ巡り♪』
タイトルの下には神保町の街並みを写した画像が見える。歴史を感じさせる古書店が軒を連ねる、ノスタルジックな風景に心が惹かれた。
今日の夜には帰る予定の京都の風景を思い浮かべる。生まれ育った土地は今や外国人向けに古都をアピールしており、居心地が悪く感じることも多い。東京も同じだろうとは思うが、せっかく観光するのだから、少しでも作り物ではない歴史を感じたいと思ってしまう。
マップアプリの指示に従い、専大通りを歩きはじめた。


記事に書かれていた老舗のカレー専門店で遅い昼食を済ませたあと、街中を散歩しはじめる。
靖国通りには涼子と同じ、観光目的の人の姿が多く見える。思った通り、過度に観光地化されていない風景。それをうれしく思う。いくつかの古書店を冷やかしたあと、少し奥まった路地に足を向けた。
普段なら入ることをためらうであろう、鄙びた雰囲気の一軒。色あせた背表紙の分厚い書籍が並ぶ書棚が入口から見える。だが、旅先で感じる非日常感が背中を後押しした。
カウンターには、中年の男性がひとり。涼子を一瞥したあと、手元の本に目を戻す。歓迎はされていないが、拒否もされていないらしい。数坪程の店内、涼子は書棚の間の狭い通路に足を向けた。
BGMは流れておらず、静寂に包まれている。古い紙のにおいが、図書館を思い出させる。書棚に収められた膨大な書籍、その数だけ存在する歴史に想いを馳せながら、歩を進める。
店の雰囲気から、専門書ばかりが並んでいるのかと予想していたが、意外にもジャンルは幅広いようだ。昭和に刊行されたであろう雑誌の書棚も見える。
なんの気なしにそのなかの一冊に手を伸ばしたところ、見覚えのあるタイトルが目に入った。
それは涼子が今でも書店で手に取ることがある女性向けファッション誌の創刊号だった。
この雑誌、こんなに前からあったんだ。
裏表紙の「1989年11月号」という文字を見て、感慨深い気持ちになる。手にしたのは、偶然にも涼子が生まれた年に発売されたものだった。
それを手に、カウンターへ歩きだした。

レトロな雰囲気を味わえる喫茶店。ネットでそう紹介されていた店で、アイスコーヒーを注文する。
店内に流れるのはジャズミュージック。オレンジ色の照明がテーブルを照らしている。涼子は鞄から先ほど買った雑誌を取り出した。
買ったことに興味本位以外の理由はなかったが、読みはじめると思った以上に楽しく思える。
よく知っている雑誌のはずなのに、年代が違うとまるで別の雑誌を読んでいるようだ。時代を感じさせるファッションはもちろん、ラジオカセットや、今は見なくなった清涼飲料水など、広告ページすらも新鮮に映る。
夢中になって読み進めていたとき、妙なページを見つけた。
冬物のコートの特集ページ。ポーズを決めるモデルの写真のなか、人型に切り取られている箇所があった。そこだけ向こう側のページが見えている。
そのあとも、ひんぱんにページのなかにぽっかりと空いた人型の「穴」を目にした。いずれもモデルを切り抜いたと思われる。カッターを使ったのか、どのようなポーズを取っていたのかがわかるほどにきっちりと切り取られている。
その意味に気づいたとき、涼子は微笑んだ。確か母から聞いたことがある。スマホはおろか携帯もなかった頃、ファッションの情報の最先端は雑誌だったと。気に入ったコーディネートを切り抜いてノートに貼りつけ、スクラップブックを作る文化もあったそうだ。
きっとこの雑誌の元の持ち主も、そうだったのだろう。本来ならばそのような古書は不良品扱いだろうが、涼子はそれがうれしく思えた。時代を超えて手にしている雑誌に、かつての読者の面影を感じることができたからだ。
運ばれてきたアイスコーヒーを飲みつつ考える。四十年近く前にこの雑誌を切り抜いた女性は、どんな人だったのだろうか。
私と同じで、仕事を頑張りながら休日には旅行に行って、彼氏はいなくても別に寂しさなんて感じていない。そんな女性だったらうれしいな。そんな想像を頭のなかで広げる。
今も生きているなら、母と同じ世代なのかもしれない。娘ぐらいの年の私が今こうやって読んでいると知ったら、どんな顔をするのだろう。
考えていると、ポケットのなかでスマホが振動した。会社からだろうか。今日は直帰すると伝えたはずなのに。現実に引き戻されたことを恨めしく思いつつ、ディスプレイに目を遣る。
『新着メッセージがあります。』
SMSのポップアップだった。ほとんどLINEしか使っていないはずなのに、誰からだろう? 深く考えずに、タップする。

送り主不明のメッセージには、画像が添付されていた。
その悍ましいコラージュを、咄嗟に脳が拒否する。時代を感じさせるデザインの冬物のコートを着て、笑顔でポーズを取るモデル。だが、モデルの頭には大きさの違う目が大量に貼りつけられている。そして、コートの裾からは同様にして貼りつけられた大量の足が生えていた。
いずれも雑誌に掲載されていた写真から切り抜いたものなのだろうか。褪せた色のノートに貼りつけられたそれは、スクラップブックの一ページを写したもののように見えた。余白には歪んだ文字で『りそうのわたし』と書いてある。
これは一体———。出来損ないの宇宙人のような異様な姿をしたモデルのコラージュ写真から目を背けたとき、不意にスマホが振動し、思わず取り落としそうになる。
また、メッセージが届いていた。
『ずっとずっと待ってた。見つけてくれたから、やっとでれた』

帰りの新幹線で、涼子は悪夢を見た。目と足がたくさんある女が笑顔でこちらを見ている夢だ。
夢のなかで確信していた。これからずっと、この夢を見ることになるのだろう。かつて、歪んだ理想を描いたどこかの誰か。歴史に触れることで、私はそれを見つけてしまったから。