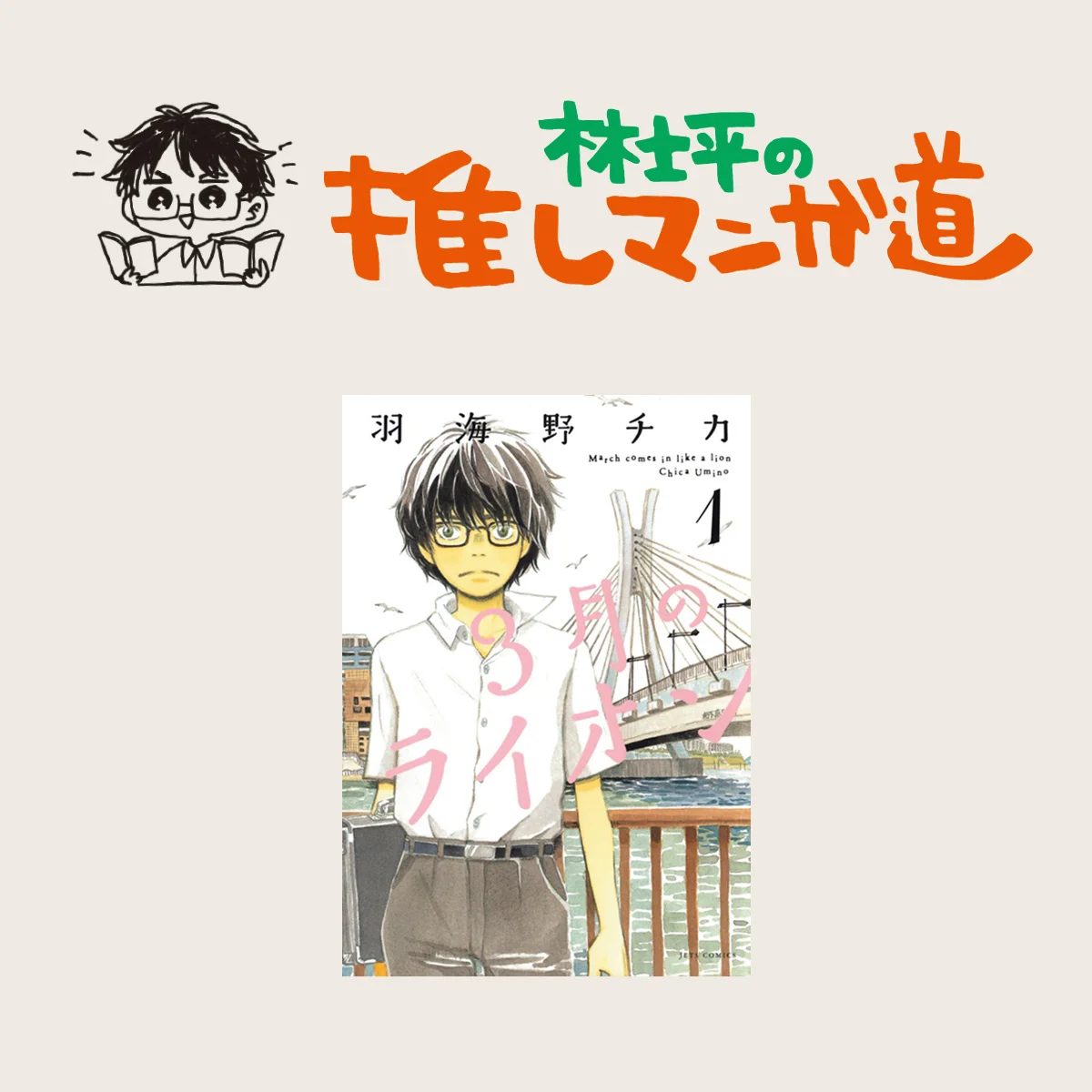シャネルによってパリに設立された“職人技の殿堂”、「le19M」が東京へ! 六本木ヒルズ森タワーの52階で開催中の『la Galerie du 19M Tokyo(ラ ギャルリー デュ ディズヌフエムトーキョー)』で注目すべき展示とは?
2025年10月20日まで、六本木ヒルズ森タワーの52階で、『la Galerie du 19M Tokyo (ラ ギャルリー デュ ディズヌフエムトーキョー)』が開催中(事前予約制)。シャネルによってパリに設立された「le19M(ル ディズヌフ エム)」は、ファッションとインテリアを極めた11のアトリエと約700人の熱心な職人や専門家が集結する、ユニークな複合施設のこと。le19Mのメゾンダールの卓越した唯一無二の技術を紹介する「le Festival (フェスティバル)」、日本とフランスの約30人の職人やアーティストによる作品を集めた没入型の展覧会「Beyond Our Horizons(ビヨンド アワー ホライズンズ)」、刺しゅうとツイードのメゾンであるルサージュの100周年を記念した「ルサージュ 刺繍とテキスタイル、100年の物語」の3章で構成された見どころ満載の展覧会から、絶対に見逃せない“7つの体験”をご紹介。
【1】手仕事の祝祭! 11のメゾンダールを紐解く「le Festival」
【2】日本とフランスの伝統と革新の対話「Beyond Our Horizons」
【3】五感で体験する、数寄屋建築とメティエダールの「ランデブー」
【4】ツイード上の泡が描く儚い情景|A.A. Murakami × ルサージュ × パロマ
ロンドンを拠点とするアーティストデュオ、A.A.Murakami(村上あずさ&アレクサンダー・グローブス)は、ルサージュとパロマとともに、ツイードの新たな可能性を探求。彼らが掲げるコンセプト「Ephemeral Tech(儚いテクノロジー)」は、スクリーンではなく、泡や霧、香りといった束の間の現象を通して美を体験するもの。ミラノデザインウィークで話題を呼んだ作品「NewSpring」の進化形として、今回はシャボン玉が舞う幻想的な空間を創出。もともと水に弱い素材であるツイードに耐水性をもたらし、泡をパールやビーズに見立てて表現するという詩的なアプローチが印象的。時間の流れとともに変化し消えゆく、儚い美意識を描く。
【5】ルサージュが100周年! 多様な手仕事の世界を映し出すアトリエを再現
【6】ルサージュの貴重なアーカイブが物語る刺しゅうの本質
【7】刺しゅうが紡ぐフランス文化の遺産と卓越性
ルサージュが担ってきた刺しゅう文化の系譜も見どころのひとつ。宮廷のドレスやインテリア装飾など、刺しゅうはフランス文化の中で長く美の象徴として機能してきた。19世紀に制作されたルイ16世様式のアームチェア用フラワー刺しゅうのサンプルなど、歴史を物語る貴重な資料も展示されている。
また、シャネルがルサージュの遺産とフランス文化の象徴として関わるパリ国立オペラ座やヴェルサイユ宮殿との連携も紹介。オペラ座では、毎年恒例のガラ公演を通してバレエ衣装の制作を支援し、ルサージュの刺しゅうが舞台衣装としても輝きを放つ。一方ヴェルサイユ宮殿では、「王妃の寝室」をはじめとする18世紀美術の修復や再現に携わり、刺しゅう職人たちの技が今も生き続けている。
ルサージュの手仕事は、装飾を超え、芸術と文化の継承そのもの。フランスの“遺産と卓越性”を未来へとつなぐ、その確かな存在感を感じられる展示だ。
職人技の美しさ、日仏の文化の交わり、そして創造の未来。そのすべてが静かに胸に残る体験。会期は残りわずか。ファッションと手仕事、アートが出合う奇跡の瞬間を、ぜひ自分の目で確かめて。
CHANEL presents “la Galerie du 19M Tokyo"
会期:~2025年10月20日(月)
会場:東京シティビュー&森アーツセンターギャラリー
住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
料金:無料(事前予約制)