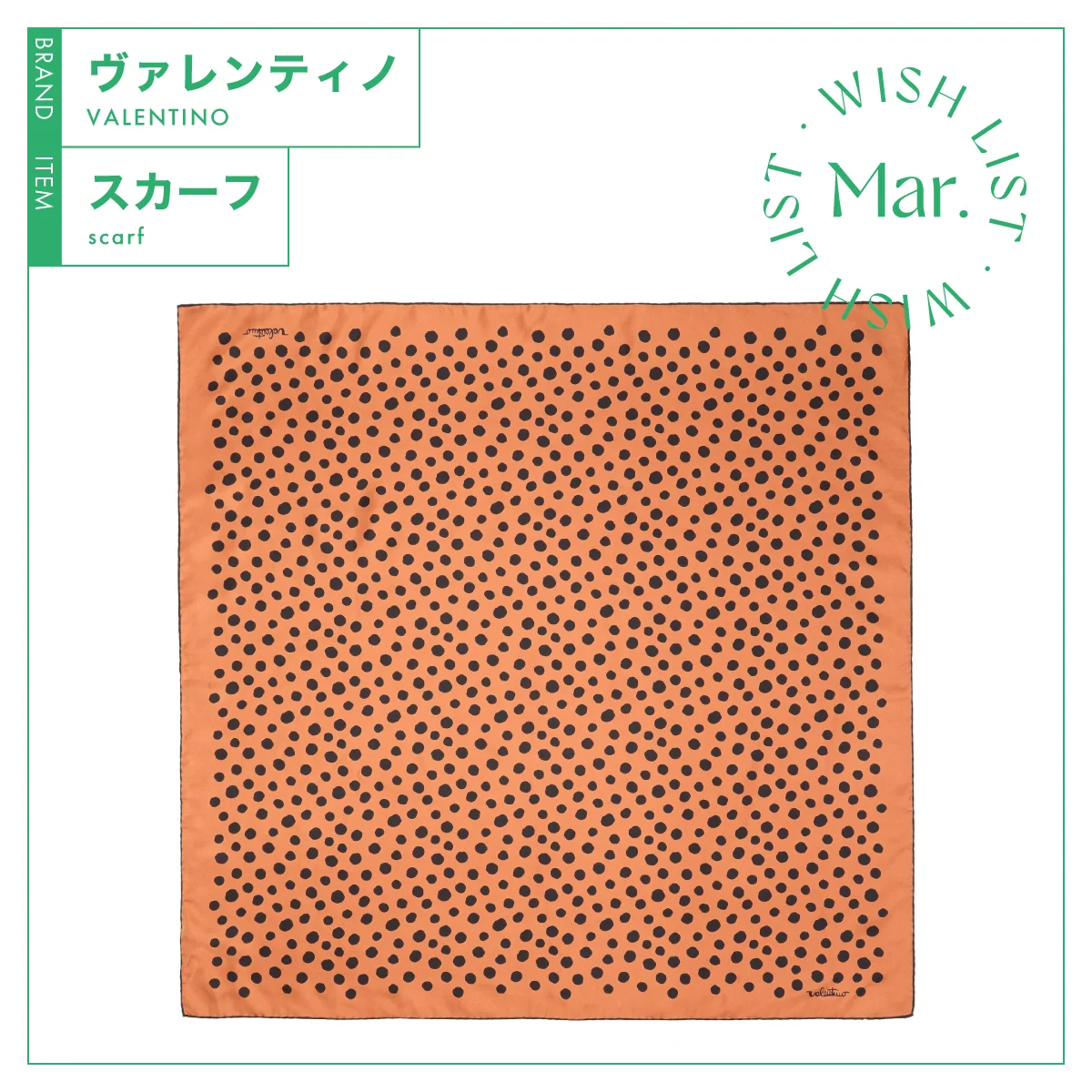3月上旬に開かれた2025-26年秋冬パリ・ファッションウイークより、事実上の終幕、または幕開け、そして新しいチャプターへの完璧な土壌を披露したコレクションを抜粋。
3月上旬に開かれた2025-26年秋冬パリ・ファッションウイークより、事実上の終幕、または幕開け、そして新しいチャプターへの完璧な土壌を披露したコレクションを抜粋。
今、ファッション界は激動の時期を通り抜けようとしている。巷では“椅子取りゲーム”と呼ばれる、デザイナー交代劇だ。各メゾンでクリエイティブ・ディレクターのポジションから退き、未だ今後の行先を発表していないのは元ヴァレンティノのピエールパオロ・ピッチョーリ、元メゾン マルジェラのジョン・ガリアーノ、元セリーヌのエディ・スリマン、元ディオール メンズのキム・ジョーンズ、元ジル サンダーのメイヤー夫妻、元グッチのサバト・デ・サルノ、そして元ロエベのジョナサン・アンダーソン。
一方最新の任命は、ロエベにジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスのデュオ(自身たちが創業したブランド、プロエンザ スクーラーから今年1月に退任)、シャネルにマチュー・ブレイジー(元ボッテガ・ヴェネタ)、ボッテガ・ヴェネタにルイーズ・トロッター(元カルヴェン)、メゾン マルジェラにグレン・マーティンス(元ディーゼルとY/プロジェクト、セリーヌにマイケル・ライダー(元ラルフ ローレン)、ジル サンダーにシモーネ・ベロッティ(元バリー)、ドナテラ・ヴェルサーチェが引退したヴェルサーチェにはダリオ・ヴィターレ(元ミュウミュウ)、そしてグッチには、バレンシアガを後にしたデムナ。
これらの大移動に揺らぎ、また不安定な世界情勢や消費の落ち込みを背景としつつも、今シーズンのパリ・ファッションウィークはポジティブな新局面を見せた。
「ロエベ」 ジョナサン・アンダーソンの有終の美
1月のメンズに続きウィメンズでもショーはしなかったものの、ジョナサン・アンダーソンの“キュレーション”の手腕を見せたプレゼンテーションで、今季のベスト・コレクションの一つに数えられたのは、ロエベ。 “アイデアのスクラップブック”として18世紀建造オテル・ド・メゾン(元カール・ラガーフェルドの邸宅)内の17の部屋で展開されたインスタレーションは、メンズ、ウィメンズ両方の最新コレクションと、ジョナサンが愛するアート作品の数々だ。ウェアとアクセサリーではトロンプルイユ、ズームインとズームアウトで変化するボリューム感、アートと職人技……とロエベにおけるジョナサンの視点が浮き彫りにされ、グループごとに少しずつ違うセッティングで展示。特にニットやレザー製品では、彼がいかに新しいシルエットやテクニックを生み出したかが一望できた。
アートではアンセア・ハミルトンの巨大なカボチャ(2022-23FWのショーのセット)や須田悦弘の朝顔と言ったスカルプチャーから、2023年にミラノサローネで発表された「ロエベ チェアーズ」のキノコ型オブジェまで、過去10年間にジョナサンを触発した作品をミックス。中でも特筆すべきは、ジョゼフ・アンド・アニ・アルバース財団とのコラボレーションだ。バウハウスのムーブメントから出発し、モダニスムの先駆者となったアルバース夫妻は、お互いが異なる作風ながら生涯インスパイアし合い続けたことで知られている。本コレクションでジョナサンは、色合わせの視覚効果を探求したジョセフによる正方形の抽象画の一連に、自身のカラーパレットを見出した。一方、まるで点描画のように見えるアニのテキスタイルは、コートやバッグに再解釈された。

キャンペーン撮影のセットに使われた巨大なリンゴを取り巻くようにして、ドレスからアウターまで、タイプの異なるアイテムの数々が共存。ルールにとらわれない、ジョナサン流のキュレーションだ。Photo: Courtesy of Loewe

ビーズつきオーガンザの糸でつくられたドレスはダイナミックな動きを見せ、スカルプチャー然とした佇まい。Photo: Minako Norimatsu

会場作り付けのキャビネットを活かした展示。手前にはマシュルーム型のJos Devriendtの一連と、ジュエリーが。Photo: Courtesy of Loewe

アニ・アルバースの織物を再解釈しての、コートとやスカート、バッグの一連。Photo: Courtesy of Loewe

組み合わせや環境、そして見る人による色の捉え方の違いを追求したジョセフ・アルバースによるHomage to the Squareの複製。Photo: Minako Norimatsu

ジョナサンは、ミニマルか装飾的かと言うデザインの方向性に関わらず、常にレザーウェアの常識を更新してきた。Photo: Minako Norimatsu
プレゼンテーションの1週間後には、数か月来の噂をコンファームすべく、ロエベがジョナサン・アンダーソンとの11年に渡る仕事に終止符を打つことが発表された。思えば私が彼を初めてインタビューしたのは、彼のメゾンでの2度目のメンズ・コレクションが発表された直後の10年前、シュプールの増刊「シュプール・メン」にて。その鋭い視線、確固としたヴィジョンに圧倒され、ただ者ではないと感じたのを今でも覚えている。ヨークシャーまでオープニングに出向いてじっくりと見た、彼のパーソナルプロジェクトとしての展覧会「Disobeident Bodies」では、彼のアートとファッションへの幅広く奥深い知識と、キュレーションの才能に驚かされた。その後数々のヒットバッグを生み出し、「ロエベ財団 クラフトプライズ」やフレグランスのコレクションをスタートさせた、彼のロエベにおける偉業は計り知れない。折しも、彼の10年にわたるコレクションとカルチャープロジェクトの数々をビジュアルとともに回顧する書籍、『Crafted World: Jonathan Anderson’s LOEWE』が発売されたばかり。そして 3月29日からは、東京で「ロエベ クラフテッド ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」が始まった。最近ではルカ・グァダニーノ監督とのコラボレーションで2本の映画(『チャレンジャーズ』(2024)、『クィア』(2025))の衣装デザインもこなしたジョナサン。彼の仕事を心から尊敬すると言うジャックとラザロの二人が、ロエベという耕された土壌に何をどう実らせるかが、楽しみだ。
「バレンシアガ」 デムナのエピローグは”スタンダード”
ロエベに先んじて、ファッションウィーク修了直後に電撃的なニュースを発表したのは、バレンシアガだ。ジョナサンとは違うやり方で、ファッションや消費社会に対するシニカルで挑発的なアプローチにより、一時代を築いたデムナ。今回が、10年間籍を置いたメゾンでの最後のショーとなった。彼の今回のテーマは、”スタンダード”。ただし、AlipinestarsやPUMAとのコラボレーションも含めたスポーツウェアからテーラードまで、ベーシックウェアを見直す、と言うストレートな解釈ではない。一筋縄ではいかないデムナだけに、「それらは果たしてファッション・アイテムになり得るか?」と言う奥深い問いかけを意味しているだろう。だから冒頭で登場した4体のメンズスーツでは(うち1ルックはメゾン常連の女性モデル、エリザ・ダグラスが着用)しわ加工や虫食い加工で、また着こなしや着る人の体型によって、似て非なるものに見せた。またデムナお得意のフーディではフードを巨大に。奇抜な色のスパンデックスは半水着・半ドレスの「スイムドレス」に、トレンディなブルジョワ風ファーコートはマキシ丈で。つまりサイズや素材、シルエットの各方面で常識を破った新しい”スタンダード”を提案したのだ。革新的なクチュリエ、と崇められたクリストバル・バレンシアガの真髄に根ざしつつ、こうしてデムナが新たに確率したバレンシアガのエスプリを、今後誰がどう受け継いでいくのだろうか? 期待が高まる。

黒一色で、迷路のごとくデザインされた会場。Photo: Courtesy of Balenciaga

”スタンダード”を象徴するテーラードコート。Photo: Courtesy of Balenciaga

こちらはデムナ流スタンダード。長さ、つま先の鋭角共に極端なブーツ。Photo: Courtesy of Balenciaga
「ドリス ヴァン ノッテン」のソフト・シフト
今シーズン取り沙汰されたもう一つの風潮は、大規模な露出よりも“親密な雰囲気”を意図しての、ショーの縮小化だ。ゲストの席数を絞ったものの大きな話題を呼んだ3つのショーは、いずれも、新任クリエイティブ・ディレクターのデビューを飾ったコレクション。ただしそれぞれのアプローチは、三者三様だった。ドリス ヴァン ノッテンは、2018年よりドリスの傍らでクリエイションに携わってきたジュリアン・クロスナーが、クリエイティブ・ディレクターに抜擢されての初コレクション。ラディカルな交代劇を描くほとんどのメゾンと違い、ここではメゾンの創始者が自身の退任を準備し、特定の名前を掲げないチームによるコレクション(2025年春夏ウィメンズ)から、ジュリアンをヘッドとしつつチームの仕事として発表したコレクション(2025年秋冬メンズ)へと段階を踏み、緩やかなシフトとなった。
こうして時間をかけたとあって、このショーにあたってはコレクションに取り掛かる時点で、オペラ・ガルニエを会場とすることが決まっていた。ドリスがメンズのショーでオペラ座を使った際は会場は舞台に設置されていたが、今回のランウェイは、ホワイエ。ただしジュリアンのインスピレーションは、オペラやバレエの衣装からではなく、劇場で観客が感じられるエモーションだったとか。子供の頃に家でクローゼットから数々の服を引っ張り出し、思うがままにコーディネートして遊んだという彼。当時の楽しさを思い出し、さまざまな要素を自由な発想で組み合わせた。それらの要素は靴紐で作ったフリンジ、小紋に似たネクタイ柄のファブリック、タペストリーのようなジャカード地、マルチカラーのシーケンス、そしてドリスも好んでいたストライプやチェック。シルエットではドレープやラップ、ムトンスリーブ、ホルターネックと言った流線に、シャープなテーラードジャケットやハイウエストのシガレットパンツが対比を成す。いずれもかつてエルテが描いたアール・ヌーヴォー・スタイルのドローイングのように、細長いシルエット。終幕ではタッセルが、オペラ座の緞帳に呼応。美観からしても、幕開けを示唆する意味合いからしても、意味深いフィナーレとなった。ショー後にフランスのテレビでインタビューされたドリスは、「とても美しい、いい仕事だ」と、一言。ジュリアンは師匠からの祝福を受けたようだ。

ファブリックをボディに自由に巻きつけて生まれたドレスの一例。頭には、舞台の役者がメイクアップ時に被るターバンを。Photo: GORUNWAY

メゾンにとって大切なテーラードの、ジュリアン流解釈。装飾的なコルセットベルトで、ややエキゾチックなタッチを。Photo: GORUNWAY

マルチカラーのタッセルで覆ったジャケットは、このコレクションで象徴的なアイテム。Photo: GORUNWAY
「トム フォード」 ファウンダーからの熱い祝福
2005年に自身の名前を冠してスタートしたブランドから、2023年に退いたトム・フォード。2009年以降は、映画監督として自身の美意識を追求している。一方ハイダー・アッカーマンは、自身のブランドやべルルッティを経て2023年にはジャンポール・ゴルチエのクチュールのゲストデザイナーとして再び注目され、「トム フォード」の後継者に。両者は完璧なテーラリングとセックスアピールと言う共通点を持ちつつ、スタイルには微妙なギャップがあった。前者はニューヨークのアップタウンやハリウッドにもてはやされる程、挑発的でグラマラス。後者は典型的なヨーロピアンで、エッジィなダーク・ロマンスがシグネチャー。つまり、セクシーVS官能的。またトム・フォードはグッチ、そしてイヴ・サンローランを手がけていた頃から1990-2000年代の空気を象徴していただけに、時代の移り変わりに飲まれてしまっていたのかもしれない。そんな経緯から、ハイダーの「トム フォード」におけるデビューは、今シーズン最大の焦点の一つだった。結果はスタンディング・オべーション、そしてトム・フォード自身がハイダーに送った熱い抱擁。約200人のみのゲストを集めた親密な雰囲気でライトをおさえた暗めのショー会場には、黒、または対照的にアシッド・カラーのスーツやスリークなドレスが生えた。また「トム フォード」がビューティ・ブランドでもあることへのオマージュか、メイクアップではグロッシーな真紅のリップがアクセントを添えた。

イエローは今シーズン複数のブランドで多用されたが、ここではアシッド・カラーで。スクエアショルダーが際立つ、強いシルエットのパンツスーツ。Photo: Courtesy of Tom Ford

シンプルながら、微妙なドレープが官能的なシルエットを生み出したドレス。Photo: Courtesy of Tom Ford

テーラード・スーツの一連で圧巻のフィナーレ。Photo: Courtesy of Tom Ford
「ジバンシィ」 未来を見つめながらのリセット
「マックイーン」を後にし、今回ジバンシィにおける初コレクションを披露したのは、サラ・バートン。かつての師匠、故リー・アレキサンダー・マックイーンが1996年から5年間デザイナーを務めたメゾンでの仕事だから、感慨もひとしおだったことだろう。彼女は、リーの後リカルド・ティッシをはじめ数人のデザイナーを経たメゾンを、ユベール・ド・ジバンシィによる創設年1952 年に、オリジナルのロゴでリセット。また当時の幾つかのドレスの例に倣って、バックスタイルの美しさに、果ては360度どこから見ても完璧であることにこだわった。ドレスの一連だけでなく、アワーグラス(砂時計)シルエットのジャケットをはじめ、ソフトショルダーでひねったアームのテーラード・ピースを見ると、その観点が顕著だ。特に強いメッセージを打ち出しているのは、ファーストルックとラストルック。また、コレクションには創設者へのオマージュも散りばめられた。例えば会場のシートは、最近故ユベール・ド・ジバンシィの元自宅のリノベーションで壁の後ろに隠されていたパターンの一式が見つかったことから、それらを包んでいたクラフトペーパーの積み重ねで。また鳥や花が飛び交う装飾的な刺しゅうは、やはり彼の自宅にあったアンティークのついたてがインスピレーション。これらの逸話を盛り込みつつ、サラは“強くて、かつフラジャイルな女性”を描き出した。

ジョルジュ・サンク通りの本社にて、クラフトペーパーの包みを積み重ねてシートとした会場セット。Photo: Courtesy of Givenchy

メッシュのボディスーツにアンダーウェア、オリジナルのロゴで、リセット感をモダンに打ち出したファーストルック。Photo: Courtesy of Givenchy

サラの持ち味であるモダン・テーラードの技術を駆使したコンビネゾン。Photo: Courtesy of Givenchy

ラストルックはチュールを惜しみなく使ったドレス。“ジョイ”を象徴するイエローで。Photo: Courtesy of Givenchy
「シャネル」 新しい時代への完璧な土壌
冒頭で触れたように、シャネルはマチュー・ブレイジーによる初コレクションを今年の秋に控え、クリエイション スタジオによるプレタポルテの発表は、今回で2度目。ファッションウィークの最終日には、メゾンのコードをしっかりと消化し、新生シャネルに向けての確実な土壌を披露した。インビテーションでも示唆されたように、今回のキー・モチーフは黒のリボン。1月のクチュールに続きセットデザインを手掛けたウィロ・ペロンが、巨大なサイズで会場に設置したのも、黒のリボンだ。コレクションではリボンがウェアのディテールやアクセサリーとしてだけでなく、トロンプロイユやプリントのモチーフにも落とし込まれたほか、パールからツイードまでのシャネルらしさが程よいバランスで散りばめられた。またシャネルらしい黒と白のルックは、クラシックからロマンティック、ロックまでのバリエーションで。そして頭から爪先まで同色、同素材のトータルルックや透ける素材のレイヤード、チャンキーなニットなどで、遊び感も多いにアピールされた。

ツイードやリボン、パールといったシャネルらしさが顕著なフィナーレ。Photo: Courtesy of Chanel

ニットの一連はグラフィックに展開。Photo: Courtesy of Chanel

極端にチャンキーなニットには、大粒のコスチューム パールを合わせて。Photo: Courtesy of Chanel

ツイードのドレスはマキシサイズのバッグとロンググローブで、レトロ・モダンに。Photo: Courtesy of Chanel
来たる新任クリエイティブ・ディレクターのデビューのうち、セリーヌは7月、しかも場所はパリか否か不明。メゾン マルジェラも7月のクチュールが転機となるのかは不明だし、プレタポルテだとしてもこれまでの形式に則るなら、ミラノか? バレンシアガは近日中にデムナの後任者が発表されても、タイミングから言って初コレクションはもう1シーズン先になる可能性が大。新生ロエベのお披露目が次シーズンなのか、その次なのかはコンファーム待ち。こんな不透明さの中、確かなデビューはマチューのみ。2026春夏シーズンに向けて、誰もがシャネルのショーを心待ちにしている。

パリ在住。ファッション業界における幅広い人脈を生かしたインタビューやライフスタイルルポなどに定評が。私服スタイルも人気。
https://www.instagram.com/minakoparis/