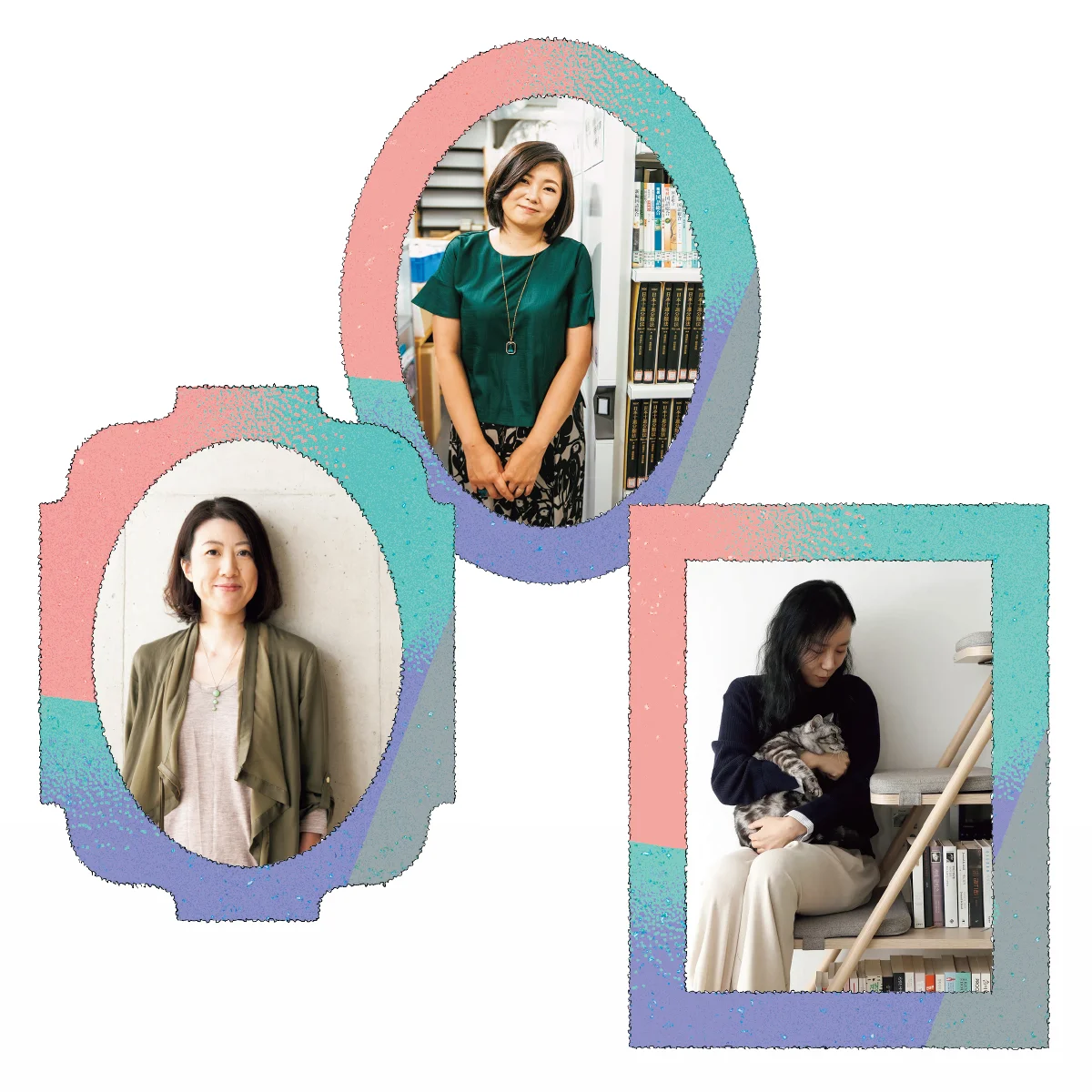「もし、このコレクションで誰かをメイクアップしたいなら? そうね、ルイーズ・ブルックスに、クラウディア・カルディナーレ……それに、ウィノナ・ライダーも!」そう言って無邪気に笑うルチアに、かつてシャネルのメークアップ部門のディレクターだったドミニク モンクルトワ氏に聞いた質問を投げかけた。もし、マドモアゼル シャネルが生きていて、あなたの創ったコレクションを見たらなんと言ってほしいかと。彼女の回答は、マドモアゼル シャネルとともに仕事をし、生前の彼女を直接知る数少ない存在のモンクルトワ氏が毅然と答えた「よい仕事をしましたね、と彼女は褒めてくれるはずです」とは、対照的なものだった。
「これ私もつけたいわ、そう言ってほしい」
そう口にして急に恥ずかしそうに、少女のように頰を赤らめたルチアに、はっとした。ここには間違いなく、地続きの体温がある。あまりに偉大なアイコンの足跡をたどりながら、連鎖し、醸成していく美学を背負う、重圧と孤独のその先にやっとつかんだ喜びを見たように思った。スタイルとは何か。女性の威厳とは何か。マドモアゼルの人生をひもとけばそのヒントは導かれてくるけれど、彼女の息遣いを耳もとで感じながらシャネルというパワーハウスで新しい何かを生み出す試練を果敢に乗り越え、これだけシックに、そしてモダンなカラーパレットを誕生させたルチアの力量とみずみずしい感性は、計り知れないと。
赤に刻まれたルチア ピカというひとりの女性の挑戦と、挑発。現代を生きる彼女のシャネルのストーリーは、今、力強く滑り出したばかりだ。
SPUR2016年9月号掲載

おしゃれスナップ、モデル連載コラム、美容専門誌などを経て現職。
趣味は相撲観戦、SPURおやつ部員。