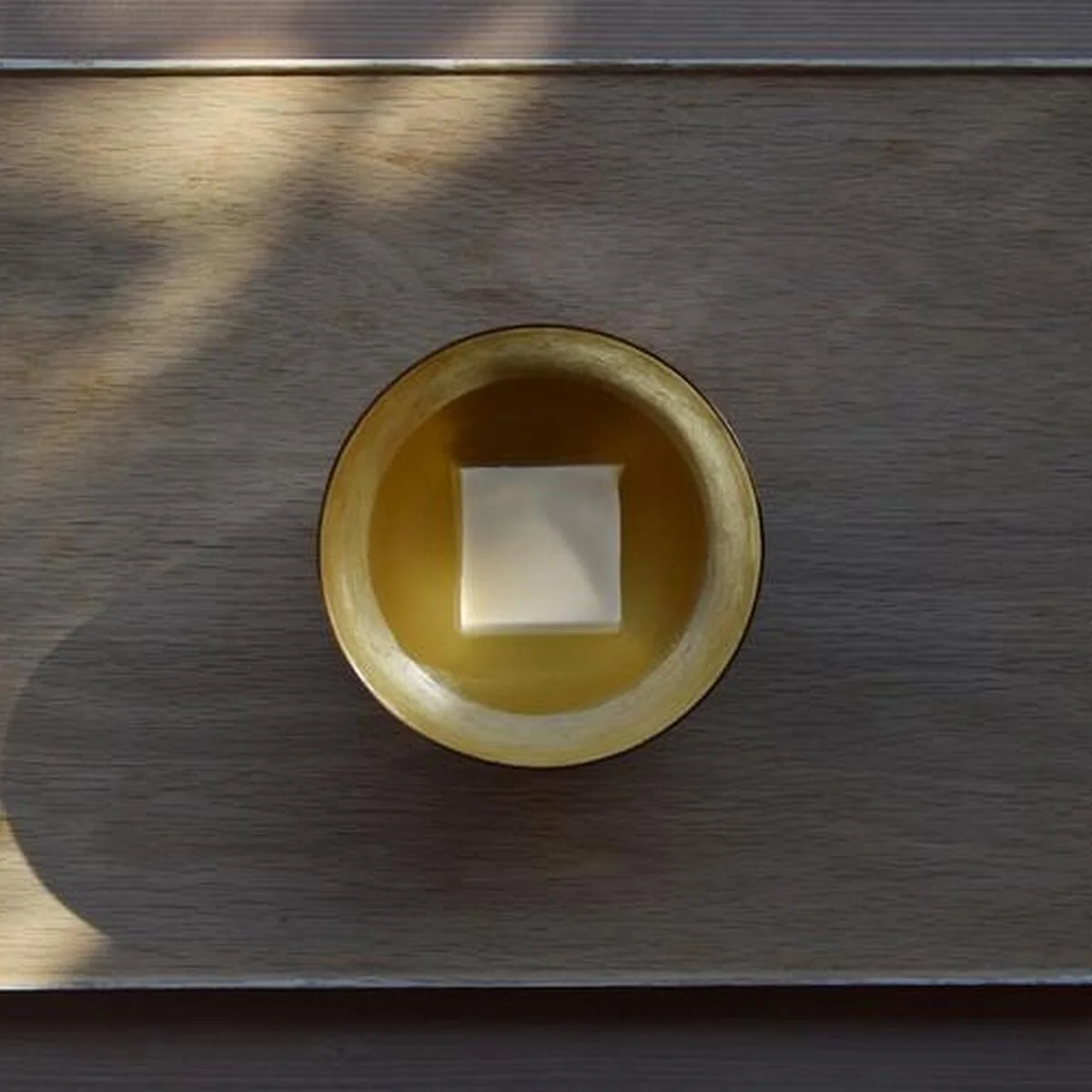飛行機に乗る機会があると、あらためて欲しくなるのがノイズキャンセリング付きのヘッドホン。普段はイヤホン派の私も、長時間の移動中は耳全体を包み込んでくれて、バッテリーも長時間持つヘッドホンがやはり頼れる存在です。
飛行機に乗る機会があると、あらためて欲しくなるのがノイズキャンセリング付きのヘッドホン。普段はイヤホン派の私も、長時間の移動中は耳全体を包み込んでくれて、バッテリーも長時間持つヘッドホンがやはり頼れる存在です。
Nothingらしさ全開のヘッドホンが登場
そんな中で発表されたNothing初のヘッドホン「Headphone (1)」。海外での発表を見たときは、「イヤホンの次はヘッドホンか〜」と思ってしまったのですが、先日日本で開催されたイベントで実物を見てみたら、思わず「可愛い〜」と声が出てしまいました。Nothingらしいスケルトンデザインに、どこかレトロな雰囲気を感じさせるフォルムとディティール。そこに未来的な要素をうまく融合させた、Nothing独自のデザイン哲学がきちんと落とし込まれていて、心をつかまれました。
AIと遊び心が共存する、Phone (3)の魅力
また、Headphone (1)とともにNothingの最新スマホ「Phone (3)」も登場しています。Phone (2)からデザインが刷新され、小型化したとのことだったのですが、手に持った印象ではそこまでの小ささは感じられず。iPhoneのProシリーズと比較すると、まだやや大きめな印象。
「毎日持つもの」だから、大事にしたいこと
そしてもちろん、Nothing Phoneならではの“光る背面”も健在。丸い窓のようなかたちになった「Glyph Matrix」は、着信や通知、音量表示だけでなく、簡単なミニゲームやツール(ストップウォッチやバッテリー残量の表示など)の「Glyph Toys」にも対応しています。通知ごとに異なる光り方に設定できるだけでなく、機能としての拡張性や遊び心も感じられるのが魅力。旧モデルの大胆な光の演出に比べると、やや控えめな印象はありますが、実用性と楽しさのバランスがとれた操作感に進化したな、と感じます。

ファッションデザインを学んだのち、海外ラグジュアリーブランドのPRなどを経て、2013年に独立。クリエイティブ・コンサルタントとして国内外の企業、ブランドのプロモーション企画/ディレクションに関わる。
また自身でのクリエイティブ制作にも注力しており、フォトグラファー、動画クリエイター、コラムニスト、モデルとしての一面も併せ持つ。強い服と少し先の未来を垣間見られるデジタルプロダクトが好き。