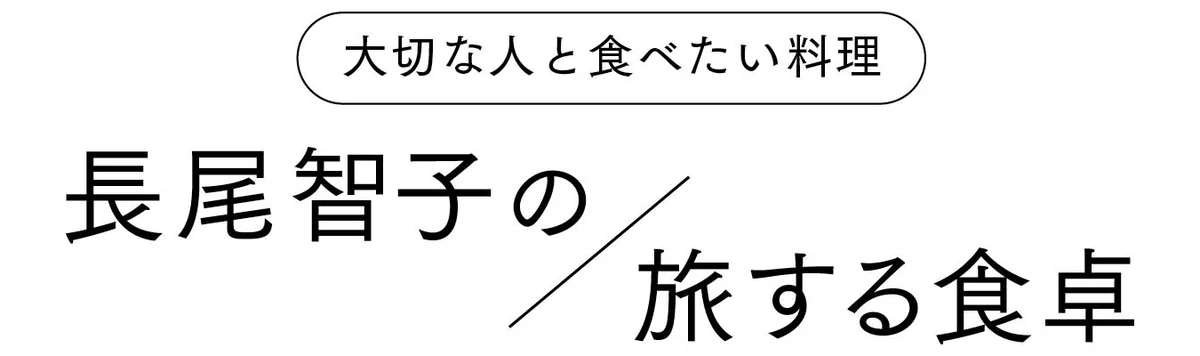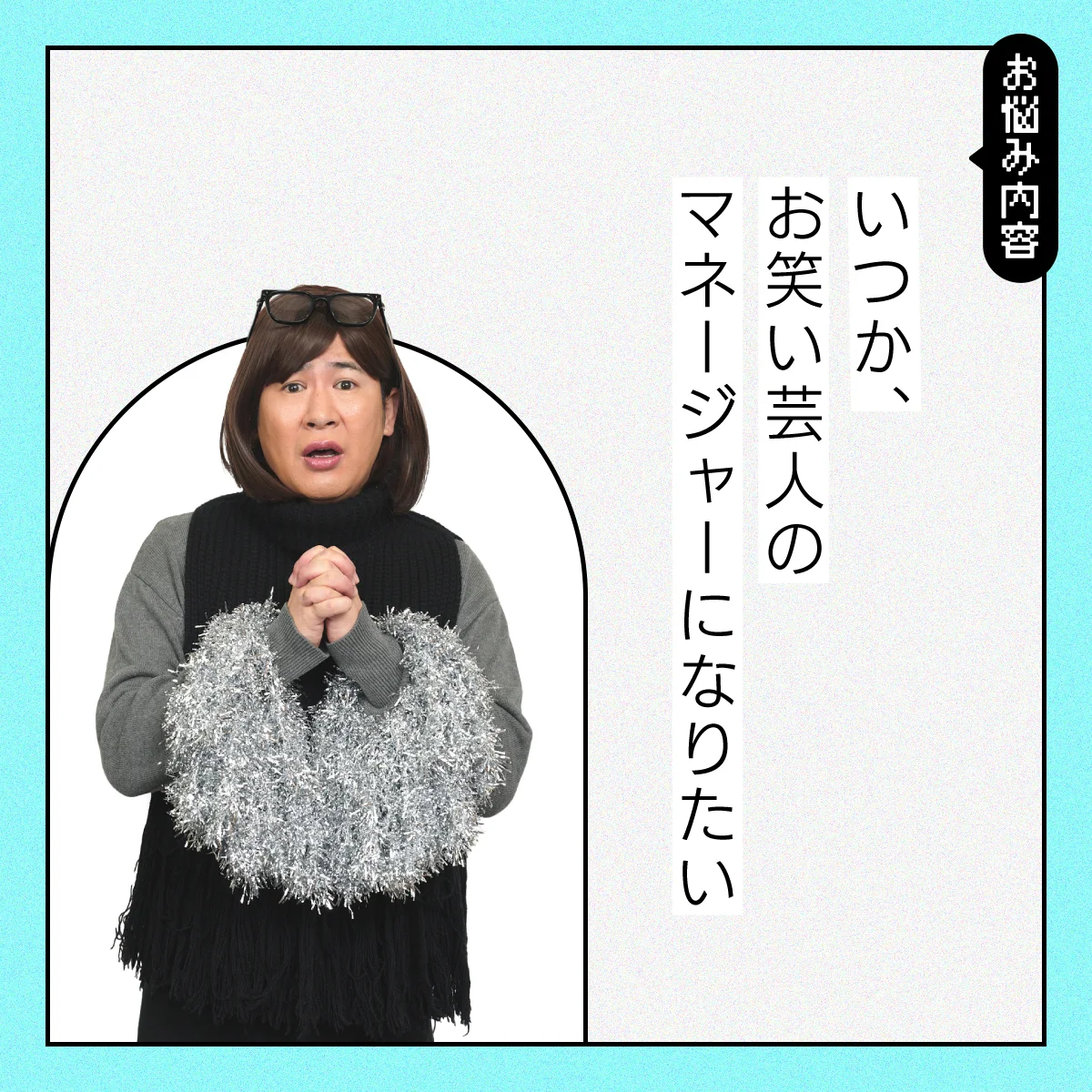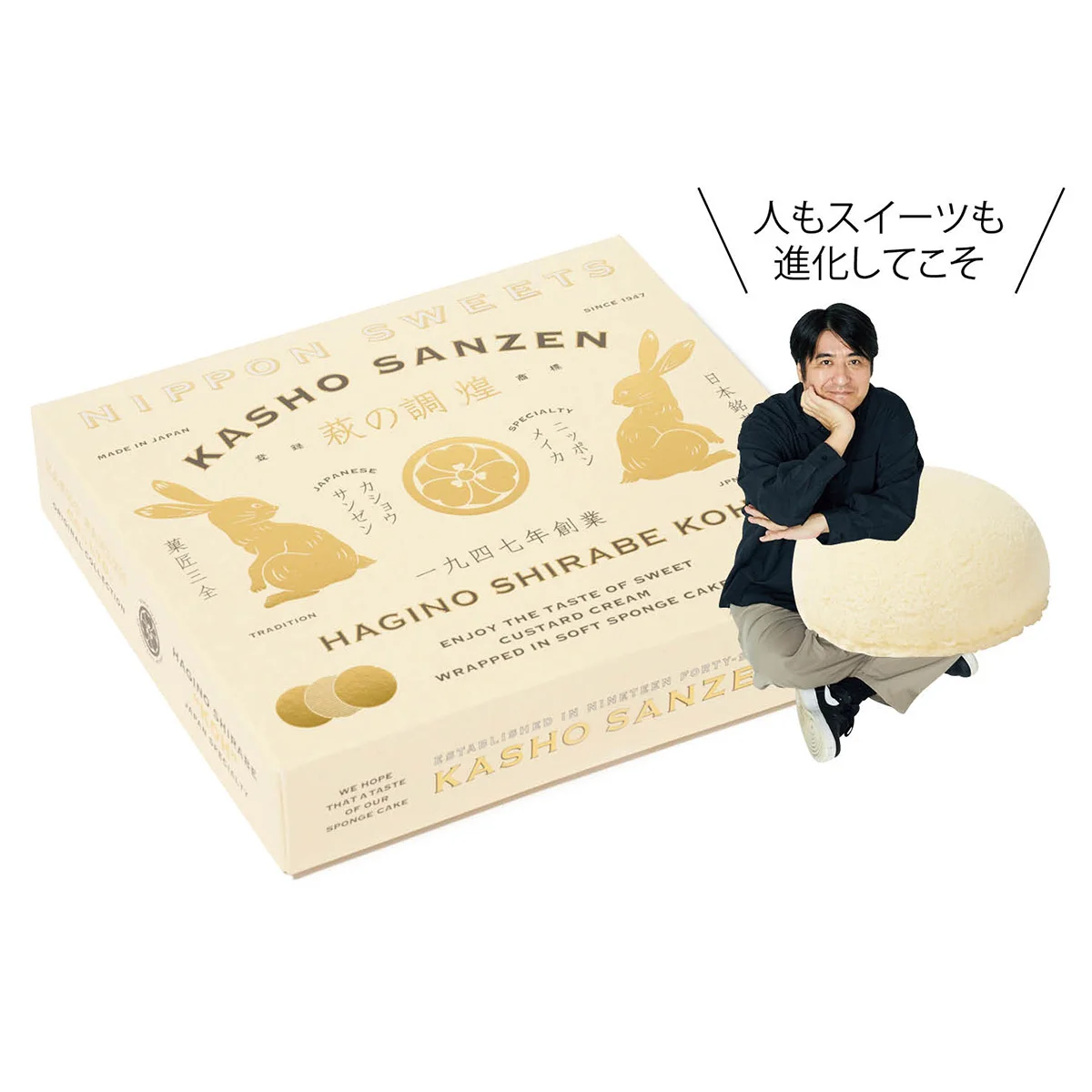「旅の楽しみのひとつは、知らなかった味に出合うこと」。現地の味を思い出したり、まだ見ぬ土地を想像しながら生まれたレシピが、旅情を刺激する。いつもの食卓で、非日常を味わおう。
「旅の楽しみのひとつは、知らなかった味に出合うこと」。現地の味を思い出したり、まだ見ぬ土地を想像しながら生まれたレシピが、旅情を刺激する。いつもの食卓で、非日常を味わおう。
豆花とは
豆乳ににがりや石膏粉などの凝固剤を加えて蒸し固める料理。日本ではシロップなどをかけてデザートとして食べるのがよく知られているが、中国北部ではきのこなどの具材をのせてしょうゆ味や塩味にしたり、四川省では辛いタレをかけたり、地方によってさまざまな食べ方がある。

豆乳スイーツとして知られる豆花は、実はトッピング次第で甘辛どちらもいけるヘルシーなご自愛食。「中国の南、広州の街角の屋台のような豆花店で出合ったのは、ピーナッツを煮たシロップをかけた甘いもの。中国の北部では、香菜や辛味を加えて食べることもあると知ってさらに興味が深まりました」。
材料はシンプルながら、蒸して固める工程は意外とデリケート。「ポイントは、とにかくそっと静かに扱うこと。にがりと豆乳を合わせるときは少しずつ丁寧に、蒸す火加減も強すぎると"す"が入るので、やや弱めの中火に抑えてゆっくり仕上げて」。
出来たての温かい状態としっかり冷やしたもの、両方楽しめるのは自家製ならでは。「最初はおぼろ豆腐のようになったり、"す"が入ってもあまり気にせず、その時々で楽しんで。段々とコツがつかめるようになります」。
夏疲れの体にしみ入るようにおいしく、甘辛を交互に口に運べば止まらない。「蒸し料理の事始めにも最適。この機会に蒸籠を調達してみては」
材料&レシピ
中国の豆花
(直径11㎝の器4個分)
無調整豆乳(大豆固形成分9〜10%以上のもの)
500cc
にがり
小さじ1(5g)
〈トッピング〉
ピーナッツ
約50g
てん菜糖
60g
きな粉
適宜
ゆであずき
適宜
香菜
1株
豆板醤
小さじ1
しょうゆ
小さじ2
油揚げ
1/2枚
松の実
適宜
ごま油
小さじ1
鍋にたっぷりの湯を沸かし、蒸籠をのせて蒸す準備を始める。別の鍋にピーナッツとてん菜糖、水600ccを入れて中火にかける。てん菜糖が溶けたら、軽く煮立った状態で20~30分ほど煮る。ピーナッツを一粒食べてみて、少し歯ごたえがある程度に煮えていたら火からおろす。
豆花を作る。ボウルににがりを入れ、豆乳を静かに注ぎ加える。スプーンで混ぜ、器に分け入れる。器を蒸籠にのせ、蓋をして弱めの中火で10分蒸す。火を止め、蓋を開けずにそのまま10分ほど余熱で蒸らす。蒸籠が2段あれば4つ同時に、1段なら2つずつ2回に分けて蒸してもよい。
香菜は葉を摘み、茎を1㎝程度に刻む。しょうゆと豆板醤は混ぜ合わせる。油揚げは短冊状に切り、フライパンで軽く焼き目をつける。①のピーナッツのシロップやきな粉、ゆであずき、ごま油、松の実とともに、それぞれを小さめの器に盛り、トッピングの用意をしておく。
②の蒸籠の蓋をそっと開け、熱いので注意しながら豆花の入った器を取り出す。甘いトッピングはピーナッツのシロップときな粉、ゆであずきの組み合わせでのせる。辛いトッピングはごま油、豆板醤と合わせたしょうゆ、油揚げ、香菜を適宜のせて、松の実を散らす。
そら豆はさやをむき、弱火にかけたフライパンに並べ入れ、火を強めて焼き色がつくまで両面を焼く。焼き上がりに塩をふって器に盛り、レモンを添える。ナッツ、飲み物やパンと一緒にピペラードに添える。
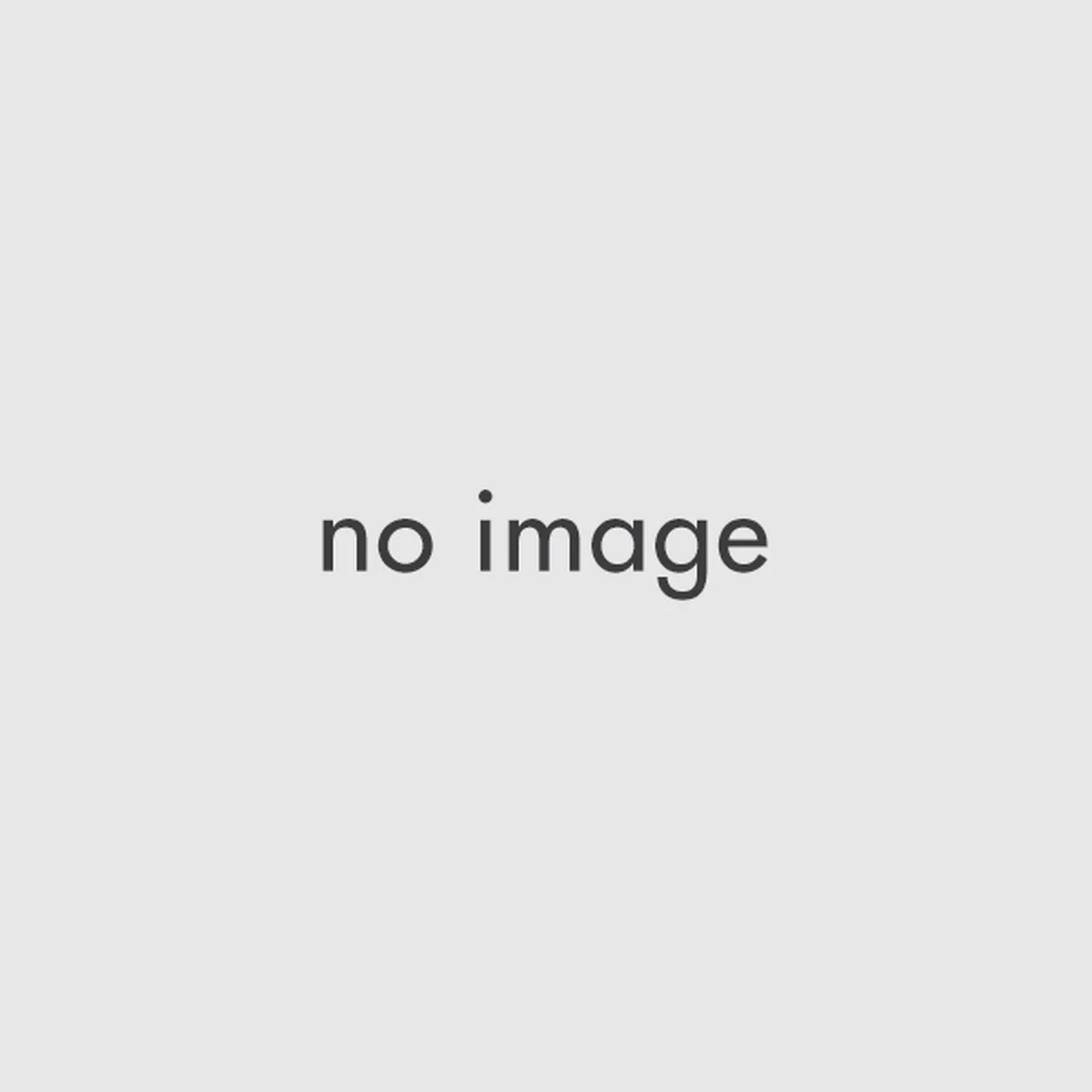
ながお ともこ●フードコーディネーター。雑誌や書籍で活躍する一方、オンラインストア、SOUPsを展開。「きのこや果物で長く持つ瓶詰を作りたくて、長期保存の実験中。この秋は素材を求めて出かけるつもり」