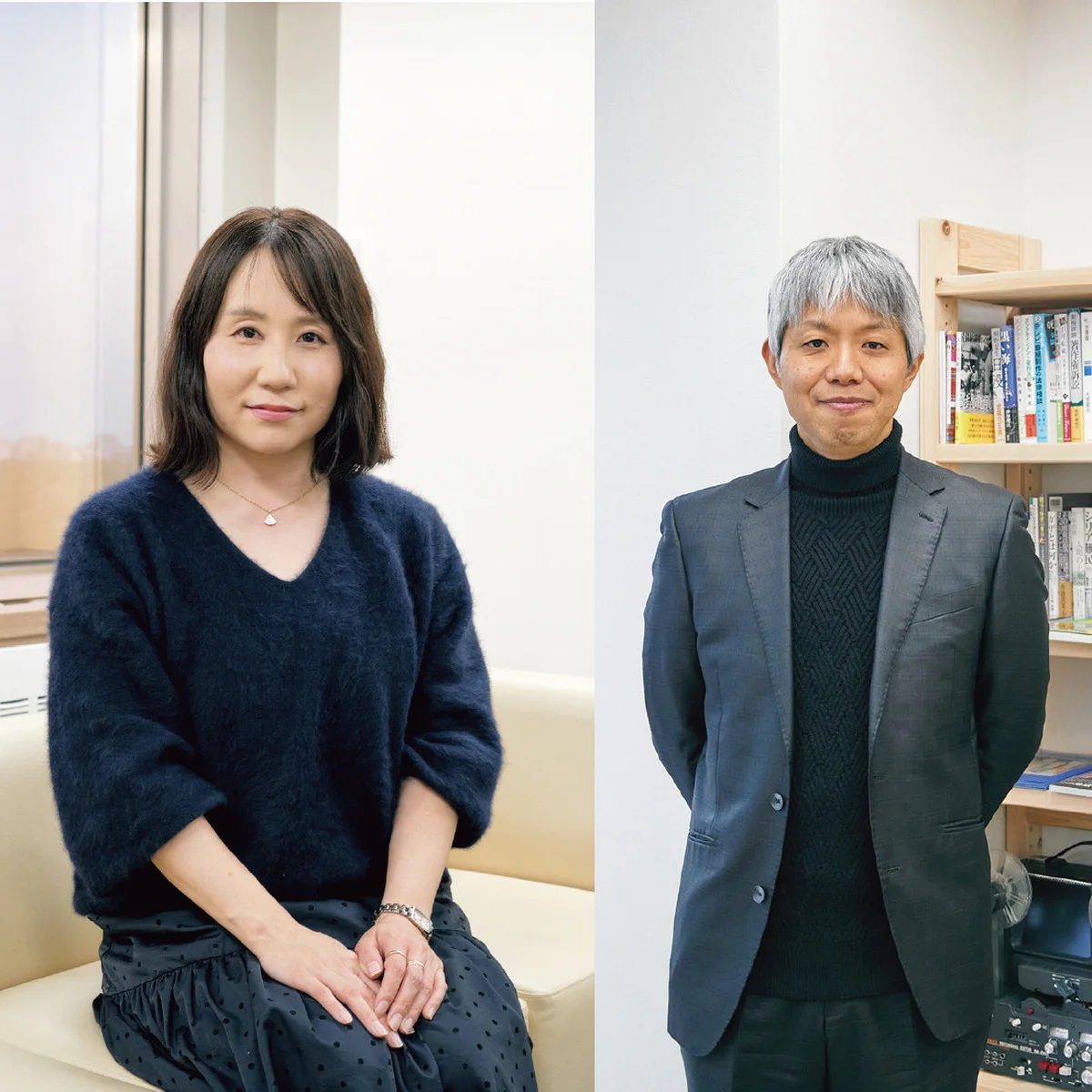「人生のお手本は、チャールズ・チャップリン。表現を通して社会を風刺し、世の中にさまざまな問題提起をし続けた彼の姿勢から、学ぶべきことがたくさんあります」。
イラン・イラク戦争(1980~88年)のさなかにイランで生まれ、物心つく頃から孤児院で生活していたサヘル・ローズさん。7歳のときに養子として引き取られ、その翌年の1993年、日本で働いていた義父を頼り、養母とともに来日した。虐待、貧困、いじめ、苛酷な試練に何度も直面し、一時は自死をも考えた。壮絶な経験を乗り越えてきた彼女はいま、俳優として活躍する傍ら、世界の貧困地域や難民キャンプ、施設で暮らす子どもたちを中心に、人道支援活動にも力を注いでいる。「支援活動を続ける中で、一番救われているのは自分自身です」。凛とした眼差しをまっすぐこちらに向け、サヘルさんは静かに語り始めた。
FEATURE
HELLO...!