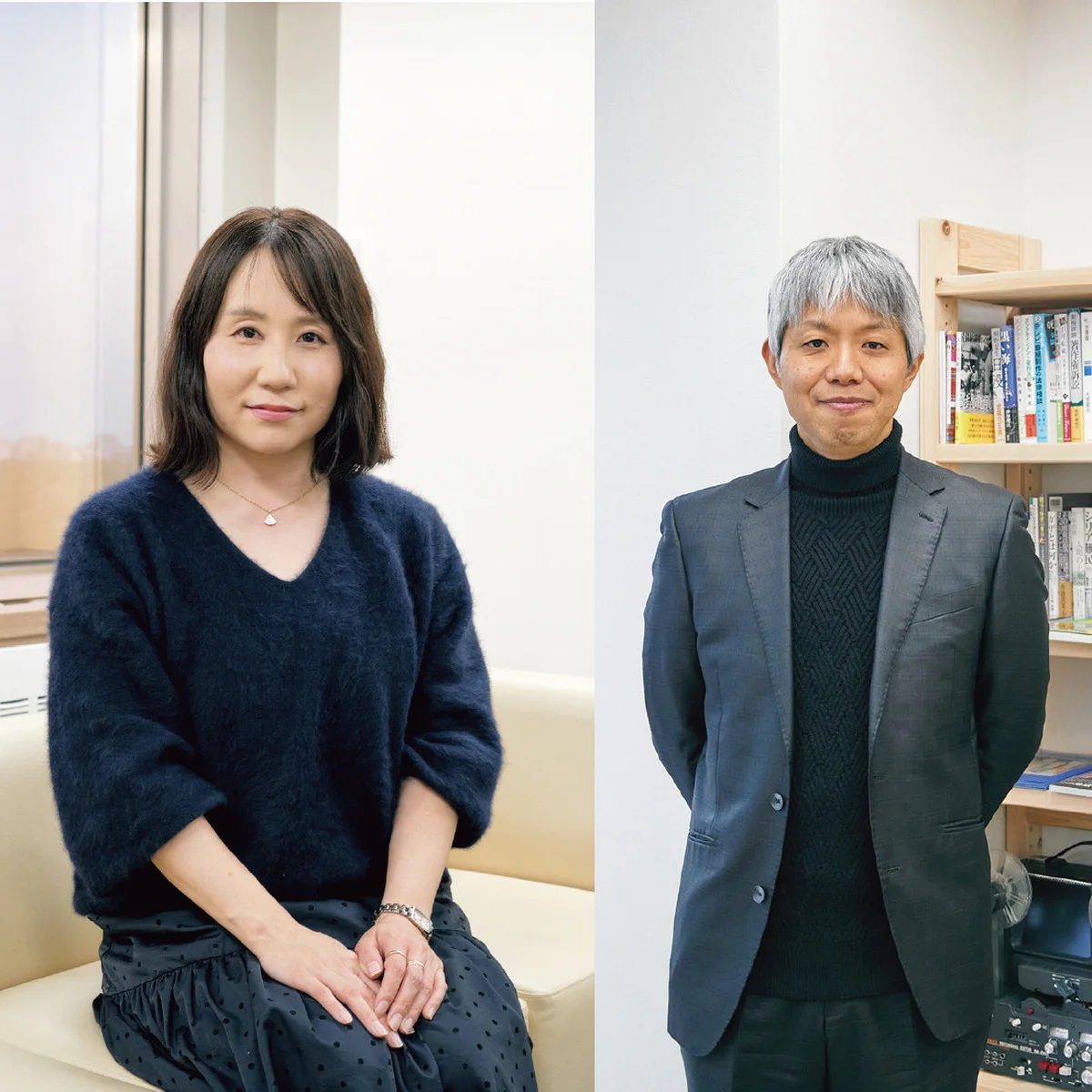1985年に日本人女性初の宇宙飛行士に選ばれ、スペースシャトルに2度搭乗した向井千秋さん。その後も国内外の大学で教鞭をとり、現在は東京理科大学特任副学長を務めるなど、70歳を過ぎた今も最前線で活躍している。医師、さらに宇宙飛行士と、大きな夢を2つも叶えながら、なおも精力的に活動し続ける向井さんのことばには、現代社会をポジティブに生きるヒントが詰まっている。

1985年に日本人初の3人の宇宙飛行士のひとりに選出。1994年、スペースシャトル「コロンビア号」に日本人として初めて搭乗し、ライフサイエンスや宇宙医学に関する実験を実施。1998年には、スペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗し、米航空宇宙局(NASA)のジョン・グレン宇宙飛行士らとともに各実験を実施。2015年、東京理科大学副学長に就任。現在は、同大学特任副学長兼スペースシステム創造研究センター「スペース・コロニーユニット」ユニット長を務める。