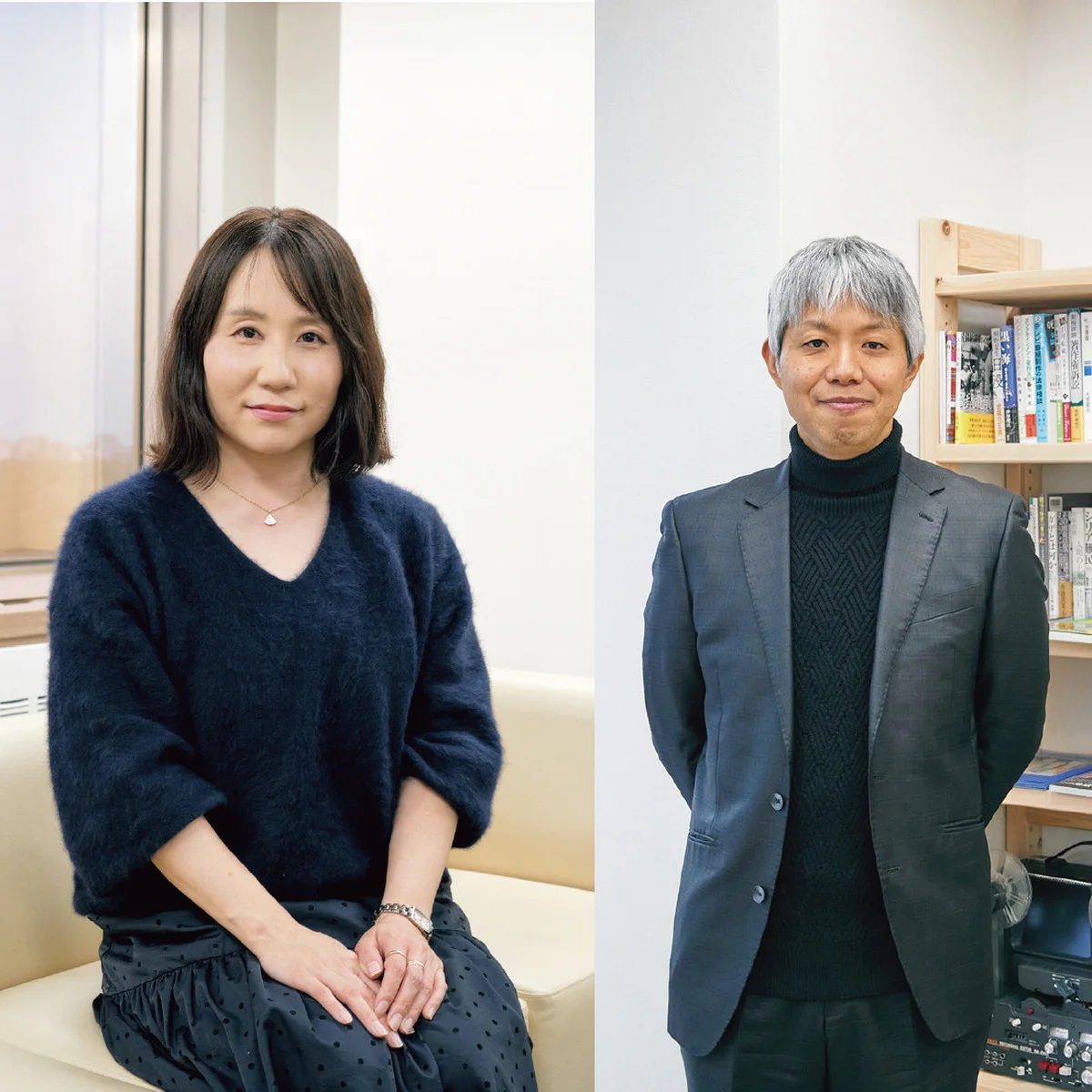貧困と差別の中、生き抜いた幼少期

1933年3月3日、三陸沖で巨大地震が起きた、まさにその日だった。アイヌのルーツをもつ両親のもとに、静江さんは6人きょうだいの次女として産声を上げた。日高山脈をのぞむ、北海道浦河(うらかわ)郡にある旧荻伏(おぎふし)村の集落で、山と海に囲まれ、感性豊かな幼少期を過ごした。小学校に入学する頃に太平洋戦争が始まると、あらゆる物資が不足し、生活は困窮していった。昆布漁や材木の切り出しで生計を立てていた父は、食糧難を受けて農業へと転向。静江さんは父の仕事を手伝ったり、でめんとり(日雇い労働)に行ったり、働きづめの少女時代を送った。
戦時中の貧しい暮らしの中、静江さんが小学校で経験したのは、アイヌ民族に対するいわれのない差別だった。民族の特徴である顔立ちの彫りの深さや、多毛であることでいじめの対象になり、同級生や上級生からは「イヌ」と罵倒された。歩いているだけで犬をけしかけられたり、川に落とされそうになったりしたこともあった。学校の教師すらも差別を公言した。なぜ自分がいじめを受けなければならないのかわからず、苦しんだ。高学年になると、生活を支えるべく一家の働き手となり、学校にはほとんど通わなくなった。
「アイヌは毛深いから『犬の血だ』なんて馬鹿にされてね。そのことが、アイヌの子どもたちの心の中に知らないうちに食い込んでいって、コンプレックスになるわけです。自分では解決できないことを差別の対象にされ、細かく、細かくいじめられました。どこにも訴えることはできませんでした。家の仕事が大変で学校に行かなくなると、勉強ができなくなります。すると通信簿で優劣をつけられて、劣等民族としてのレッテルを貼られてしまう。『アイヌのくせに』と蔑まれるんです。これは、和人社会特有の性質です」
小学校でいじめに遭うまで、静江さんは「アイヌ」という言葉を知らずに育った。両親は、あえて静江さんには出自を教えなかったという。
「明治期の和人たちは、『アイヌなんか殺したって罰を受けない』という認識を持っていました。そんな中で親たちは生きてきましたから、なまじっかアイヌの歴史や文化を子どもたちに教えるのは危険だと思ったのでしょう。もしも子どもたちが和人に応戦したら、取り返しのつかないことになるかもしれない。アイヌ語で会話をしたら、スパイだと疑われるかもしれない。苦労の中で生きてきたからこそ、子どもたちを守るためにもルーツを教えなかった。アイヌ自身が、アイヌの文化を切り捨てていかざるをえない状況だったのです」
虐げられてきたアイヌ民族の歴史

日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々は、屈辱的な差別を受け、虐げられてきた歴史がある。明治維新後の1869年、政府は北海道に開拓使を設置した。それまで独自の文化を持って暮らしてきたアイヌ民族に対して、「旧土人」という差別的呼称を使い、和人との同化政策を進めていった。アイヌの人々は日本人とされたが、当時の戸籍には身分表記欄があり、「旧土人」と記載された。もともと狩猟や漁猟を生業としてきた人々に、政府は農業を奨励し、住んでいた土地を没収し、日本語を強要した。文字を持たないアイヌの人々は、口承で歴史や物語を伝えてきたが、アイヌ語が禁止されたことで独自の文化が急速に失われていった。
1899年に「北海道旧土人保護法」が制定された。アイヌを「保護」するという名目で、希望者に農地が与えられたが、実際には和人を対象とした殖民地選定や区画事業が優先されたため、アイヌの人々には農業に不向きな粗末な土地ばかりがあてがわれた。アイヌの人々の共有財産は国のものとなり、居場所はどんどんなくなっていった。この法律は1997年に廃止されるまで、約100年もの間アイヌの人々を苦しめることになった。
「アイヌは、旧土人保護法によって、生活の基盤を根こそぎ略奪され、禁止されました。鮭も、熊も、鹿も、何もかも獲ることができなくなり、海藻や山菜まで制限されて、アイヌとして生きられないような状況に追い込まれたんです。アイヌの人々の生活や文化、言葉、誇り、すべてが否定され、奪われました。その屈辱は、はかり知れません。アイヌの歴史は、何も是正されないまま今に至っています」
内なるアイヌと向き合う決意、そして挫折

親の仕事を手伝い、満足に小学校にも通えなかったが、静江さんの中で勉強したいという思いが消えることはなかった。町役場のゴミ捨て場で拾った、漢字にルビが振られた哲学書をいつもそばに置き、両親の手伝いの合間に読んでいた。20歳のとき、「嫁にいきなさい」という親をなんとか説得し、札幌の中学に入学する。卒業後に就職を試みるも、札幌ではアイヌであることを理由に雇ってもらえなかった。東京の大学に進学する友人の誘いを受け、23歳で上京。早稲田の喫茶店で働きながら、都内の定時制高校に通った。店に来る学生たちが話題にする、世界文学の名作を聞き覚えては古本屋で購入し、仕事終わりに夢中で読んだ。
子ども時代のいじめのトラウマもあり、誰とも結婚しないと思っていたが、縁あって27歳のときに結婚し、二児の母となった。当時住んでいた公団住宅で知り合った、詩人会議(1962年に発足した詩人集団)のメンバーの女性に勧められ、浦川恵麻というペンネームで詩を書き始めた。すると自身の作品が、詩人会議を立ち上げた壺井繁治さんの目にとまり、月刊詩誌『詩人会議』に掲載される。「彗星のように現れた詩人」と絶賛され、その後もいくつかの詩を発表した。だが、アイヌのことはどうしても書けなかった。詩を書けば書くほど、内なるアイヌと向き合えない葛藤が生まれた。自分の心の中にあるアイヌをどう表現すればいいかわからず、悶々とした。
「上京してからは、自分の出自を隠すことこそしなかったけれど、自らアイヌであることを明らかにしようともしませんでした。これまで受けてきた差別を脱ぎ捨てるような気持ちで東京に来て、平穏な日々を送っていたのに、アイヌのことを忘れられなかった。30代になって、アイヌのために活動しなければと思ったときは、詫びるような気持ちでした」

アイヌとして胸を張って生きていこう。アイヌ同士が支え合える場を作ろう。そう決意した静江さんは、1972年2月8日、朝日新聞の「ひととき」という女性投稿欄に記事を投稿し、「ウタリ(アイヌの同胞)たちよ、手をつなごう。私たちはあなたとの語り合いを望みます。どうぞご連絡ください」と呼びかけた。38歳のときだった。その翌年に「東京ウタリ会」を設立し、東京在住の同胞たちと積極的に交流した。
アイヌとしての自覚を促す活動を始めたが、静江さんの活動に理解を示す同胞は少なかった。「自分たちはアイヌとして生きたいとは思っていない。せっかく東京に出てきたのだから、放っておいてほしい」といわれた。静江さんの思い切った行動に、「寝た子を起こすようなことをしてくれた」と迷惑がる人も少なくなかった。
「当時は背中を叩かれるような思いで活動を始めたのですが、アイヌはまとまれませんでした。長年差別されてきたことで、アイヌであることに誇りを持てなくなってしまったんです。家族にさえも、自分がアイヌであることを隠し続けている人もいました。今でこそ、同胞に会うとよろこんでもらえますが、当時は同胞だとわかっても目をそらされた。私のことを慕ってくれていた甥っ子たちも、私がアイヌ問題をやると、途端に敬遠するようになりました。同胞どうし認め合うこともできなくなっていた。それが、長年のアイヌ差別がもたらした実態です」
『アイヌ神謡集』との出合い。63歳で古布絵の世界へ

差別がなくなる世の中にしたい。そのためには平等な社会でなければならない。そう思って活動を続けてきたが、同胞たちに思いが届くことはなかった。掲げた理想とは程遠い状況に悩み続けた約25年間を、「惨めな活動だった」と静江さんは振り返る。
たくさんの挫折を経て、63歳のときに出合ったのが布絵だった。百貨店で開催されていた、古い和服の布きれの展示を見に行ったとき、布で作られた絵を見て「これだ」と思った。暗いトンネルに、突然光が差し込んだような気持ちになった。アイヌの世界を布絵で表現したい。たどり着いたのは、アイヌ民族が口承で語り継いできた物語(ユカラ)をまとめた『アイヌ神謡集』だった。
「アイヌの文化というと、歌や踊りなど、ちょっと浮いたところばかり取り上げられていますが、実はものすごく緻密で深いものなんです。私たちアイヌは、森羅万象、あらゆる動植物にカムイ(神)が宿っていると信じています。植物も虫も、水も火も、人間が作れるものではありません。それらはみんなカムイが作ったものだから、汚したり、粗末にしたりしてはいけない。カムイと対峙して生きるということは、小さな虫一匹に対しても気をつかうということなんです。両親は私たちにアイヌ文化を教え込もうとはしませんでしたが、今思えば、日々の暮らしの中でアイヌの精神性を教えてくれていたんだなと思います。
神謡集では、フクロウをはじめ、カエルやヘビや魚など、動物たちを主人公にした物語を通じて、アイヌの子どもたちに教訓を伝えています。神謡集を読んで、親たちが昔話してくれたことを思い出しました。私はそれまで、あまりアイヌ文化のことを深く考えたことがありませんでしたが、神謡集に出合ったとき、これこそがアイヌの教育だと深く感動しました」
 静江さんが作った古布絵。シマフクロウをモチーフにした作品(左)と、捨てられた子どもを助けるアイヌの人を描いた作品(右)。
静江さんが作った古布絵。シマフクロウをモチーフにした作品(左)と、捨てられた子どもを助けるアイヌの人を描いた作品(右)。
札幌に住む知人のもとに下宿しながら、アイヌ刺しゅうの教室に通い、伝統的なアイヌ手芸の技法を基礎から学んだ。和服の古い布にアイヌの刺しゅうを施し、アイヌの物語の情景を表現する。そこには、二つの民族の共生という願いが込められている。静江さんは、自身が生み出した手法を「古布絵」と名付けた。最初にモチーフに選んだのは、アイヌの村の守り神といわれるシマフクロウだった。大きく見開いた鋭い目には、「私たちアイヌは、まだここにいます」という為政者への強いメッセージが託されている。
「昔、まだ自然が破壊されていなかった頃は、村の身近なところにフクロウがいて、怪しい人物やクマなどが家に近づいてくると、鳴き声で知らせてくれたといいます。フクロウが見張ってくれていたおかげで、昔のアイヌの人たちは危険から身を守ることができました。フクロウはアイヌ語で『カムイチカップ(神の鳥)』といいます。フクロウの神様のことを『カムイチカップカムイ』といって、親たちは敬っていました。
神謡集に出合わなければ、私はただの活動家に過ぎなかった。神謡集を通じて、私は初めて本当のアイヌになることができました。私のアイヌ観は、ここから始まっています」
静江さんの古布絵を見た同胞たちは、アイヌの伝統を破ったと批判した。「人や動物などを具象化すると、悪いカムイの魂が宿る」という言い伝えがあるからだ。アイヌの作品を作ったけれど、同胞たちには見向きもされなかった。辛い経験だったが、一方で静江さんの作品を賞賛し、支援してくれる人もたくさんいた。古布絵作家としての活動が評価され、2011年に吉川英治文化賞を受賞。日本各地をはじめ、海外でも作品展や講演を行い、アイヌ民族の存在を世界に広く知ってもらうことに貢献した。
未来に向けて、「アイヌ力(ぢから)」を発揮せよ

奇しくも、静江さんが古布絵を始めた頃、悪法といわれた北海道旧土人保護法が廃止された。そして2019年5月、アイヌ新法(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律)が施行された。アイヌ民族を「先住民」と明記した初めての法律で、アイヌ文化の振興や、研究の推進などが盛り込まれている。しかし、アイヌ文化の基盤となる伝統的な狩猟や漁猟などの先住民族の権利については、この法律では触れられておらず、依然として禁止されたままだ。静江さんは、アイヌの人々の生活が安定し、自立するためにも、「奪われたアイヌの仕事を返してください」と訴え続けている。
カムイに感謝し、畏敬の念を持ち、自然の恵みを分け合って生きる。静江さんはアイヌの精神性を「アイヌ力(ぢから)」と呼ぶ。アイヌがひとつになるために、今こそアイヌ力を発揮せよ。そんな思いを込めて、2020年10月に『アイヌ力よ!』という詩を発表した。
アイヌよ
自分力(りょく)を出せ
アイヌが持つ力は 世界を変える
自分を出すは 自分力
自分力は アイヌ力(ぢから)
アイヌよ
大地を割って出るが如く
力を出せよ
アイヌ力を!
 静江さんの著書(写真左から)『大地よ!——アイヌの母神、宇梶静江自伝』(藤原書店、2020年)、『アイヌ力よ!——次世代へのメッセージ』(藤原書店、2022年)。
静江さんの著書(写真左から)『大地よ!——アイヌの母神、宇梶静江自伝』(藤原書店、2020年)、『アイヌ力よ!——次世代へのメッセージ』(藤原書店、2022年)。
解決すべき問題はまだたくさんあるが、それでも静江さんが活動してきた50年間で、状況はずいぶん変わってきた。「今は、アイヌとして生まれてよかったと思っています」。静江さんは、穏やかな笑顔でそう話す。北海道の白老町に移住して2年、力を注いでいるのは、アイヌとしての生き方をともに考える「アイヌ学」の確立だ。交流施設としてオープンさせた「シマフクロウの家」では、定期的に勉強会や講演会を開き、アイヌひとりひとりが自分のことを語ろう、アイヌの問題を理解しようと呼びかける。たくさんの同胞たちが、静江さんのもとを訪ねてくるようになった。「アイヌが少しずつ動き出している」静江さんはそう感じている。
「アイヌの人たちも、私の活動をよろこんでくれるようになりました。応援してくださる和人の方もたくさんいらっしゃいます。もちろん、アイヌに対する偏見や差別を隠し持っている人が多いのも事実で、そこはまだ凍りついたままです。これを雪解けに持っていくためにも、自分が学んできたことを積極的に語っていきたい。
最近は体が思うように動かず、布絵を作るのは難しいですが、アイヌの権利回復のためにできる限りのことを、希望を持ってやっています。2024年春には、全国のアイヌを集めたアイヌ大会の開催も予定しています。ウタリも、和人のみなさんも、みんなが認め合い、平和な社会を作っていってほしい。それが、私の最後の願いです」
何度も壁にぶつかり、何度も倒れてきた。それでも、90歳になった今もなお、前に進むことをやめない。「私はカムイに生かされている」と静江さんはいう。アイヌはここにいます。私たちのことが、見えますか——。かつて思いを託した幻のシマフクロウは、静江さんを見守り、今も導いてくれている。