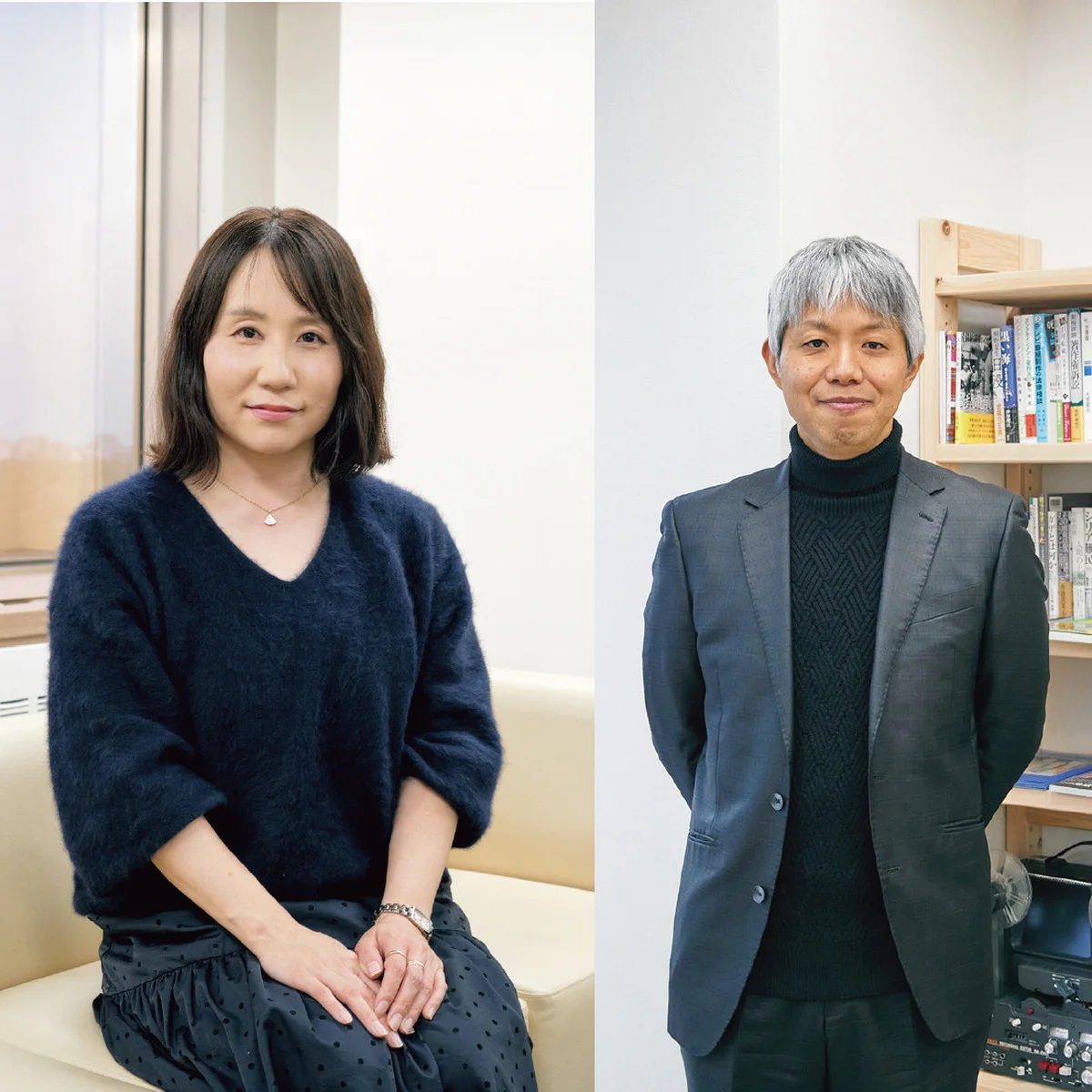世界と比べてみても、日本での服用率が圧倒的に低いピル。まずはメリット・デメリットは何なのか、正しく知ることから始めよう。もしかしたら、快適に過ごすための選択肢のひとつになるかもしれない。
PART4 「わたしとピル」を語る
ピルとのつき合い方は、人の数だけ違うもの。実際どうしているのか経験者に聞いてみました

鎮痛剤が手放せない痛みには、我慢しすぎないという選択肢を
ピルを飲み始めたのは2年半前。それまで私は生理痛が重い体質で、鎮痛剤が手放せませんでした。生理のつらさは人と比べられないものなので、「自分の我慢が足りないのかな」「体力がないのがいけないのかな」と考えて、その期間はまったく使い物にならなくなってしまう自分を不甲斐なく思い、周囲にも申し訳ない気持ちで過ごしていたんです。
ある時、あまりの激痛で病院に運ばれたところ、「子宮内膜症でチョコレート嚢胞ができている」と診断されて初めて、自分はただ生理痛が重いだけではなく、病気を患っていたのだと知りました。再発の可能性があるため私は手術はせずに、低用量ピルを服用して経過を観察することに。それまでピルはハードルが高い薬だと考えていて、自分自身で服用を検討したことはなかったのですが、ひたすらにつらい生理の期間が短くなったのは大きな出来事でしたね。ただ服用すれば生理痛がなくなって「すべてがハッピー!」とはなりませんでした。私の場合は、それまでのつらさが10だとしたら7になったくらい。あとは生理の時期を把握しやすくなったので、仕事量を事前に調整したり、近しい人にアナウンスして、なるべくストレスを減らすようになりました。
私の周りでもここ2、3年で服用を公表する人が増えてきたように思います。一度SNSで「ピル」と検索したら、下ネタの一部として消費している人ばかりが出てきて驚きました。ピルを服用しているのは決して恥ずかしいことではありません。私は堂々と冷蔵庫に貼りつけて必ず目につくようにして、懸念事項だった飲み忘れを防いでいます。たとえ、服用の理由が”避妊のため”でも、自分自身で体のコントロールをするのは当たり前の権利。避妊や生理、将来の妊娠のことを含む自分たちの体とうまくつき合うための選択肢のひとつとして、ピルがあるのだと思います。
Profile


医師と決めたピルの服用が、現役生活のプラスになった
私は20歳でアメリカのリーグに移籍したのですが、そこではチームメイトのほとんどが当たり前のようにピルを服用していて驚きました。みんながピルを飲んでいる理由を知りたくて、彼女たちに話を聞くうちに自分も興味を持ち、帰国して婦人科を受診しました。私の場合、サッカーの現場にいつも医師がいて、気軽に相談できたのが心強かったです。医師には気になっていたことを細かく質問して、現役生活を長く続けるために多くの面でプラスになると判断し、服用を始めました。私は服用中には幸いにも副作用がほとんどなく、生理の日数や経血量も減り、よいパフォーマンスの維持に役立ちました。以前から毎日体温を測り、生理日を記録していたので、ピルの計画的な服用で体調をコントロールできたのはとても助かりました。
現役選手として活動する中で、女性は妊娠、出産によるプレーの中断を余儀なくされます。若い頃に排卵を止めることで卵巣の状態を良好に保ち、機能を温存することが、のちの妊娠によい影響を与えるという医師の指導のもと、出産への自信を持ち続けながら、37歳まで大好きなサッカーを続け、ワールドカップやオリンピックでよい結果を残すことができ、現役生活を全うすることができました。選手として最後の年の8月に結婚して、年末の引退後にはピルの服用を中止し、翌年の3月に妊娠して、その翌年には無事出産しました。
日本では未だにピルに対して知識不足や偏見、先入観等により、ネガティブな判断をしている人も多いかと思います。また、生理が原因で、パフォーマンスに悪影響が出てしまうアスリートも少なからずいます。私の周りの選手たちの中には、妊娠を心配する人や、PMSで悩んでいる人もいました。引退した後に出産を望む選手は多いです。そんな中で、私が経験したことを少しでも伝えられたら彼女たちの不安を解消する一助になると思い、自分自身がピルを服用していることをオープンにしました。周りの選手から質問を受ければ、自分の経験を伝え、その結果、服用を始めた選手たちもいました。何よりも私は、信頼するドクターに健康に関する相談をして、指導を受けていたので、ピルも不安なく服用することができました。まずは婦人科を受診して、悩みを相談してみてください。女性一人ひとりが、かかりつけの医師やホームドクターを持つことが、とても大事です。
Profile

SOURCE:SPUR 2021年1月号「もっと知ろう、ピルのこと」
illustration: Yuka Takamaru text: Rio Hirai, Ayako Nozawa