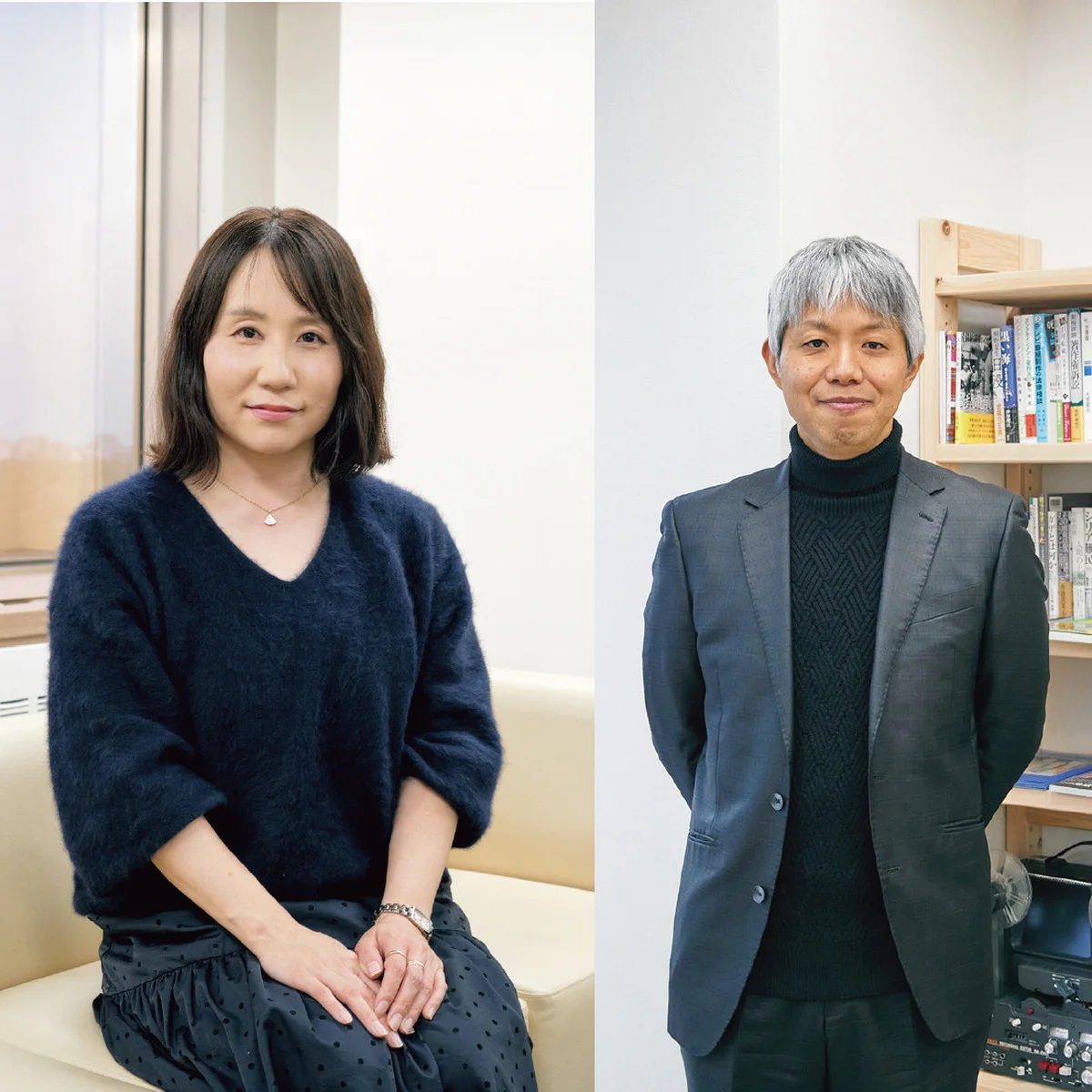87歳になった今も世界のアートシーンの最前線を走り続けているアーティスト、田名網敬一さん。その創作の原点にあるのは、子どもの頃の戦争体験。鮮烈で生々しいその記憶を語る
リヤカーには人々の亡骸が、折り重なるように積まれていた
田名網さんは、東京・京橋で「田名網商店」という服地問屋を営む家の長男として生まれた。当時、日本橋の髙島屋百貨店の裏手一帯が洋服の問屋街で、街は活気にあふれていたが、1941年、5歳のときに太平洋戦争が始まると状況は徐々に変化していった。
「子どもだったので、戦争がどういうものかはわからなかったけれど、母親の慌てる様子なんかを見て、ただならぬことが起きているんだなとわかりました。やがて父は出征し、商売どころではなくなって店も閉められました。残された僕と母は、目黒にあった母方の祖父母の家に転居したんですが、ここでたびたび空襲に遭いました」
戦争が激化した1942年、アメリカ軍の東京への空爆が始まると、戦闘機、B29が東京の至るところに爆弾の雨を降らせた。爆弾は、建物を焼き払う薬剤を積んだ「焼夷弾」を使ったため、木造建築の日本家屋は激しく燃え、街は炎に包まれた。
「空襲はたいてい夜でした。家の前の小さなはげ山に防空壕があって、空襲警報が鳴ると、暗い中、母とそこへ逃げ込みました。すると爆音とともにB29が何十機と編隊を組んでやってきて、空一面が戦闘機になります。地上からのサーチライトに照らされた夜空が、B29の銀色の機体で埋め尽くされるんです。そして、〝絨毯爆撃〟という言葉の通り、絨毯を敷き詰めたように一帯を徹底的に焼き尽くしていく。
その熱風が防空壕の中にも吹き込んできます。顔なんか火ぶくれができちゃうくらい熱いので、母が防火用の貯水池に手拭いを浸して、僕の顔にのっけるんですけれど、貯水池がヘドロの池になっているので、その手拭いが猛烈に臭い。払いのけようとしても、母がまた顔に貼りつけてくる。もう何十年も前の話だけど、今でもその臭いは忘れられません。
防空壕の中に、40〜50人はいて、満員電車のようにぎゅうぎゅう詰め。でも、中に入れた人はまだいい。10分、20分とたち、空襲警報が解除されて外に出ると、あたりは火の海で、そこには逃げ遅れた人たちの変わり果てた姿がありました。血まみれで、体の一部を失い、絶命した人たち。まさに地獄絵図です。
中でも忘れられない記憶があります。亡骸を運ぶリヤカーには、死体が折り重なるようにして積まれていて、その上にむしろがかけられている。そこから人の腕がだらりと下がっているんですね。そしてその指先を伝って、ぶわーっと大量の血が地面に流れていて、リヤカーが通ったあとには、真っ赤な線ができていました。これは本当にショックでした。
また、家の庭にも小さな防空壕があって、そこに避難することもありました。入り口付近には、巨大な水槽があって、見上げると、ゆらゆらと金魚が泳いでいる姿が見えました。祖父が趣味で、高価な金魚の養殖をしていたんです。それで庭には縦2メートル、横4メートルほどの巨大な水槽が置いてあって、琉金、蘭鋳(らんちゅう)、出目金など、たくさんの金魚が泳いでいました。防空壕の丸い入り口から見ると、それがちょうど円型のスクリーンに映し出された映像のように見えるんです。
空襲のとき、B29は照明弾をまず落として、一帯を明るくしてから狙いを定めて爆弾を落とします。そのとき、オレンジ色の光線が真っ暗闇を照らして、一瞬、真昼より明るくなるんですけれど、その光が金魚のうろこに乱反射するんです。キラキラと発光しながら水槽を泳ぐ姿は、異様な美しさを放っていました。恐怖から逃れたいという気持ちもあったのかもしれないけれど、それは非常に幻想的な光景で、まるで夢の中にいるようでした」
唯一楽しみだった叔父との時間。でも、その彼も帰らぬ人に
「戦時中、食べものはほとんどありませんでした。週に1回、お芋をすりつぶした粉末の配給がある程度。それを水で溶いて焼いて食べるんです。粗末な食事でしたけれど、不思議とおなかがすかなかった。極限状態で、子どもながら精神的に追いつめられていたんでしょう。何か食べたいとか、何か欲しいっていうような欲望が奪われていたんだと思います。
そんな中での唯一の楽しみが、叔父さんと過ごす時間でした。慶應義塾大学の学生だった叔父は、サブカルチャー的なものが大好きで、今で言う〝オタク〟だったんですね。あの頃では珍しかった。それで当時、日本の同盟国だったドイツの雑誌や絵葉書なんかを集めていました。これがとてもモダンなデザインですごくかっこいいんです。
出征する前は、よく遊んでもくれました。組み立て式のおもちゃの作り方を教えてくれたり、紙で船を一緒に作ったり。それで僕は工作が好きになったんですね。だけどその叔父も戦死して、帰らぬ人となりました。
祖母は戦後も亡くなった叔父のコレクションをずっと大切に納戸にしまっていました。僕はそれが見たくてしょうがないんだけど、祖母から「さわっちゃいけない」と言われてた。それで祖母が出かけると、すぐに納戸に入って、絵葉書なんかを引っ張り出して見たりして。僕がデザインの道に進んだのは、きっと叔父の遺伝だと思います」
戦争末期には、新潟県の六日町に疎開し、1945年、終戦を新潟で迎えた。田名網さんは9歳になっていた。
「目黒に戻り、権之助坂の上から街を見たとき、仰天しました。疎開前は、まだ建物も緑もあったのに何もないんです。更地になっちゃってる。焦土がどこまでも続いていて、焦土の赤茶色と空の青と2色しかない。うちが焼けずに残っていたのは奇跡でした」
幸い父親も戦地から無事に戻り、復興の熱の中で10代を過ごした田名網さん。戦後、大量に入ってきたアメリカ文化の豊かさに驚愕し、すぐにとりこになっていった。
「家の近くの権之助坂の途中に掘っ立て小屋みたいな映画館があって、よく通ってましたね。まだアメリカの占領下から間もなかったから、作品も『アメリカは偉大だ!』というプロパガンダの色が濃かったけれど、その華やかさや技術力はとても魅力的で。僕を含めて若者は、すっかりそれに乗せられていました。
ただ、あるとき、客席に特攻隊のような服を着て、日の丸のハチマキをした人がいたんです。その人が映画が始まったとたん、日本刀を出して、スクリーンをめった切りにしたんですね。まだまだ複雑な思いを抱えている人がいることを知ってショックを受けたのを覚えています。で、今だったら、そこで上映中止になると思うけれど、あのときはそのままズタボロのスクリーンで映画を上映したんです。そういう混沌とした時代でした」
疎開先の新潟で見たニワトリ。真っ赤なトサカが炎のようだった
アニメーション映画を初めて観たのもこの頃のこと。「ウォルト・ディズニーやフライシャー兄弟の作品には衝撃を受けました。僕がその後、アートの世界に進んだのは、このときの体験が大きく影響しています」というように、田名網さんは、やがて日本のポップアートを牽引する存在となっていく。しかし一見、カラフルでポップなその作品をよく見ると、銀色に彩られたB29や色鮮やかな金魚のモチーフがしばしば登場し、「戦争」の影が色濃く映し出されていることがわかる。
「作品を作るときは戦争をイメージして作っているわけではないんですが、心の中にしまわれていたものが、何かの拍子にぶわっと出てくるんですね。もちろん見る人には、楽しい絵として感じてもらっていい。でも、自分の中に潜伏していた戦争の恐怖が無意識に形として出てくる。金魚はそのひとつですし、ニワトリもそうです。
新潟に疎開していたとき、農家が何百羽というニワトリを飼っていました。そのニワトリが、ラジオで空襲の警報が流れると、まだ爆撃機は来てないのにトサカを真っ赤にして、うわーっと騒ぐんです。それが炎のように見えるんですよ。だから僕の作品に出てくるニワトリは、爆撃の炎や恐怖の象徴なんです」
今でもテレビでウクライナの映像を見ると、「当時、見たものが二重写しになって画面に映るくらい、まざまざと記憶がよみがえる」という。
「戦時中は、『死』というものが日常化するくらい身近にあって、戦後も子どもたちはトラウマを抱えていたと思います。僕は絵を描くことで、精神的な屈折とか闇を、ある程度吐き出すことができた。それで何とか救われたけれど、今でもまだ『死』に取りつかれたままです。
日本は今また戦前に回帰していくようなムードがありますよね。ウクライナの映像なんかを見て、戦争の悲惨さはみんな頭では理解していると思うけれど、結局、映像を見ただけでは、本当の恐怖は伝わらないし、自分のこととして、とらえられていないんじゃないでしょうか。要は他人事。そこが怖いところです。戦争のような地獄は何としても避けなければならない。あんな悲劇には、もう誰も巻き込まれてほしくないと僕は願っています」

1936年東京生まれ。武蔵野美術大学を卒業。1960年代よりグラフィックデザインやアニメーション、絵画、彫刻など、ジャンルを超えた活動を続けている現代アートの巨匠。ニューヨーク近代美術館(MoMA)にも作品が常設展示されるなど、世界的な評価も高い。今年1月には、赤塚不二夫の作品とコラボレーションが実現し、話題となった。今秋には、プラダ財団が企画する展覧会に参加予定。