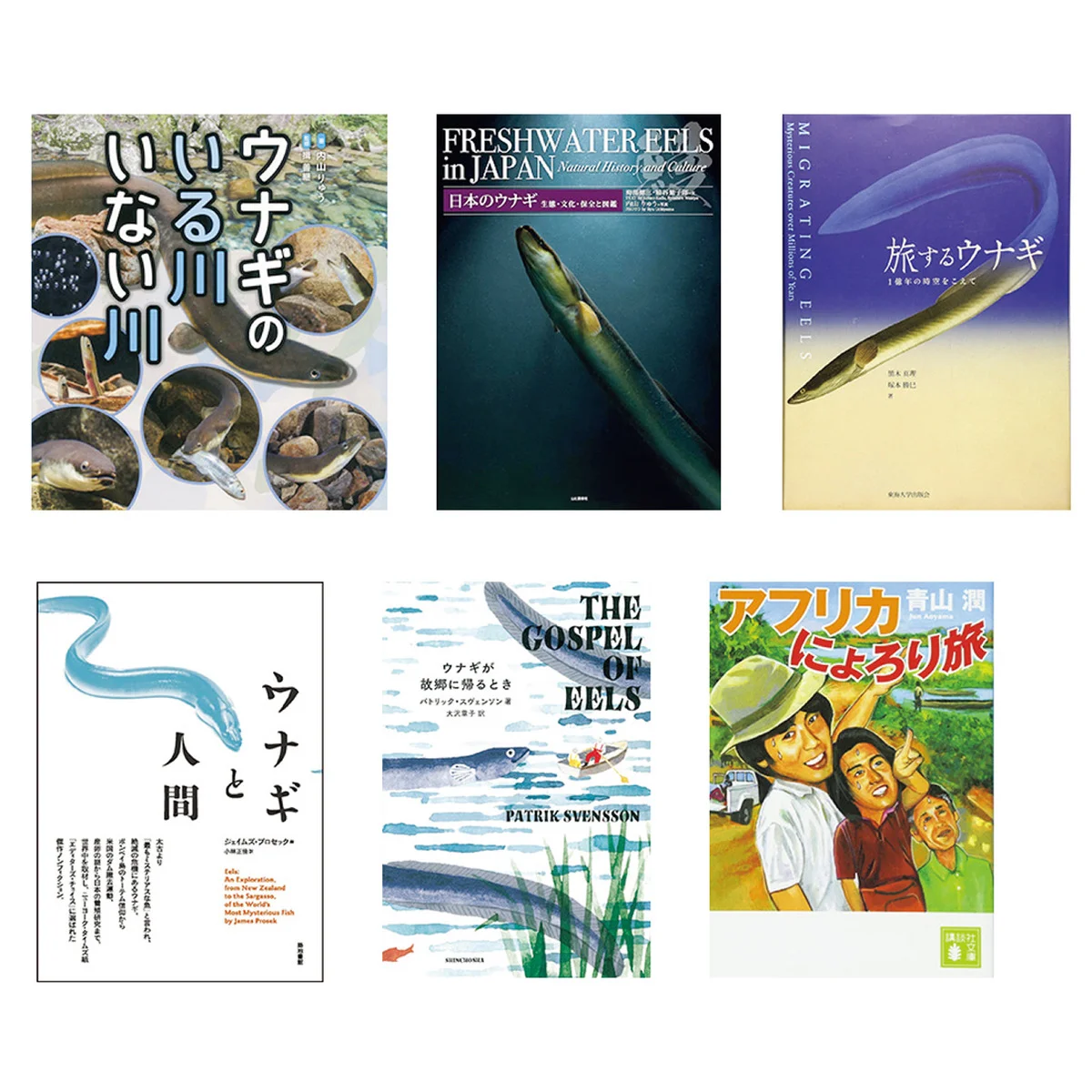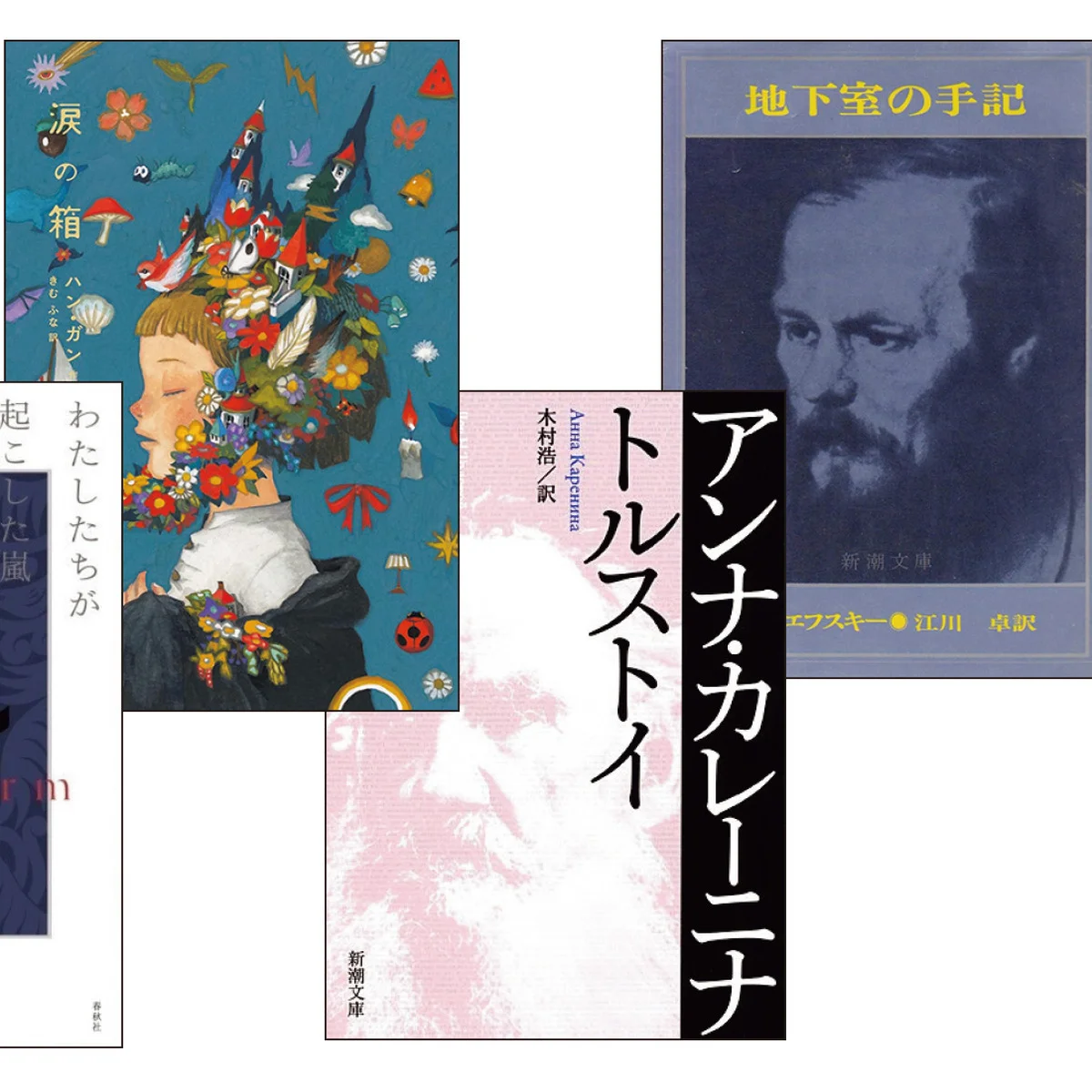公開されるや否や世界で議論を巻き起こした映画『サブスタンス』。エイジズムやルッキズム、そして不平等な社会構造まで、脱線しながらネタバレ全開で読み解く。映画を観たあとに読めばあなたも語り合いたくなる!
公開されるや否や世界で議論を巻き起こした映画『サブスタンス』。エイジズムやルッキズム、そして不平等な社会構造まで、脱線しながらネタバレ全開で読み解く。映画を観たあとに読めばあなたも語り合いたくなる!
『サブスタンス』から社会を語る会
エンターテインメント映画が鏡となって映す現代社会。そのゆがみを評論家、映画ライター、美容ライターがディスカッション。
「注目中毒」のトラップにはまる
映画『サブスタンス』は、コラリー・ファルジャ監督が40代になって感じた強烈な自己嫌悪をもとに作られている。主人公はエクササイズ番組に出演する俳優、エリザベス(デミ・ムーア)。彼女は男性プロデューサーに降板を告げられ、危機を感じて謎の物質、サブスタンスを注射する。その結果、彼女の体から出てくるのが若く美しい自分の分身、スー(マーガレット・クアリー)だ。彼女たちはふたりでひとつ。1週間ずつ交代で体の持ち時間を与えられる。果たして共存は可能なのか——その問いの背景に、ルッキズムやエイジズムを加速させる今の社会構造が描かれる。では早速、物語を深掘りしてみよう。
荻上チキ(以下荻上) 映画では鏡が象徴的に繰り返し出てきて、「これは鏡ですよ」とわかりやすく提示されています。ただ、鏡としての映画は女性だけではなく、それを見ている人やもっと大きな枠組みも映している。『サブスタンス』を観て、美にこだわる女性を「バカだね」と男性視聴者が思うのであれば、むしろ彼らに「ここにある鏡をじっくり見てみないか」という呼びかけがなされている。
長田杏奈(以下長田) 若さにこだわり続ける年をとった女性像というのは、一般的な作品では罰せられ、嘲笑の対象になりがち。でも本作では、それは誰が作った構造なのかが描かれている。そこが今までとは違うと思いました。エイジズムは誰にでも平等に降りかかる差別で、性差別やルッキズムを増幅させるところがある。しかも、自分がかつて年を重ねた人に向けたまなざしや偏見がブーメランのように戻ってくるんです。それもわかりやすく伝えている。自分の分身が、自分のためには動いてくれない不都合さもリアルです。
萩原麻理(以下萩原) 一番つらかったのはホラー的な場面ではなく、エリザベスがデートに出かけようとして、鏡の前で何度も服や化粧をやり直す日常的なシーンでした。
長田 最初は堂々たる肌見せドレスがかっこいいのに、どんどん隠す方向に行き、結局若い自分(スー)と比べて卑屈になってしまう。そしてデート相手のリアルなひとりに好かれることよりも、「みんなが私を愛してくれる」という方向に強い衝動が向くのが現代的だな、と。いわゆるアテンション・エコノミーでの「注目中毒」になっていくんです。
自尊心とメディアの密接な関係
——テレビ業界の話であると同時に、エリザベスの自宅の窓から見える、スーが映し出された広告が大きな役割を果たします。
荻上 SNS画像や雑誌、広告が生み出すイメージに触れれば触れるほど、男女ともにその自尊心が下がるというメディア研究の結果があります。女性は美や若さに反応する。男性は、筋肉がついていない自分に対して自尊心が下がり、運動をしていない状態をサボっている、怠惰だ、と思ってしまう。それで筋トレをして、プロテインをとる。
萩原 映画には若さを求める男性治験者も出てきますが、罪悪感になるんですね。コラリー・ファルジャ監督もインタビューで10年前のボディポジティブな流れがあった頃と比べて今は状況が悪くなっていると言っています。
長田 「今また、ウェイフモデル(極度に痩せたモデル)がきてる」とか……。見た目が投資や自己啓発に還元される空気も蔓延している。お金や権力があれば装備を選べる、みたいな感覚があるのかもしれないですね。
荻上 ルッキズムという言葉の使われ方も変わってきているんですよ。もともとは会社の面接のような場面で、外見の評価と能力評価を誤認してしまうときに使われていました。今はもっと広く解釈されていて、見た目に言及する行為そのものもルッキズムと呼ばれる。言葉の意味が拡大するのには理由があって、それは多くの人たちが外見に言及されることを不快に思っていたから。ところがそれに対して、「いや、ルックスも含めてパーフェクトになろう」と推し進める産業もまた大きくなっているのが現状なんです。
——その圧倒的なシステムにのまれているから、個人では暴走が止められないんですね。
長田 最近は美容業界でも、「20秒できれいになる」とか、クイックさが増している。効果が分刻みで語られることもあります。
ルッキズムの若年層化
——日本ではなかなかそういう話が問題になっていない気がします。
荻上 周りの方と話していて思うのは、海外で議論された社会正義が輸入される前に、日本ではそのバックラッシュだけが輸入される。
長田 わかります!
荻上 米国の公聴会で問題になったのは、フェイスブックが若者のメンタルヘルスの悪化に関係するデータを隠していたこと。そのデータが先ほど触れた、男女ともSNSに触れると自尊心が減っていくという話なんです。
長田 私たちが見ているものって、たいてい加工されているんです。フィジカルにも、デジタルでも。顔がちっちゃくなって、頰がピンクになったりするアプリもありますよね。すると小さい頃から「あ、これが可愛いんだ」と刷り込まれてしまう。それに憧れるようにに導かれ、リアルじゃないものと自分を比べる。昔は他人と比べたけれど、今は現実の自分と加工している自分を比べて、加工しているほうに合わせるんですよ。そういう美容クリニックでの施術の話も聞きます。
萩原 劇中のスーの体も、胸やお尻など、実は特殊メイクだそうです。つまり誰も「あのレベルの美」には到達しないと。
——実際、ルッキズムにさらされる人々は、どんどん若年層化しているんでしょうか。
長田 そうですね。デジタル・ネイティブ世代に、ルッキズムとアテンション・エコノミーの合わせ技が直撃。親の影響もあります。
荻上 ストレスは増大してますね。
長田 フランスでは15〜24歳女性の死亡原因で交通事故に次いで2位に摂食障がいがあるというデータを取っている。これを社会問題として重く受け止め、解決策の一環として、広告写真でモデルの体をレタッチした際は「加工写真」と明記するよう義務化。近年では、インフルエンサーが美容整形とタイアップするのを禁じる法律も。日本もまずはこういう調査をして、危機意識を高めてほしい。
その枠組みを作っているのは、誰か
——劇中の食べ物の比喩も面白いですよね。
萩原 序盤のデニス・クエイド演じる男性プロデューサーがエビを汚く食べる場面から始まり、エリザベスが狂ったように料理をする場面がある。性的対象を英語では「ミート」と言うこともあるし、いろんな生々しさの象徴になっていますよね。
長田 エリザベスが料理を作りまくって、食べまくる。あれは自分をいじめていますよね。
荻上 摂食障がいというだけでない、ある種の自傷行為が続く。でもその刃は誰が用意したのかというと、彼女が自分で用意したものではなく、そう仕向けられている。
——最後に出てくる株主たちを含め、その権力構造ははっきり提示されています。
荻上 最後の大晦日番組で、プロデューサーが株主に「私が作った完璧な作品をご覧にいれましょう」と言う。でも、彼は実は何にもしていないじゃないですか。しかもその番組には胸を出したダンサーがずらっと並んでいて、セクシーを前面に押し出す。もし彼が作ったとするなら、その枠組みです。女性が努力する環境ではなく、彼女たちを性的なフレームに当てはめる場所作り。さらにこの映画は舞台が限られていて、社会がほとんど出てこないのに、出てくるときは「2億人が君を見てるよ」といったセリフとして登場する。
長田 数字だ。
荻上 数字でしか社会が描かれない。生活感もなくて、エリザベスもスーも自宅と「見られる」場所との往復なんですよ。孤立感が強い。セルフケアもなく、エリザベスとスーにケアをし合う発想もなく。
長田 家にはペットもいないし。
萩原 友達もいない。40代、50代だったらもう少しサポートシステムを作っているはずですが、エリザベスにはまったくない。
荻上 ストーリーに分岐点がいくつかあるじゃないですか。もしデートに出かけていたら、違っていたかもしれない。サブスタンスを中止すれば、終わっていたかもしれない。でもあの反復において、やっぱり止められない、止まらないさまが描かれている。
萩原 本当に今、古い言い方ですが「人には親切にしよう」とか、そういうことしか変化のきっかけにはならない気がします。
荻上 小さくても確かなつながりを確保するのは、すごく大事ですよね。
長田 私もエリザベスとスーが仲よくなれたらよかったのに、と思いました。文通するとか、自分も泡風呂でリラックスするとか。
デミ・ムーアが演じる意味
——デミ・ムーアの演技は圧巻でした。
長田 彼女のリアルなヒストリーと、エリザベスが重なるところがありますよね。
萩原 デミ・ムーアはこの役でゴールデングローブ賞を受賞して、「私は30年前にポップコーン女優と呼ばれ自分でもそう信じていました」とスピーチしていましたが、本当に実力よりはセックスアピールのある俳優とされていました。私生活でもセンセーショナルな扱いをされて。妊娠時にはヌード写真が雑誌の表紙になり、アシュトン・カッチャーという年下の男性と結婚し、『チャーリーズ・エンジェル フルスロットル』(’03)でカムバックしたときには大金をかけて全身整形した話がマスコミで取り沙汰されました。
長田 あの頃のセレブゴシップって、今よりずっと意地悪で、「美にこだわって、若さにしがみついて、若い男と結婚して」と書き立てた。そういうゴシップのネタにされていた人がこれをやるんだ!と思いました。
萩原 最後に主人公がリベンジを果たしますが、デミ・ムーアが世間に復讐をしている映画でもあると思う。
それでも、心の解放を目指す
——ラストシーンはどうでしたか?
長田 私はハッピーエンドだと思いました。
荻上 主観的幸福で終わりますからね。彼女は解放されたけれども、ただ世界は何も変わっていないという。
萩原 でも映画を観た人にはいろんなもののばかばかしさが伝わる。そこはちょっと解放されるんじゃないかと思います。
長田 ルッキズムは自分もその構造の中にいるし、どうにもならないと思うときもたくさんありますけど、「こういう構造なんだ」というのをエンタメとして見せてくれるのはいいなと興奮しました。ルッキズムについて、客観視を促す寓話というか……。
荻上 自分のことを語りたくなる映画でもありますよね。
長田 映画を観て「デミ・ムーア(笑)」となる人は、作品を〝鏡〟に使ってほしいです。

1967年生まれ。映画ライター。雑誌編集を経てフリーランスに。映画や音楽の記事を執筆、翻訳を行う。訳書に『ボビー・ギレスピー自伝』(イースト・プレス)ほか。本誌で映画連載を担当。

1977年生まれ。ライター。雑誌やWEB、書籍で美容やフェミニズムにまつわる記事、インタビューを手がける。著書に『美容は自尊心の筋トレ』(Pヴァイン)。

1981年生まれ。メディア評論家、編集者。ラジオ番組「荻上チキ・Session」(TBSラジオ)パーソナリティ。著書に『社会問題のつくり方 困った世界を直すには?』(翔泳社)ほか。