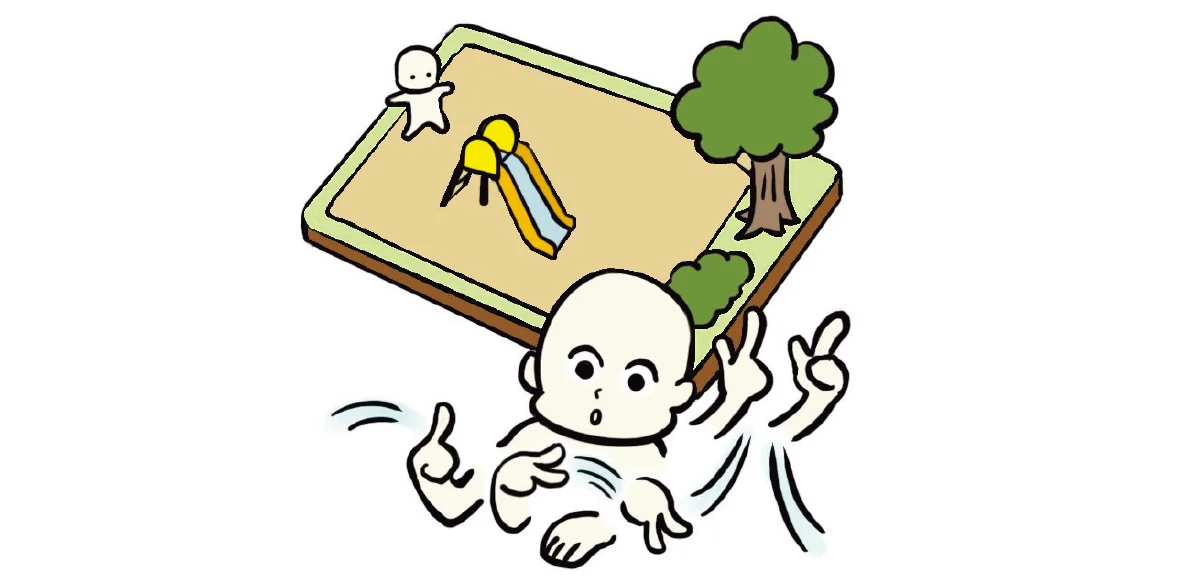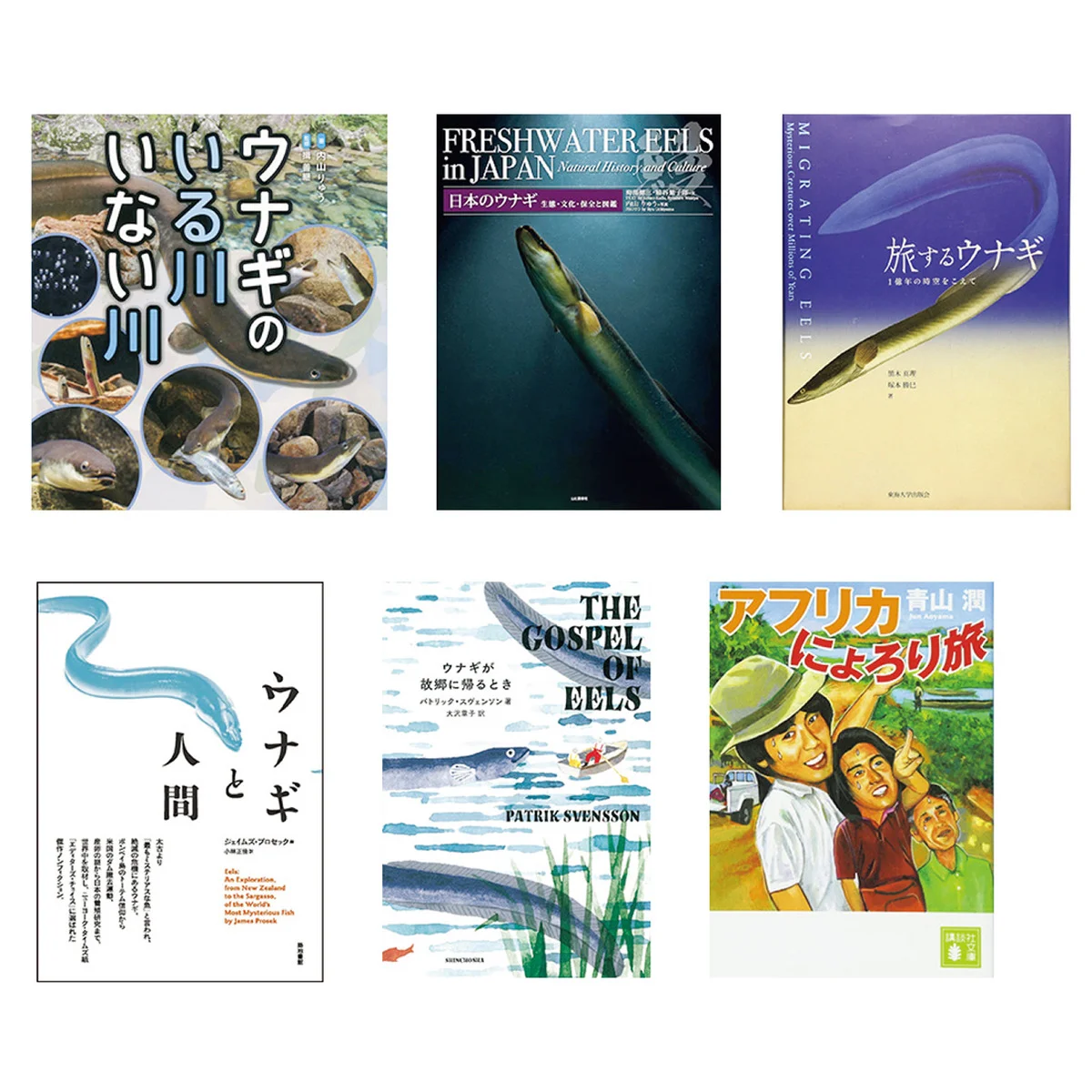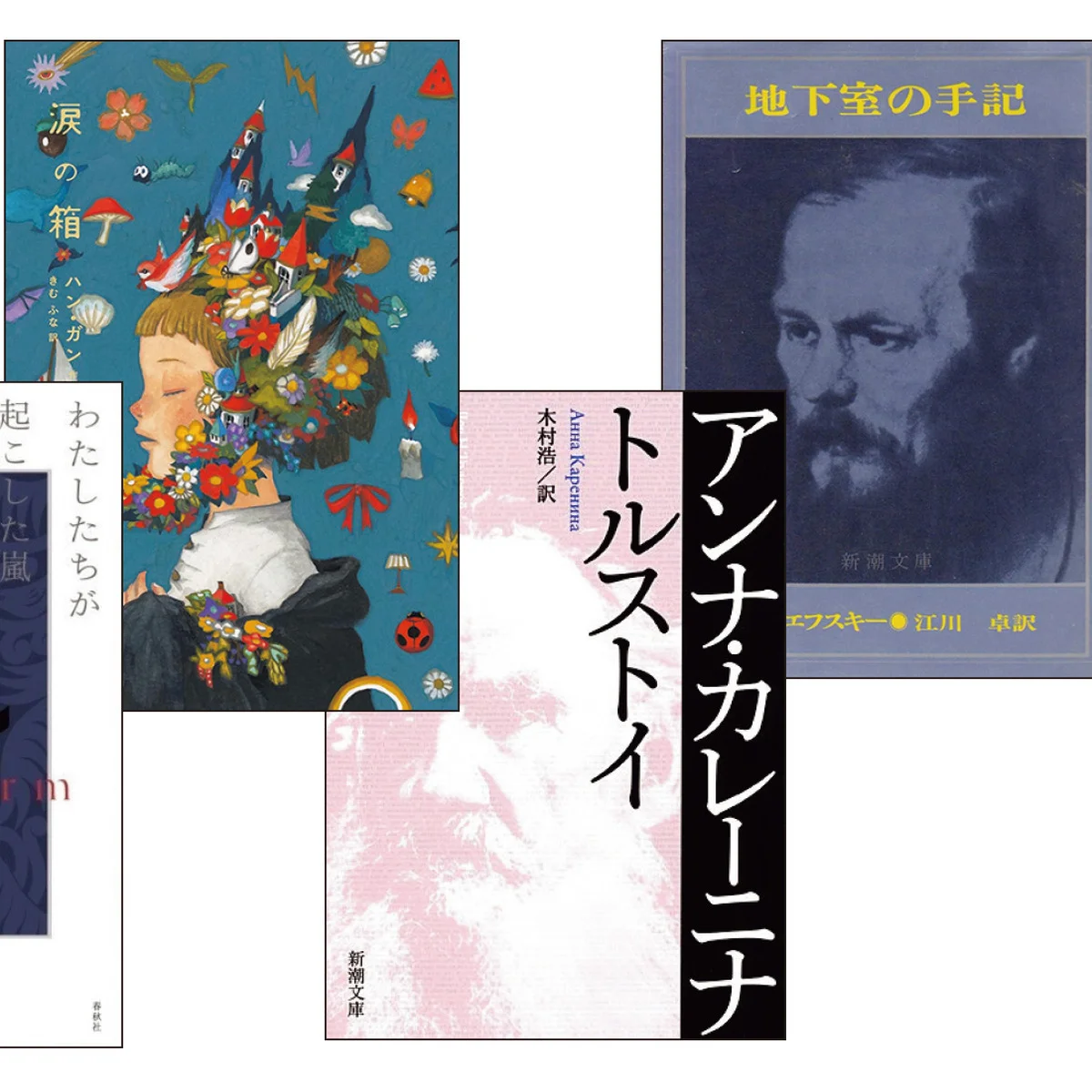耳のきこえないアスリートのためのオリンピックが今秋、日本で初開催される。スポーツ手話言語通訳と大会運営、裏方としてデフリンピックをサポートする関係者が期待するものとは?
耳のきこえないアスリートのためのオリンピックが今秋、日本で初開催される。スポーツ手話言語通訳と大会運営、裏方としてデフリンピックをサポートする関係者が期待するものとは?
手話通訳士 佐藤晴香さん
福祉の手段ではなく手話言語の奥深さ、楽しさを感じてほしい

さとう はるか●東京大学先端研究センター・熊谷晋一郎研究室に学術専門職員として所属。デフ水泳のサポートスタッフなど多方面で活動する。
全日本ろうあ連盟 事務局次長、デフリンピック運営委員会事務局長 倉野直紀さん
ろう者ときこえる人の間にある壁を越えて大会を築く。初の試みが新たな共生の道へ

くらの なおき●15年前に全日本ろうあ連盟理事に就任。スポーツ委員会事務局長を経て、2017年から3大会連続で日本選手団総務を務めた経験も。