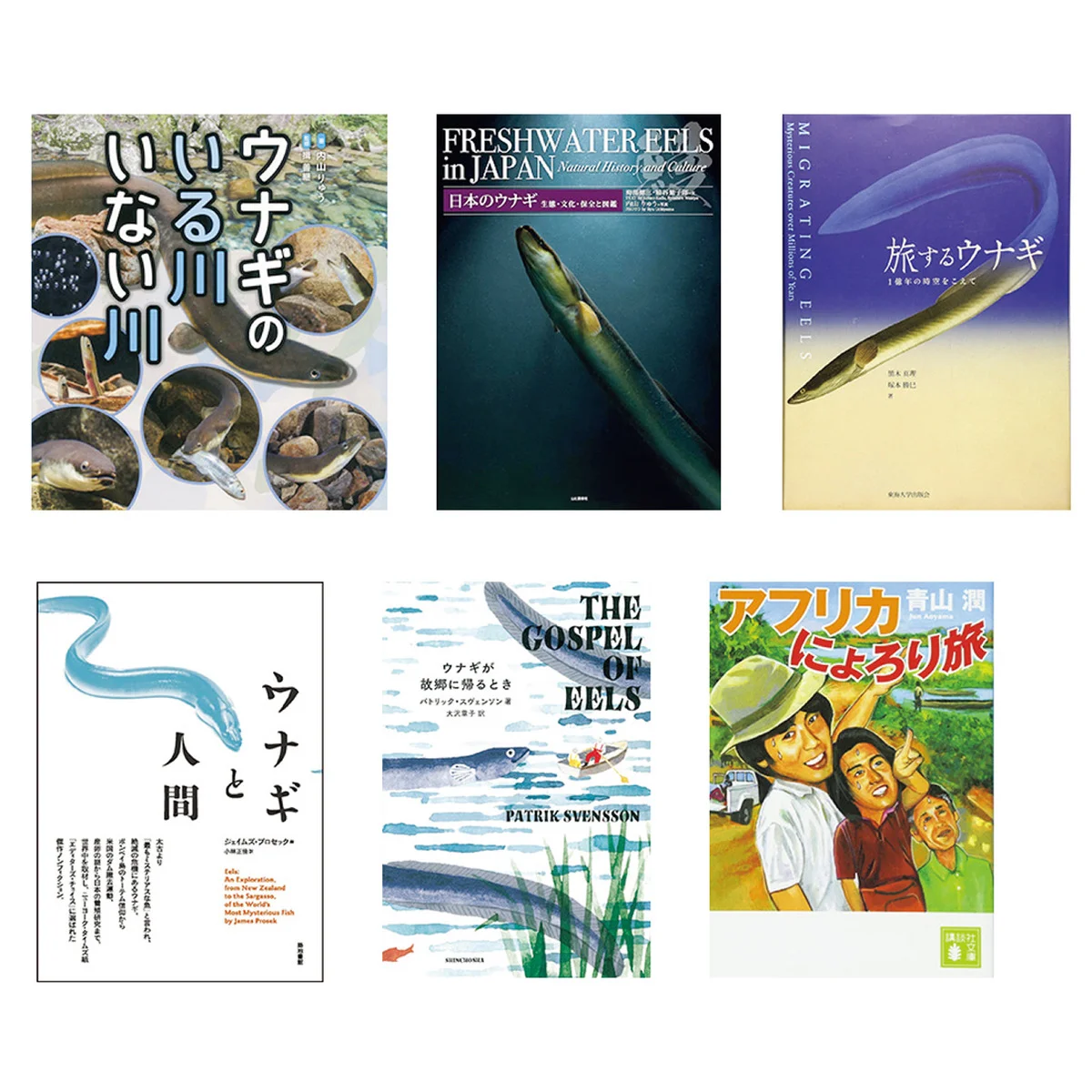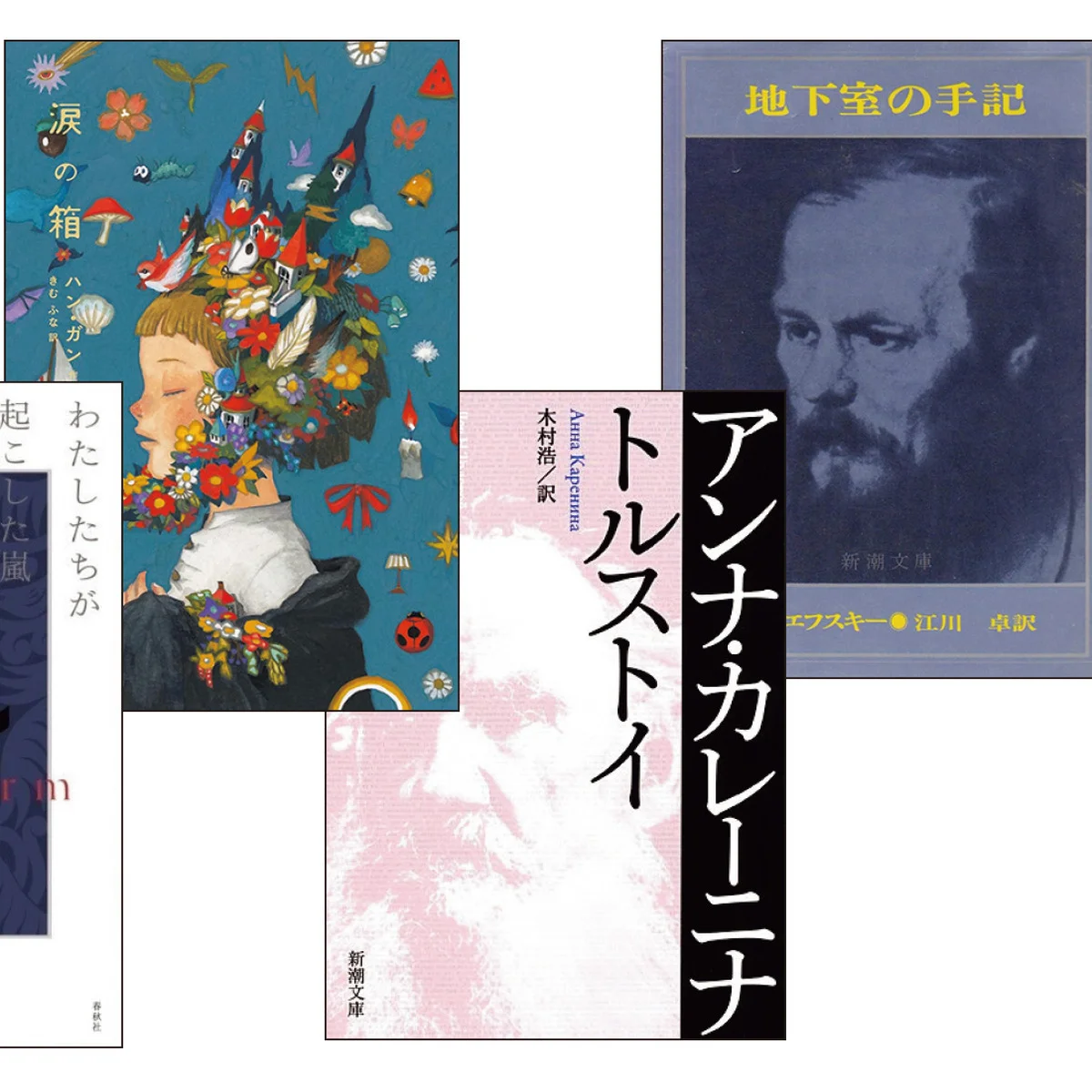日本語訳で読むブローディガンでしか味わえないものある
20年来の友人という翻訳家の岸本佐知子さんと山崎まどかさん。「私は岸本さんを勝手に師匠だと思っている」と山崎さんが言えば、岸本さんが「やめてちょ(笑)」と返す仲のよさ。二人に翻訳のリアルについて伺った。
――さまざまな作品を翻訳してきたお二人ですが、翻訳する際、苦労するのはどんなことですか。
山崎 今年出版されたイヴ・バビッツの短編集『ブラック・スワンズ』(7)は、翻訳に結構苦労しました。
岸本 でも、すごくよかった。あれは山崎さんじゃないと訳せないと思う。
山崎 うれしい。ありがとう。作者は60年代にアメリカのエンタメ業界で、その名を知られたアーティストで。
――今でいうところのイットガールのような存在だったんですよね。
山崎 そうですね。彼女の文体は文学的なところもありつつ、ざっくばらんで、すごく魅力的だけど独特なんです。そしてヘンリー・ジェイムズ(19世紀の英米文学を代表する小説家)のファンということもあって、ひとつのセンテンスがとても長い(笑)。私は原書を読んでいるときの気持ちよさを伝えたかったんですけれど、そのまま日本語にすると破たんしてしまうので、もとの文体を活かしつつも読みやすさを尊重して、仕方なく文章を分けたところもありました。
岸本 わかる。何年翻訳をやっていてもどこでセンテンスを切るかは毎回悩みますね。一章全部がつながっているとか、作者が意図的にやっている場合もあるし。短く切れば翻訳は簡単になるけれど、それだと原文の個性がなくなってしまう。翻訳は妥協の連続です。原文尊重と読みやすさを天秤にかけて、どこに落とし所を見つけるかということを毎度やっているんです。
山崎 それと悩むことといえば、一人称問題がありました。これは翻訳家仲間でもよく話題になりますね。
岸本 そうそう。英語では「I」だけど、日本語だと私、僕、俺、わたし……といろいろあって、「読者に対して主人公がこういう顔で見えてほしい」というのが訳者の中にないと、どの一人称にするか決められないんです。逆にそれを決める訳者は責任重大で。
山崎 イヴ・バビッツは、「私」じゃなくて、「わたし」にしました。平仮名のほうが彼女らしいと思って。
岸本 そういうことですよね。私は昔、ニコルソン・ベイカーの『中二階』を訳したとき、最初は「僕」でやってたけど、途中で「私」に一括変換したことがありました(笑)。主人公が30歳くらいの男性で、細かいことにこだわりすぎる性格とか、いろいろ考えたら「私」のほうがいいだろうと。
山 崎 あれは「私」が正解だと思う。
岸本 だから訳者って、その本のプロデューサー的な役割を兼ねていると思う。一人称をどうするかというのは、その第一段階なんですよね。
――翻訳家で影響を受けた方、すごいなと思う方はいらっしゃいますか。
岸本 藤本和子さんですね。大学生のとき、初めて原文と日本語訳を照らし合わせて読んだのが藤本さん訳のリチャード・ブローディガン『西瓜糖の日々』でした。原文を読んでみると、英語はすごく簡単なんです。これなら自分にもできるかもしれないと思って訳してみたら、スッカスカにしかならない。それまでは翻訳って文章の意味を訳す、横のものを縦にするみたいなイメージだったんですけれど、そうじゃないんだ、もっと体ごと、作品の世界に入り込んで、その世界を生み直すみたいなことなんだなと気づきました。
山崎 『西瓜糖の日々』は日本語でしか読んでいないけど、ショッキングだった。切なすぎるというか、あのきらめきみたいなものは、ひょっとしたら日本語訳で読むブローディガンでしか味わえないものかもしれない。
岸 本 本当にそう。文章は意外となめらかじゃなかったりするんだけど、1行目からその世界が出来上がっている。結局、何が理想の翻訳かといったら、原作を読んだときに受けるイメージや感動の質と量を、日本語でもなるべく同じにして読者に伝わるようにすること――というのが基本だと思うんですね。イメージを伝えられなければ、言語的に合っていても誤訳なんです。
山崎 そこは私も大事にしたい。翻訳家というのは原作者のヴォイスを預かる仕事だから。とはいえ、原作を読んだときに、声が聞こえるものと聞こえないものがあって。
岸本 それは確かにありますね。
――「声」というのは、日本語で何か聞こえてくるということですか?
山崎 いや、具体的な言葉というより、作中の人物の声の調子が聞こえてくる感じかな。ズカズカ入ってくるなとか、控え目だなとか。それが聞こえてくれば、「この作品は私がすくい取れるかも」って思えるんですよね。
岸本 逆に内容は面白いけれど、声が聞こえない場合は自分が訳す作品じゃないなと思ったりしますね。
原書では「I」という一人称が日本語訳では「弊機」に!?
――最近、「翻訳のチカラ」を感じた作品を教えていただけますか。
山崎 1950年代に活躍したアメリカの詩人シルヴィア・プラスの『ベル・ジャー』(5)という小説があるんですね。
岸本 英米では女性のバイブル的な存在の作品ですよね。私は最初の翻訳でも読みました。当時は『自殺志願』というタイトルだった。
山崎 そう、これまで何回か翻訳されているんですよね。内容は作者の自伝的要素が強くて、華やかな世界の中で孤立を感じて、最後は精神的に病んで自死しようとする女性の話です。2024年に小澤身和子さんの新訳が出たんですけれど、これがすごくいいんですよ。「今読まれるべきシルヴィア・プラス」という文体で、今の若い女性たちにも受け入れられる力強さがある。
岸本 『自殺志願』で読んだときは、ヒロインはか弱くて、ひたすら病んでいくイメージだったけれど、小澤さんの訳では全然違う印象で驚きました。
山崎 ただの弱々しい人じゃなくて、すごく闘っているし、もがいている。
岸本 翻訳者はなるべく自分を出さないように消すのが仕事だけど、それでも10人いたら10通りの翻訳作品ができるんですよね。それが面白いところです。
山崎 この作品の中に「I am I am I amと私の心臓がいう」という有名な箇所があるんですけれど、「I am」の訳がそれぞれ違うんですね。『自殺志願』では、「わたしわたしわたし」と訳していて、90年代の訳は、「私は生きている、私は生きている……」で、小澤さんは「わたしは、わたしは、わたしは」だったんです。もともと完結していない文章で解釈はいろいろ考えられるわけで、その余韻が訳にも感じられるなぁと思って。
岸本 翻訳はリズムもとても大事ですよね。よく言われるのが、「文章の息を揃えろ」。呼吸みたいなことですね。多少意味を犠牲にしてもリズムを優先させることもありますね。
――岸本さんのおすすめの作品は何ですか。
岸本 私は日本翻訳大賞の選考委員をやっているんですけれど、2021年に大賞をとったマーサ・ウェルズという作家のSF小説『マーダーボット・ダイアリー』(2)は衝撃でした。ロボットが主人公で、過去に重大な事故を起こしたものの記憶を消されて警備ユニットとして働いているんです。しかもひそかに自らをハッキングしながら人間の管理から独立していて、趣味の連続ドラマを楽しんでいる(笑)。で、さっき一人称の話が出ましたけど、このロボットの一人称が「弊機」なんですよ。
山崎 えっ、原文は「I」?
岸本 そう。ただの「I」を「弊機」と訳しているんですね。それがこのロボットのいじけたキャラとぴったりで、大発明だなと思いました。正直、原作より面白くなっちゃってるけど(笑)。受賞が決まったとき、作品のファンがXで、「弊機、おめでとう!」って盛り上がっていたのが印象的でした。
――お話を聞いていると翻訳本のポテンシャルは無限大ですね。
岸本 翻訳の技術とか考え方ってどんどん進化していて、昔よりずっと質が向上しているんです。最近、韓国文学が人気ですけれど、立役者の斎藤真理子さんをはじめ、翻訳者がみんなとてもうまいんです。「翻訳本はなんか難しいから苦手」という人も翻訳次第で、ぐっと心をつかまれるような作品に出合えると思います。
山 崎 それと外国の小説だと共感できる要素が少ないんじゃないかと思われがちですけれど、小説を読むって、そういうことではないはずなんですね。自分とは遠い気がしていた人の中に自分を見出すことに醍醐味があると思うし、その距離が遠ければ遠いほど感動も大きく、豊かになると思うんです。そういう意味で外国の文学は、まさに距離の遠いものですから、ぜひ多くの人に手に取ってほしいですね。