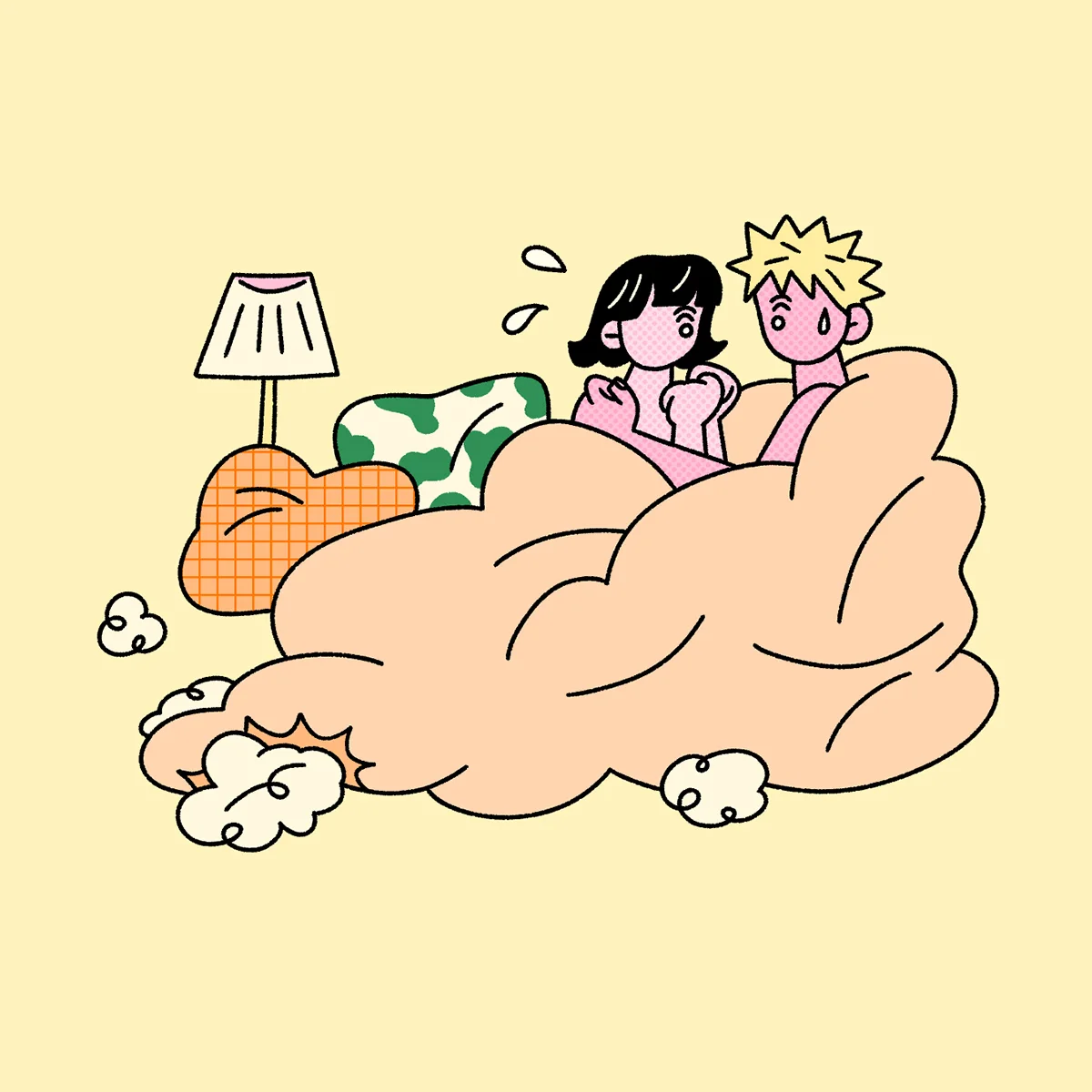2025年10月末、緊急避妊薬の「ノルレボ」が認証され、薬局で買えるようになる。これまでは病院で処方してもらう以外の入手方法がなかったため、アクセス先が広がる大きな一歩だ。
緊急避妊薬は、妊娠の可能があるすべての人にとって、いつ必要になってもおかしくないもの。いざというとき慌てないために、いま基本的な仕組みや使い方を知っておくことには大きな意味がある。知識があれば、自分だけでなく、身近に困った人がいたとき力になれるかもしれない。
産婦人科医・稲葉可奈子先生へのインタビューをとおして、「緊急避妊薬とは何か」「どう使うのが適切なのか」「OTC化※で何が変わり、何が変わらず課題として残ったのか」を整理していく。
※OTC化とは、医師の処方箋が必要だった医薬品を、処方箋なしに薬局やドラッグストアにて購入できる市販薬にすること
2025年10月末、緊急避妊薬の「ノルレボ」が認証され、薬局で買えるようになる。これまでは病院で処方してもらう以外の入手方法がなかったため、アクセス先が広がる大きな一歩だ。
緊急避妊薬は、妊娠の可能があるすべての人にとって、いつ必要になってもおかしくないもの。いざというとき慌てないために、いま基本的な仕組みや使い方を知っておくことには大きな意味がある。知識があれば、自分だけでなく、身近に困った人がいたとき力になれるかもしれない。
産婦人科医・稲葉可奈子先生へのインタビューをとおして、「緊急避妊薬とは何か」「どう使うのが適切なのか」「OTC化※で何が変わり、何が変わらず課題として残ったのか」を整理していく。
※OTC化とは、医師の処方箋が必要だった医薬品を、処方箋なしに薬局やドラッグストアにて購入できる市販薬にすること
婦人科で緊急避妊薬をもらう場合の診察内容や、家族に知られるか否か
——薬局で緊急避妊薬を買えるようになった後も、病院で相談をしたほうがいいケースはありますか?
今後の避妊方法を考えたい方は、病院がいいと思います。その場で経口避妊薬の処方やミレーナの挿入まで対応できます。
生理痛など月経困難症の症状があれば、ピルは保険適用で月500円ほどのものも。自費だと3,000円前後なので、差は大きいですよね。ミレーナは5年間使えて、生理痛や過多月経があれば保険診療で1万円ちょっと。「同じ不安をくり返したくない」と感じるなら、こうした方法を検討してほしいです。
——婦人科での診察は、どんなものでしょう。
基本はお話を聞く問診で、内診はありません。生理周期の確認のほか、避妊に失敗したタイミングは確認しますが、これは72時間という期限があるからで、それ以上の詳細は必要ありません。
ただ、望まない性行為の結果として緊急避妊薬を求めに来られるケースもあるので、そんな空気を感じたら、さりげなく話を振ることはありますね。
——受診や処方の事実を、人に知られることはありますか?
受診した記録は、病院で管理するカルテには残ります。ただ緊急避妊薬は自費診療なので、保険証を通じて「どこの病院で、いくらの診療を受けたか」の通知が、親や家族に行くことはありません。
——緊急避妊薬で妊娠を回避できたけれど、パートナーとのあいだにすっきりしないものが残ったという話をよく聞きます。
「避妊しなくてもアフターピルを飲めばいい」と考える男性は、残念ながらいます。女性の負担を理解しないまま「女性ってたいへんだね」で済ませてしまう。その誤解を正す性教育や啓発は、これからもっと必要でしょう。
私は低用量ピルを処方するとき「彼氏に言わなくてもいいよ」と伝えることがありますが、これは女性が主体的に避妊していると、男性が「じゃあコンドームはいらないよね」となることがあるからです。低用量ピルを内服していればコンドームは不要、というわけではなく、性感染症を防げるのはコンドームだけ。この点は強調しておきたいです。
——OTC化をきっかけに、緊急避妊薬、ひいては避妊について考える人は多いと思います。
望まない妊娠は、個人の問題や本人の責任ではなく、社会全体の課題です。性教育の充実や緊急避妊薬へのアクセス改善は、その課題に向き合うアプローチのひとつです。
避妊に公的補助を出す国があるのは、「女性がかわいそうだから」でなく、望まない妊娠が起きると、女性が教育やキャリアの機会を失い、所得が下がり、生活が不安定になる可能性が高くなるからです。そうした不利益は次の世代にも連鎖し、社会全体の損失になり、それを支えるのは社会なのです。連鎖を断ち切るために、国が補助などで負担を引き受けている。日本でも、望まない妊娠を社会課題として位置づけ、制度で支える方向に進んでほしいです。

京都大学医学部卒業、東京大学大学院博士課程修了。大学病院や市中病院を経て産婦人科専門医となり、2024年に渋谷駅直結のInaba Clinicを開業。より多くの人が気軽に受診できる、受診したくなる、かかりつけにできるレディースクリニックを目指している。SRHR(性と生殖に関する健康と権利)や性教育など、生きていく上で必要な知識や正確な医療情報とリテラシーを、SNS、メディア、企業研修などを通した発信も行う。