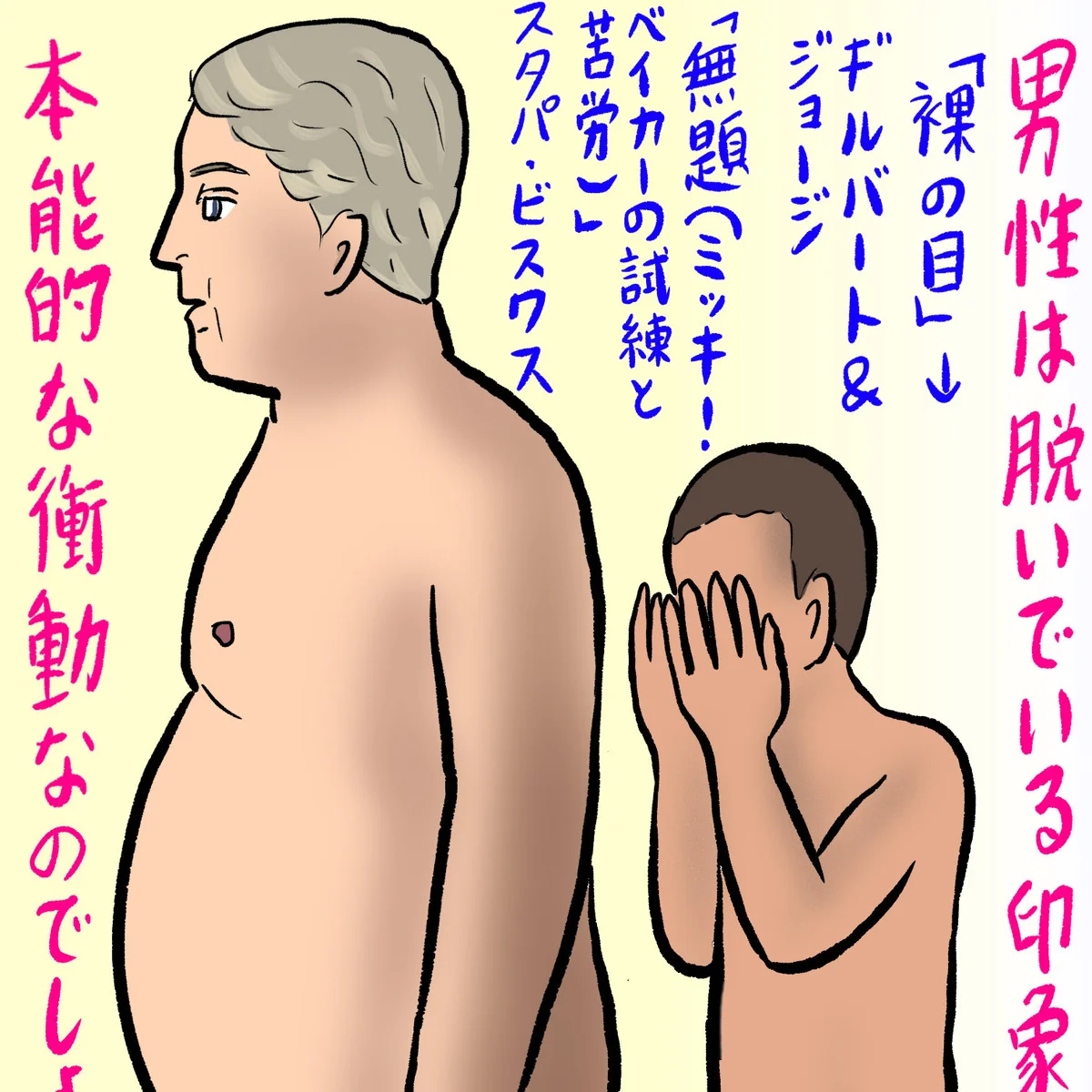松谷みよ子さん Miyoko Matsutani
1926年東京都生まれ。享年89歳。児童文学作家。終戦後、坪田譲治に師事し、’51年、作家デビュー。以降、『ちいさいモモちゃん』で、野間児童文芸賞を受賞するなど、モモちゃんシリーズが大人気に。また全国から民話を集め、『現代民話考』をまとめるなど精力的に活動。戦争をテーマにした児童文学(『ふたりのイーダ』『あの世からの火』など)も多数手がけ、戦争を語り継ぐ必要性を訴え続けた。取材後永眠。
着物などと交換で農家の人に野菜をもらって歩きました
「あの頃は着の身着のまま。髪にも衣服にもシラミがついていました。でも、いちばんつらかったのはひもじかったことです。いつもいつも飢えていました」
そう語るのは児童文学作家の松谷さん。戦争末期の1944年頃になると、戦闘の激化とともに、人々の暮らしには大きな負担がかかるようになっていた。学生や労働者は軍需工業などに動員、鉄などの金属は軍に供出、「御国のため」に誰もが犠牲を強いられた。とくに東京では食糧難が深刻で、当時、まだ19歳だった松谷さんも日々食糧の調達に追われていた。
「当時は配給がありましたが、お米がほんのちょびっと。一日に食べられるのは、おじやにしてふやかしたご飯がほんの少しだけ。大豆やじゃがいもが手に入ればいいほうでした。闇市で調達する人たちもいましたが、わが家は父親が亡くなっていたため、それもままならず、私と姉はいつも買い出しに追われていました。
畑の多い東久留米まで行き、あてもなく歩いては、農家の人に『何か分けてください』と頼みました。『何もないね』とたいてい冷たい返事です。そこでふたりで畑の草をとり始めます。向こうはしらん顔していますが、そのうち『何か持ってきたか?』と聞いてくる。そこで私たちが着物などを出すと、やっと大根や小麦粉を分けてくれました。
でも、それも命がけでした。あるとき、畑の中を歩いていると、突然アメリカ軍の戦闘機に襲われました。顔が見えるくらいの低空飛行で、ダダダダッと上から機銃掃射されました。姉とふたりで亀のようになって、じっとしているだけ。もうこれで終わりかと思いました。
あの頃は毎日生きるのに必死で先のことなど想像もつかなかった。自分たちに、将来なんてものがあるとは思えませんでした」
あの戦争は何だったのかと、終戦のときは腹が立ちました
さらに’44年から’45年にかけて、東京には100回以上の空爆が繰り返され、次第にその攻撃は激しさを増していった。
「各家庭には防空壕が掘られました。わが家も植え込みの陰にスコップでひたすら穴を掘りました。母と姉、姉の息子と私の家族4人がしゃがんで入れるくらいの大きさが必要なので重労働です。そこに雨戸などの板で蓋をして、上に土を盛って目立たなくします。空襲に備えて夜は靴を履いて寝るようになりました。
また当時は『隣組』という組織がありました。♪とんとん とんからりと 隣組~という歌を今でも覚えていますが、ご近所10人くらいがグループを組んで助け合うのです。消火活動でバケツリレーの練習などをしましたが、そんなもの、とても空襲には対抗できません。焼夷弾が落ちると木造家屋はあっという間に燃えます。風上に一目散に逃げるだけでした」
厳しい状況に耐えながらも「当時はいっぱしの軍国乙女だった」と振り返る。
「軍から女子挺身隊(勤労奉仕団体)の募集がきたときも真っ先に応募しました。空爆で狙われるかもしれないけれど、お国のためならいいと本気で思っていました。でも、私だけでなく、あのときはみんなそうでした。上の兄が南方のスマトラ島へ出征したときも、駅でみんなで万歳を三唱して、旗を振って見送りました」
繰り返される大空襲で、父親が所有していた神田の事務所や江古田の家も焼失。
「切ないですけれど、ほかの人も焼け出されていますからね。『これでやっと人並みになれた』という思いでした。感慨などありません。心のスイッチを切って、何も感じない生き方を身につけないと生きてはいけませんでした」
住む家も失い、先に長野県に疎開していた姉のもとへ松谷さんも行くことに。空襲の緊張から逃れたことで、徐々に自分らしさを取り戻していった。
「終戦の玉音放送を聞いたときは、ほっとするのと同時に怒りがこみあげてきました。じゃあ、あのばかげた戦争は何だったのかと。その一方、自分が知っている戦争は被害者としての小さな体験に過ぎないということにも気がつきました。私の知らない戦争がほかにもある。それで戦後、日本の戦争の話を採集する仕事を始めたのですが、そこで知ったのは、この戦争が加害者の戦争でもあったということでした。そのとき、私の反戦の意志はさらに強いものになりました」