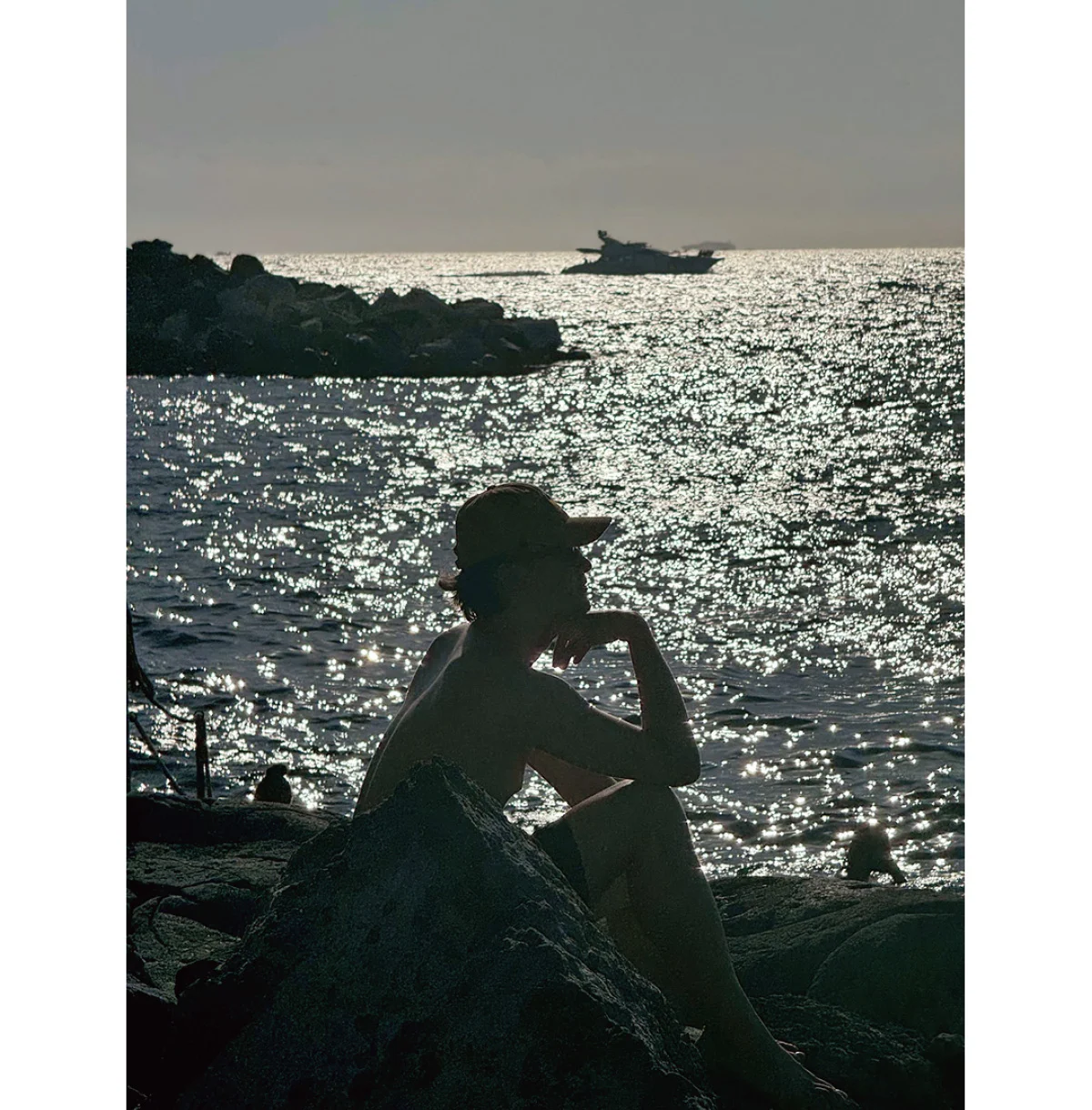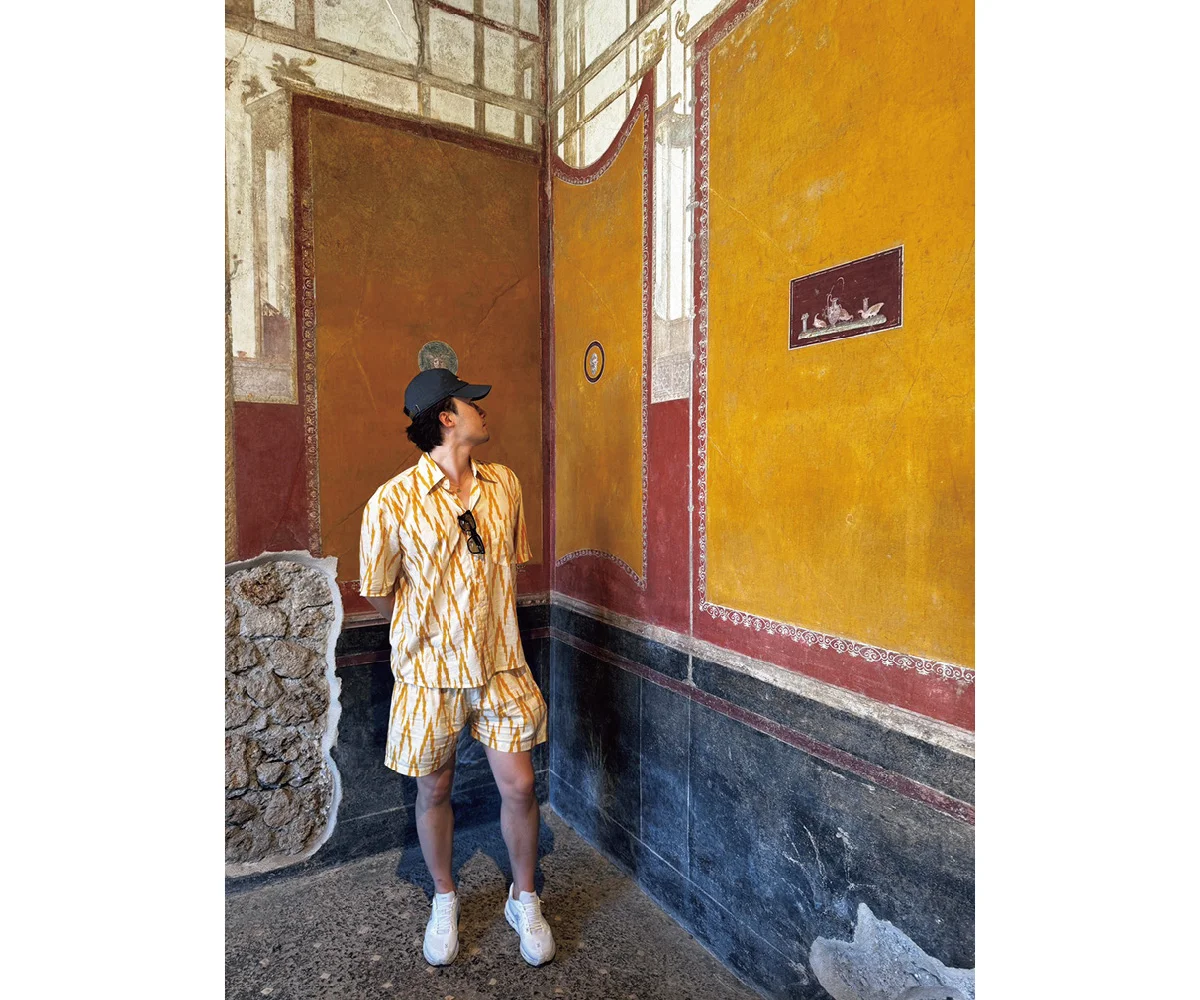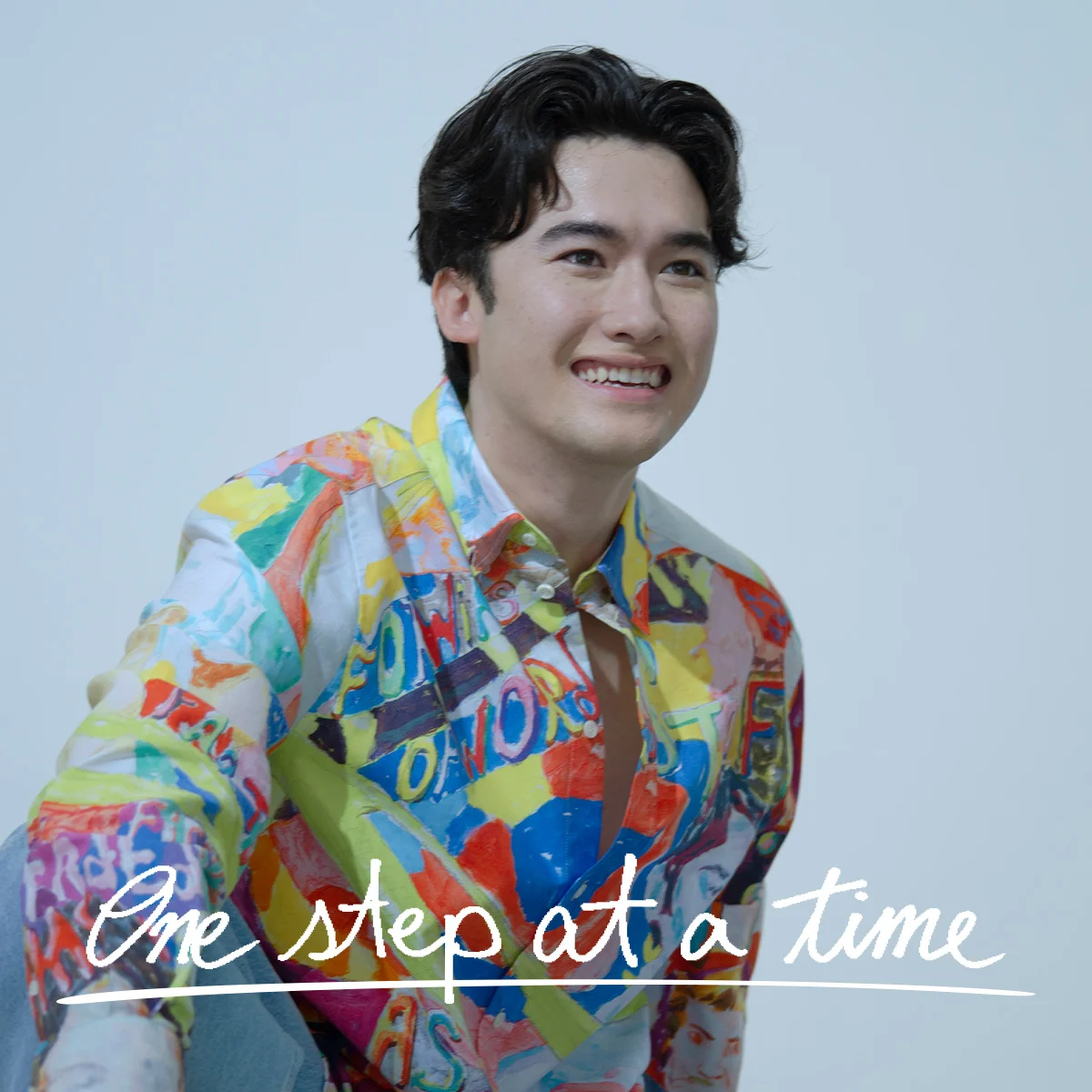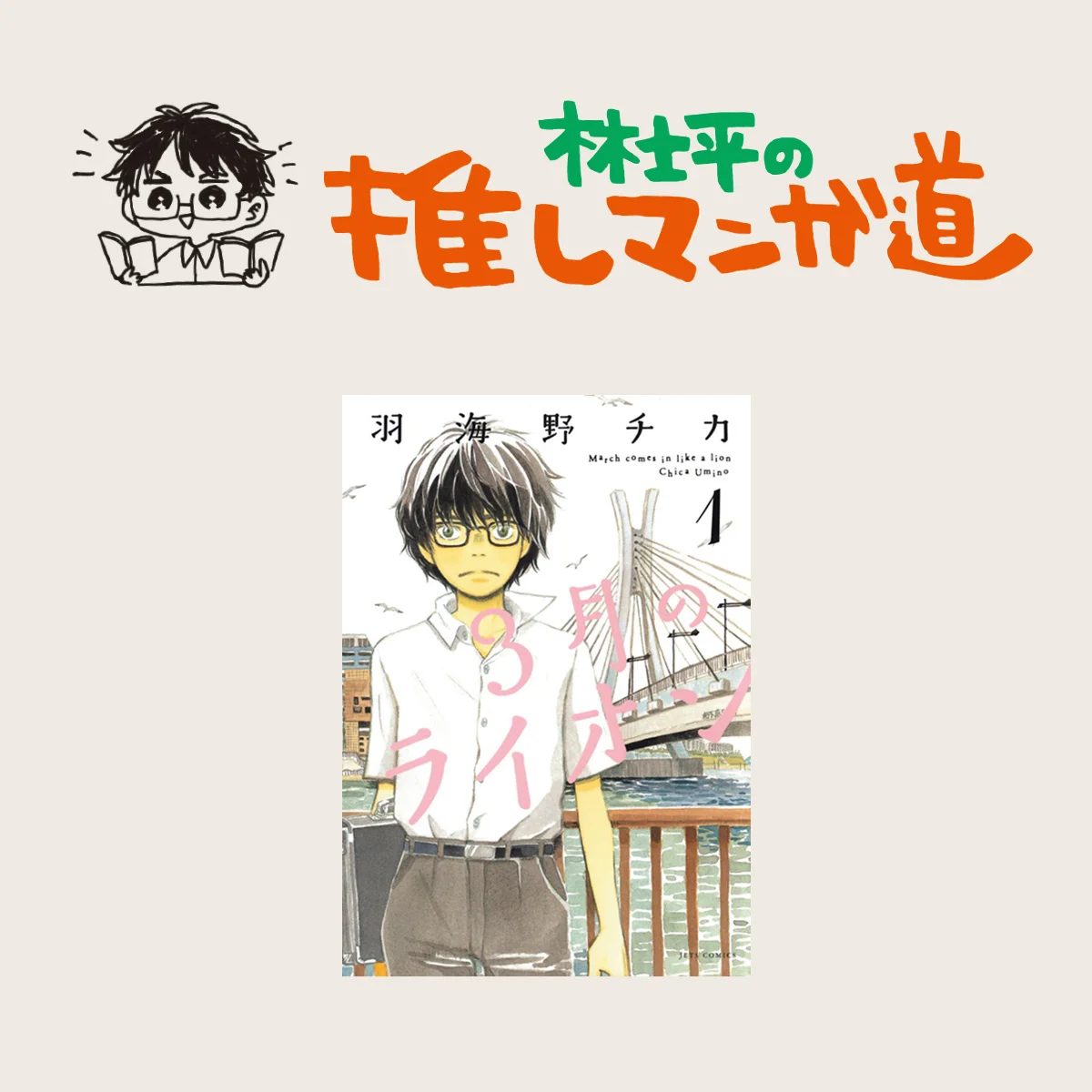M: Marius
S: SPUR
S マリウスさん、今日もよろしくお願いします!
M お願いします! SPURさん、昨日の雨、大丈夫でしたか? 僕は外を歩いていたら急にゲリラ豪雨になって、渋谷川が氾濫しかけてて焦りました。
S 危なかったですね。この酷暑といい、異常気象は全世界的に深刻になっています。さて、今日のテーマですが、経済的不平等についてということで、ちょっとヘビーなテーマです。
M はい。なぜこのテーマを選んだかというと、この前、Amazonの創業者のジェフ・ベゾス氏が再婚して、その結婚式がベネチアであったんですけれど、その費用が5000万ドル以上だったというニュースを見たんですね。
S 見ました! 日本円で約73億円。信じられない金額ですよね。プライベートジェットを100機貸し切りとか、スケールが違いすぎました(笑)。
M 「富を誇示している」という批判もありましたけれど、もっと信じられないのが、その金額は、彼の推定純資産(2440億ドル=約36兆円)のわずか0.02パーセントくらいで、平均的なアメリカ人の労働者にとっての250ドルくらいにしかならないそうなんです(※1)。
S 250ドルというと3万円〜4万円くらい? 彼にとってはむしろ格安な結婚式ってことでしょうか(笑)。驚きです。
M 経済的な格差は以前から問題になっていますけれど、格差はより拡大しているんだなと感じました。フランスの経済学者トマ・ピケティらが運営する「世界不平等研究所」の研究によると、2021年に世界の上位1%の超富裕層の資産が世界全体の個人資産の37.8%を占め、上位10%になると全体の資産の75.6%を占めるという結果になりました。一方、下位50%の資産は全体のたった2%で、超富裕層が富を独占しているのがよくわかります。
S すごい格差……。お金持ちな人とそうでない人がいるのはわかりますが、何十兆円もの資産を持つ超富裕層の存在はうらやましいというより、もやもやします。
※1 ニューズウィーク日本版より
頑張っても普通の生活を維持できない人がいる
Mピケティは、『21世紀の資本』という代表作の中で、こんなことを話しています。経済的な不平等はどの社会にも存在しているもので、どう正当化しているかが社会によって違うと。たとえば前世に悪いことをしたから貧乏になったという社会もあれば、身分制度を格差の言い訳にしている社会もある。頑張っている人はお金持ちになって当たり前だという能力主義の社会もあります。
S アメリカなどは顕著ですよね。
Mはい。まさにアメリカンドリームで、頑張れば夢がかなえられるというのは、決して悪いことではないと思います。ただ一方で、どれだけ頑張っても普通の生活を維持できない人たちが存在するのも事実です。日本でもシングルマザーで、働いても子どもに食べさせていくお金がないとか、派遣労働に従事していて、ダブルワークでも貯金ができないワーキングプアの問題などがあります。
S 以前から問題ではありますが、能力とは関係ない要因の場合もありますよね。
Mかつての日本は中流階級が分厚くて、格差が少ない社会だったのですが、近年は中流階級が小さくなり、格差が拡大しています。僕の周辺でも物価高のせいで、生活が苦しくなったという話をよく聞きます。ピケティいわく、資本収益率が経済成長率を上回ると、格差が拡大するというんですね。
S えっ、急に難しい! もう一度お願いできますか。
Mもちろん! 彼は格差拡大の法則を提言していて、株式や不動産、家賃などの賃料などから得られる利益の伸び率が、労働によって得られる利益の伸び率よりも高いと格差は広がる、としています。つまり、このままでは格差は拡大する一方なんですね。富の不均衡を解消するためには、何らかの手を打たないといけないというのがピケティの見解です。
S これだけの格差を解消するのは大変そうですが、具体的にはどんな方法があるんでしょうか。
Mまず超富裕層と言われる人たちの税率を高くするという方法がひとつ。これで貧困層の教育費や医療費を補うことができるので一石二鳥です。また相続税も高くして、過剰な富が継承されないようにするという手があります。
S 超富裕層が猛反対しそうです……。
M政治家も彼らから献金を受けているので、なかなか法案を通しにくい。一方、貧困層を救うには社会保障の充実が欠かせないと思います。たとえばドイツは子どもの医療費はかからないし、学校も公立校なら大学まで無償なので、家庭の経済事情にかかわらず、大学に進学できる。もちろんお金がある家の人は、塾に行ったり、家庭教師をつけたりして、よりいい大学を目指せるので、完全な平等ではないけれど、それでも不平等の解消に役立っていると思います。
S 大事なことですよね。競争社会は機会の均等が大前提であってほしいです。今は「親ガチャ」なんていう言葉もありますが、日本では、親の年収が子どもの学歴に影響したり、どんな家庭に生まれたかで将来が決まってしまう面があります。格差が固定しないように社会的なサポートは大事ですね。
Mもっと進んで、ベーシックインカムという考えもあります。これは最低限の所得を国が保障するという制度で、たとえば一人につき月額10万円と決めて支給する。ただこれをやると働かなくなる人が増えるという意見が根強かったり、コスト面などの問題もあったりして、正式に導入している国はまだないようです。
「自分には関係ない」ではなく自分のこととして考える
Mスペインの大学にいたときに、授業で友達の発言にすごく共感したことがあります。そもそもその人が地球に生まれたのも、その国に生まれたのも、その家庭に生まれたのも本人の意志ではない。貧しい地域、貧しい家庭に生まれたのは、ただの偶然だし、逆に裕福な家に生まれたのもただのラッキーでしかない。だからこそ、みんながいい人生を送れるように、お互いサポートすることが大事だという話をして、「めっちゃ同意する!」って思ったんです。
S 素晴らしい考えだと思いますが、残念ながら、同じ社会に貧しい人がいても「自分には関係ない」と考えてしまう場合もあるかもしれません。
Mそうですね。日本にはまだそういう地域はないですけれど、富裕層が住むエリアを塀で囲って居住者しか入れないゲーテッドコミュニティを作っている国もあります。社会のゴタゴタとは切り離して、自分たちだけの世界で完結したいという富裕層もいる。でも、「自分には関係ない」というのは違うと僕は思います。たとえば職のない人が増えれば、犯罪が増えたり、薬物に走る人がいたりして治安が悪くなる。また生活が苦しいと、それを誰かのせいにしたくなって、外国人排斥運動が起きたり、極端な思想に走ったりする場合もあります。社会不安が起きれば、富裕層も打撃を受けます。
S 今、諸外国もそういった分断の問題を抱えていますよね。
Mだから貧困は自分の問題だと捉えているし、みんなにもそう捉えてほしいと思います。どんな家庭に生まれた人も、どんな人種でも、どんなジェンダーでも、この世に生まれたからには、一人の人間としていい人生を送る権利があると思います。「お金のない人のために、自分たちが損するなんて、まっぴらごめんだ」と思う人もいるかもしれない。でも、働けないのは病気や怪我のせいかもしれないし、誰かの介護のためかもしれない。家庭が貧しくて、仕事に活かせるスキルを身につける機会がなかったからかもしれない。貧困に陥るのは社会が作りだした仕組みだとしたら、それは社会がカバーしないといけないんじゃないかと僕は思うんです。だって、そういう状況に誰でもなり得る可能性があるわけだから。
S その通りですね。手を差し伸べ合える社会のために、自分自身の抱える問題として意識し続けていたいです。