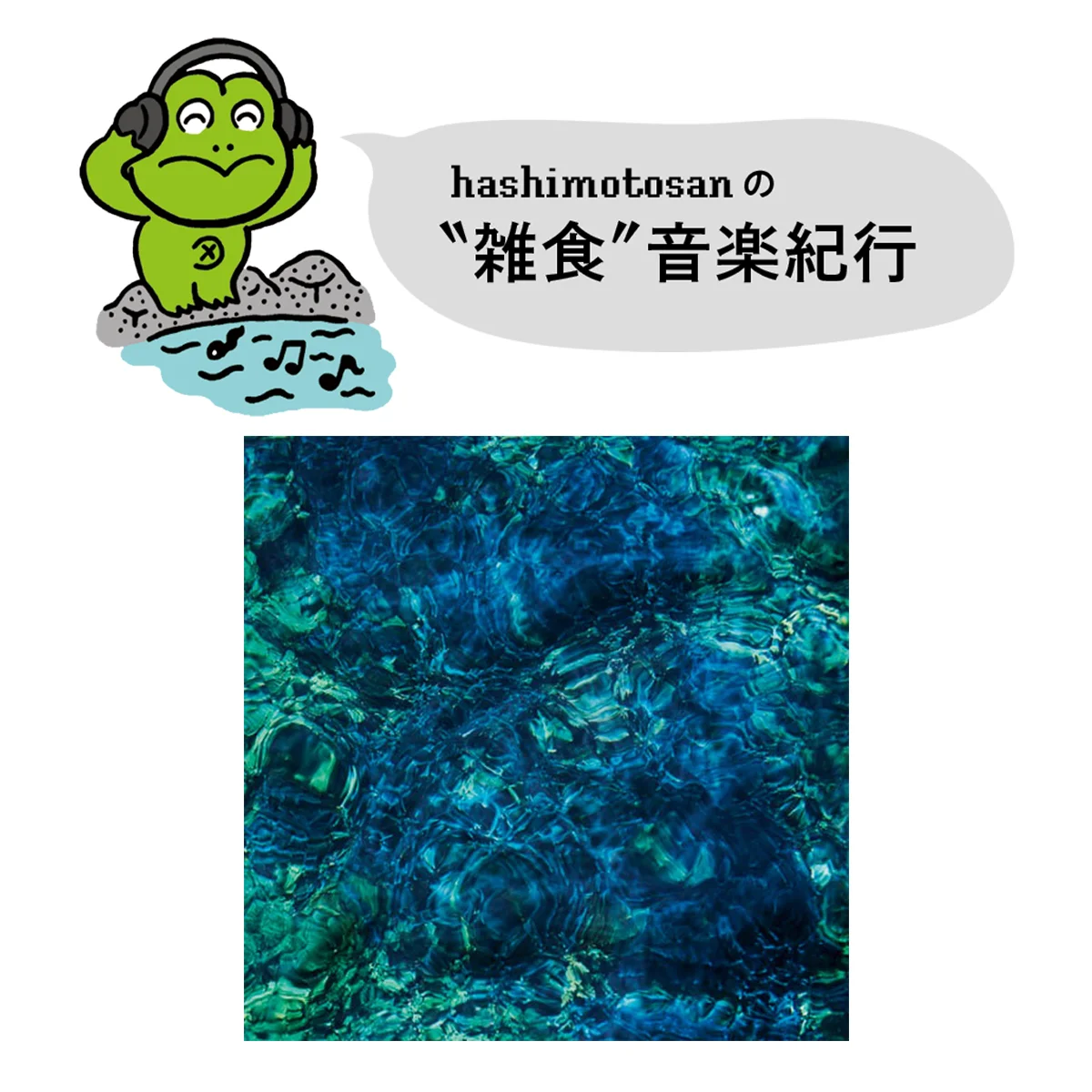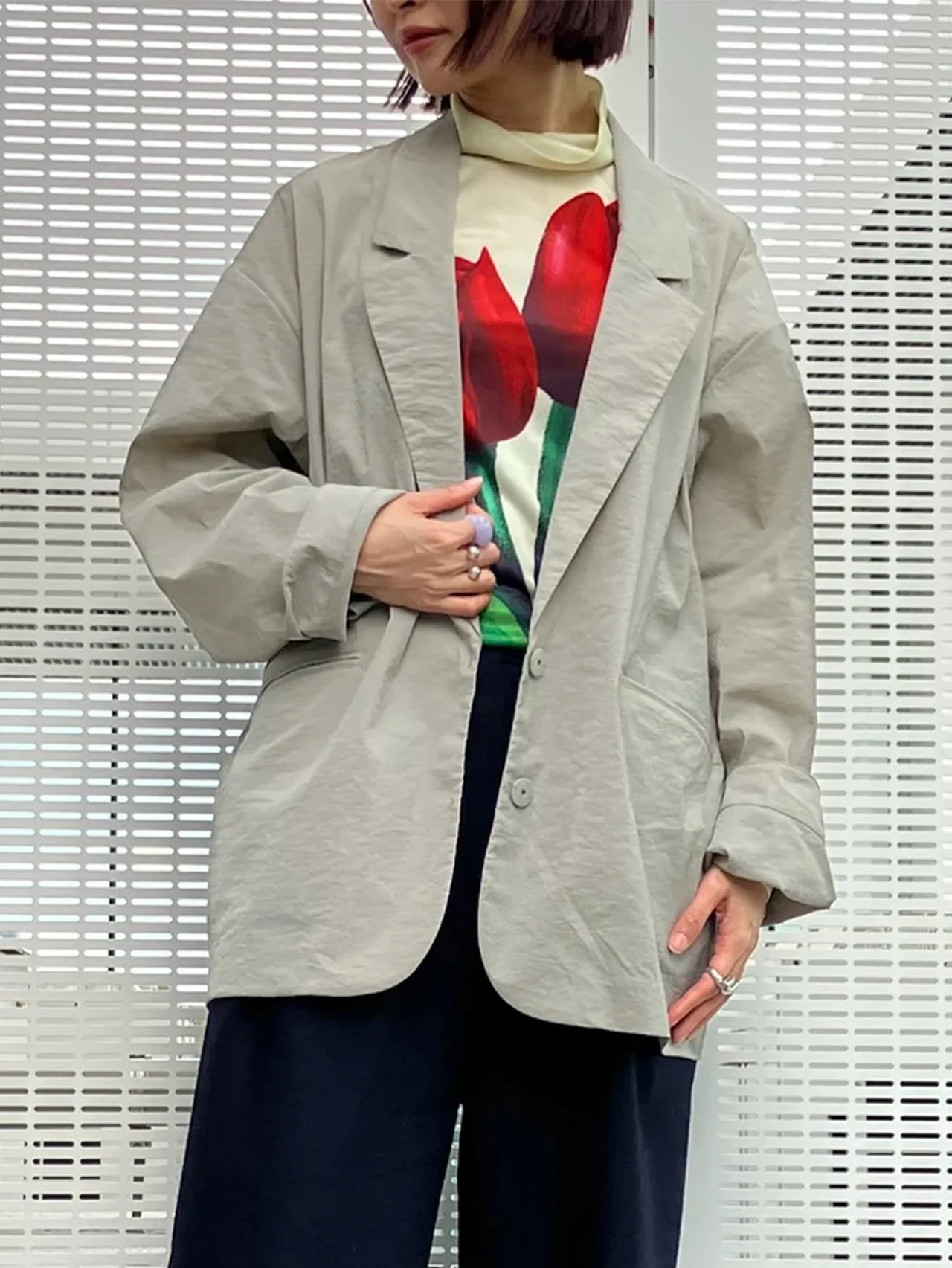"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。

ブレイディみかこライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)を6月出版予定。
「そろそろエンパシーの話をするのも飽きてきた頃でしょう」
昨年、オンライン対談をしたときにそうわたしに言ったのは、何を隠そう、武田砂鉄さんだった。それぐらいあちこちでエンパシーという概念についてしゃべりまくってきた。最近では中高年男性の読者が多い媒体からも「エンパシーについて聞かせてください」という取材がある。
こうした取材でよく出るのが、「他者の考えや気持ちを想像する力というのは、どうすれば身につけられるのでしょうか」という質問だ。「いきなり想像しろと言っても予備知識がなければ無理なので、やはり日頃から自分とは違う環境で働いたり暮らしたりしている人たちと話す機会を持つようにするとか、たくさんの本を読むとか映画を観るとか、知識のインプットが必要ですよね。さらに、そのアップデートも欠かせません」と答えるようにしているが、他者の靴を履く、というのはあくまでメタファーであり、都合よくそこに転がっている靴をフィジカルに履いてみることではない。つまり、頭の中で誰かの靴を履いてみるわけだが、それがどんな靴であるか、色や形がまったく想像がつかない場合には思い描くことすらできない。勝手に自分でデザインした靴をいくら頭の中で履いてみたって、それは他者の靴ではなく、自分のお手製の靴を履いていることにしかならないので、エンパシーと知識のインプットは切っても切れない関係にある。
そういう意味で、いまいろんな人に「見たほうがいいよ」とおすすめしているドラマがある。第1回にはウクライナから多数の難民が英国に押し寄せるシーンが出てきます、と言ったら最近作られたものだと思われそうだが、実は2019年に英国BBCでそういうドラマが放送されていた。ロシアのウクライナ侵攻を予言していたと話題になっている「2034 今そこにある未来」だ。
それ以外にも、まるでコロナ禍を予測していたかのような感染症や外出禁止令が出てきたり、トランプ前大統領の女性版と言えるような英国の女性首相が登場したり、異常気象や金融破綻の再来、米中関係の悪化により核ミサイルが発射されたり、少し前に話題になった米映画『ドント・ルック・アップ』(’21)よりも遥かに現実味のある近未来ディストピアが描かれている。
とはいえ、2019年に英国でこれを見ていたわたしたちは、「ブラック・ユーモアがきいてるねー」とのんきにお茶の間で笑っていた。『ドント・ルック・アップ』に出てくる彗星が地球に衝突する可能性に比べれば、起こり得る未来が描かれているとはいえ、「まさかこんなことがあるわけない」と思っていたからだ。しかし、パンデミックや核兵器使用の脅しや第3次世界大戦勃発の危機など、3年前には「うっそー」としか思えなかったことが現実になっているいま、このドラマを忘却の彼方に葬ることはできない。そんなわけでわたしはこの全6回のドラマを再び見てしまった。世界はこの作品を追っているようにしか思えないからだ。
このドラマのすばらしいところは、『ドント・ルック・アップ』のように学者や政治家やメディア人などの社会に影響を与える立場の人々を中心に据えるのではなく、彼らに影響を受ける側のふつうの家族を主人公にしているところだ。しかも、今回見直してしみじみ思ったのは、この作品、究極のシスターフッド・ストーリーなのである。
実際、このドラマの中では、おっさんが実に役に立たない。時代の激変の中にあって、金融破綻で資産を失って茫然としたり、不安や不満を埋めるために不倫して家庭を失ったりして、人を妬んだり恨んだりするようになってふらふらとダークサイドに落ちていく。反対に、たくましく立ち上がって巨悪と闘うのは女性たちなのである。おばあちゃんとその孫たち、孫の妻やひ孫たちは、必ずしも家庭生活の中で仲がいいわけではなかった。みんな世代も人種も職業も趣味嗜好も違うし、投票する政党も違う。が、ここぞというところで「なんだかんだ言いながら、あなたのつらさはわかっていた」みたいなエンパシーを互いに発揮し合い、手をつなぐ。そして最後には、一般家庭の女性たちがなんでこんなすごいことをしているのかと驚くような行動で世界を変えようとするのだ。
女性たちとともに闘うのが同性愛者の難民の男性だったり、ひ孫の一人がトランスジェンダーだったり、また、もう一人のひ孫はもはやジェンダーどころか人間であるという壁すら飛び越えたいトランスヒューマンだったりするのも面白い。要するに、これまでのシステムがガラガラと崩壊していくときに、失うもの(資産とか社会的地位とかプライドとか)を持っていたおっさんは脆く壊れていくしかないのに、社会の中心にいることを許されなかった人々は、大変動の時期にこそ底力を発揮するというか、協働して全力で抵抗し、世界の終わりを防ごうとするのだ。なんというかこう、社会の中心がずぶずぶと沈没していくときに、周縁にいた人々がしっかりと足を踏ん張り、手をつないでどんどん真ん中に出ていく様子をイメージしてみてほしい。
ここ3年ぐらいの世界の激変具合というか、どんなに政治や社会に関心のない人でも「なんとなく、これまでどおりではいかなくなりそう」程度のことは感じているだろう動乱期にあって、このイメージが示唆するものは深い。これからは、いろんなレベルでの反転が始まるのではないか。最後まで見るとつくづくそう思わされる。
ちなみに、英国には社会の周縁にいる人々が手をつないで闘う映画の系譜があり、たとえば、フォード自動車の工場で60年代に起きた女性工員たちのストライキを描いた『ファクトリー・ウーマン』(’10)や、80年代の炭鉱労働者のストライキに、同性愛者コミュニティが協力した実話を描いた『パレードへようこそ』(’14)などがある。ディストピア描写があまりに強烈なので一見すると気づかないが、「2034 今そこにある未来」もこの系譜を引いていると言っていいと思う。戦争や難民の報道が毎日流れているときにつらくて見たくないという声もあるが、むしろいまこそ見るべき作品だ。来たるべき反転の予兆に勇気をもらえる。
※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。
SOURCE:SPUR 2022年7月号「ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY」
illustration: Yuko Saeki