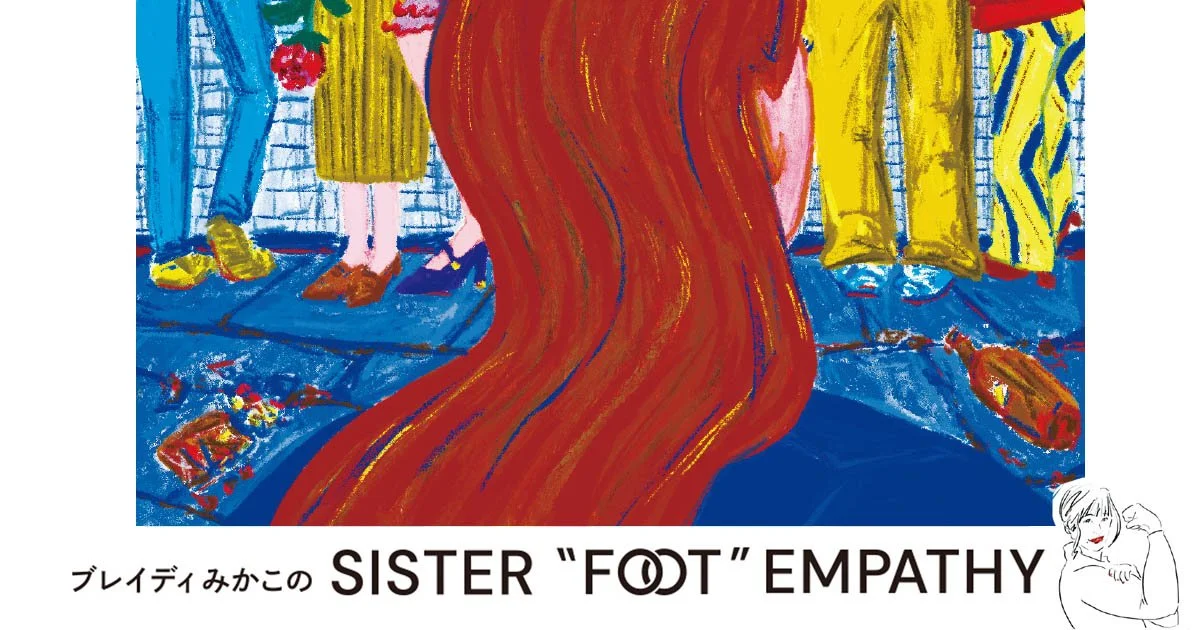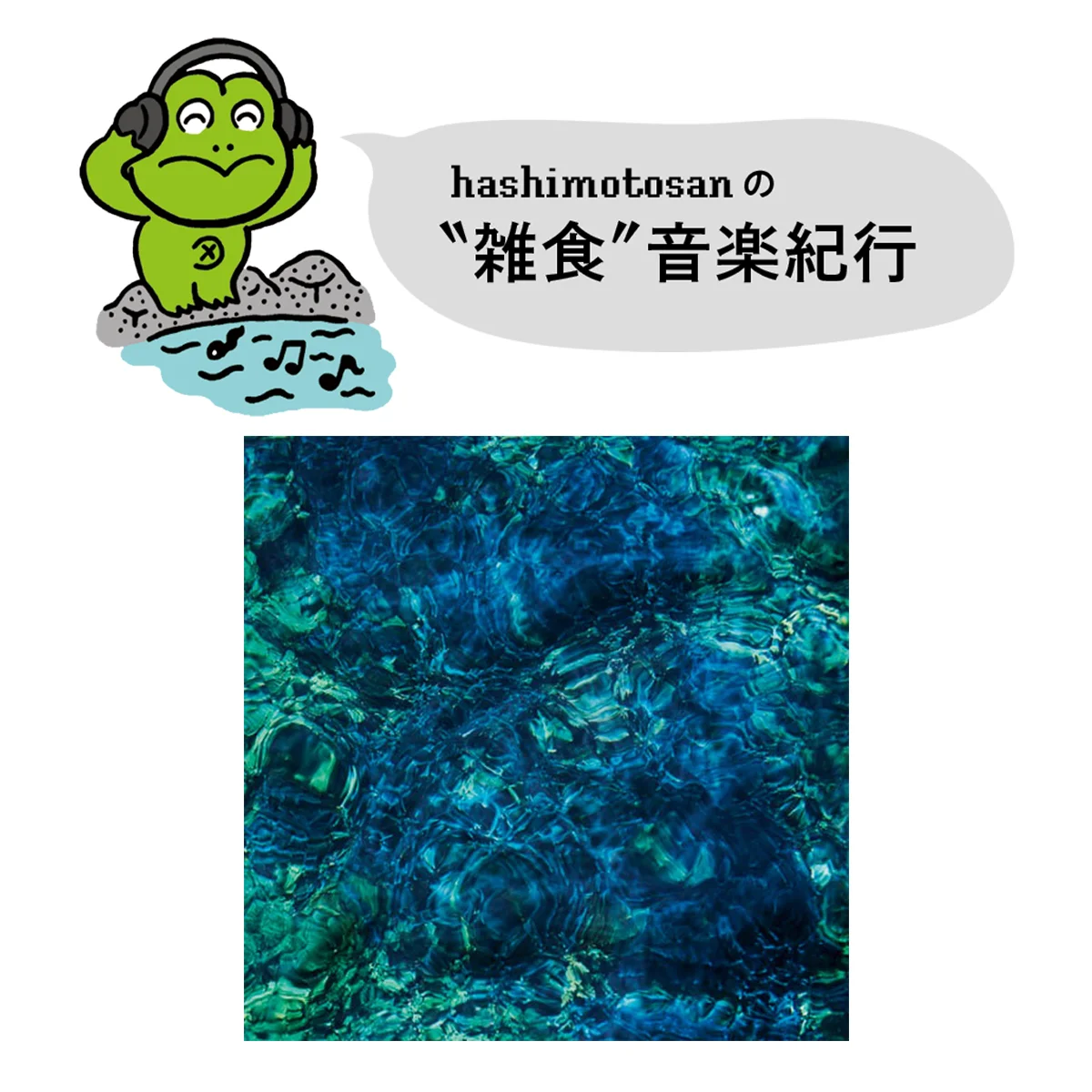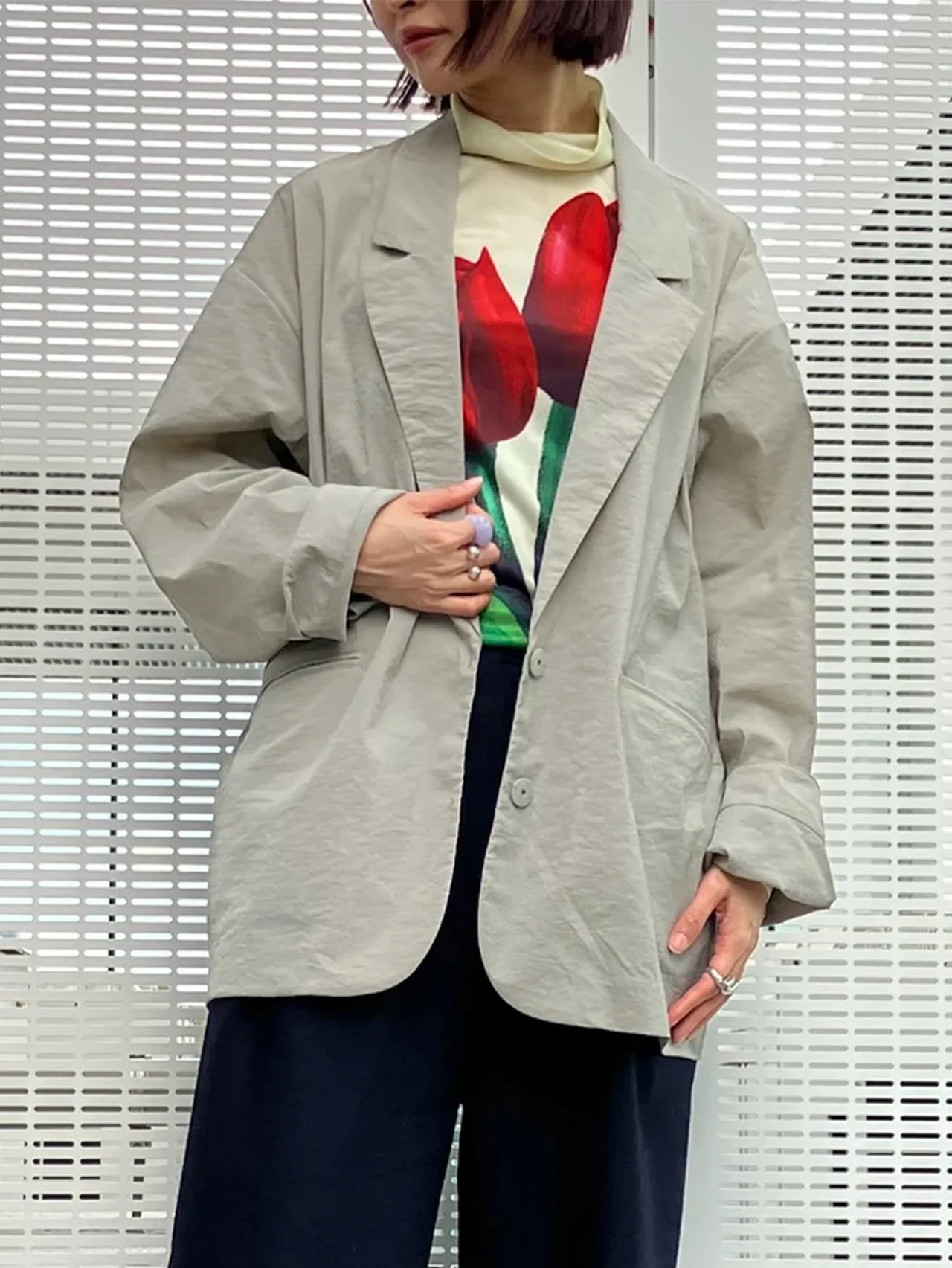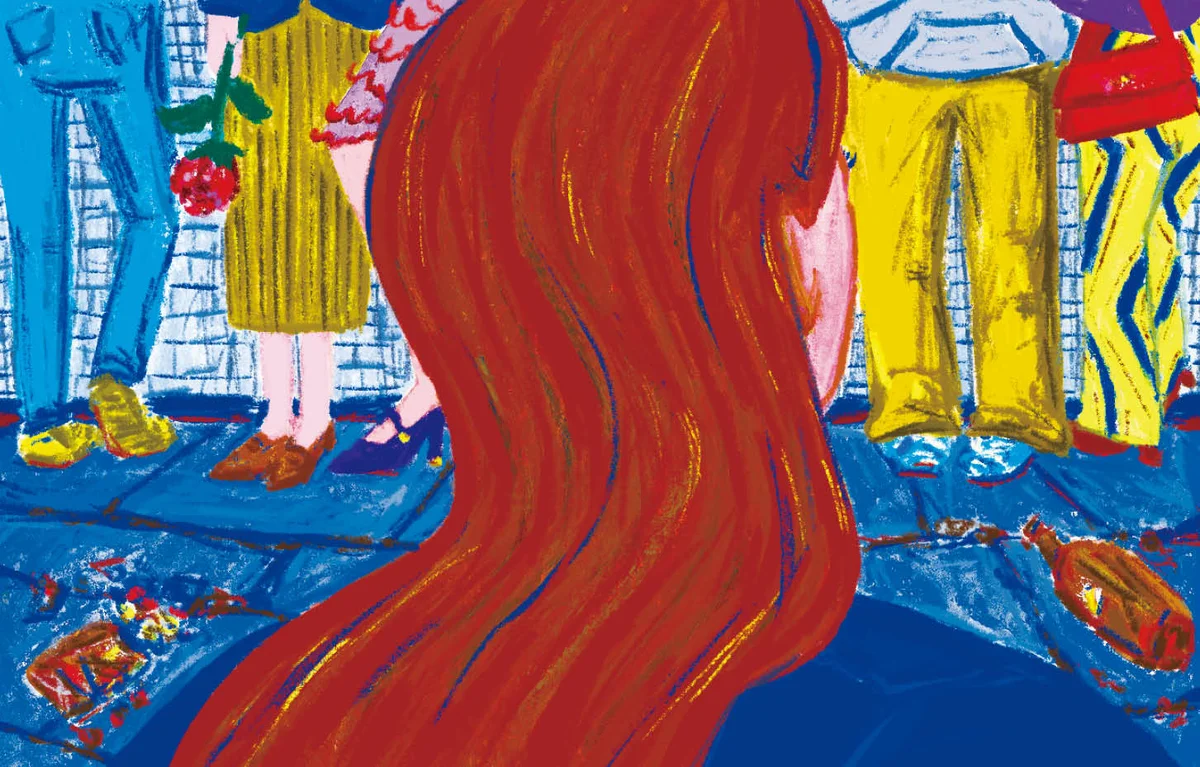
"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
日本でも『切り裂きジャックに殺されたのは誰か』(ハリー・ルーベンホールド著)が発売されたそうだ。2019年に英国で出版されて大きな話題を呼んだ本である。「切り裂きジャック」とは、19世紀末のヴィクトリア朝時代のロンドンで、2カ月の間に5人の女性を殺害し、当時の人々を震撼させた連続殺人犯だ。いまでも未解決の事件であること、そして殺害方法があまりに残忍だったことから、世界中で有名になった(ロンドンには「切り裂きジャック博物館」まである)。
この事件は、多くの関連書籍が出版されたり、映画やドラマの題材にもなってきたが、『切り裂きジャックに殺されたのは誰か』という本はこれまでのどの作品とも切り口が違う。
この本の英語のタイトルは『The Five』だが、女性著者は、犯人ではなく5人の被害女性たちに焦点を当てた。今日でも犯人は誰だったのか検証を続けるマニアたちがいる一方で、被害者たちは「売春婦たち」とひと括りにされてきた。だが、それは間違いだったと著者は主張する。彼女たちは、夫や家族を失ったり、病に苦しんで住む家を失ったりしてホームレスになった社会的弱者だったのだと。
女性は男性よりも劣るので家庭に入って生きるべきだと信じられていた時代に、何らかの理由で庇護者を失って困窮することになった女性たちは、社会から排除された。同情すべき存在というより、「好ましい女性」の規範から外れる非倫理的で不道徳な存在と見なされたからである。それだから、「切り裂きジャック」がどれほど有名になっても、被害者の5人の女性については深く調査されることもなく、「売春婦」という表現で顔のない存在にされてしまった。
だが、『切り裂きジャックに殺されたのは誰か』の著者は、チャップブック(主に17世紀から19世紀にかけてイギリスで発行されたポケットサイズの本)の販売人だったり、裕福な邸宅の使用人だったり、妻だったり、母だったりした被害者たちを一人ひとり違う人間として描く。彼女たちは、これまでの説のように路上で客引きをしていたせいで犯人に襲われたのではなく、酔っていて、ホームレスで、おそらくは眠っていたから被害に遭ったのではないか。つまり、彼女たちは貧しく寄る辺ない女性たちだったのである。
ヴィクトリア朝時代のロンドン東部の貧困のすさまじさが浮かび上がってくるが、貧困化が進む時代には女性がとりわけ過酷な状況に置かれるという事実は現代も同じだろう。女性の問題と貧困の問題、さらに言えば女性蔑視と貧困者差別は分かちがたく絡み合っているのだ。
3年ほど前の話だが、英国のある女性誌が「英国における女性の貧困の隠された真実」という特集を組んだことがあった。記事には「英国では520万人の女性が貧困です。でも、あなたはそれに気づくでしょうか?」という見出しが出ていた。
その女性誌のサイトによれば、男性の貧困当事者は約470万人で女性より少ない。だが、路上で寝ているホームレスの人々や、「小銭はないですか?」と話しかけてくる人たちは圧倒的に男性が多い。貧困当事者の女性(特に若い世代)はどこにいるのだろう。その特集では、貧困を経験した20代の女性にインタビューを行なっている。ある女性は、若い女性が自分の貧困を「カムアウト」することの難しさを語っていた。私が若い頃には、「カムアウト」という言葉は、同性愛者の人々が自分の性的指向を周囲に明かすときに使われたものだったが、いまや若い女性が自分が貧困であることを周りの人たちに明かすときにも使われているのかと驚いた。
ロンドンの支援団体によれば、女性は貧困の当事者であることを隠すために、民家の庭の小屋で眠ったり、女性であることを隠すために体の線が出ないバギーな服を着たり、髪を短くしたりするという。そこまで切羽詰まった状況でなくても、チャリティショップでブランドの服を買い、自分が貧しいことをひた隠しにしていたという女性の談話も紹介されていた。
女性が貧困を隠そうとするのは、もちろん暴力から身を守るためでもある。が、なんとなくそこには「切り裂きジャック」の時代から変わらない、貧しく不運な女性への偏見があるような気がするのだ。女性は身ぎれいで美しく、幸福そうであってほしいという「好ましい女性」の規範は現在でも存在しているのではないか。そして社会は、というより人々は、その規範からこぼれる者たちに冷たい。「できれば見たくないもの」として視界から排除しようとする。だからこそ若い女性たちは貧困を恥じ、誰にも言えなくなってしまうのではないだろうか。
この特集記事を掲載した女性誌の調査では、もし突然に仕事を失って職探しをしなければならなくなったら生計を立てるのに十分な貯金がないと答えた読者が59%いたそうだ。こういう数字を見ると、女性の貧困はけっしてほんの少数の限られた層の問題ではない。一歩間違ったら私も……、という危機感を抱いている人は多いということである。それなのに貧困を「カムアウト」できない世の中というのは、一部の幸運に恵まれた成功者たち以外は、等しくみんな生きづらさを感じている社会ではないだろうか。
実は自分のそばにいるかもしれない貧困の当事者に「カムアウト」してもらえない理由は、私たちのふだんの言動に貧困問題への冷淡さや偏見が垣間見えるせいかもしれない。エンパシーという他者への想像力が足りないがゆえに、隣人の境遇やその変化に鈍感になっている場合もあるだろう。病気をしたり、会社が潰れたりしたら誰だって当事者になる可能性があるのに、本当のことを言い合えず、一番助けが必要な局面で支え合うことができないシスターフッドなんて空疎だし、無意味だ。エンパシーとは見たいものだけを見ることではない。シビアで過酷な現実にも目を向け、知ることによって目を開かされることだ。そうやって視野を広げていくことがさまざまなことを「カムアウト」しやすい社会をつくり、必要なものを求める動きにつながる。勤労世代の一人暮らしの女性の3人に1人が貧困の状況にあるといわれている日本でも、この問題は切実であるはずだ。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。