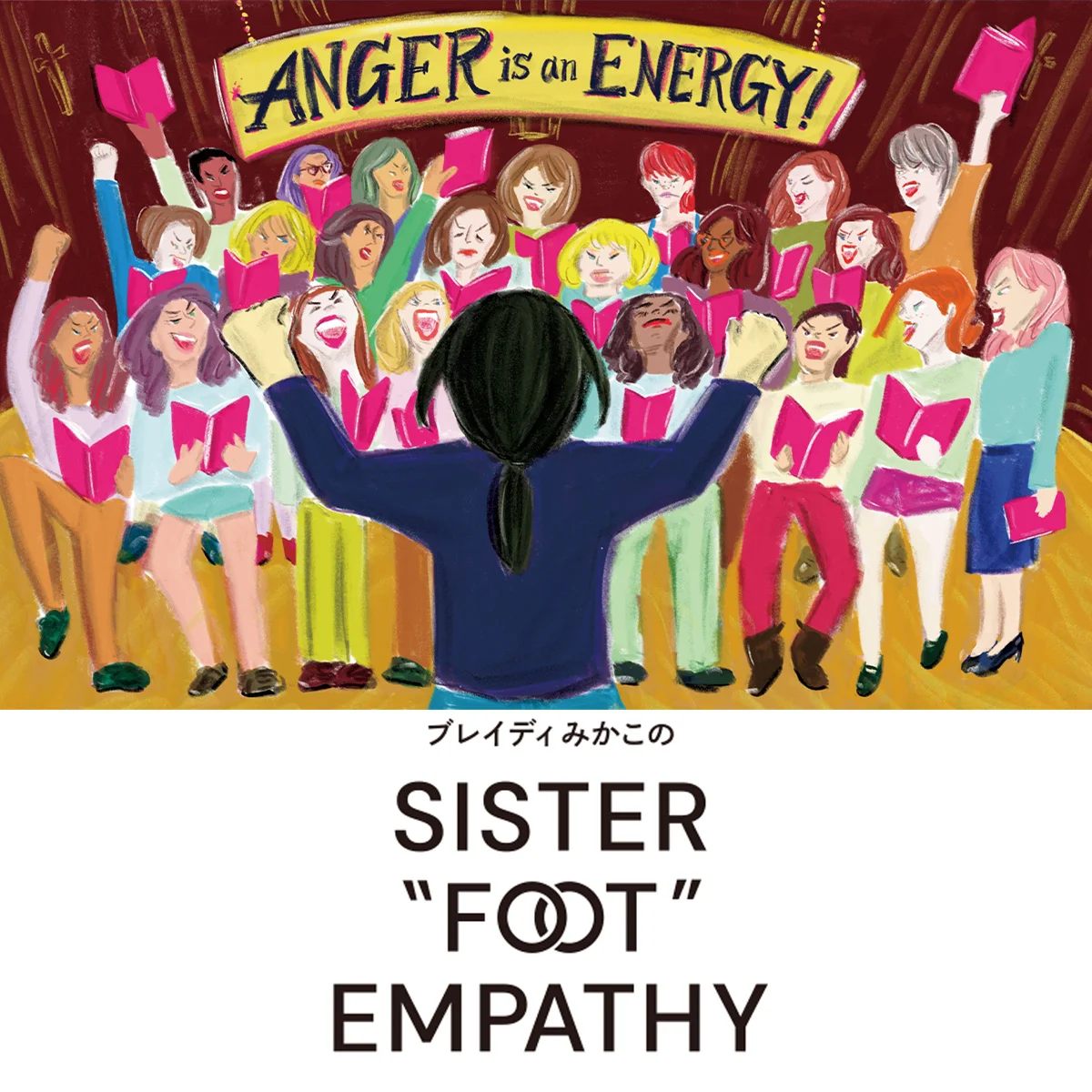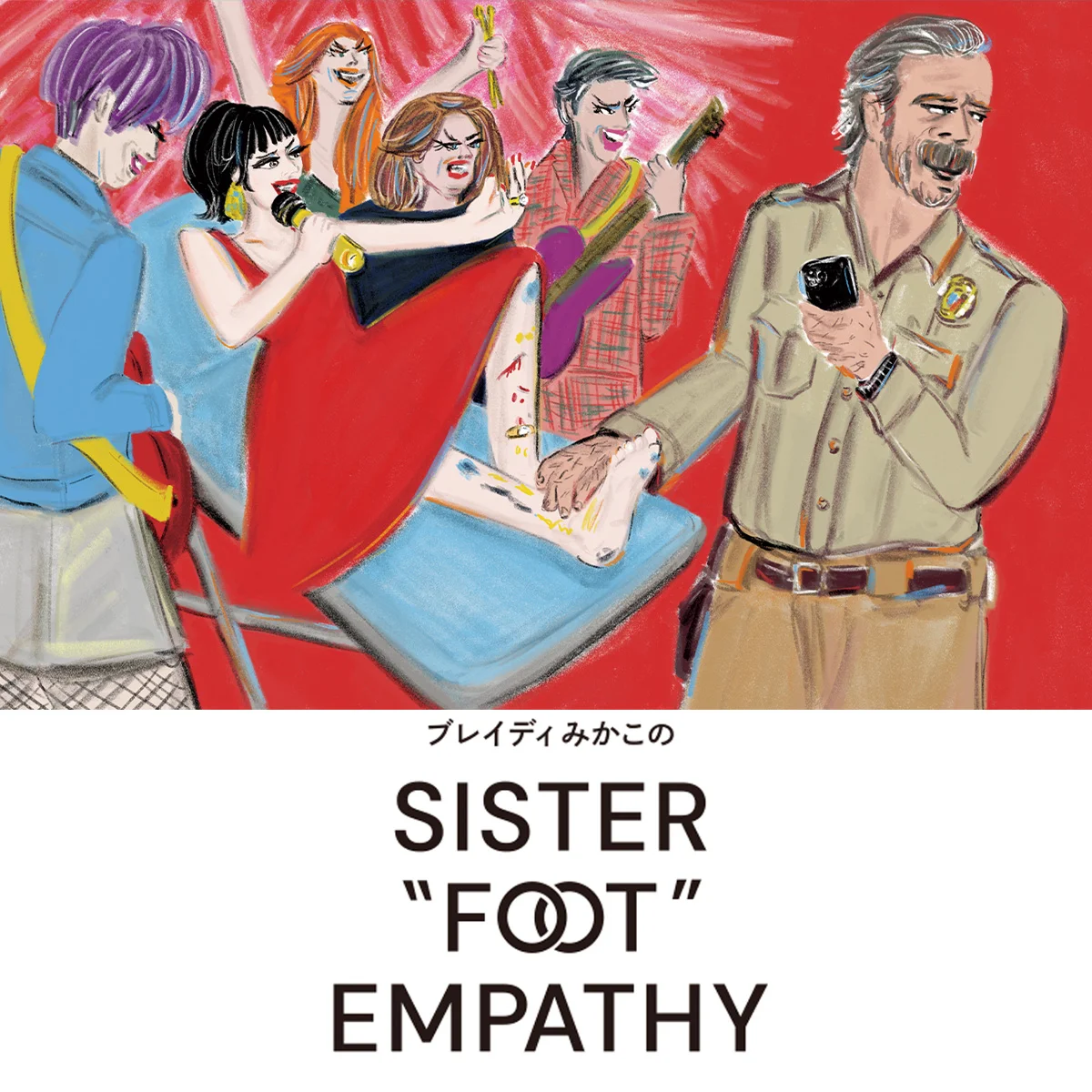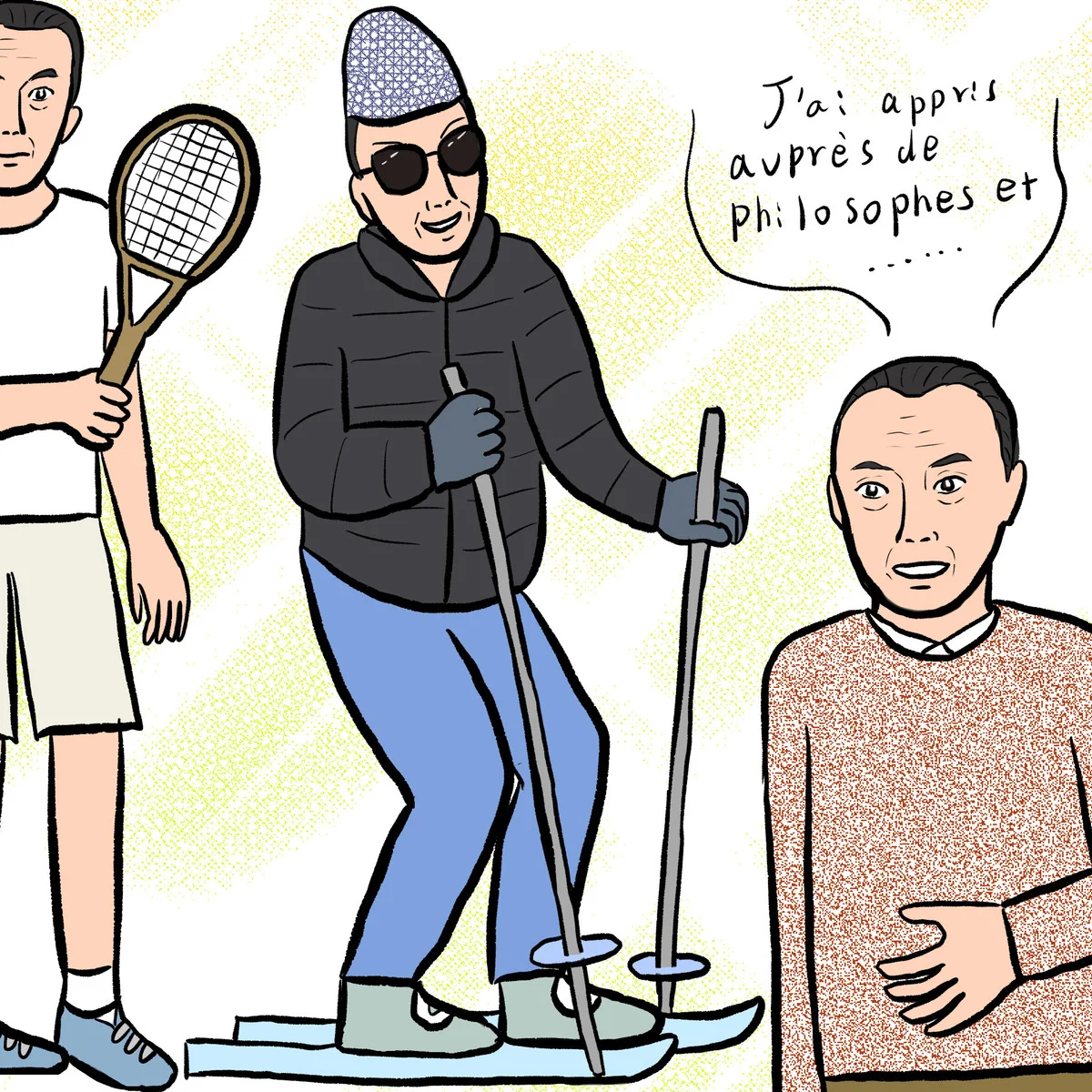ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY
"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談
※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

最近、人と会うとAIの話題になる。今年の英国は本当にそういう印象がある。うちの場合、大学生の息子がいるからかもしれないが、ティーンから大学生ぐらいの年代の若者や、その保護者たち、そして教育関連の仕事をしている友人・知人まで、みな真剣にAIの影響を心配している。
というのも、大学の新卒レベルの仕事はAIに置き換えられると言われていた未来が、もはや未来のことではなく、現実になってきたからだ。それも、最初に置き換えられていくのは、テック関連、金融、コンサルティング、法律などの、いわゆる高学歴、高収入の職種の新卒レベルの仕事だ。つまり、これまで「頑張って勉強して、いい学校、いい大学に行って、こういう仕事についたらリッチになれるよ」と言われていたエリート・キャリアの道がもはや通用しなくなってきた。たとえば、法律事務所なら、これまでは若い新人が任されていたような定型的な契約書作成なんかは、定型的であるがゆえにAIがパッと作成できる。人間なら何日もかかるようなリサーチだって、AIならあっという間に答えを出してくる。AIなら24時間働かせられるし(残業代も、有給休暇もいらない)、ハラスメントで訴えられる心配もない。雇用主にとって、こんなに使い勝手のいいスタッフはいないし、上司たちにとっても、黙って夜間も週末も手伝ってくれる優秀なアシスタントとして、AIは最高の部下なのだ。
さらに言えば、AIはすでに人事部の仕事も代行している。履歴書を読んで審査しているのはAIだったり、最初の面接でさえオンラインでAIがやったりしているし、応募している学生でさえ、AIを使って履歴書や応募書類を作成している。うちの息子なんかも、バイトに応募する書類や、それを添付するメールの内容までAIに書いてもらっている。「みんな普通にそうしているよ」と言うのである。AIが書いた履歴書をAIが読み、AIが不採用の通知を書く。それで傷つくところだけがまだ人間の担当かと思うと、なんとも皮肉な時代になったものだ。
さて、こうなってくると、本連載的には取り上げねばならないことがある。それは、AIの女性差別問題だ。テック業界には男性が多く、学習させられているデータにもジェンダーの偏りがあるため、AIは就職の現場で女性を不利にしがちだということが、数年前から問題視されてきた。こうした問題がある上に、AIが新卒レベルの仕事まで奪い始めると、それでなくとも数が減っていく椅子の争奪戦が繰り広げられる中で、若い女性たちはいよいよ不利な立場に追い込まれるのではないか。
文句も言わず、報酬も求めず、いつでも上司のサポートをしてくれるAIアシスタントの「従順」で「言いなりになる」態度が、女性の新入社員を選ぶときの基準に影響を与えたりすることになれば、テクノロジーは女性の権利を大幅に後退させる可能性もあるだろう。
『The New Age of Sexism: How the AI Revolution is Reinventing Misogyny(セクシズムの新たな時代:AI革命がいかにミソジニーを再創造しているか)』の著者、ローラ・ベイツは、『ガーディアン』紙に寄稿したコラムで、「男性たちを輝かしい未来へ押し上げると約束しているテクノロジーによって、女性たちは暗黒の時代に引き戻されるリスクがある」と書いた。彼女は、大規模言語モデル(LLM)のLlamaを使ったChub AI(AI駆動のチャットボットを提供するプラットフォーム。ユーザーは、テキスト、画像、動画、音声を通じて知的でカスタマイズ可能なキャラクターと対話できる)がはらむ問題に警鐘を鳴らす。そこにはすでに月額5ドルでアクセスできる、15歳未満の設定の少女キャラが働く「売春宿」が存在するそうで、サイト上には「フェミニズムのない世界」と表記されているという。また、猛スピードで開発されている「セックスロボット」や、中には疑似レイプを体験できる環境を考案しているメーカーもあるという事実を指摘する。
こうしたロボットまで行かないにせよ、いわゆる「AIコンパニオン」(ヴァーチャルなガールフレンド)とのつき合いを楽しんでいる男性たちはすでにたくさんいる。ヴァーチャルな恋人はひたすら従順で、ユーザーの思い通りになり、24時間いつでもそこにいてくれて、男性たちを拒否したりしない。胸のサイズや性格でさえ、ユーザーが好きなようにカスタマイズすることが可能だ。間違っても「あなたの言うことには賛成できない」などと口ごたえすることはないし、「今日は疲れているから一人になりたい」と会うことを断ったり、男性が着せたい服に「そういう服は好きじゃない」と自分の意見を言ったりすることもない。思うがまま、いつでも従ってくれる、自分の好きなようにできる玩具か奴隷のようだ。
当たり前だが、生身の女性はそんなことはない。男性と議論することもあるし、表面的には静かでも、表情や態度で反抗することもある。生きている人間は、自分の気分次第でいじめたり、八つ当たりをしたり、都合のいいように作り変えることのできる存在ではない。
ヴァーチャルな世界で何をしたっていいじゃないか、単なるファンタジーだから、と言う人々もいる。女性の側が「キモい」と遠ざけておけばいいのだからと。だが、ヴァーチャル・フレンドやヴァーチャル・ロマンスの世界だけでなく、職場というリアルな場にAIが進出し、若い女性たちとアシスタントレベルの業務を奪い合うようになると事態は変わってくるかもしれない。生身の人間の側が「男女同権」とか「雇用法が」とか決して言わない機械みたいに働くことを期待されるようになるのではないか。AIには人権はないが、人間にはある。「私たちはAIではありません」と女性たちが闘わねばならない時代が来るかもしれない。
「tech bro」という言葉もある通りAIの開発者には男性が多いが、実はAIの利用者にも男性と女性の格差があるそうだ。18歳から24歳の男性の71%がAIを毎週使用していると答えているのに対し、同じ年齢層の女性ではわずか59%だったという調査結果もある。男性がAIの多数派ユーザーである限り、テクノロジーは男性の視点で設計され続けるだろう。
このあたりから、変えていく必要があるのではないか。AI革命でシスターたちが生きづらくなる未来を避けるために。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。本連載をまとめた『SISTER"FOOT"EMPATHY』(集英社)が好評発売中。