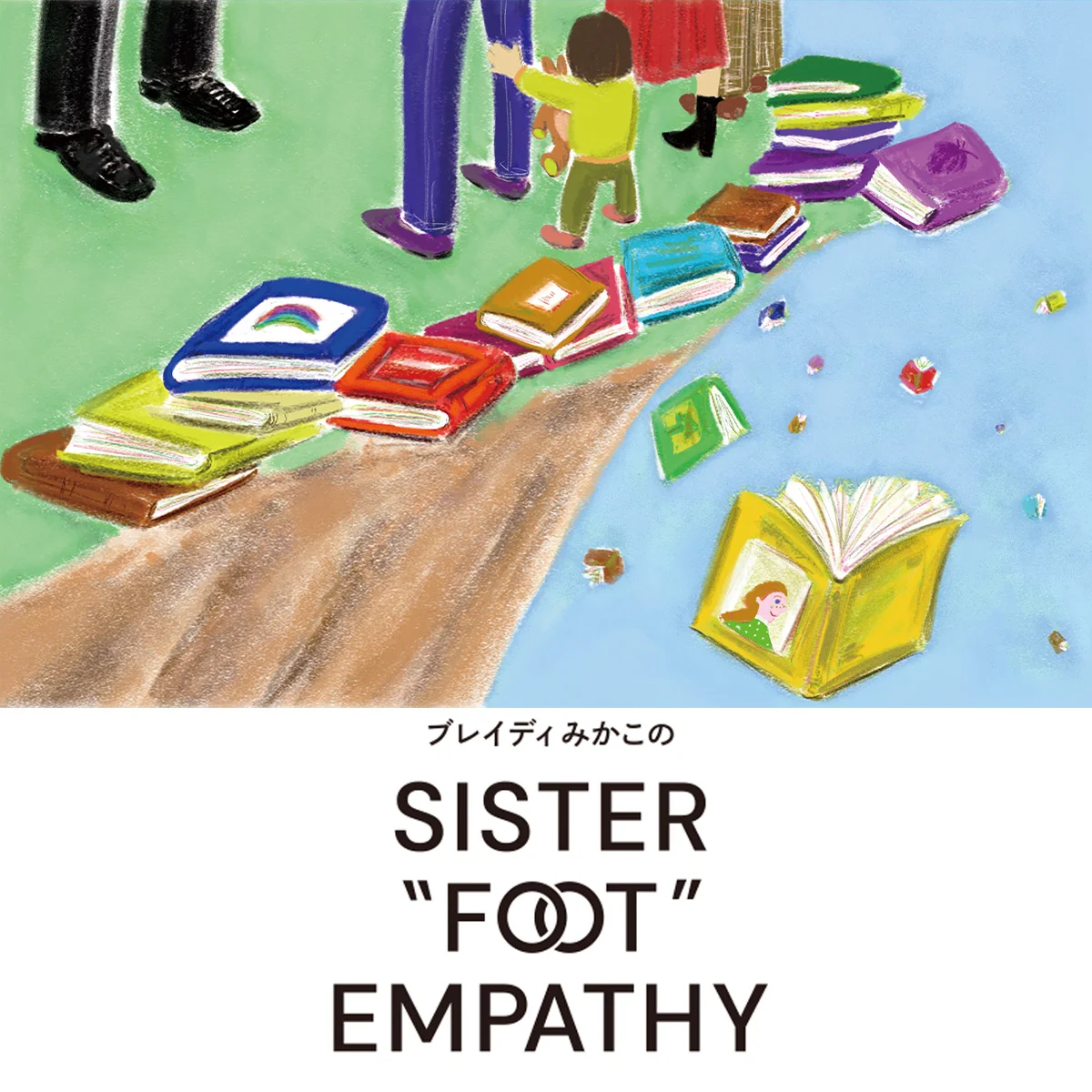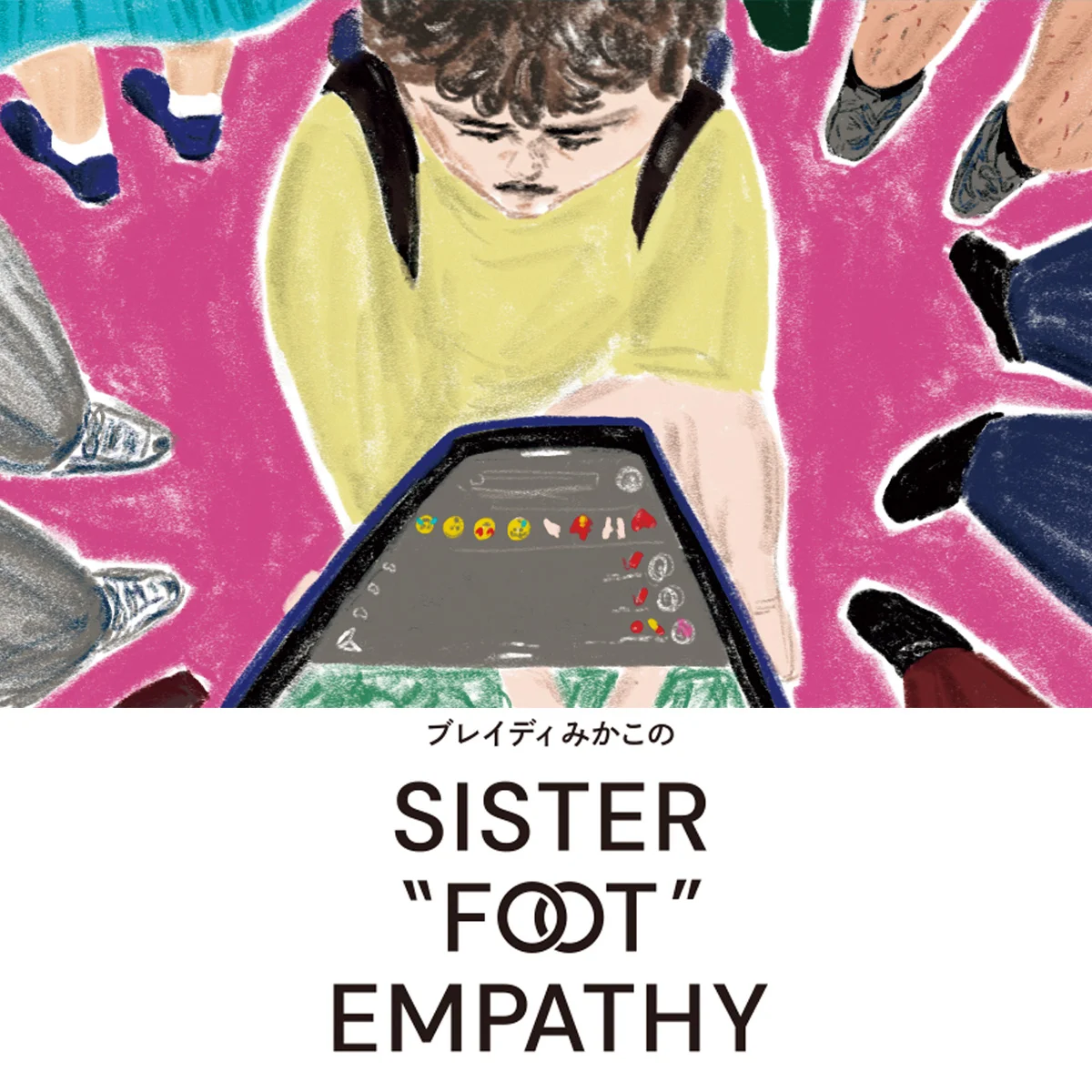数えきれない性暴力が「なかったこと」にされる国で、何の後ろ盾もなくたった一人で声を挙げた。小さな声に耳を傾けるジャーナリストが、未来に向けて伝えたいこと。

絶望のどん底にいてもジャーナリズムだけは諦めない
「正直、裁判の結果にはそこまで期待していませんでした。どんな結果になろうともプロセスが大事だと思っていたから。今まではプロセスさえも見ることができなかったブラックボックスが、一部とはいえオープンになったことは、大きな一歩です」
伊藤詩織さんが「望まない性行為で精神的苦痛を受けた」と、元TBS記者の山口敬之氏に対し損害賠償を求めた民事裁判で、2019年12月18日、東京地裁は山口氏に330万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。異例の逮捕状取り消しを経て刑事事件では不起訴、検察審査会でも不起訴相当とされ、「なかったこと」にされ続けた。苛烈なバッシングを受けながらも発し続けた声が法律で認められるまでに5年の月日が費やされた。被害を受けたのは2015年の春。事件当時に満開だった桜はフラッシュバックの引き金になるため、今でも見ることができない。
かつて失意の底にいた彼女に、声を挙げ続ける覚悟と希望をもたらしたのは、米軍内での性犯罪を長期取材した連作で知られるフォトジャーナリスト、メアリー・F・キャルバートが撮影した一枚の写真。『世界報道写真展』で展示されていたレイプ被害者と家族のその後を追った作品との出合いだった。
「当時は、ジャーナリストであると同時に当事者であるという難しさを突きつけられ、私にとっては大事件だけれど、社会にとっては取るに足らないよくある話なのかもしれないと、くじけかけていました。メアリーの作品を目の前にし、性犯罪は昔からあるけれど、今なおジャーナリズムの世界で報じられるべき問題なんだと再確認できたんです」。思わず我がことのように感じ衝撃を受けたのは、自ら命を絶った被害者キャリー・グッドウィンさんの日記を写したもの。リストカットされた手首のイラストが大きく描かれ、死をもって終止符を打とうとする彼女の苦しみが伝わり、写真の前で動けなくなった。
「もうこの世界にはいない人の日記が、どれだけ多くの人にメッセージを伝えられたのだろう。あの写真を見て、今耳を傾けてもらえず日の目を見なくとも、ボールを投げ続けたら、いつか伝わるときがくると信じる気持ちが湧いてきました。私生活は絶望の底で日本で生活していける望みすら断たれていたけれど、ジャーナリズムだけは諦めちゃダメだ。どうせ死ぬ気でいるのなら、伝えることだけは信じてやっていこうと決意した瞬間でした」
その後、国連の活動を通して運命を変える写真を撮った本人と知り合う機会に恵まれ、親睦を深める。米ワシントンDCを訪れた際、メアリーは自宅に泊めてくれただけでなく、検察による捜査が続いている最中に山口氏がフェローとして招かれたシンクタンクで、実質的な雲隠れ先である「イースト・ウエスト・センター」への取材にも同行。「そのセンターの責任者への取材で、通常は複雑な手続きを経て選出されるポジションに、笹川平和財団の推薦という異例のルートで山口氏が招聘(しょうへい)されたこと、2017年の3月まで在籍しながらほとんど顔を見せなかったという実態がわかりました。誰も答えてくれないような疑問でも、諦めずにぶつけ続ければ小さな答えが返ってくるし、小さな答えを並べれば真実の輪郭が浮かび上がってくるんです」
誰にも耳を傾けられない小さな声を届けたい
現在の拠点はロンドン。友人のスウェーデン人ジャーナリストと一緒に、ドキュメンタリー作品の制作会社「Hanashi Films」を立ち上げた。
「日本に住めなくなってロンドンに移ったときに、助けてくれたのがHanna。HannaとShioriで、Hanashiです。ジェンダーに基づく人権をテーマに、小さな声をスロージャーナリズムで伝えたい」
時間をかけてゆっくり伝えることにこだわるのは、国際ニュース通信社のインターンとして「いかに使われるかに主眼を置いた、一時的に消費されるための3分間映像」を作り続け、フラストレーションを抱いた苦い経験から。何よりも、「簡単につぶされるちっぽけな存在と思い知らされた恐怖と痛みを知っているからこそ、誰にも耳を傾けられない小さな声を届けたい。私は人間が好きだし、伝えることの力をすごく信じているんです」
2018年以降は、西アフリカのシエラレオネ共和国を主なフィールドとして、女性器切除(略称FGM)の問題を追い続けている。
「FGMは、女性器を切除したり縫い閉じる通過儀礼で、シエラレオネでは9割の女性が体験しています。儀式の中で命を落とす子どももたくさんいるし、出産時に問題が起きるなど、心身に深刻なダメージを与える慣習。国際社会から非難を浴びたこともあり、この2年間でシエラレオネでもようやく問題視されてきたところ。一応18歳以上に同意を得てからという規則はあるのですが、ほとんど守られていないのが現状で、犠牲になっているのは子どもたち。まともな医療措置もなく不衛生な環境で行われ、切除後は1カ月程度ジャングルの小屋にこもって、よき母よき妻になるとはどういうことかを教わるのが習わしです」
シエラレオネでは、2014年からのエボラ出血熱の大流行で学校が閉鎖されると、子どもに対する性暴力が激増。学校再開時には、多くの女子生徒が妊娠していて、それを理由に登校を禁止された。「少女たちへの性暴力の取材を進める中で、9割の女性が経験しているFGMの問題に関心を持つようになりました。まだ幼いうちに女性器切除の儀式を通して女性として一人前と見なされるようになり、性暴力や児童婚の標的にされてしまう。中には、5歳で切除を受け13歳で初体験、学校にも行けないまま一人で子どもを育てている少女もいました。他国の文化に口を出すなと言われることもありますが、命に関わるジェンダーベースバイオレンスを見過ごすことはできない」
つい先日は、時代の流れを取り入れて切除はせずに形式的な儀式だけを行うコミュニティへの、飛び込み取材を敢行。「ダメ元で始まる時期に行ったら、『君も儀式を受けるんだったら撮影していい』と言われて。ジャングルにある小屋に集まったのは、下は6歳から上は16歳の63人の少女たち。歌って踊って、薬草を飲んだり体に塗ったり。踊りが下手だと怒られ、お尻を叩かれたこともありました」
1週間を過ぎた頃、マラリアと腸チフスで動けなくなっているところを知人に救出されたと、こともなげに語る。
「儀式では、長老のおばあさんたちの言うことが絶対。隔離された環境で粉々に自己をつぶされて服従し、コントロールされる恐怖を味わいました。実際に体験する前は、なんで誰もおかしいって言わないのか、どうしてもっと早く病院に行かないのかと歯がゆく思っていたけれど、そのコミュニティで抗いがたいパワーバランスのもとで暮らす身になってみれば、選択肢はないのだと認識を改めました」
9割が切除を受ける世界で、1割のマイノリティとして“不完全女”のレッテルを貼られると、学校ではいじめられ、就職でも結婚でも差別される現実がある。女性器切除を取り巻く構造は、遠く離れた日本で起きるセクハラや性暴力のそれとよく似ていた。
「ひとつはパワーのアンバランス。もうひとつは女性だったらこうしなければならない、枠にはまらなければ認めないという社会的圧力の存在です」
性暴力は紛争の武器にも使われる重大な犯罪
著書『Black Box』には、性暴力被害者の声を阻む多くの障害の実情が克明に描かれている。医療、警察を含む行政、司法、被害後のサポート体制や、セカンドレイプが蔓延する世間の声に及び腰の報道……。「変わってほしいことは数えきれない」と言う詩織さんの最大の願いは、性暴力に対する一人ひとりの意識変革だ。「減るもんじゃないしよくあること、騒ぐようなことではないと何度も言われました。私はサバイバーの方に、Believe Your Truth(あなたの真実を信じて)とよく伝えるのですが、自分の受けた傷は、自分がいちばんよくわかるんですね。どれだけ周りに大したことないと言われても体は覚えていて、何年もたってからトラウマが吹き出すこともある。南米の元ゲリラの人々に取材したこともあるし、命の危険を感じたこともあるけれど。性暴力によって一度だけ奪われた自分の体のコントロール、尊厳を踏みにじられた記憶はより強烈で、今でも苦しめられています。サバイバーというと、もう克服したように聞こえるけど、正しくはサバイビング。今も生き残ろうともがいている最中なんです。レイプはその人の土台を崩し、周囲の人にもダメージを与える犯罪。紛争地帯では、敵を屈服させ次世代まで傷を残す武器として使われる重大な犯罪です。一人ひとりに自分の真実を信じて心の声に耳を澄ませてほしいし、性犯罪が一人の人間をどれだけ破壊するかを知り、想像してほしい。どんなに大きな問題やシステムも、すべては一人ひとりの行動やマインドでできているのだから」

2018年から女性器切除の問題について、西アフリカにあるシエラレオネをフィールドに取材を続けている。この1月には63人の少女たちに交じって、切除を伴わない通過儀礼の儀式に参加。少女たちの置かれた状況を身をもって体験した。写真提供:伊藤詩織
Shiori Ito
1989年生まれ。ジャーナリスト、映像作家。NYの大学でジャーナリズムと写真を学ぶ。孤独死を扱った監督作「Undercover Asia: Lonely Deaths」が国連共催のコンテストで高く評価された。著書に自らの性被害について告発するノンフィクション『Black Box』(文藝春秋)。
SOURCE:SPUR 2020年4月号「伊藤詩織が届ける『声』」
interview & text: Anna Osada photography: Mie Morimoto hair & make-up: Takae Kamikawa〈mod’s hair〉