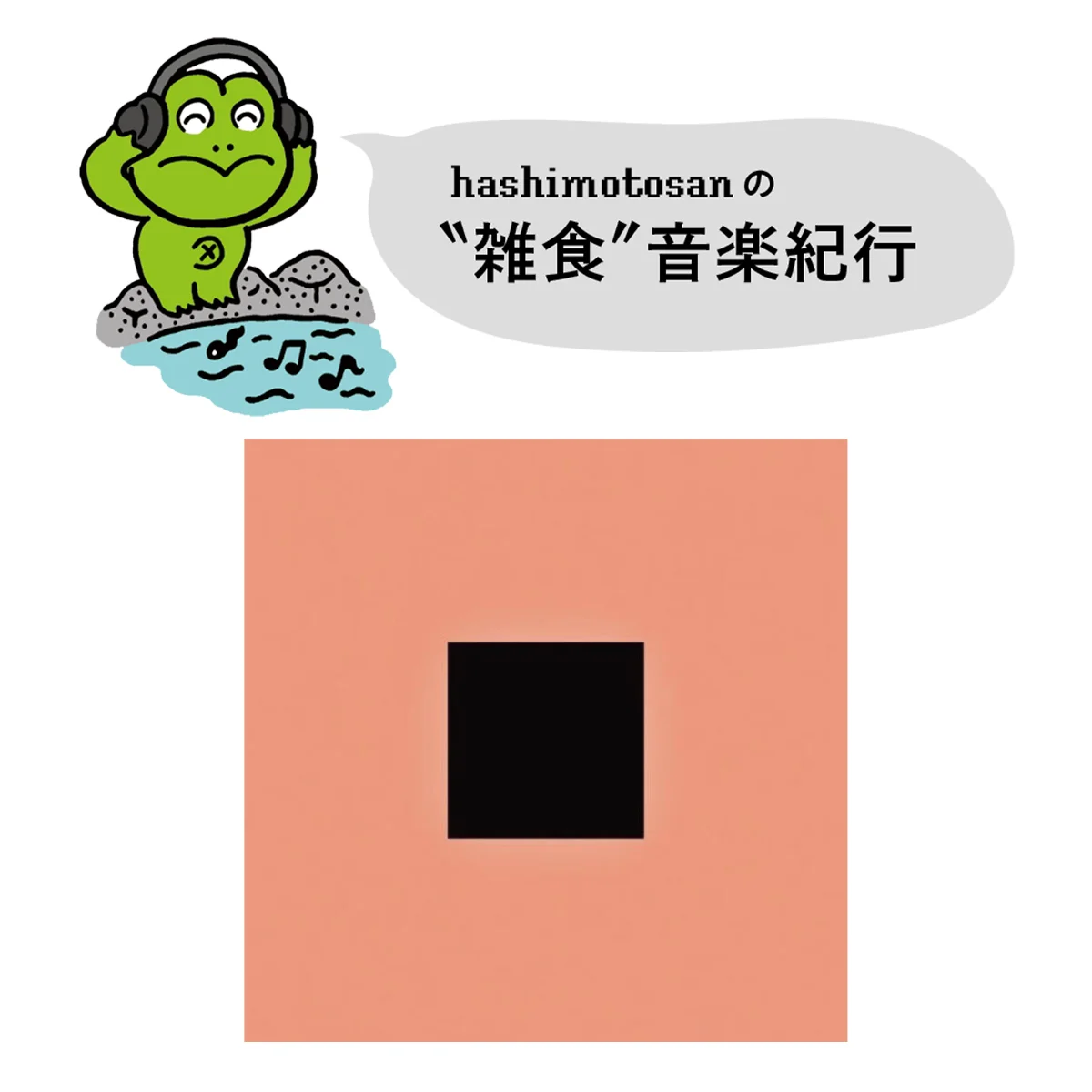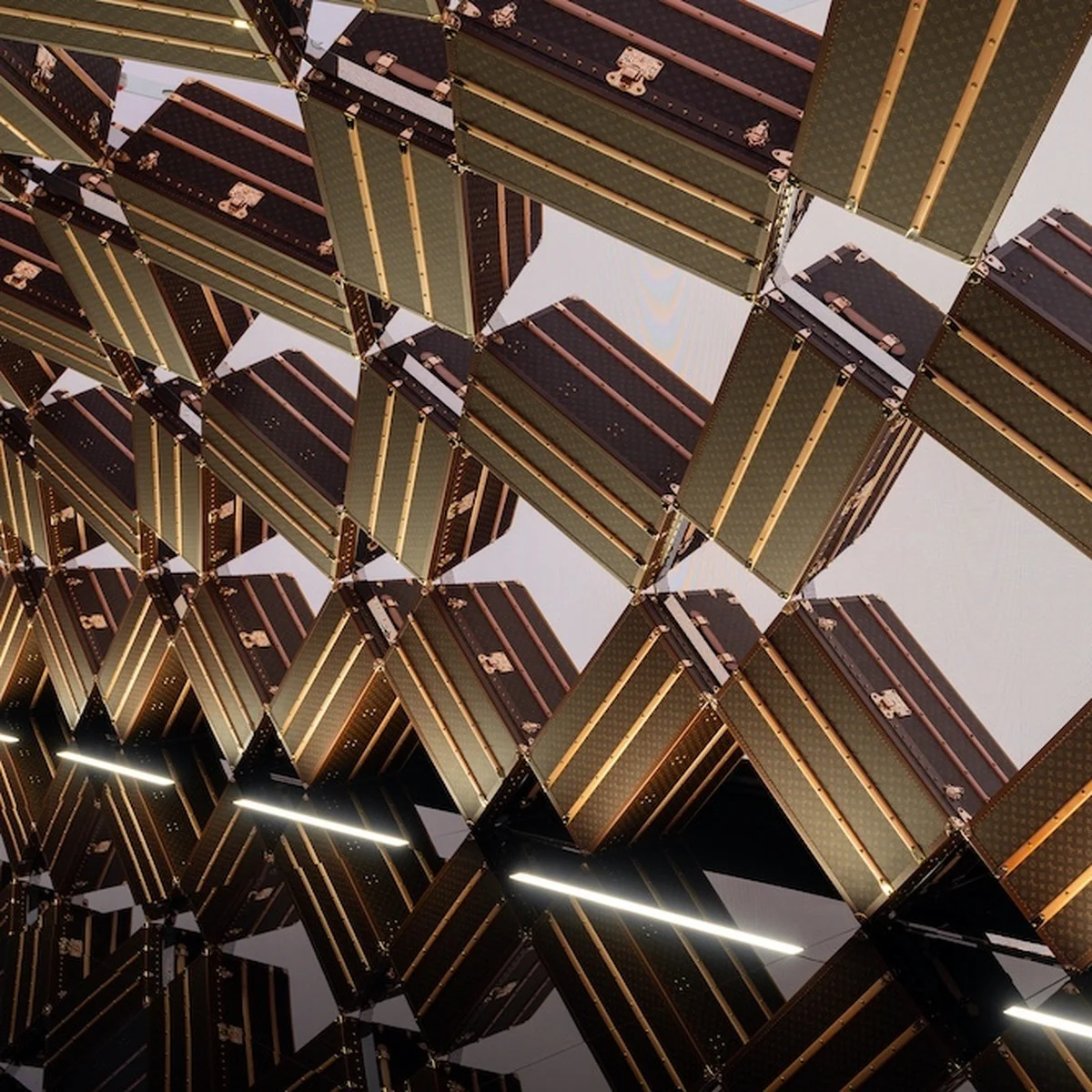いつのまにか私たちは、戦争を「目を背けたい恐ろしい過去」「自分たちとは関係のないこと」「やむを得ないこと」という安易な認識で捉えてしまってはいないだろうか? 戦争体験者だからこそ、あるいは戦後生まれであっても、その本質に真摯に対峙して作品を創り出している作家、アーティストの姿勢とその作品から、かけがえのない平和を守るために思考し、行動する力をもらおう。
※この記事はSPUR本誌2015年9月号にて掲載された同名特集を転載しています。

PROFILE
つかもと しんや
●1960年東京都生まれ。’89年、劇場デビュー作『鉄男 TETSUO』がローマ国際ファンタスティック映画祭でグランプリ受賞。代表作に『六月の蛇』(’02)、『KOTOKO』(’11)、『斬、』('18) がある。2016年、マーティン・スコセッシ監督『沈黙-サイレンス-』に出演するなど、俳優としても活躍。
彼らが異常なのではなく、戦場では誰もがそうなる。それが戦争のリアル
映画監督 塚本 晋也さん
「今やらなければ、今後、もう作ることができなくなるかもしれない。今の時代の流れになんとか疑問を投げかけたい。そんな危機感を感じて作りました」
塚本監督がそう語るのは、2015年の夏に公開された映画『野火』。戦争文学の傑作といわれる大岡昇平の小説を自主製作で映像化した作品だ。第二次世界大戦時、約100万人が命を落としたとされる南方戦線。長引く激戦に加え、武器や食料の補給もなく、熱帯のジャングルで日本軍は過酷な戦いを強いられた。小説の舞台もそんな激戦地のひとつ、フィリピン・レイテ島。病気で分隊を追い出された一等兵の田村は飢えと病に苦しみ、密林をさまよう中で人間の狂気を目のあたりにする。
「高校生のとき、初めて読んで衝撃を受けました。田村は国のために命を投げ出すことの理不尽さをずっと抱えているような客観的な目線の持ち主です。だから戦争を知らない僕でもその主観にシンクロして読めたんでしょう。まるで戦場に放り込まれたような感覚に陥りました。なかでも心に残ったのが南国の大自然と兵士たちのコントラストです。景色が美しいぶん人間の心の闇が強烈に映し出されていて。その衝撃は何度、読み返しても薄れるどころかますます鮮明になり、ずっと映像化したいと思っていました」
本腰を入れ始めたのは2005年あたりから。
「レイテ島から生還した元兵士の方々に話を聞いて、もっと血肉化したいと思っていた」と当事者への取材を開始。悲劇の実態がより鮮明になっていった。
「当時の写真がアメリカ側の資料に載っているんですが、手榴弾で自爆した日本兵の無残な姿や、まさに骨と皮だけになった日本兵の姿があり、それは壮絶なものでした。話を聞いた方々も動いているものがあれば何でも食べたと言っていました。水牛も寄ってたかって殺して、足の硬い爪以外、骨さえも全部食べ尽くしたと。『野火』では、飢えから、やがて人を殺して食べる兵士の姿が描かれますが、彼らが異常なのではなく、あの状況に置かれたら誰でもそうなって不思議はないということです。それが戦争のリアルなんだと思います」
戦争を懐疑的に描く作品が敬遠されるようになってしまった
しかしその後、『野火』の映像化には、さまざまな壁が立ちはだかることに。
「当初は予算がネックになっていましたが、2010年くらいからOKが出ない理由が変わってきたんです。それは戦争を懐疑的に描くということに対する拒否反応のようなものでした。何かのために命を投げ出すことへの熱狂とか尊さみたいなもののほうが、観客に受け入れられやすいということで、戦争もヒロイックな描かれ方をされるものが増えていきました。一方、戦争の恐ろしさや理不尽さを描くものが敬遠されるようになってしまった。これは急激な変化でした」
巷にあふれる戦争を美化した映像や小説。「若い人たちの意識下にこれがすり込まれてしまう怖さを感じた」という監督は『野火』の映像化を固く決意。監督・脚本・主演・撮影を自らが担い、自主製作で映画を作り上げた。製作費削減のためメイン4人の俳優以外はすべてツイッターで募集したボランティア。スタッフも痩せた人から採用し、ヒゲを伸ばしてエキストラとして出演してもらった。
「最初はもう自撮り映画しかないと思ったので、カメラを三脚で立てて、その前でひとり演技するつもりでした。でも最終的には多くの人が協力してくれた」
大作にも劣らないスケール感や熱量は、こんな監督の思いを反映してのものだろう。そして美しい自然の中、容赦なく映し出される人間の深い業。目を背けたくなるようなむごいシーンの連続だが、これは決して絵空事ではなく、やがて私たちが直面するかもしれない未来でもある。
「戦争の痛みを肌で知っている方が減るにつれ、日本は危険な方向へ急速に舵を切ってるように思います。かつては『反戦』なんて、ありきたりのテーマだったのに、それを描くことも憚られる世の中になってしまった、と。でも戦争になれば、この映画のような悲劇が繰り返される。そのときになって後悔しないためにも踏みとどまってほしい。そう願ってます」

『野火 Fires on the Plain』
第二次世界大戦末期、フィリピン・レイテ島で日本兵が体験した地獄を描く。フィリピン・ミンダナオ島をはじめ、ハワイや沖縄などでロケを敢行。出演に塚本晋也、リリー・フランキー。(2020年夏、全国にてアンコール上映中)
SOURCE:SPUR 2015年9月号「6人が向き合った、『戦争』」
photographs:Kikuko Usuyama interview & text:Hiromi Sato