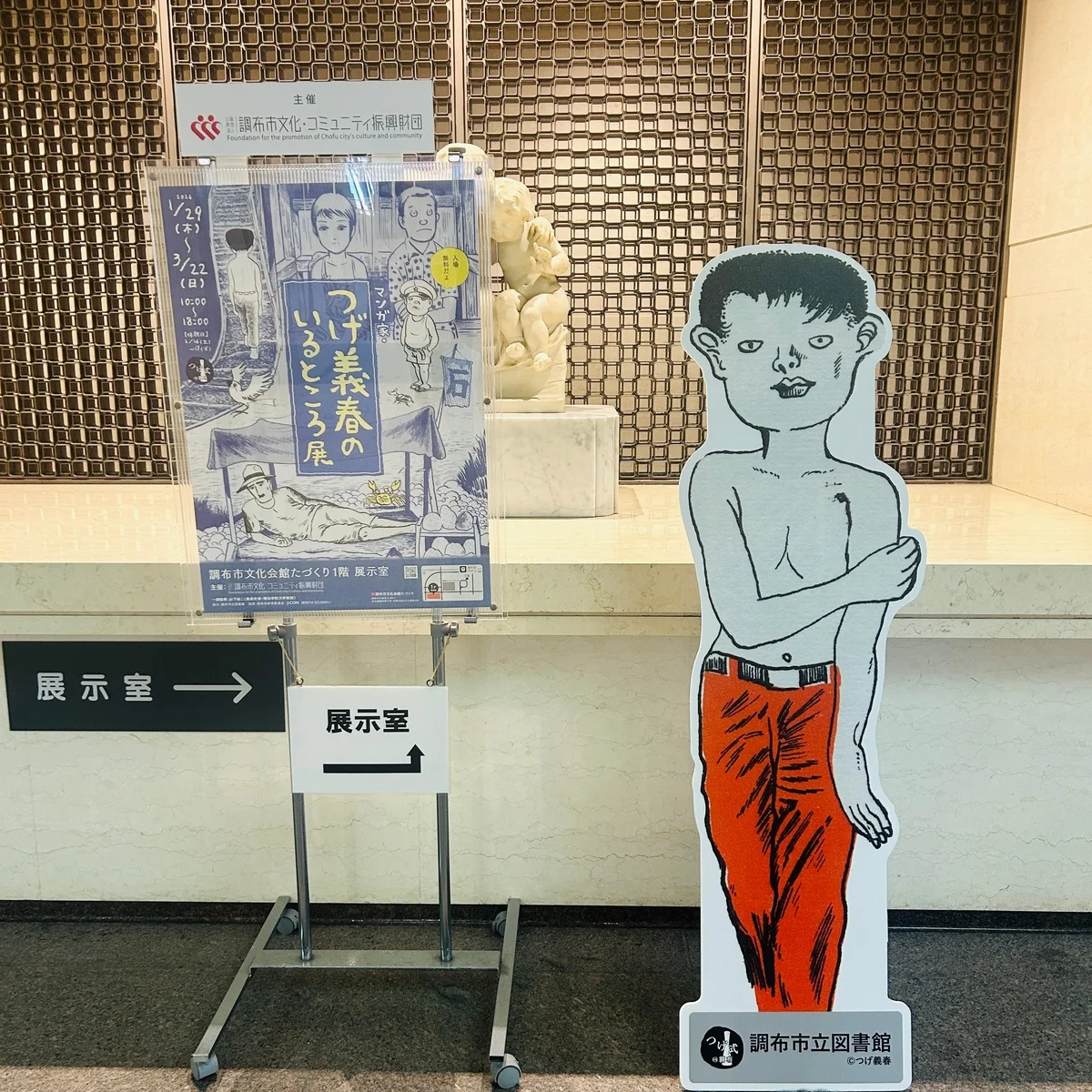クリエイターのクローゼットに、必ずと言っていいほど存在するブランド。個人的に思い入れのあるシーズンの服を、「マイ・ヴィンテージ」として大切に着るファッションプロも多い。愛用者の私的スタイルとともに、熱いラブコールをキャッチした。
Part 1 愛用者たちの、マイ・ドリス・スタイル
時がたつほどに魅力を増す服。自分だけの物語が詰まったお気に入りの一着と、春夏の着こなしについて語る

1976年生まれ。1989年にNHK大河ドラマで俳優デビューし、1999年には映画『あつもの』で第54回毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。著書に、『野生のベリージャム』。

ベーシックなアイテムを、凛とした女性像で品よく遊ぶスタイリングに定評がある。アシスタント時代から、ドリスを追いかけている。

ヴィンテージショップが集うマーケットを主催。100回目のショーを記念した書籍『Dries Van Noten 1-100』を定期的に読み返している。

各方面にアンテナを張り、流行の一歩先を行くスタイリングを手がける。SPUR2016年12月号のドリス特集では、新旧織り交ぜて提案。

数誌のファッションディレクターを経て独立。モード誌やカタログなどを手がける。趣味である茶の稽古でも、ドリスの服を愛用する。
Part 2 ファッションジャーナリスト・乗松美奈子が綴る 私とドリス ヴァン ノッテン
「アントワープ6」に興味津々で、初めてこの街を訪れたのは、私がパリに住み始めた1990年代初頭のことでした。旅のハイライトは、ドリス ヴァン ノッテンのブティック、”モードの殿堂”なるHet Modepaleis。膨大なドリスのコレクションがずらりと並んだそこは、ブティックというより色彩と柄が祀られた神聖な場所のようで、ただただ圧倒されました。
この体験を本誌の当時の主任編集者に話したところ、フリーのエディターとして駆け出しの私がアントワープでの仕事を依頼されたのが、1994年春。大特集のための滞在は1週間にわたり、ドリスが通うと評判のレストランで食事をしてみたり、Het Modepaleisに今度は取材者として訪れたり、ドリスに一歩近づけたうれしさを密かに噛み締めた旅でした。一番印象的だったのは、歴史的な中央駅での、ドリスの花柄ドレスの撮影(2)。20世紀初頭の趣が残る大聖堂のような美しさの駅のホームに出ると、なんとドレスとマッチする色の電車が! 当時はまだタリス(高速列車)はなく、時代がかった車両の電車が往来していて、すべてがまるで映画のセットのようでした。大輪の花のドレスに羽織ったのは、ベーシックなカーディガンと、ウエストをフィットさせたジャケット、と野暮ったさと紙一重の組み合わせ。アヴァンギャルドとは違うけれど、今まで見たことのない、不協和音のようでいて調和が取れている、いわゆるドリス節をこの環境でこそ深く理解できたのだと思います。
この1年後には、初めてドリスにインタビュー。やわらかな物腰で淡々と語るインスピレーションについて耳を傾けると、私はますます彼と彼のクリエーションのファンになったのです。この機会に私が初めて手に入れたのが、小花柄と小紋柄の微妙なパッチワークによる、膝丈ワンピース。ランウェイには出なかったコマーシャル・ピースなのですが、いろいろな都市の土産的ポストカードをちりばめたプリントの、1995年春夏のルック写真(1)を見ると、マイ・ファースト・ドリスを着まくった夏が思い出されます。しかしあまりに着用、クリーニングを続けたため、繊細な薄手のシルクはところどころ破れ、着られなくなってしまいましたが。
その後も私のドリス・コレクションは毎シーズン少しずつ増えていきました。中でも着すぎて色褪せてきたけれど今でも愛用しているのは、2012年春夏のサンドレス(6)。モノクロの風景画はどこかヨーロッパの古都を思わせるので、ローマやアルルに行くときは、必ずこれをスーツケースに入れます。ちなみに2014年、『INSPIRATIONS』と題された展覧会(パリ・装飾美術館)でもこのシリーズの展示が。感極まって、自分が代表作の一つを持っていることがうれしい、とこの機にインタビューした彼にも報告(3)。
まったくの主観ですが、ドリス節を堪能するためにワードローブに一つでも加えたいのは、大胆なグラフィック柄と、ラメ使いです。この両点が一つになったのが、2017-‘18年秋冬のジオメトリック柄のニット(5)。カジュアルにジーンズや無地のパンツと合わせるだけでもアップビートなルックになるし、カチッとしたシャツを中に着て白い襟をアクセントにしたり、色や柄物のボトムと合わせてミスマッチにしてみたり、と着こなしの可能性は無限大。
そして一番最近のお気に入りは、3年前のクリスチャン・ラクロワとのコラボレーションのコレクションから、花柄のフーディ・ドレス(4)。ショー直後に二人をインタビューする機会があったことも手伝って、絶対に欲しいとチェックした一点です。やっと届いたのは、コロナ禍初期。だから気持ちを上げてくれたのは言うまでもありません。パリではやっとロックダウンが緩和されたその夏、バースデーディナーで着たのもこのドレスでした。
ドリスの服はどれも、買ってもすぐには着なかったり、着続けた後クローゼットに眠らせておくこともあります。でもあるときまた、いずれかが必須アイテムにランクアップ。パーソナルなクリエーションだから、いつまでも持っていたい、そして着たいと思わせる、愛おしい服たちなのです。

静岡県生まれ。上智大学卒業後、『STUDIO VOICE』編集部で1年間ファッションを担当し、1992年に渡仏。現在もパリ在住。ファッションを中心にライフスタイルやアートと、幅広い分野でのジャーナリスト、コンサルタントを務める。
Part 3 【ドリス ヴァン ノッテン】新作ウィッシュリスト
"服への愛"をテーマに発表された2023-’24年秋冬コレクション。現地でショーを目撃した面々をはじめ、ファッションプロ6名にブランドへの想いと、今季手に入れたい逸品について聞いた。