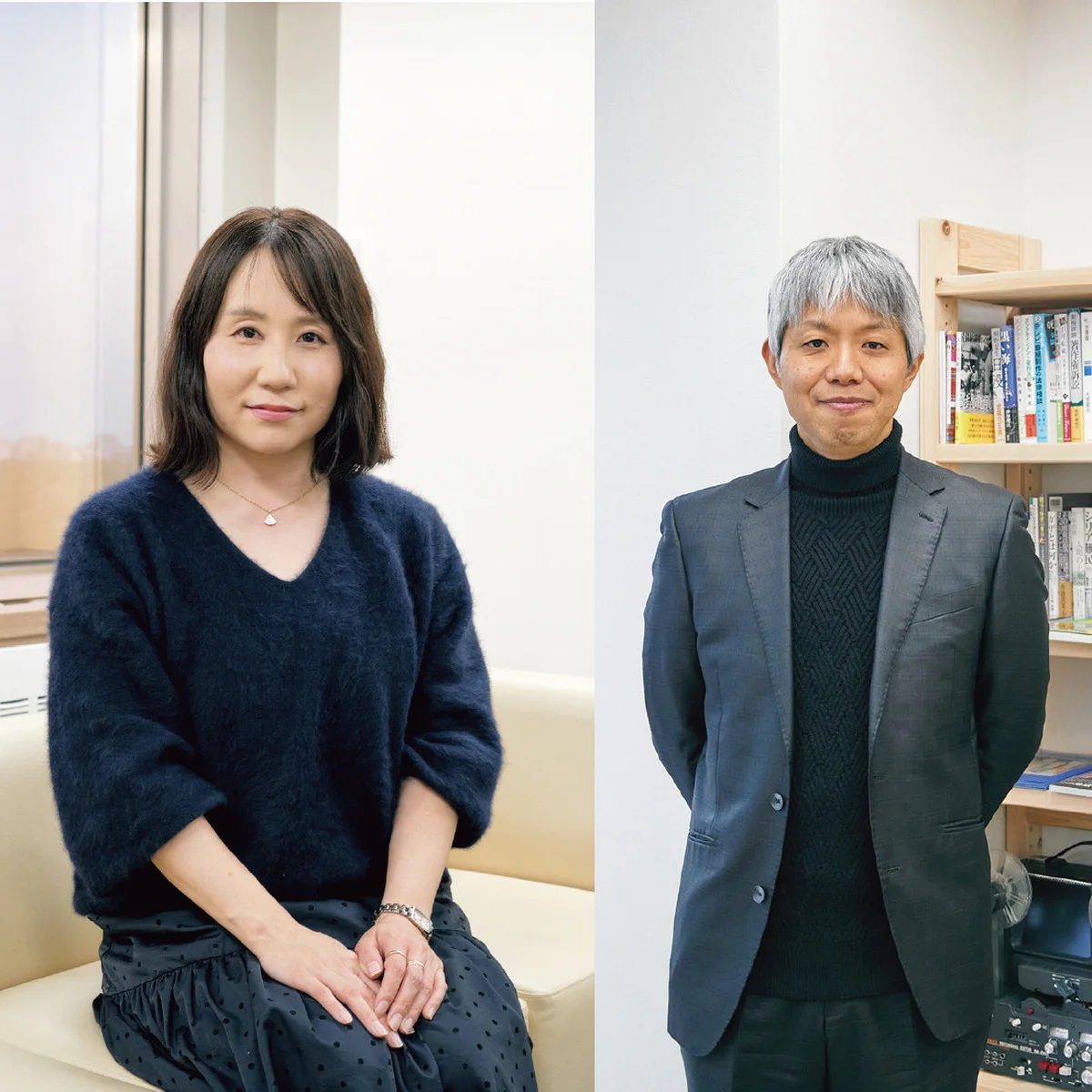第二次世界大戦中に、凄惨な地上戦を経験した沖縄。1945年3月、慶良間(けらま)諸島に上陸した米軍と日本軍との間で繰り広げられた激しい戦闘により、沖縄県民の4人に1人が犠牲となった。その後、1972年5月15日に復帰を果たすまで、27年にもおよんだ米軍統治時代。復帰から半世紀以上が経った現在もなお、沖縄には米軍基地が存在する。「僕たちは、生きている人の語りを聞くことすらしてこなかった。戦後から今を生きる沖縄の人たちの生の声を聞きたい」。そう話すのは、長年にわたり沖縄で質的調査を続ける社会学者の岸政彦さん。2023年5月に刊行された監修本『沖縄の生活史』(みすず書房)に込められた思いや、ご自身の研究について伺った。
残さなければ消えてしまう、100通りの沖縄戦後史
100人の聞き手が、100人の沖縄の人たちの人生の歩みを聞き取り、100篇の語りとして収録した『沖縄の生活史』。地元紙の沖縄タイムスが、2022年5月の日本復帰50年に合わせて企画した長期連載プロジェクトを、800ページを超える一冊にまとめた大著だ。岸さんと、沖縄出身の社会学者である石原昌家さんとの共同監修のもと、100人の聞き手を公募し、語り手を選び、それぞれの語りを聞き手自身が約1万字に記録・編集した。
「最初はもっとささやかな企画だったのですが、やっているうちに沖縄タイムス社の方も乗り気になってくださって、最終的には一般公募型の大規模な生活史モノグラフが完成しました。聞き手のほとんどは沖縄出身の若い方で、祖父母や親の語りを聞いて文章に残したいという思いで応募してくださいました。沖縄の人たちは家族愛や親族ネットワークがものすごく強いんです。みなさん戦後の過酷な状況下で懸命に働き、家族で助け合って子どもや孫を育ててこられましたから。そういった背景もあって、おじいちゃんおばあちゃんが孫に話しかけるような、穏やかな語りが多いのが本書の特徴です。『沖縄の生活史』を作るプロセスの中にも、“沖縄らしさ”が入ってきたなと感じています」
人生の語りを聞き取る面白さ、広めたい
さまざまな人たちの語りを集めた生活史を作りたい。岸さんがそう明確に思ったのは、なんと中学生の頃。きっかけは1970年代に活躍し、インタビューの名手と謳われたアメリカ人作家、スタッズ・ターケル氏の名著(『死について!』『大恐慌!』など)との出合いだった。
「人々の語りをそのまま載せるというスタイル自体は、僕のオリジナルではなく、先人がいました。ターケルのほかにも、W.I.トーマスとズナニエツキが『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』という本を1920年にまとめていて、それは現在の社会学の原点のひとつになっています。生活史を聞き取るのが面白いという流れは、これまでにもなかったわけではありません。ただ、地道に人々の語りを集めるよりも、『現代社会は今こうなっている』といった大きな話をする社会学者の方が人気が出ていたので、地味な調査をやる人が目立たなかったことは確かです。人々の語りに耳を傾ける社会学者はたくさんいます」
沖縄を好きになった自分を否定することから始まった研究
大学を卒業後、たまたま旅行で行った沖縄にすっかり魅了され、沖縄をテーマに研究の道へ進むことを決意した岸さん。大学院博士課程で沖縄でのフィールドワークを始めるが、その後は苦労の連続だったと振り返る。
「勉強すればするほどわかってくるんです。沖縄に基地と貧困を押し付けている側の内地の日本人が、ズカズカと沖縄に入り込んで論文を書き、自分の業績を上げていく。それは簡単に言えば、沖縄の搾取なんですよ。沖縄の人たちに会って話を聞いて、博士論文を書いて、それが後に僕の最初の本『同化と他者化―戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版)になりました。以降、沖縄の研究をライフワークにして、教授にもなって。そうやって自分だけ出世していっても、基地問題も貧困問題も何も変わらない。そういうことで悩んで、何年も書けない時期もありました。沖縄の調査をやると決めてから今に至るまで、決して楽な道ではありませんでした」
かつては、沖縄をいいところだと思うことすら自分自身に禁止していた時期もあった。それでも、行くたびに沖縄が好きになる、と岸さんは微笑む。
「基地の問題はそのままなのに、内地の人間が沖縄の独自性に惹かれて、いいところだなと思うのは植民地主義なんじゃないかと思っていた時期もありました。なので、沖縄にハマった自分自身を否定することから僕の研究は始まっています。ただ、何年も調査で通っていると普通は冷めてくるものですが、僕の場合は初めて来たときの感動がいまだにあるんですよ。社会学者の友達からも、つくづく幸せものだなって言われます。研究で苦労はしてきましたし、今でもその苦労は続いていますが、やめようと思ったことは一度もありません」
沖縄戦は「今」とつながっている
米軍基地が今も存在する以上、沖縄戦と戦後から現在までの人々の経験は連続していると岸さんは言う。そして基地に限らず、沖縄が抱える貧困や格差の問題もまた、沖縄戦や長年におよんだ軍政とひと続きだ。
沖縄戦の激しい戦火により、沖縄の社会と経済は壊滅した。沖縄の人々は県内各地の収容所に送られ、先祖代々住んでいた土地も奪われた。1950年代に本格的な復興が始まると、資材不足で鉄くずに高値がつき、「スクラップブーム」が到来。人々は地面を掘り返し、米軍によって投下された大量の爆弾の破片(不発弾を含む)を売って現金収入を得た。その際に不発弾が爆発し、亡くなった人もいた。岸さんは著書『同化と他者化』で次のように述べている。
沖縄戦で同胞の命を奪った爆弾の欠片を、いくらかの現金のためにふたたび掘り返す作業は、それをした人々にとって、どのような経験だっただろう。頭上に落とされた暴力の欠片と引き換えに現金を得るその姿は、戦後の沖縄を象徴しているのかもしれない。それは沖縄の人々のたくましさであると同時に、沖縄という場が背負う歴史そのものであり、日本と日本人への問いでもある。
27年間にわたる米軍支配のもと、戦後の沖縄では基地の収入や補助金に頼る「基地依存型経済」が形成された。沖縄戦で米軍と戦い、辛い経験をした人たちも、食べていくために基地施設の従業員として働いた。そして復帰後は、日本政府の援助による公共投資中心の経済へと移り変わり、それまでの高度経済成長期は終わりを迎える。
「那覇で食事をしていると、飲食店のレベルの高さと値段の安さに驚かされることがあります。復帰後の沖縄経済は公共事業が主体となったので、民間セクターが弱く、十分な雇用が生まれなくなりました。そこで参入障壁の低い飲食店をやる人が多くなったのですが、飲食店は場所さえ借りられれば誰でもできる反面、廃業率も高く、入れ替わりも早い。そんな中で5年以上続いている店は、だいたい美味しいんです。つまり、那覇の飲食店のレベルの高さには、沖縄特有の経済的条件が深く関係しているんです」
生活史から何を学ぶかは、読み手に委ねられている
東京、沖縄、大阪と3つの生活史プロジェクトを手掛けた岸さんだが、『沖縄の生活史』に限っては自分だけの本にしたくなかったと話す。「これは僕の本ではなく、沖縄の人の本であるべきだと思いました。そもそも沖縄タイムス社の企画だったわけですが、監修も、僕が最も尊敬する沖縄の社会学者でありフィールドワーカーである石原昌家先生にお願いして、引き受けていただきました」
沖縄に関する調査はこれまでにも数多く行われてきたが、戦後の経験も含めた100人分の語りを生のかたちで残した本は、『沖縄の生活史』以外にはない。では読み手であるわたしたちは、この貴重な一冊とどう向き合うべきなのか。「何を学ぶかは、読み手に委ねられている」と岸さんは言う。
「この本の面白さをうまく表現する言葉は、まだないんだと思います。歴史本でもなければフィクションや文学でもない。けれども、読めば必ず得るものや学ぶものがあるはずです。たった100人の1万字の短い語りでも、この分量になるんです。沖縄には150万人近くの人たちが暮らしていて、そのひとりひとりが、文字にすれば何十万字にもなるような生活史を持って生きているということ、そこに基地を置き、彼らの頭上にオスプレイを飛ばしているということを、読み手がどれぐらい想像できるか。この本が、そういったことを考えるきっかけになればと願っています。『沖縄の生活史』は、今後100年、200年経ったときにすごく貴重な資料になるでしょう。この本を世に出せてよかったと心から思っています」