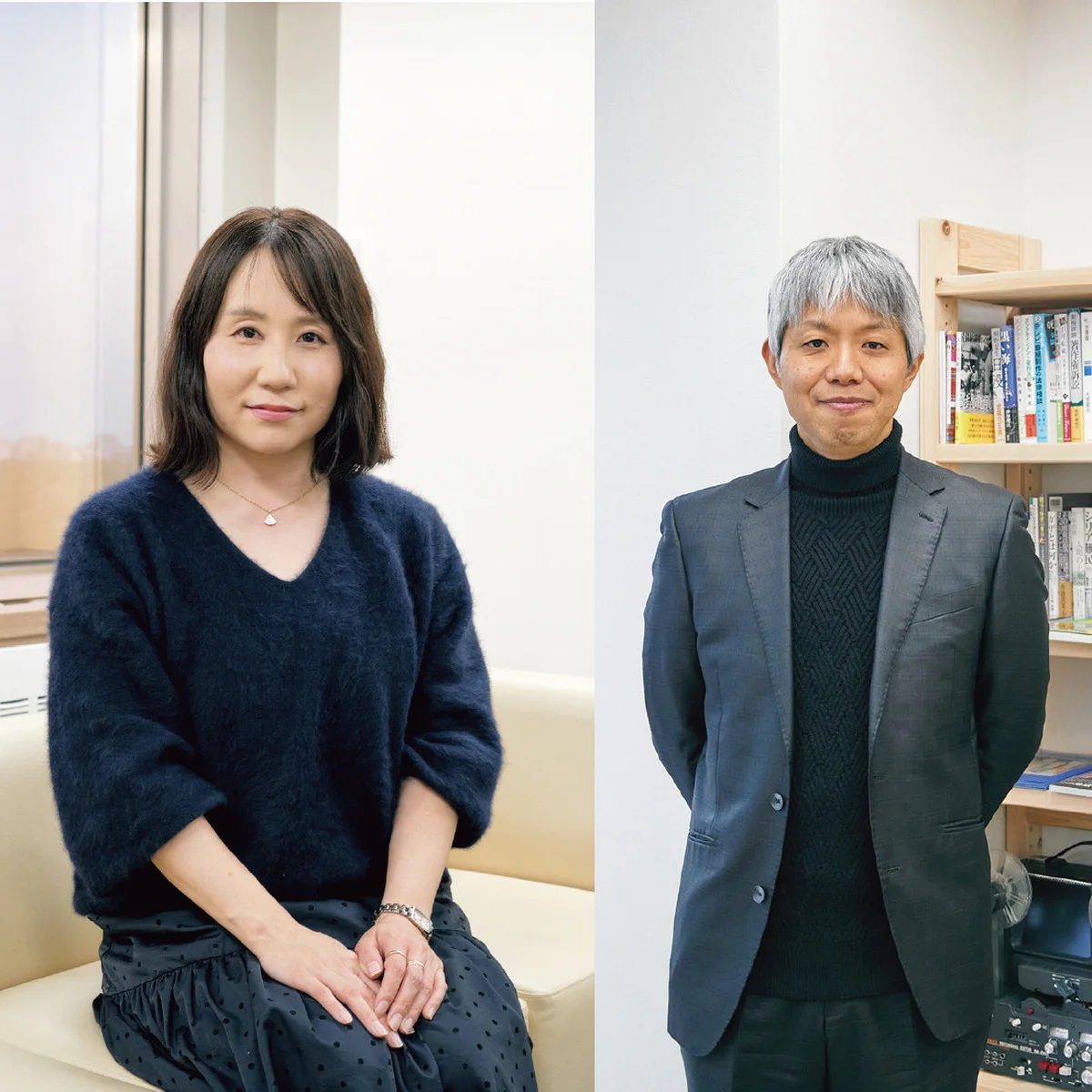東京や神奈川を中心に甚大な被害をもたらした関東大震災から100年の節目となった、2023年9月1日、森達也さんが監督を務めた劇映画『福田村事件』が公開された。題材となったのは、震災直後の1923年9月6日、千葉県東葛飾郡福田村(現野田市)で、香川県から訪れた薬売りの行商の一行が、地元の自警団らに朝鮮人と決めつけられ殺害された事件。史実としてほとんど記録されておらず、事件そのものを知る人もほとんどいない、歴史の闇に葬られていた100年前の惨劇をもとに、森さんが伝えたいメッセージとは何か。「100年前も今も変わらない」と森さんが指摘する集団の狂気を丹念に描いた本作から、現代を生きるわたしたちが向き合うべきことを考えてみたい。
流言飛語、不安と恐れが生んだ惨劇
第一次世界大戦が終結し、深刻な不況に陥っていた20世紀初頭の日本。1919年には日本統治下にあった朝鮮半島で三・一独立運動が起こり、朝鮮総督府は軍隊と警察で徹底的な弾圧を行った。日本政府やメディアはその頃から「不逞鮮人(ふていせんじん)」という差別語を使い、「朝鮮人は暴徒だ」と警戒を煽る報道を重ね、国民の政権への不満を逸らそうとしていた。
不穏な時代の空気のなか、1923年9月1日午前11時58分、関東大震災が発生。未曾有の災害によって10万を超える人の命が失われた。混乱に乗じて飛び交ったのは、「朝鮮人が集団で襲ってくる」「朝鮮人が放火をした」などの流言。これらの根拠のないデマには内務省の関与があったとされているが、そのような流言を新聞が「事実」として報道し、広めた。関東地方に戒厳令がしかれたことにより、軍や警察は朝鮮人をはじめ、中国人や社会主義を唱える日本人に対しても厳しい取り締りを行った。「朝鮮人らに襲われるかもしれない」と怯えた民衆もまた、政府の呼びかけに応じて各地で自警団を組織。数千人もの朝鮮人や中国人、日本人が虐殺されたとされている。
善良な人を豹変させる心理を検証したい
オウム真理教の信者を内部から撮影したドキュメンタリー映画『A』(1998)や、記者の姿を通して日本の報道の問題点を描いた『i-新聞記者ドキュメント-』(2019)など、タブー視されがちなテーマに取り組んできた森さん。今から20年ほど前、テレビ番組の制作会社でディレクターをしていた頃、千葉県野田市で福田村事件の慰霊碑を建てるという新聞記事がたまたま目に留まり、この事件に興味を持ったという。事件に関する資料はほとんど見つからなかったものの、現地に行って聞き取りやリサーチを繰り返すうちに、少しずつ事実が見えてきた。
福田村事件を番組にしたいと考えた森さんは、各局の報道担当者に企画を提案する。しかし、視聴率やスポンサーとの関係などの理由から受け入れてもらえず、企画は頓挫。それでも森さんは諦めきれず、長年あたため続けてきた。奇しくも同事件に関心を寄せていた脚本家で映画監督の荒井晴彦さんとの出会いにより、企画は再び動き出し、今回の映画化が実現。クラウドファンディングを通じて製作費を集めた。
加害者側を描くことで見えてくるもの
福田村事件を映画化するにあたり、森さんの中に大前提としてあったのは、被害者側だけでなく、加害者側の人間模様もしっかり描写するということだった。加害者側は単なるモンスターではなく、彼らも同じ人間で、平凡な日々の営みがあった。作中では、事件が起こる前の福田村の人びとの個々の人格や葛藤を細やかに描き出したことで、ごく普通の人が凶悪なことをやってしまう恐ろしさを見事に浮き彫りにした。
広島県呉市生まれ。1995年の地下鉄サリン事件発生後、オウム真理教の信者たちを内側から描いたドキュメンタリー作品『A』を1998年に発表。ベルリン国際映画祭をはじめ多数の海外映画祭に招待され、世界的に話題となる。2001年に映画『A2』が山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別賞・市民賞を受賞。2020年2月、ドキュメンタリー作品『i-新聞記者ドキュメント-』が2019年 第93回「キネマ旬報ベスト・テン」で文化映画部門の第1位に選出。このほか、『A3』(集英社インターナショナル)が講談社ノンフィクション賞を受賞するなど著書も多数。近著に『千代田区一番一号のラビリンス』(現代書館)。