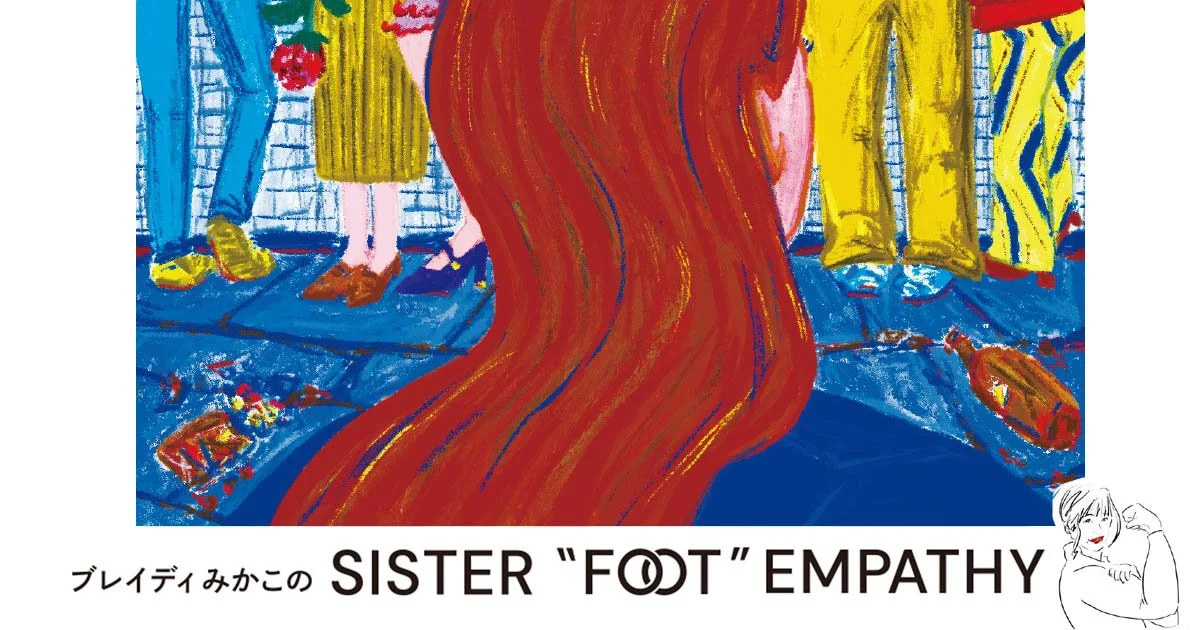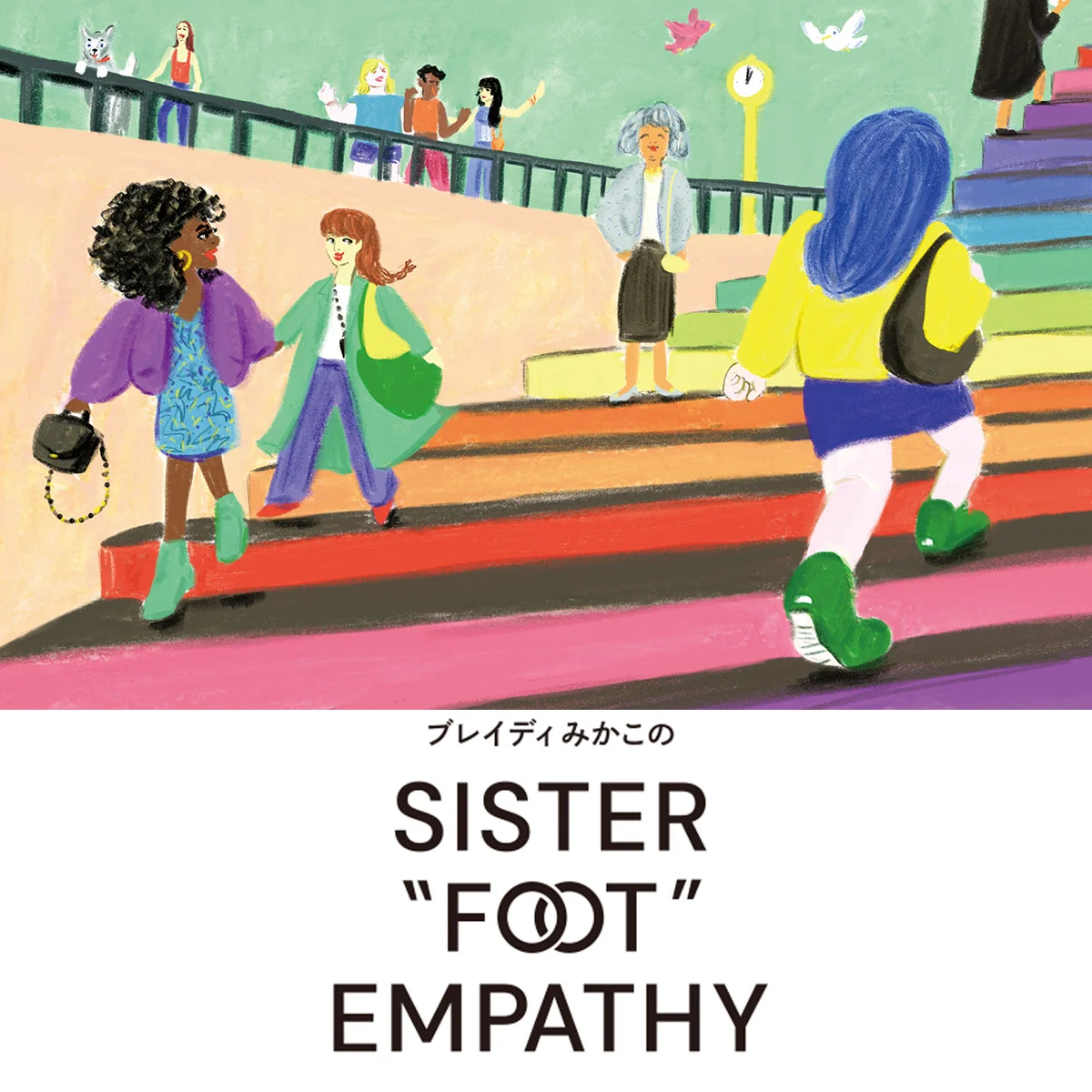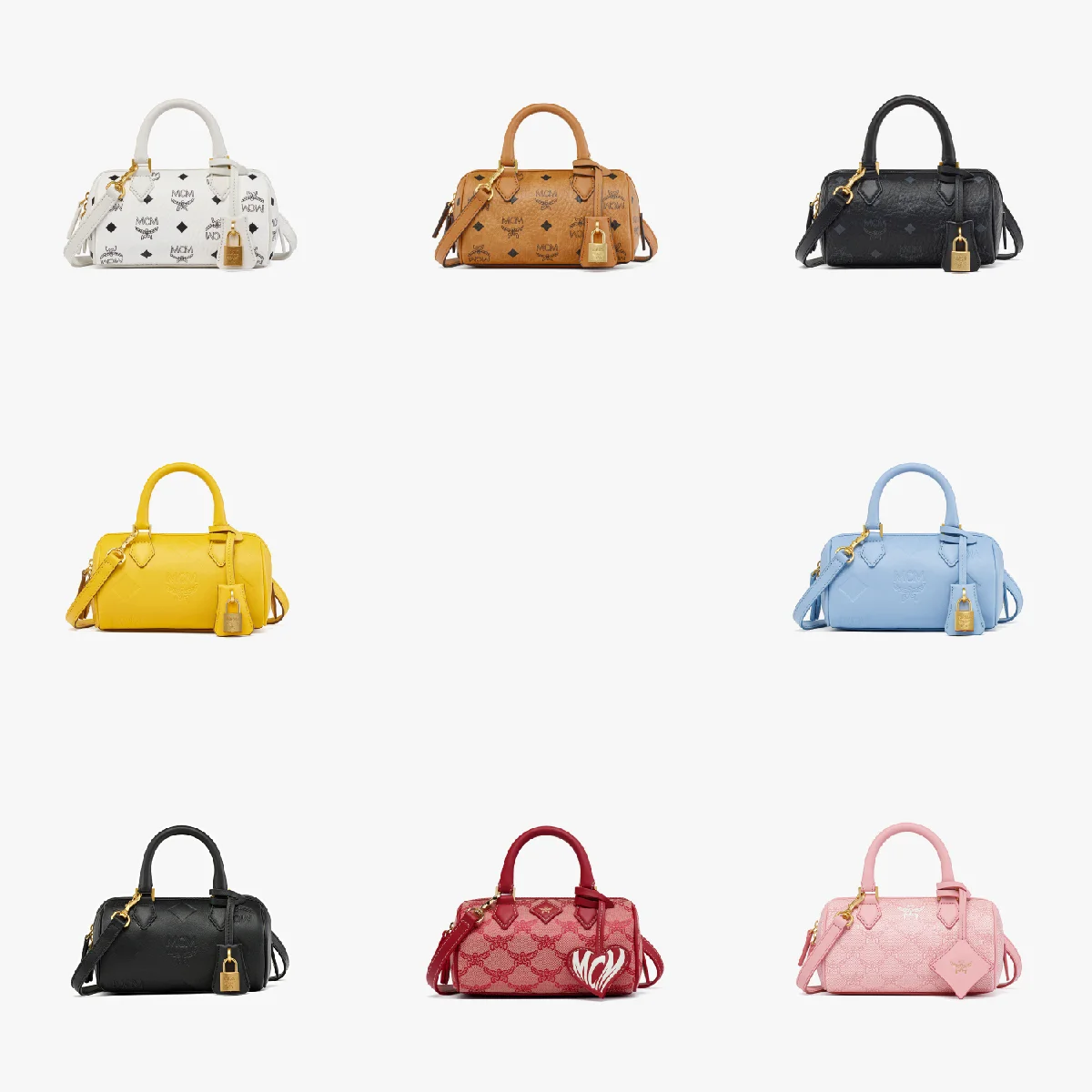"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談。
※ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

例えば、インさんとヤンさんという二人の女性がいるとしよう。インさんは高学歴で裕福な家庭の出身。文化資本の豊かな環境で育ち、教養豊かで古い因習にとらわれず進歩的。その一方で教養のない人々をどこか見下しているところがあり、世の中が変わらないのはそういう人たち(特に、覚醒せず、自立できない女性たち)がいるからだと考えている。
他方でヤンさんは、貧しい家庭で育ち、少女小説を読むのは大好きだったが、インさんのような学歴も教養もない。男たちのわがままや横暴には嫌気がさしているが、女性は結婚して生きるしかないと思っていて、別の生き方を模索する勇気はない。だが、苦労しただけあって困っている人には優しく、ケアの仕事をさせると微に入り細に入りの気遣いを見せて本領を発揮する。
ふつうだったら出会う機会もなさそうなインさんとヤンさんだが、インさんの家が没落してしまったことから、二人はルームシェアをすることになる。インさんはヤンさんの生い立ちに同情はするが、話をすればするほど退屈だし、ヤンさんのような存在が女性の権利を後退させると陰でいろんな人に言っている。また、ヤンさんのほうも、最初はインさんの華やかさや知性に憧れたが、家事一般の面倒な仕事を全部自分に押し付け、1ミリも感謝の念を抱いていないばかりか上から目線で文句ばっかり言っているインさんの人間性を疑うようになる。
そんなとき、インさんが重い病にかかってしまい……。
というのは、いま書いている新しい小説のプロットではない。インさんはわたしの祖母、ヤンさんはわたしの実母をモデルにした半実話だ。明治生まれのシングルマザーであり、やりたいように生きた自由人の祖母は、「あの子は頭が悪い」と母について言った。その祖母の実家が没落してから生まれ、ずっと祖母の日常の世話をし続けた母は、「あの人は、頭はいいかもしれないが情がない。自分の体を動かさない」と祖母について言った。
双方から互いの悪口を聞かされながら、わたしは二人のあいだで育った。だからだろう。人間のキャラクターを形づくるのは、世代や血筋だとは思わなくなった。なぜなら、年老いた祖母のほうが母よりはるかに進歩的だったし、二人は実の親子なのにどこも似ていなかった(外見さえそうだった)からだ。
人をつくるのは環境なのである。
そう思うようになってからは、どちらかといえば母より仲が良かった祖母の態度が鼻につくようになった。自由な考え方をする祖母のほうが話している分には刺激的で面白かったが、自分の自由を地味なところで支えている人間がいることを当然のものとして捉えていることが嫌になったのだ。だから、たぶんわたしがインさんとヤンさんの物語を書いたとしたら、著者の視点はだんだんそういうふうに偏向してゆき、インさんには不幸な結末が待っているかもしれない。
いや、しかし、それではシスターフッドの話にはならないだろう。インさんとヤンさんの和解、とまではいかなくても、共存&共闘。それこそがいま描かれるべき物語なのだ、たぶん。
7年ほど前、サフラジェットたちを描いた『未来を花束にして』という映画のロンドンプレミアで、ある抗議活動が起きたことがあった。サフラジェットとは、19世紀末から20世紀初頭にかけて、女性参政権を求めて闘った女性たちのことで、特にイギリスのエメリン・パンクハーストとクリスタベル・パンクハーストが率いた団体WSPU(Women’s Social and Political Union)のメンバーたちを指す。ハンガー・ストライキや器物損壊、放火など過激な手法も辞さず、命がけで闘った女性たちの姿を描いた『未来を花束にして』は、フェミニズムの歴史を振り返り、今日までのその達成を思い起こさせる映画として話題になっていた。リーダーのエメリン・パンクハーストをメリル・ストリープが演じたほか、キャリー・マリガンやヘレナ・ボナム=カーターなどの大物女優が出演した同作のプレミアはフェミニズムの祭典のように見なされていたが、当日、レッドカーペットの上に侵入して抗議活動を行った女性たちのグループがいた。
「死んだ女性たちは投票できない!」と叫びながらレッドカーペットに寝ころんだ女性たちは「シスターズ・アンカット」というグループのメンバーたちだった。彼女たちは、政府の緊縮財政による予算削減のせいで、DV被害者のためのシェルターや相談サービスなどが閉鎖されたり、縮小されていることに抗議し、映画のプレミアに乱入したのだった。ゴージャスなドレスを着た女優たちやセレブリティーが歩くレッドカーペットに、黒いトップスとスプレーで落書きを施したパンツという姿で寝ころんだ彼女たちは、まるで「99%のためのフェミニズム」を体現しているようだった。
「99%のためのフェミニズム」とは、1%の富裕層ではなく、「99%のわたしたち」のためのフェミニズムという文脈でよく使われている言葉だが、もし本当にそうであれば、99%の中にはヤンさんのような女性たちも含まれている。世間一般的に「女性は」「娘は」「妻は」「母は」こうしなければいけないと思われている役割を、窮屈に思いながら(そして時には男性からのハラスメントに耐えながら)、しょうがないと諦めて一生懸命に果たしている人々がいる。そしてその人たちの中には、ヤンさんがインさんに反感を抱いていたように、自由な女性たちを快く思わない人、偉そうだと思っている人なんかもいるかもしれない。
だが、「シスター〝フット〟」が「足元からの」連帯を意味するのであれば、ヤンさんたちの生きづらさをすくい取らないわけにはいかない。エンパシー(自分とは違う他者への想像力)というのは、自分と似た考え方を持つ他者だけを対象にするものではないし、自分の同胞だけを99%と呼ぶのであれば、それは狭い小宇宙に過ぎないからだ。
この連載が「エンパシー」という言葉と「シスターフット」という造語をタイトルに掲げるからには、99%の意味を考えていかなければならない。そう思うのは、わたし自身、母に対するエンパシーが足りなかったことを反省しているからだろう。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。