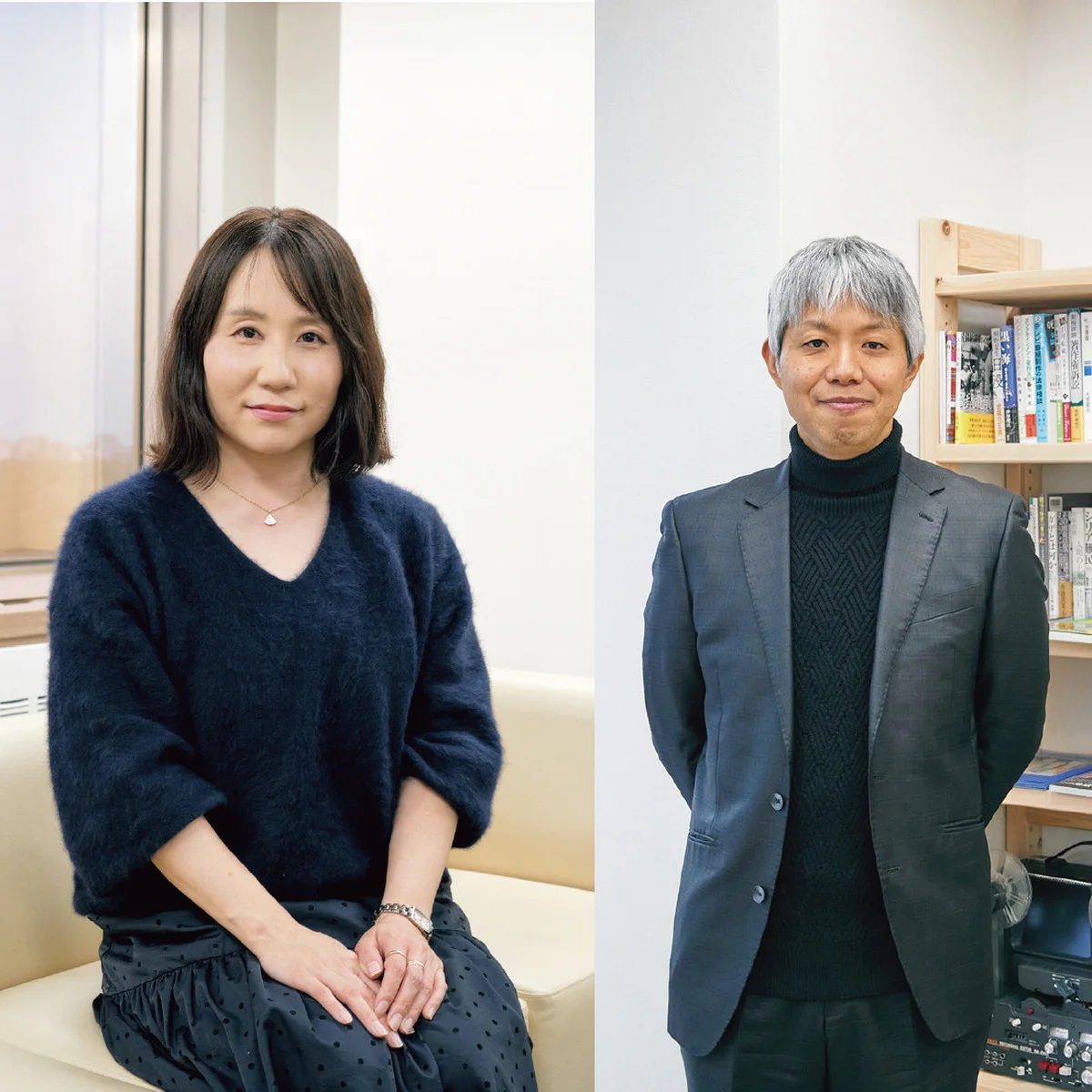80歳で「カラフルな魔女」に

玄関の扉、リビングの壁、書斎の本棚……角野さんの家には「いちご色」があふれている。赤とピンクの中間くらいのビビッドなその色がパッと目に飛び込んでくると、それだけで魔法にかけられたような気持ちになる。「この家を建てるとき、何かひとつ色を決めた方が統一感が出ると言われたの」と角野さん。老後の暮らしを考え、都内から鎌倉に引っ越したのが2001年。迷わず選んだ「いちご色」は、角野さんのチャーミングで力強い生き方を象徴する色だ。
この日、角野さんはすみれ色のワンピースに真っ白のアトリエコートを羽織り、トレードマークの眼鏡姿で出迎えてくれた。Eテレ番組『カラフルな魔女~角野栄子の物語が生まれる暮らし~』(2020年~22年放送)や、それをもとに制作された同名のドキュメンタリー映画が2024年1月に公開される前から、シルバーヘアに映える鮮やかな着こなしが注目されていた。コーディネートはすべて、娘のくぼしまりおさんが考えている。
「80歳になる手前ぐらいから、店に行って試着して服を買うのが億劫になってしまったんです。こういった取材の日や『魔法の文学館(江戸川区角野栄子児童文学館)』で読み聞かせをする日などは、娘が用意してくれたコーディネートを着ています。アクセサリーから靴下まで、一式そろえてくれるんです。ただし、文句を言わないことが条件。彼女は色のセンスが良いので、いつも面白がって着ているんですよ。娘も私を着せ替え人形にして楽しんでくれているようです」
 娘のくぼしまりおさんがデザインを手がけるブランド、EIKOFULのアトリエコートは「魔法の文学館」のグッズショップで販売中。 (左から)〇◇アトリエコート¥20,900・マルチストライプエイコート¥23,100。まんまるのブローチは、角野さんが愛用しているアクセサリーブランド、designsixとのコラボレーションアイテム¥5,170。
娘のくぼしまりおさんがデザインを手がけるブランド、EIKOFULのアトリエコートは「魔法の文学館」のグッズショップで販売中。 (左から)〇◇アトリエコート¥20,900・マルチストライプエイコート¥23,100。まんまるのブローチは、角野さんが愛用しているアクセサリーブランド、designsixとのコラボレーションアイテム¥5,170。
ワンピースとアトリエコートは角野さんの定番スタイル。同じ型を、色や模様違いで何着も持っている。体型の変化や要望に合わせて、りおさんと一緒に何十年も試行錯誤しながらたどり着いた理想型だ。「物語を書くときも、服を着るときも、自由で楽しいのがいちばん」。角野さんはそう言って朗らかに微笑む。
終戦の記憶と、解放されたよろこび

13歳の少女が親元を離れ、一人前の魔女になるためにさまざまな困難を乗り越える姿を描いた『魔女の宅急便』(福音館書店)。リンゴの顔をしたわがままなぬいぐるみ、シュールで憎めないキャラクターが魅力の『リンゴちゃん』(ポプラ社)。中学2年の少女が戦後の世界に飛び込んでいく、自叙伝的作品の『イコ トラベリング 1948-』(KADOKAWA)。角野さんが生み出す物語は自由奔放であたたかいと同時に、どこかほろ苦く、ほんの少しの怖さもにじむ。その不思議な作風の原点には、幼くして母を亡くしたことや、飢えに苦しんだ戦争体験が根付いている。
1935年1月1日生まれの89歳。角野さんの人生は波瀾万丈だった。5歳のときに実母が病気で他界。幼い頃から「いなくなるってどういうことだろう?」と考え、“どこか違う世界”に想いを馳せる少女だった。その翌年に太平洋戦争が勃発。東京の下町にあった家は空襲で焼け落ち、生活の基盤を失った。戦後の補償や救済はいっさいなかったが、終戦を迎えた後の解放感はとても大きかったと角野さんは振り返る。
「戦争が終わったとき、私は10歳でした。戦後もしばらくは食べるものがなくて、5年くらいはとても苦しかった。千葉の田舎に疎開したまま3年ほど過ごした後、東京の中学校に編入しました。戦時中は『日本は勝つ』というひとつの言葉で統制され、『我慢して助け合おう』とみんなが思っていました。でも戦争に負けて、その締めつけが突然なくなった。正しいと思っていた言葉が嘘だったと気付かされたわけです。それまでの軍国主義がいきなり民主主義に変わって、当時はわけがわかりませんでした。でも、真っ暗だったところに少しずつ電気がつき始めていったんです。
灯火管制のもと、電球の傘に風呂敷をかぶせて、そこからうっすら漏れる灯りの下で本を読むことぐらいしかできなかった戦時中とは打って変わって、空襲に怯えることなく明るいところで暮らせるようなった。少しずつ、自分の好きなものを選べるようにもなっていった。そのよろこびは今も鮮明に覚えています」
ブラジルへの移住。貧しくても心は自由だった

1957年に早稲田大学英文学科を卒業後、紀伊国屋書店出版部に就職するが、翌年23歳で結婚と同時に退職。誰かに強制されたわけではなかったが、「女性は結婚したら仕事を辞め、家庭に入るもの」という考えが当たり前の時代だった。
戦後の生活が変化していくと、自由を求める気持ちは海外へと向かっていった。欧米から入ってくる映画や本に触れるたびに、まだ見ぬ世界を見てみたい、遠くに行きたいという思いが湧き上がっていった。転機となったのは1959年、24歳のときに夫婦でブラジルへの移住を決意。喜望峰まわりで2ヵ月の船旅を経て、サンパウロに渡った。
「当時の日本は海外観光渡航が自由化されていなかったのですが、ブラジルとアルゼンチンとパラグアイには自費移民というかたちで行けたんです。ちょうどその頃、ブラジルではブラジリアが新首都として建設されていて、とにかく面白そうだから行ってみようということに。もちろん親は心配しましたけれど、私たちに迷いはありませんでした。戦争が終わって、希望という宝物を手に入れたんですから。その頃の若者はみんな海外に行きたかったのよ」
ブラジルに移り住むと、言葉が通じず職探しに苦労した。生活に馴染めず、家の中に引きこもっていた時期もあった。外に出るきっかけを作ってくれたのは、同じアパートの隣の部屋に住む11歳の少年、ルイジンニョだった。一緒に市場へ買い物に行ったり、サンバを踊ったり、彼を通じてブラジルの人々や言葉に触れ、角野さんは生きていく楽しみを見出すことができた。このルイジンニョ少年をモデルに書いた物語が、後に1970年のデビュー作『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』(ポプラ社)となった。「ブラジルでルイジンニョに出会わなかったら、私は作家になっていなかった」。角野さんにとって、彼は今でもかけがえのない存在だ。
 角野さんのテーマカラーの「いちご色」に染められた、広松木工のラビットチェア。2023年11月に東京都江戸川区にオープンした「魔法の文学館」の館内什器としても採用されている。
角野さんのテーマカラーの「いちご色」に染められた、広松木工のラビットチェア。2023年11月に東京都江戸川区にオープンした「魔法の文学館」の館内什器としても採用されている。
日系人向けの短波放送ラジオのスポンサーを探す営業の仕事に就いた角野さんは、ブラジル人のおおらかな国民性に惹かれていく。
「アメリカの大手企業にアポイントメントもなく突然売り込みに行って、『英語を話せる方はいませんか?』と聞くと、すぐに呼んできてくれたんですよ。日本の会社だったらきっと門前払いでしょ? ブラジルってすごくいいところだなと思いました。商談の際に日本の歌謡曲のレコードを聴いてもらうと、『日本人はこんな曲が好きなんだね』と言って1年間の契約を結んでくれましたね」
数社の契約を取り、ある程度貯金ができたタイミングで、カナディアン・パシフィック(1987年まで存在していたカナダの航空会社)との契約を取り付けた角野さん。そのときに支払われたコミッションは、現金ではなくファーストクラスの航空券だった。それをふたり分のエコノミーチケットに変えて、夫婦で9000キロのヨーロッパ旅へ。ニューヨークとカナダを経由し、1961年に日本に帰国した。
「日本に帰ってきたときは、一銭もお金が残っていませんでした。最近の人たちは慎重だから、こんな無謀な旅はしないでしょうし、海外に行きたくない人も多いみたいですね。でも、行くと自分の世界が広がりますよ。やっぱり現地の人と会って話さないとね。相手の言葉が自分の中に入ってくると、日本語のボキャブラリーも豊かになります。ブラジルにいた2年間は貧しい暮らしだったけれど、心はとても自由でした」
育児にときめきを与えた執筆活動
 娘のりおさんが幼い頃に、角野さんが手編みした人形。自宅の階段に飾られている。
娘のりおさんが幼い頃に、角野さんが手編みした人形。自宅の階段に飾られている。
帰国して数年後、31歳のときに長女のりおさんを出産。専業主婦として育児に追われる日々のなかで、角野さんは焦りを感じていたという。
「ちょうどバブル期で、日本社会がものすごく忙しい時代だったんです。深夜残業なんて当たり前。夫も仕事がすごく忙しくて、帰ってくるのは毎日夜中でしたから、私は小さな子どもとずっとふたりきりでした。保育園なんて、当時は利用できなかった。学校の先生や看護師などの専門職に就いている方が優先でしたから。もちろん子どもはすごく可愛いし、面白いこともたくさんありましたけれど、育児中は『自分』というものをあまり持てなかった。何か生きがいになること、ときめくようなことが欲しいと思っていましたね」
悶々としている角野さんに、ブラジルでの経験を書いてみないかと話を持ちかけたのは、早稲田大学時代の恩師であり、翻訳家の龍口直太郎さんだった。
「先生に、世界の子どもという童話シリーズを作っている出版社があるから、ブラジル編を書いてみないかとお誘いをいただいたんです。最初は書けるわけがないと及び腰だったんですけれど、それでも強く言われました。先生は私の卒論しか読んだことがなかったはずなのにね。
はじめからうまくは書けないから何度も書き直すのですが、同じことを書き直していてもすごく楽しくて、満足感があったんです。画板を肩から下げて、紙を洗濯バサミで挟んで、動き回る子どもを追いかけながら毎日書いていました。まとまった時間は持てなかったけれど、自分がいかに物語を紡ぐことが好きかわかって、そのときに一生書いていこうと決めたんです。私はそれまでずっと、何をしていいかわからなかったんだけれど、先生のおかげでライフワークに出合えました」
好きなことに食らいついていけば、いつかは魔法になる
 角野さんが物語を紡ぐときは、真っ白な紙にいたずら描きから始まるという。
角野さんが物語を紡ぐときは、真っ白な紙にいたずら描きから始まるという。
35歳のとき、デビュー作の『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』(ポプラ社)を刊行。その後も次々と新しい物語を生み出し、2018年には「小さなノーベル賞」と呼ばれる「国際アンデルセン賞」作家賞を受賞。50年以上にわたり、200以上もの作品を発表し続けている。
「ここのところあんまり忙しかったので疲れていたんですけれど、最近少し落ち着いてきたので、また執筆に取りかかろうと思っています。長く連載で書いていた童話があるので、それを書き直して一冊の本にする予定です。この先いつまで書けるかわからないけれど、書いているときがいちばん平和だし、気持ちが安定しますね」
締め切りは設けず、筋書きのない散歩のように物語を紡ぎ、書き上げたときに編集者に見せる。マイペースで自由なスタイルが角野流だ。89歳になった今も、執筆の手を止めることはない。ひたすら前に進み続ける原動力はどこからくるのだろうか?
「それはもうひと言、書くことが好き。これに尽きます。書けないと思ったことはこれまでに何度もありますが、書くのをやめたいと思ったことは一度もありません。大切なのは、好きという気持ち。それも、憧れや『瞬間的な好き』ではダメよ。好きなことにコツコツ食らいついていけば、いつかそれが魔法になるんです」
大切なのは「自分の言葉」を持つこと

戦時下の国家主義教育や昭和のジェンダー観など、時代特有の価値観に翻弄されながらも、30代半ばで思いがけず「好きなこと」に巡り合うことができた。好奇心いっぱいに、楽しみながら書き続けてきた角野さんは、自由な心を持つことの大切さを訴える。
「自由っていうのはね、みんなでワイワイするような賑やかなものじゃないの。自由は個人のものだから、孤独なんですよ。だから決意がないといけないんです。日本人は隣の人と同じ意見を言いがち。本当は違っていても、無理に押し込めようとしますよね。だってその方が楽だから。今の子どもたちには自分なりの考え方で、『自分の言葉』を持ってもらいたいです。そのために必要なのは想像力。たくさんの素敵な本と出合い、読書を通じてイマジネーションを培ってほしいですね。戦争を体験した私は、自分の言葉を持てない悲惨さをよく知っています。日本の教育が、子どもたちの自由な心を育てるものになってほしいと願っています」
誰しもが、不安や孤独を感じて塞ぎ込むときがある。しかしそういったネガティブな感情こそ、人の心を動かす力になる。角野さんの波乱に満ちた人生と、そこから生み出された数多くの作品が、そのことを物語っている。気持ちも装いも自由気ままに、どうやったら楽しめるかを想像することで、灰色だったはずの景色がカラフルに見えてくる。つまるところ、想像力は私たちが持つ一番の魔法なのかもしれない。