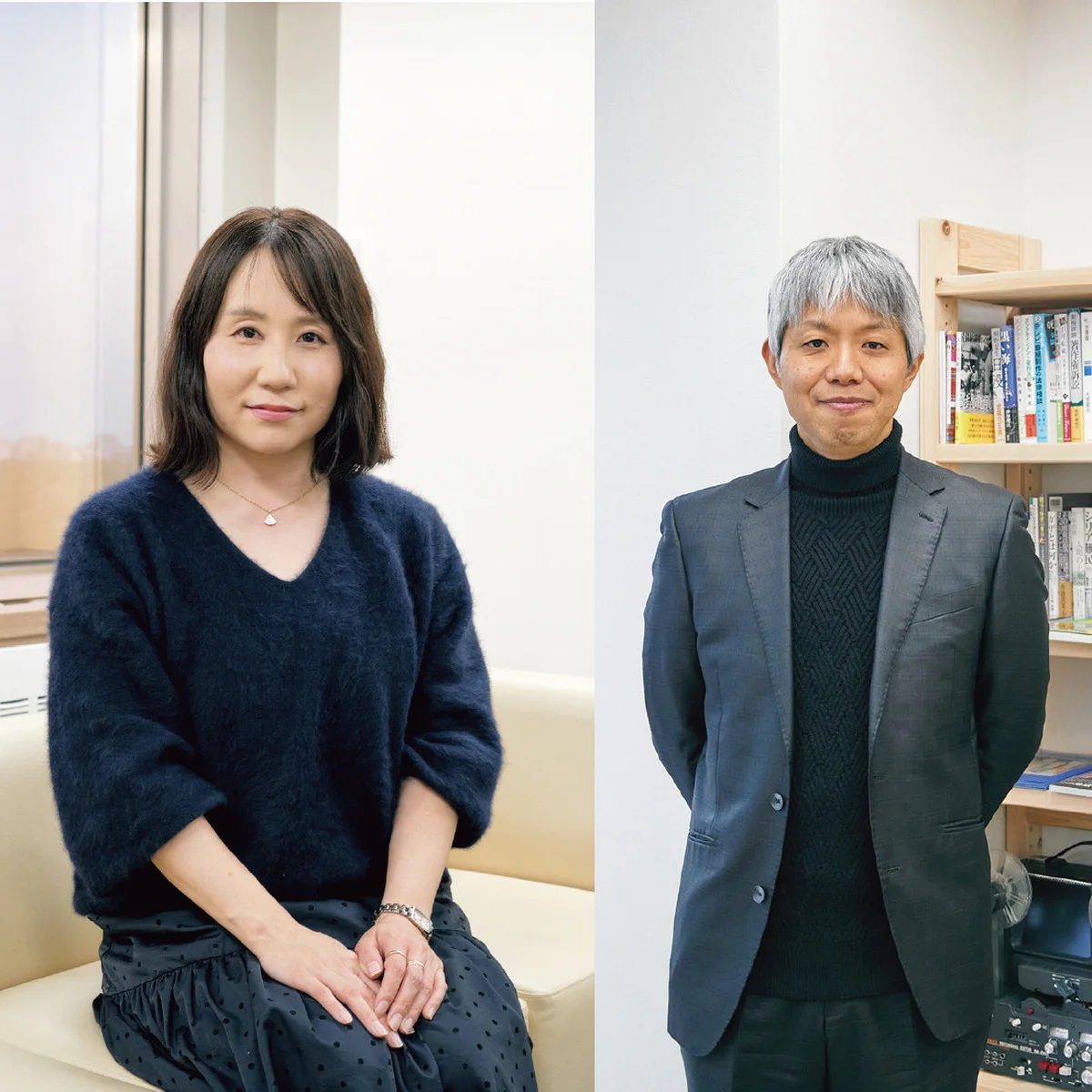4月より開催される「KYOTOGRAPHIE」(京都国際写真祭)のテーマは「SOURCE」。ルーツや源、始まりを意味する言葉を世界各国の写真家がそれぞれ解釈した。SPURでは展示を行うフォトグラファーに、自身の創作活動の源、そして社会との向き合い方を聞いた。写真が提示した新しい世界の在り方を一緒に考えたい。
川内倫子さんと潮田登久子さんが考える、写真が持つ力

かわうち りんこ●1972年生まれ。2002年に写真集『うたたね』『花火』(ともにリトルモア)で第27回木村伊兵衛写真賞受賞。国内外で作品を発表し続けている。近著にエッセイ『そんなふう』(ナナロク社)のほか、写真集を多数発表している。

うしおだ とくこ●1940年生まれ。石元泰博と大辻清司に師事し、1970年代からフリーの写真家として活動をスタート。代表作に「冷蔵庫」や「本の景色」シリーズなど。写真集『マイハズバンド』(トーチプレス)を2022年に発表した。
ヴィヴィアン・サッセンが模索する、写真表現の次なる目的地

1972年、アムステルダム生まれ。幼少期をケニアで過ごし、ユトレヒト芸術大学とアトリエ・アーネムで写真を学ぶ。2007年にオランダで最も権威ある芸術賞のローマ賞を受賞。
自分の二つの面を象徴する、ファッションとアート
ヴィヴィアン・サッセンというアーティストの名前を聞いて、最初に頭に思い浮かぶのはどんなイメージだろう? 幼少期を過ごしたケニアや南アフリカで現地の人々をモデルに撮影した、謎めいた写真の数々? ステラ・マッカートニーやルイ・ヴィトンといったメゾンの広告キャンペーンビジュアル? もしくは、大胆にカットアップした写真で構築したシュールなコラージュだろうか?
光と影が交錯しビビッドな色彩がコントラストを成す、彼女のマジカルなビジュアル表現。それらを堪能できる、キャリア最大規模の回顧展が『PHOSPHOR: Art & Fashion1990-2023』だ。さる2月までパリのヨーロッパ写真美術館(以下MEP)で開催されていたこの話題の展覧会が、「KYOTOGRAPHIE」にやってくる。
「MEPは非常にヨーロッパ的なクラシカルな建物なんですが、『KYOTOGRAPHIE』で会場に用いる場所は、ラフでインダストリアルな、まったく違うタイプの空間(京都新聞ビルの地下にある印刷工場跡)。そこに、セノグラファーの遠藤克彦建築研究所の協力を得て展示スペースを用意するんです。日本人の視点でさまざまな課題に対して、われわれ西欧の人間とは異なる回答を提示してくださるはず。最終的にどんな仕上がりになるのか自分でも読めないので、今からとても楽しみです」と話すヴィヴィアン。
普段は「この先に何が待っているのか探し出すこと」に夢中で、過去を振り返ることにはさほど興味を抱かなかったという。しかし、一年を費やして本展の準備を進める中で、さまざまな発見があったそうだ。
「MEPのキュレーターであるクロチルド・モレットとの共同作業で展覧会を作り上げたんですが、作品の数があまりにも多く、すべてを見てもらうのは物理的に難しくて。まず私自身が各時代、各シリーズから、展示したい作品の候補を大まかにセレクトしました。自分のベストを選ぶつもりで。すると、すっかり存在を忘れていたピースが見つかったりしたんです。たとえばその一つは、1990年に撮影した自画像にペインティングを施した作品で、まさに、ここ数年間に私が試みてきた手法なんですよね。“30年前と同じことをやっているのか”と愕然としました(笑)。もちろん表現は当時より深まっている。でも、核の部分は変わっていないんです」。
そこでヴィヴィアンは、展覧会のスタート地点を1990年に設定。当時18歳だった彼女は芸術大学に進んで写真を専門的に学び始めた。“Art & Fashion”とタイトルに掲げているように、卒業後プロとして仕事を始めた当初からパーソナルなアート写真とより商業的なファッション写真、二つの表現を並行して追求してきた。時にはその境界線をぼかしながら。
「アート写真とファッション写真はお互いに影響し合い、同時に進化してきました。アート写真の制作で得た知見が、ファッション写真に反映されるのはもちろんのこと、逆の場合も少なくありません。私は『POP』や『PURPLE』といったインディペンデント雑誌でファッション写真を撮影することが多く、自由に実験的な試みを行なってきました。またその撮影には大勢の人が関わりますから、コラボレーションを通じてさまざまなアイデアを試すこともできるので、そういった体験がアート作品に影響を与える。
過去にも言ったことがありますが、両者は私のパーソナリティの二つの面を象徴していて、内向的な面を象徴するのがアート写真。ややシリアスかつメランコリックです。他方で、外向的な面を象徴するファッション写真はよりプレイフルですから、両者のバランスをとることが私にとってすごく重要なんです」
本展を構成する上でも、そのバランスをヴィヴィアンは重視。ファッション写真とアート写真だけでなく、ほかにもアナログ表現とデジタル表現といった補完的なカテゴリーに分けられる作品を、バランスよく配置した。
「とはいえ、カテゴリーに関係なく、すべての作品が必要なことに気づきました。究極的にはどれも生と死に関わっており、誘惑や思慕、恐れといったテーマが共通していた。これらの作品は自分の内面のエモーショナルな領域において、カタリストの役割を果たし、制作を通じて一人の人間としても成長できたんです」
クラウディア・アンドゥハルが写し続けた、正義のあるべき姿
『ヤノマミ|ダヴィ・コペナワとヤノマミ族のアーティスト』

サンパウロのモレイラ・サレス研究所の現代写真部門長兼、同研究所が出版する雑誌『ZUM』の編集長。キュレーターとして森山大道やウィリアム・エグレストンの展覧会を手がけ、ハッセルブラッド国際写真賞2019などの審査員も務める。
世界を動かしたのは、市民一人ひとりがとらえた写真

1981年テヘラン生まれ。2006年に渡仏、2011年に「ル・モンド」紙に記者として入社。国際部に所属して中東地域を担当。2016年から3年間イラン特派員を務めた。

1980年ペルピニャン生まれ。マグナム・フォト勤務を経て、2011年から「ル・モンド」紙のフォト・エディターに。写真やビジュアルのセレクションなどを統括。
会期:2024年4月13日〜5月12日
会場:京都文化博物館 別館、京都新聞ビル地下1階、二条城 二の丸御殿 台所・御清所、京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階、京都芸術センターほか。